証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

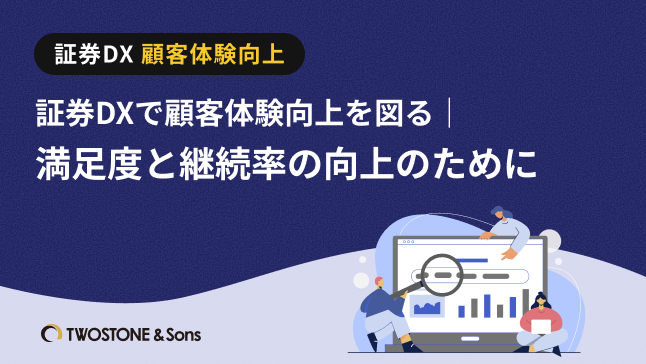
証券DXを推進して顧客体験向上を実現させた具体的な事例を紹介しながら、継続利用やブランド価値強化につなげる方法を解説します。初心者にも使いやすく、学びながら取引できる設計や、証券DXの効果的な推進方法がわかります。
これまでの証券業界は、商品力や手数料の安さを武器に顧客を獲得してきました。しかし近年、投資家のニーズは多様化し、特に若年層や初心者層の間では「どのような体験ができるか」が証券会社を選ぶ基準になりつつあります。さらに日々進化するデジタル技術によって、利用者の期待値も急速に高まっています。
そうした背景から証券業界でも顧客体験を軸にサービス設計を見直す動きが加速しており、証券DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性は一段と高まっているのです。
本記事では、なぜ今証券DXによって顧客体験を向上させる必要があるのかを明らかにし、その具体的な理由を3つに分けてご紹介します。最後まで読むと、どのように顧客との接点を強化すれば満足度や継続率の向上につながるのかが見えてくるはずです。今後の証券ビジネスの方向性を模索している企業様は、ぜひ参考にしてください。

証券会社の主な競争軸は、もはや商品や価格だけではありません。現代の利用者が重視しているのはサービスを通じて得られる快適さや便利さ、そして安心感です。こうした体験価値を高めるためには、紙ベースの手続きや電話応対に依存した旧来型の仕組みから脱却し、デジタル技術を駆使した顧客接点の刷新が必要です。
特に、スマートフォンアプリやチャットボット、オンライン上の手続き完結型サービスなど、利用者に負担をかけずにサービスを提供できる環境の整備が求められています。証券DXの本質は単なるシステム導入ではなく、顧客視点に立ったサービスの再設計であり、そこにこそ企業の真価が問われる時代になっています。
デジタル技術を活用することで、証券業務の効率化だけでなく顧客体験を進化させることが可能になります。
ここでは、証券DXの推進においてなぜ顧客体験が注目されているのかを3つの観点から整理します。
第一の理由は、顧客体験の質が長期的な利用につながるからです。システムが使いやすく情報が整理されており、迅速に対応される環境が整っていれば、顧客は他社への乗り換えを考えにくくなります。結果として継続利用率が高まり、顧客あたりの取引額や商品購入率も上昇します。
例えば、取引履歴やポートフォリオの可視化機能をアプリ内に実装することで、月間アクティブユーザーを増加させ、既存顧客からの追加投資を促せるでしょう。このように顧客がストレスなく投資判断できる環境を整えることが、継続率と単価の両面で好影響をもたらすのです。
次に注目すべきは、若年層や投資初心者が体験価値を重視しているという点です。この層は金融知識が十分でない場合も多く、直感的に操作できるインターフェースや学習コンテンツの充実を重視しています。
例えば、チュートリアル付きのアプリやAIが投資スタイルを診断してくれるサービスは、初心者にとって心強い味方です。こうしたユーザーが初めて利用した証券サービスでポジティブな印象を持てば、その後も他社へ移る可能性は低くなります。顧客が証券会社を選ぶ際の基準は、わかりやすさや親しみやすさへとシフトしているのです。
顧客体験が注目される理由は、対応スピードの速さが顧客満足度を左右するためです。問い合わせに対して即時に回答が得られるか、取引がスムーズに完結できるかどうかは信頼感に直結します。
例えば、チャットボットやFAQの自動応答、24時間対応のサポート機能を導入すると、顧客の不安や疑問を迅速に解消する環境を整えられるでしょう。特に業務時間外でも情報が得られる仕組みは、現代の顧客ニーズに合致しています。
対応が遅れたり煩雑な手続きが必要だったりする場合、顧客は他の証券会社への乗り換えを検討しやすくなります。だからこそ、スピードと簡便さを意識したデジタル対応の強化が競争優位の決め手になるのです。
証券業界では、顧客の利便性を高めるための取り組みが加速しています。特にデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、これまで煩雑だった手続きや取引体験が改善されつつあります。
ここでは、証券DXがもたらす具体的な顧客体験の向上について4つの観点から見ていきます。
かつて証券口座の開設には多くの書類と手続きが必要で、時間も手間もかかっていました。しかしDXの推進により、本人確認や署名、提出書類の処理といったプロセスがオンライン化され、スマートフォンやPCで完結できるようになってきています。これにより、顧客は空いた時間に手軽に口座開設を進めることができ、申し込みから実際の取引開始までの時間が短縮されるのです。
実際に、スマートフォンでマイナンバーと本人確認書類を撮影してアップロードするだけで、最短即日に口座が開設されるサービスも登場しています。これにより顧客がストレスを感じる機会が減少し、サービス利用への第一歩がスムーズに踏み出せる環境が整いつつあります。
DXにより、証券会社は取引画面や手順を視覚的かつ直感的に設計できるようになります。従来の証券アプリは専門用語や複雑なボタン配置でユーザーを混乱させるケースが多く、特に初心者にとっては心理的なハードルが高いものでした。
現在では、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)の観点からフローを簡素化した設計が重視されています。例えば、「買う」「売る」などの基本操作を画面中央に配置し、リアルタイムのチャートやニュースを必要な場所に表示することで、操作の迷いが生じにくくなるでしょう。これにより、利用者は安心して取引を進められるようになるのです。
単に画面をきれいにするだけでなく、ユーザーの行動をデータで把握し、それに合わせて操作導線を最適化することが重要です。UX設計では、顧客が何を求めているのか、どこでつまずいているのかといった課題を明らかにし、その解決に向けた改善を継続的に行います。
例えば新しい銘柄を探す機能において、過去の検索履歴や購入履歴に基づいて候補を提示するなど、パーソナライズされた提案が可能になります。このように顧客が自分に最適な選択肢にすばやくたどり着けるようになれば、自然と利用頻度の向上にもつながるでしょう。
顧客体験の向上には、サポートに依存せず自分で問題を解決できる環境の整備も不可欠です。セルフサービス化とは、顧客が疑問や操作ミスに直面した際に自ら対応できるような仕組みです。これにより待たされるストレスが減少し、顧客の満足度が上昇します。
例えば、AIによるチャットボットやわかりやすく整理されたFAQの設置によって、問い合わせ件数を削減しながら、即時の課題解決を実現できます。こうした自立的な利用環境が整えば初心者でも安心して継続利用しやすくなり、全体としての利用定着率が高まるのです。

顧客体験を本質的に高めるためには、単なるデジタルツールの導入だけでは不十分です。ユーザーが求めていることを深く理解し、タイミングよく対応する姿勢が求められます。
ここでは、証券DXによって実現可能な具体的な施策を紹介します。
NPS(Net Promoter Score)などの顧客満足度指標を活用することで、利用者がどのような体験に満足しているか、どこに課題を感じているかを定量的に把握できます。これによって改善すべきポイントが明確になり、迅速かつ効果的な対応が可能となります。
例えば、NPSのスコアが低い層にはフォローアップの施策を展開し、満足度の向上を狙うなど、データに基づいた戦略が立てられるでしょう。顧客一人ひとりの声を可視化することで、企業側の判断精度も向上していくのです。
年齢、投資経験、興味関心などに応じてパーソナライズされた情報提供を行うことは、顧客にとって価値の高い体験となります。このような情報提供のためには、誰にでも同じ情報を一斉送信するのではなく、それぞれの属性に応じて最適な内容を選定する必要があります。
例えば、初心者には基礎的な投資情報や用語解説、中級者には市場分析や戦略に関する情報を配信するなど、段階に応じたアプローチが有効です。これにより情報の受け手は「自分のために用意された情報」であると感じやすくなり、エンゲージメントが強化されます。
顧客の関心や行動は常に変化しています。そのため、通知の内容や頻度も状況に応じて調整する必要があります。そんな時に機械学習などの技術を活用すれば、各ユーザーの反応データを基に通知内容を自動で最適化できるでしょう。
例えば、過去の反応から週に一度のマーケット情報は高く評価されている一方で、日々の取引履歴通知は読まれていないとわかれば、配信内容を変更するなどの柔軟な対応が可能になります。適切な通知は、ユーザーにとって有益なサポートとなり、継続利用の動機づけにもつながります。
問い合わせ対応にかかる時間は、顧客満足度を左右する要素です。そのため、問題が発生した際にはできるだけ迅速に解決できる体制を整えておくことが重要です。近年はFAQやチャットボットを導入することで、即時対応が可能な環境を構築する企業が増加しています。
例えば、よくある質問をカテゴリ別に整理したFAQを設け、チャットでは営業時間外でも基本的な質問に対応できるようにするなど、顧客目線に立った設計が求められます。こうしたサポート体制はユーザーの不安を解消し、ストレスの少ない体験を提供する基盤になるのです。
顧客体験が洗練されると単なる利便性の提供にとどまらず、企業全体の印象や信頼性にも良い影響を与えます。とりわけ証券業界では、顧客が感じる安心感やわかりやすさがそのまま企業ブランドの強さに直結するのです。
ここでは、具体的にどのような取り組みがブランド価値の向上につながるのか、観点ごとに解説します。
サービス提供の一貫性は、顧客に「この会社は信頼できる」と感じさせる重要な要素です。例えば、カスタマーサポートの品質やトーンが窓口・チャット・メールなどのチャネルで統一されていれば、どの接点においても違和感が生まれません。結果としてユーザーは不安を感じにくくなり、長期的な信頼関係の構築につながります。
このような環境を実現するためには、社内でのガイドライン整備と対応履歴の一元管理が不可欠です。部門をまたいだ連携がスムーズになれば対応のばらつきを抑えられ、信頼を損なわない運営が可能になります。
専門性が高い金融商品を扱う証券業界においては、初心者への配慮がブランドの印象を左右します。例えば、投資初心者向けのコンテンツや用語解説を充実させることで、ここなら自分にもわかる、と感じさせられます。
加えて、取引画面や資料内の言葉選びにも工夫を凝らすことで、理解のしやすさが向上するでしょう。こうした丁寧な姿勢が利用者の不安軽減につながり、企業への安心感として蓄積されていきます。
UI(ユーザーインターフェース)の質は、顧客が企業に抱く印象に直結します。操作性の高い画面や適切なタイミングでのアニメーション、スムーズな遷移などが備わっていれば、それ自体がユーザー体験を豊かにし、印象に残る体験となります。
例えば、取引完了時のアニメーション演出や成果を視覚的に示すダッシュボードの導入などは、小さな工夫でありながら利用者に強い印象を残す効果があるでしょう。こうした演出の積み重ねが競合との差別化となり、ブランドイメージの向上を後押しするのです。
顧客との接点をオンラインのみに限定せず、リアルな場と組み合わせて提供するハイブリッドな体験は、ブランドに厚みを加える手段として有効です。例えば、オンラインセミナーとリアルセミナーを連携させることで参加者はより深く情報を理解でき、企業との距離も縮まります。
また対面サポートとチャットサポートを連動させることで、ユーザーは自身の好みに応じたサポート手段を選べるようになります。こうした選択肢の柔軟性が顧客の満足度を底上げし、他社では得られない体験価値として企業ブランドを高めるのです。
実際に証券DXを推進して顧客体験の改善に成功した企業の事例は、今後の取り組みを検討する上で参考になります。
ここでは具体的なDX推進の事例を3社紹介し、どのような工夫が顧客の満足度や利便性向上につながったのかを解説します。
SBI証券は2024年2月、スマートフォン向けの取引サイトを全面リニューアルしました。この取り組みの中心には、わかりやすさと使いやすさがあります。特に投資初心者にとっては複雑な金融商品や専門用語がハードルになりやすいため、情報の整理や表示方法に工夫を加えました。
実際にメニュー構成を簡潔にし、よく使う機能へのアクセスを直感的に行えるようにしたほか、株式や投資信託の選定を補助するガイドコンテンツも強化されました。利用者が自分の知識レベルに合わせて学びながら取引できる環境が整っており、金融リテラシーの向上と同時に取引体験の質も高められています。
参考:SBI証券株式会社
大和証券では、顧客との接点を強化する手段としてLINEを活用しています。従来、Webサイトや郵送でしか得られなかった情報がLINE上で手軽に受け取れるようになったことで、日常生活の中に自然に投資情報が入り込む仕組みが実現しました。
例えば、保有商品に関する情報や市場の動向を反映した投資信託のレポートがタイムリーに届くようになっており、通知の内容も顧客の興味関心に基づいて最適化されています。これにより、情報の見落としを防ぎつつ必要な情報を負担なく得られる状態が保たれているのです。手軽さと的確さを両立するコミュニケーション設計が、継続利用の後押しにつながっています。
参考:大和証券株式会社
マネックス証券では、投資家の理解を深める手段として動画コンテンツの活用に注力しています。特にアクティビスト・ファンドなどの専門性が高い商品については、文字情報だけでは伝えきれない内容を図解やアニメーションを交えた動画で分かりやすく説明しています。
このように商品設計の意図やリスクの捉え方を丁寧に解説する動画シリーズを展開することで、顧客は納得感をもって投資判断を行えるようになるのです。また、情報の伝達速度と理解の定着を両立するこの取り組みは顧客自身の金融知識を深める助けにもなっており、商品への信頼にもつながっています。
このように証券DXによる顧客体験の変革は、単なる技術導入にとどまらず、個別ニーズに応じた設計と工夫がカギとなります。
参考:マネックス証券株式会社

証券業界におけるDX推進は、取引の効率化やコスト削減といった側面に加えて顧客との関係構築やブランド強化にも直結しています。顧客が使いやすいと感じ、安心して取引できる環境が整っていれば、それは単なる利便性の提供ではなく継続的な利用を促す強力な要因となります。
また、顧客体験の改善は一度の施策で完結するものではなく、常にアップデートされるべき取り組みです。ユーザーの声を拾い、ニーズの変化に即応しながら小さな不便を減らし、価値を実感できる瞬間を積み重ねることが求められます。
そのためには、現状の課題を明確にし、自社の状況に合ったアプローチを計画的に進めることが欠かせません。顧客体験をより高めるためにも、本記事を参考に実効性を備えたDX施策の検討を進めてみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
