証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

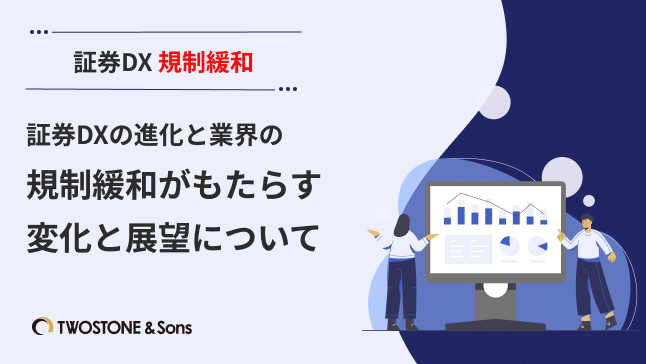
証券DXの規制緩和によって顧客対応の質向上や業務効率化が進んでいます。本記事では最新の国内外の事例や海外市場の動向を詳しく解説し、規制緩和を活用した効果的なDX推進の重要性や具体的な手法について丁寧にご紹介します。
近年、金融業界ではデジタル変革が急速に進んでいます。中でも、証券分野はデジタル技術の進展と並行し、国の規制緩和により転機を迎えつつあるのです。
顧客の利便性向上や業務の効率化が求められる中、証券DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進はもはや避けられない流れでしょう。しかし制度の変化を十分に理解し、自社に合ったDX戦略を描くのは容易ではありません。
本記事では証券業界における最新の規制緩和の動向を踏まえ、証券DXがどのような変化をもたらしているのかを具体的に解説します。さらに、業務の効率化や新サービスの創出、他金融機関との連携強化といった視点から実際にどのような展望が広がっているのかをご紹介します。
証券業務に携わる方々にとって、今後の意思決定に役立つ実践的な視点を得られる内容となっていることでしょう。

これまで日本の証券業界は顧客保護や市場の安定性を重視する観点から、さまざまな規制が設けられてきました。特に、紙ベースでの手続きや対面での説明義務などは法令で厳しく管理されており、業務の柔軟性に制限をかけていたのです。
しかし、テクノロジーの発展とともに金融商品取引法や電子記録債権法などの制度に見直しが入り、デジタル対応を後押しする動きが加速しています。
例えば、2021年の金融商品取引法改正では電子交付に関する要件が緩和され、顧客の同意を得ることで重要書面をオンラインで提供することが可能になりました。これにより、証券会社は従来よりも柔軟かつ迅速にサービス提供ができるようになり、顧客接点の拡大や非対面チャネルの整備が進んだのです。
こうした制度変更は単なる効率化にとどまらず、新たな顧客体験を創出する大きなチャンスと捉えられています。
制度の見直しが進む中、証券業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は一層の加速が期待されています。
ここでは、規制緩和によって証券DXがどのように発展していくか、具体的な影響を3つの観点から掘り下げていきます。
まず書類交付や署名・押印などの従来は紙で行われていたプロセスを電子化することで、事務作業の簡素化が可能になります。
例えば、口座開設時に必要な本人確認書類の提出や契約書面の交付・回収をオンラインで完結できれば、郵送や対面での対応にかかる手間の軽減が期待できるのです。また、電子署名やワークフロー自動化ツールを組み合わせることで確認作業や承認フローのスピードが向上し、顧客対応までのリードタイムも短縮されます。
その結果従業員の負担が減り、リソースをより戦略的な業務に充てることが可能になるのです。コストの面でも紙の印刷・保管・郵送といった物理的な処理が不要になるため、年間で見ると経費削減効果が期待できます。
このように、規制緩和はDXの推進を通じ、業務全体のパフォーマンスを底上げする力を持っています。
規制が緩やかになったことで、従来は難しかった商品設計やマーケティング施策も、より自由度の高い形で展開できるようになりました。特にデジタル技術を活用したサービス開発では、顧客のニーズに細やかに対応した設計が可能になります。
例えば、資産運用に関心を持つ若年層向けにスマートフォンアプリを通じたミニ投資サービスを提供したり、AIを用いたポートフォリオ診断機能を実装したりといった取り組みが挙げられます。
このようなサービスは、UX(ユーザーエクスペリエンス)を重視したインターフェース設計とともに、法制度上の制約が緩和されたことで実現しやすくなりました。企業側としても新しい顧客層の開拓につながる戦略的な施策を打ち出せるようになり、結果としてビジネスの幅が広がっています。
近年の規制緩和は証券会社と銀行、あるいは他の金融機関との情報連携をスムーズにする基盤を整えつつあります。特にAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)の活用が推進されており、異なるシステム間でもリアルタイムなデータ連携が実現可能になりました。これにより、顧客が銀行で保有する資産情報と証券会社での取引履歴を、それぞれ統合的に把握することが可能になります。
例えば顧客のライフプランに応じた資産運用の提案、クロスセルによるサービス展開などがより的確に実施できるようになります。こうした連携が円滑になることで、本人確認プロセスやリスク評価なども一貫した基準で実施可能になり、金融サービス全体の信頼性向上にもつながるのです。
情報の共有は単なる業務効率の改善だけでなく、顧客にとっての利便性と安心感を高める重要な要素となっています。
証券業界でDXを進める上で制度が後押しとなる一方、大きな課題として立ちはだかっているのが「2025年の崖」と呼ばれる問題です。これは経済産業省が2018年に提言したITシステムの刷新課題であり、特に金融業界においては深刻な影響が想定されています。
ここでは、大きく分けて3つの影響について解説します。
まず、大手証券会社の多くが1990年代以前に構築された基幹システムを使い続けている、という現状についてです。このようなレガシーシステムは長年にわたる改修や機能追加によって複雑化しており、全体構造を正確に把握できている技術者が限られているという問題を抱えています。
例えば、新しいデジタルサービスを導入しようとしても既存のシステムに適合させるための時間とコストがかさみ、開発が遅れる傾向があります。さらに、バグの発生リスクや運用トラブルも無視できません。これにより、革新的な取り組みをスピーディーに展開するのが難しい状態となっているのです。
この構造的な複雑さを放置したままでは、どれだけ規制が緩和されても本質的なDXは進みません。したがって、システム全体の刷新またはモジュール化による段階的な移行を早期に計画し、既存資産を見直す動きが求められます。
もう1つの課題はIT人材の高齢化です。金融系のシステムはCOBOLや汎用機など現在では教育の場でもあまり取り扱われない言語、技術で構築されています。そのため対応できるエンジニアが年々減少しており、技術継承が進まないまま退職者が増えているのが現実です。
実際に、メインフレームに精通する担当者が数名しかおらず、保守業務の属人化が進んでいる企業も出てきています。万が一そのメンバーが急に抜けた場合、システム障害や復旧に大きな支障が生じる恐れがあります。このような人材依存型の構造は、事業の持続性を著しく低下させるのです。
また若い世代のエンジニアは、レガシー技術ではなくクラウドやAIなどの先端分野に関心を持つ傾向があります。そのため証券業界が今後も魅力的な職場として機能するには、古い技術体系を脱却し、開発環境をアップデートすることが不可欠です。
一方でフィンテック企業の台頭は証券会社にとって新たな脅威であり、同時に刺激ともなっています。これらの新興企業は、クラウドネイティブなシステムやアジャイル開発体制を基にスピーディーかつ柔軟にサービスを提供しています。
例えば、個人投資家向けの低コストで使いやすい取引アプリの提供、AIを活用した自動投資アドバイス機能を持つプラットフォームなどが注目を集めているのです。こうした動きは従来の証券サービスが持つハードルを取り払い、より幅広いユーザー層を獲得することに成功しています。
このような市場環境において、伝統的な証券会社がフィンテック企業と互角に渡り合うにはスピード感と柔軟性が不可欠です。従来の業務プロセスや社内規定に縛られていては、変化に追いつけません。規制緩和をチャンスと捉え、迅速に事業モデルを再構築する必要があります。
証券業界におけるDX推進は、規制緩和を背景にさまざまな技術革新や業務改善の機会を得ています。従来の枠を超えた、新たなビジネスモデルやサービスの創出が期待されているのです。
ここでは今後特に注目される技術や取り組みを詳しく解説します。
AI技術は、証券DXにおいて欠かせない存在となりつつあります。規制緩和によってデータ活用の自由度が広がったことで、AIの導入が加速しているためです。AIを活用した膨大な顧客データや市場情報の分析によって、より精緻なリスク評価や投資判断支援が可能になります。
実際にAIは、顧客の過去の取引履歴や行動パターンを学習し、最適な投資プランを自動的に提示できるようになってきています。これによって、従来は人間の専門家が時間をかけて行っていた作業が効率化されるだけでなく、個人投資家でも高度な投資戦略にアクセスできるようになるのです。
AIは業務効率化のみならず、サービスの質的向上と個別化を同時に実現する技術として証券DXを強力に後押ししているのです。
規制緩和の一環として、金融機関間のデータ連携を促進するオープンAPIの活用が急速に進んでいます。これにより異なる企業のシステムやサービスが柔軟に接続され、新しい価値提供が可能になるためです。
実際に、証券会社と銀行の口座情報がリアルタイムで連携し、投資資金の入出金がシームレスに行えるようになるケースが増えています。こうした連携は顧客の利便性を高めるとともに、運用面でもリスク管理の高度化を実現可能です。
オープンAPIは単なる技術連携を超え、業界全体の構造変革を推進するカギとなっています。
近年、分散型台帳技術であるブロックチェーンも証券DXの注目技術に挙げられます。透明性と改ざん耐性の高さから、証券取引の信頼性向上やコスト削減に貢献できるためです。
例えば株式の発行や売買にブロックチェーンを活用し、取引記録をリアルタイムかつ安全に管理できるようになれば仲介コストの削減や決済スピードの向上が期待されるでしょう。実際に、セキュリティトークンを用いた新しい資金調達モデルも広がりつつあります。
これらは従来の紙ベースや中央集権的なシステムから脱却し、分散型の仕組みを通じて透明性と効率性を両立する取り組みです。規制緩和により実証実験や実際の導入が加速し、業界全体のDX推進に寄与するでしょう。
証券業界では未だに手作業や紙ベースで行われている業務も多数あり、こうした業務の自動化は規制緩和を背景に推進されている分野です。これによって、人為的ミスの軽減と業務スピードの向上を両立できます。
実際に顧客の本人確認や契約手続きのデジタル化が進み、オンライン上で手続き完結が可能になるケースが増えています。これにより顧客は窓口に足を運ぶ手間が省け、証券会社側も運用コストの削減につながるのです。
また、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)技術の導入でデータ入力や照合作業といった反復業務が自動化され、社員はより付加価値の高い業務に集中できる環境が整いつつあります。こうした自動化は、人材不足への対応策としても効果的です。
このように業務プロセスの見直しと最適化がDX推進の基盤となり、効率化の波を証券業界全体に広げています。
近年、環境・社会・ガバナンス(ESG)要素を重視するサステナブル投資が世界的に注目を集めています。証券会社もこうした社会的要請に応えるため、新たな商品開発やサービス設計に取り組んでいるのです。
実際に規制緩和によりESG関連の情報開示基準が整備され、投資判断に活用しやすくなっています。これにより顧客に対して社会貢献性の高い投資案件を提案でき、企業の持続的成長を促進するサポートが可能になるのです。
また、環境関連のプロジェクトや地域活性化ファンドと連携した独自商品も増加傾向にあります。こうした取り組みは単に投資機会を提供するだけでなく、企業イメージの向上や新たな顧客層の開拓にもつながります。
これからの証券DXではサステナブル投資を中心に据えたビジネスモデルの構築が欠かせません。
最後に、規制緩和の恩恵を最大限に活かす戦略としてM&Aや外部企業との提携も重要なポイントです。成長戦略や技術力強化のため、既存の証券会社がフィンテック企業を取り込む動きが加速しています。
実際に、AI分析技術やブロックチェーン技術を持つスタートアップを買収し、自社のサービスに統合するケースが増えています。これにより短期間でDXを推進できるだけでなく、市場の競争優位性を高めることが可能です。
また、共同開発や業務提携によってノウハウや資源を共有し、新たな商品やサービスの創出に結び付ける取り組みも活発です。こうした協業は、単独でのイノベーション創出が難しくなった現在において有効な戦略となっています。
これらの動きは規制の枠組みが緩和されることで一層促進され、証券業界のDX加速に大きく寄与すると見込まれます。

規制緩和は国内の証券業界に留まらず、世界各国でもDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の原動力となっています。特に、デジタル資産やデジタル証券の取り扱いに関する法整備や新たな制度の導入が進み、市場環境が変貌を遂げているのです。
海外の先進事例を学ぶことで、国内証券業界が目指すべき方向性や課題を明確に把握できます。
ここでは、規制緩和を契機に証券DXを加速させた欧州連合、イギリス、シンガポール、中国及びタイの5つの市場を取り上げ、それぞれの特徴的な取り組みを紹介します。
欧州連合はデジタル資産市場の信頼性向上と透明性確保に向け、包括的な規制枠組みを整備しました。これにより暗号資産やセキュリティトークンなど、新しい金融商品の流通基盤が確立されつつあります。
欧州委員会が2020年に提案した「Markets in Crypto-Assets(MiCA)」規則は、加盟国間で共通のルールを適用し、投資家保護と市場健全化の両立を図ることを目的としています。これによって従来の金融商品とデジタル資産の境界線が明確になり、規制の曖昧さから生じていた市場混乱を抑制しました。
欧州の規制緩和は単なる規制撤廃ではなく、明確なルール設計による市場インフラの強化を目指している点が特徴です。これは国内における証券DX推進の参考になるでしょう。
イギリスは規制環境の柔軟性を活かし、金融イノベーションを促進するための実験場としてデジタル証券に特化したサンドボックス制度を設けました。このDigital Securities Sandbox(DSS)は、新規事業者が規制の枠内で安全にサービスを試験できる枠組みを提供します。
サンドボックス制度は規制当局が監督の下でリスク評価を行いつつ、参加企業に柔軟な対応を許可する点が特徴です。これにより、従来の規制の制約を超えた革新的な商品や取引手法の実証が可能となっています。
イギリスのDSSは規制緩和と安全管理のバランスを巧みにとった先進的な事例であり、日本を含む他国でもサンドボックス制度の導入検討に影響を与えているのです。
シンガポール金融管理局(MAS)は、国家戦略として金融テクノロジーの発展を強力に後押ししています。特にデジタル証券と貿易金融分野における規制緩和が目立ち、証券DXの推進に大きな役割を果たしているのです。
デジタル証券に関しては規制の枠組みを柔軟にすることで、スタートアップ企業や伝統的金融機関双方が安心してデジタル資産関連事業を展開できる環境を整備しています。投資家保護のための監督基準を維持しつつ、新技術の実証実験を支援する取り組みも活発です。
貿易金融分野では、紙ベースの書類や複雑なプロセスをデジタル化するための共同プラットフォームが構築されており、複数の関係者間でリアルタイムな情報共有が可能になりました。これにより取引の透明性が増し、不正リスクの低減や取引スピードの向上に寄与しています。
シンガポールの成功の要因は、金融庁がリーダーシップをとり、規制と技術革新のバランスをとった点にあります。これにより国内外からの投資を呼び込み、地域の金融ハブとしての地位を一層強固にしました。
中国は近年、外国資本の参入障壁を段階的に緩和して証券市場の国際化を促進しています。特に中国上場企業への投資に関わる規制が見直され、外国投資家に対するアクセスが改善されました。
具体的には、QFII(Qualified Foreign Institutional Investor)制度の緩和やH株(香港市場に上場する中国企業株式)に対する取引条件の改定が進められています。これによって外国人投資家はより容易に中国市場に参加できるようになり、多様な資産運用の機会を得られる環境が整備されました。
規制緩和は、中国証券市場の流動性拡大と国際的信頼性の向上をもたらしています。結果として中国国内の証券DXが加速し、取引の電子化やリスク管理の高度化が進んでいるのです。
東南アジアの成長市場であるタイも、証券DXを促進するために外国企業の参入環境を改善しました。証券取引委員会が中心となって外国証券事業者向けのガイドラインを策定し、手続きを簡素化しています。
これにより、これまで複雑で時間のかかっていたライセンス申請や規制対応のプロセスが効率化され、海外企業のタイ市場への参入障壁が引き下げられました。実務的な負担が軽減されたことで、多くのフィンテック企業や証券会社がタイ市場での事業展開を加速させています。
タイの取り組みは、規制の合理化が外国資本の誘致と証券DXの推進に直結する好例として注目されています。
証券業界における規制緩和は、単に新しいサービスを生み出すだけでなく、既存の業務プロセスの効率化や顧客対応の質向上にも影響を与えています。規制の枠組みが柔軟になることでデジタル技術を積極的に活用しやすくなり、顧客満足度の向上や業務の迅速化に成功した事例が増えてきました。
ここでは、国内大手証券会社におけるDX推進の具体的な取り組みを見ていきましょう。
株式会社SBI証券は、デジタル技術を活用してオンライン証券取引の利便性向上に注力しています。
特に、「ROBOPRO for SBI証券」はロボアドバイザーを活用した資産運用サービスとして知られており、投資初心者から上級者まで幅広い層に支持されているのです。このサービスは、AIアルゴリズムを駆使して個々の投資家のリスク許容度や投資目的に応じたポートフォリオを自動で提案し、運用の最適化を支援します。
規制緩和によって金融商品のデジタル提供が拡大した結果、SBI証券は「ROBOPRO」を通じて従来の窓口対応を減らし、顧客の自己完結型取引を推進しました。これにより顧客の利便性が高まるだけでなく、社内の業務効率も向上しました。
今後はさらなる機能拡張や新たな金融商品のデジタル化を視野に入れ、オンライン証券のモデルを進化させています。
参考:株式会社SBI証券
みずほ証券株式会社は顧客対応の質を高めつつ業務負担を軽減するため、AIを活用した電話自動応答システムやチャットボットを導入しました。これらの技術は顧客からの問い合わせに24時間対応可能であり、基本的な質問や手続きの案内を自動化することでオペレーターの対応時間を削減しています。
実際に、チャットボットがWEBサイトやスマートフォンアプリに組み込まれ、投資情報や手続き方法、トラブルシューティングなどを迅速に案内しています。これにより即座に回答を得られるため、顧客満足度の向上につながっています。
規制緩和によりデジタル対応が促進されたことでこうしたAI活用がスムーズに実現し、みずほ証券は顧客接点のデジタルシフトを加速させました。
参考:みずほ証券株式会社
株式会社大和証券グループ本社は最新のブロックチェーン技術を用いたセキュリティトークン(STO)を活用し、資産運用の新たなデジタルサービスを展開しています。セキュリティトークンとは、株式や債券などの金融資産をブロックチェーン上でトークン化し、安全かつ効率的に取引できる仕組みです。
この技術により従来の紙ベースの手続きや中間業者を減らし、取引の透明性と信頼性を高めることに成功しました。特に資産運用サポートの分野において、顧客がオンラインで手軽に分散投資やポートフォリオ管理を行える環境が整備されました。
規制緩和によりこのような革新的な技術を導入しやすくなった背景もあり、大和証券は業界の先駆けとしてデジタル化の先端を走っているのです。

証券業界における規制緩和は、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進にとって大きな追い風となっています。金融商品のオンライン提供やAI活用、ブロックチェーン技術の導入など規制が緩和されたことで実現可能なサービスは多岐にわたります。顧客ニーズが多様化する中、迅速かつ質の高い対応が求められる現代において規制緩和を活用したDXの推進は不可欠です。
本記事で紹介したような具体例は単なる技術導入にとどまらず、業務の効率化や顧客体験の革新に直結しています。今後も規制の動向を注視しつつ、新しい技術を積極的に取り入れていくことで競争力を高められるのです。
変化の波に対応しつつ業界の未来を切り拓いていくためにも、自社の状況を見直しながら、より実効性の高いDX戦略を検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
