証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

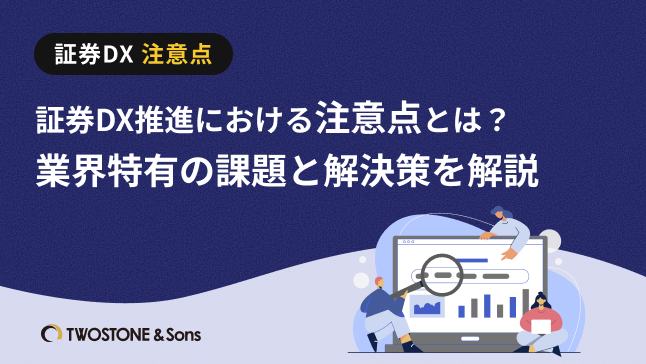
証券DXを成功に導くための具体的手順や注意点、成功事例、そして実践に役立つ4つのポイントを詳しく解説しています。DXの方向性に悩む方は、段階的な取り組み方や現場主導の設計、人材育成など実践的なアプローチをぜひご参考ください。
近年の証券業界において、紙の書類が山積みになり、顧客対応や事務作業に追われている、といった悩みを抱えている企業様は少なくないでしょう。証券業界では今、デジタル技術を活用した業務改革、いわゆる証券DX(デジタル・トランスフォーメーション)が急速に注目されています。中でもペーパーレス化は、業務の効率化だけでなく顧客満足の向上にも貢献する取り組みです。
本記事では、証券業界におけるDXの基本からその背景、そして具体的な効果までを分かりやすく解説します。デジタル化の流れを正しく理解し、競争力を高めたいと考える証券会社の担当者や経営層にとって業務効率と顧客満足の両立を実現するヒントが得られるでしょう。

証券業界におけるDXは単なるデジタルツールの導入ではなく、企業文化や業務プロセスそのものを変革し、新しい価値を創出する取り組みです。とりわけペーパーレス化を含む情報のデジタル管理は、業務の透明性やスピードを向上させる重要な一歩とされています。
証券DXとは、顧客管理、取引処理、書類作成などのアナログ業務をデジタル技術を用いて最適化することです。取引の自動化、クラウド活用によるデータの一元管理、AIを使った分析業務の高度化などが具体的な手段として挙げられます。単にITシステムを導入するのではなく、業務の根幹にデジタルを組み込み、業界全体の変革を促すという視点が求められています。
証券DXが注目を集めている背景には、業務の煩雑化と顧客ニーズの高度化があります。従来の紙ベースの業務は手間が多く、ミスも発生しやすいという課題がありました。顧客の多様なニーズに迅速に対応するには、柔軟で効率的な業務体制が必要になってきたのです。
加えて、金融業界全体に求められるコンプライアンスの強化や非対面取引の拡大も、デジタル化の後押しとなっています。これらの要因が重なり、業界を挙げた変革が求められるようになっているのです。
証券DXの推進で得られる効果は、業務効率の改善だけにとどまりません。例えば、ペーパーレス化によって書類の保管や検索の手間が省かれ、担当者の作業時間が短縮されるでしょう。
また、顧客とのやり取りもデジタルチャネルを活用することで迅速化し、問い合わせ対応や取引のスピードが向上します。これによって顧客満足度が上がり、競争力の強化にもつながるでしょう。
さらに、業務フローの自動化によって属人化を防ぎ、人的ミスのリスクを低減できます。組織全体としての生産性底上げは、新たなサービス開発や顧客体験の向上にもつながるでしょう。
証券DXは、業務効率化や顧客体験の向上に大きな可能性を秘めていますが、実際の現場ではさまざまな課題に直面するケースも少なくありません。単にツールやシステムを導入するだけでは思うような効果が得られず、現場の混乱や形骸化が起こるリスクもあります。
ここでは、証券DXの推進にあたり特に多く見られる障壁について解説します。
最初に挙げられる課題は、テクノロジーの導入が目的になってしまい、本来の業務改善や顧客対応の質の向上という目的が見えにくくなる点です。特に「最新技術を取り入れている」という表面的な取り組みで満足してしまうと、業務の本質的な変革につながりません。
例えば、ペーパーレス化を実現するために電子書類システムを導入しても、社内フローの見直しがされていなければ、紙の代わりに画面で承認作業をしているだけという状況になりかねません。重要なのはテクノロジーを使うことではなく、どう活用するかを明確にすることです。目標を定義し、その実現に向けた手段として技術を選定するプロセスが求められます。
次に直面しやすいのが、デジタル人材の不足です。証券業界は従来の業務慣習や専門知識に強みがある一方で、ITリテラシーやデータ活用に長けた人材はまだ少ない状況です。結果としてツールを導入しても使いこなせず、現場での定着が難しくなってしまいます。
例えば、RPA(業務自動化)ツールを導入してもそれを管理・改善する人材が不足しているため、想定した生産性向上が実現しないケースがあります。これを防ぐためには、既存の従業員への研修機会の提供と並行して、外部からの専門人材の確保や外部パートナーとの連携を検討することが有効です。
また、部門横断的なプロジェクトチームを編成し、ITと業務の知識を融合させる取り組みも有効とされています。業界特有の事情を理解しながらテクノロジーを使いこなせる人材の育成が、DX成功のカギとなります。
DXがうまく進まない理由の1つとして、社内全体にDXの目的やビジョンが十分に共有されていないという点も挙げられます。経営層と現場の間で意識のギャップが生まれると推進した仕組みが適切に活用されず、単なる業務負担と捉えられてしまう可能性があります。
例えば紙からデジタルへの移行を現場に一方的に指示した場合、具体的なメリットが説明されていなければ、従業員は不安や反発を感じるかもしれません。そうした心理的抵抗は、結果としてDXの足かせになってしまいます。
このような事態を防ぐには、DXの背景や意義、推進によって得られる利点を全社的に丁寧に説明することが不可欠です。定期的な説明会や社内ニュースレターを活用して情報を発信し、関係者全員が同じ方向を向けるようにする取り組みが求められます。
最後に、技術的な課題として多く挙げられるのが既存のレガシーシステムとの整合性です。証券業界では、長年使用されてきたシステムが多数存在し、それらが複雑に連携しているケースも珍しくありません。このような環境では、新しいシステムの導入が技術的にもコスト的にも大きな負担となります。
例えば、顧客情報を管理している既存の基幹システムが古くAPI連携に対応していない場合、新しいCRMやマーケティングツールを導入しても十分に活用できない状況に陥ることがあります。このようなケースでは、段階的な移行計画を立て、小規模な単位からリプレースを進めていくアプローチが現実的です。
また、既存システムと新規システムを併用する「ハイブリッド構成」を採用することで、移行期間中のリスクを抑えながらDXを進める企業も増えています。これらの企業が増えている中で競争優位性を保つためには、柔軟な視点で技術的な制約と向き合う姿勢が求められます。
証券DXを成功させるには、単なるシステム導入にとどまらず組織全体で長期的な視点に立った戦略を描く必要があります。見落としがちな点や初期段階での判断ミスは、後々の運用や成果に影響を及ぼすでしょう。
ここでは、証券DXを円滑に進めるために押さえておきたい5つの重要な注意点について、具体的な事例や対応策を交えて解説します。
証券DXを実効性のある取り組みにするには、経営層の関与が不可欠です。現場主導の施策だけでは全社的なスケールでの変革が難しく、個別最適にとどまってしまう可能性が高まります。
例えば業務プロセスの見直しやデータ活用の高度化には、部門横断的な連携が求められます。こうした変化をスムーズに進めるためには、経営層がDXのビジョンを明確に提示し、その意義を全従業員に発信する必要があるのです。また、DXに関する意思決定のスピードや資金配分にも経営の関与が影響を与えます。
推進体制を整備する際には、CIO(Chief Information Officer)やCDO(Chief Digital Officer)を中心とした専門チームの設置が有効です。これにより、現場の課題を吸い上げながらも、戦略的な視点からプロジェクトをリードする体制を築けるでしょう。
金融業界においては、個人情報の取扱いやデータ管理に関する規制が厳格です。DXの過程ではクラウドサービスや外部ベンダーとの連携が増えるため、法令遵守が一層重要となります。
例えばクラウドを用いて顧客データを管理する場合、サーバーの設置場所やアクセス制限、暗号化の有無などが問題視される可能性があるのです。さらに証券業界では、金融商品取引法やマネーロンダリング対策規制など独自の規制も多いため、システム導入時には細心の注意を払う必要があります。
コンプライアンス対応を徹底するには、法務部門とIT部門が密に連携し各種規制への適合性を事前に確認するプロセスを整えることが重要です。加えて、ベンダーの選定時には、セキュリティ対策や法規制対応の実績も確認項目に加えるべきです。
証券会社の多くは、長年にわたり複雑なシステム構成で業務を運用してきました。そのため、新しいDX施策を推進する際には既存システムとの整合性が大きな課題になります。
例えば、顧客管理システム(CRM)と取引管理システムが別々に存在し、それぞれが連携していない場合、データの二重管理や業務の非効率が発生するリスクがあります。このような状況では一気に全システムを刷新するのではなく、段階的に移行していくことが現実的なアプローチとなるでしょう。
移行計画を立てる際は、まずどの領域がボトルネックになっているかを把握する必要があります。その上で影響範囲の少ない領域から段階的にデジタル化を進め、定着を確認しながら他の領域にも展開していく方法が効果的です。移行中のトラブルを防ぐためにはリスク評価とシミュレーションを徹底し、予備プランを用意しておくと安心です。
DXは一度推進して終わるものではなく、顧客ニーズや業務環境の変化に応じて継続的に改善していく姿勢が求められます。そのためには、ユーザーの声を反映したPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの運用が不可欠です。
例えば、新たに導入したオンライン口座開設システムに対して利用者から「操作がわかりにくい」といったフィードバックが寄せられた場合、それを基にUI設計の見直しやガイド機能の追加を行う必要があります。同様に、現場の従業員から業務プロセスの改善案があれば、柔軟に取り入れることで現場の納得感も高まります。
改善サイクルを有効に機能させるには、フィードバックを収集する仕組みをあらかじめ用意しておくことが重要です。アンケートフォームや定期的なヒアリング、FAQのアクセス分析など、定量・定性的な手法を併用しながら課題を洗い出すことでより効果的な改善が可能になります。
DXを進める上では、システム導入やインフラ整備にかかる初期投資だけでなく運用開始後の維持費用も視野に入れる必要があります。導入時にコスト面を軽視すると、後々の予算超過や運用困難につながる危険性があるのです。
例えばクラウドベースのツールを採用した場合、月額課金制が一般的であり、導入当初の費用は抑えられても長期的に見ると相応のコストが発生します。また、ソフトウェアのアップデート対応やサポート契約の継続も必要となるため、費用対効果を定期的に見直す姿勢が求められます。
費用面のリスクを最小限に抑えるには、初期段階でTCO(Total Cost of Ownership:総保有コスト)を正確に試算し、中長期的な収益貢献と照らし合わせることが大切です。また、プロジェクト予算にある程度のバッファを持たせ、予期せぬ変更やトラブルにも柔軟に対応できるよう備えておきましょう。

証券業界でDXを効果的に進めるには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。特に、現場の実情や経営層の意向、顧客ニーズなど多角的な視点を踏まえた手順を踏むことで、スムーズな推進と定着が期待できます。
ここでは、証券DXを推進する際に取り組むべき5つのステップをご紹介します。
まず重要なのは、現時点で抱えている課題や業務プロセス上の非効率な部分を把握することです。
具体的には、紙ベースの業務が多く残っている、部門間で情報が分断されている、顧客対応のスピードに課題があるなど業務フロー全体を俯瞰しながら問題点を洗い出します。この段階では、現場の従業員からのヒアリングや業務プロセスの可視化ツールを活用すると客観的な視点が得られやすくなります。
実際に、営業担当と管理部門との情報共有が非効率なため、業務の重複や対応漏れが頻発している、という企業は少なくないでしょう。現状分析によってこうした構造的な課題を見える化し、次のステップへの足がかりを得る必要があるのです。
全社的なDXを進めるには、最初に「何を改善したいのか」「どこにギャップがあるのか」を明確にすることが出発点になります。
自社の課題を把握した後は、それに対応できる具体的な解決策を探す段階です。
ただしここで重要なのは、「トレンドだから」「他社が導入しているから」といった理由で技術を選ばないことです。社内の風土や従業員のデジタルリテラシーの水準、業務スタイルなどにマッチするツールやアプローチを選定する必要があります。
例えば業務に対する現場主導の関与が強い企業では、カスタマイズ性の高い業務支援ツールが有効です。一方トップダウン型で変革を進めやすい体制を持つ企業であれば、クラウド型のSaaS導入がスピーディに進む傾向があります。
実際の選定プロセスでは、複数のベンダーに提案を依頼し、デモやトライアルを実施しながらフィット感を確認する方法が効果的です。
DXは単なるIT導入ではなく、組織変革そのものです。そのため、実行責任の明確化が成功のカギを握ります。
特に部門横断的に関係者が多くなる場合、誰が最終的な意思決定をするのかが曖昧だとプロジェクトが頓挫する恐れもあります。推進責任者を経営層から選出し、実務担当者には現場とテクノロジーの両方に理解のある人材を充てることが望ましいです。
DXの初期段階では、プロジェクトマネージャーに加えてデータ分析やITインフラに明るい担当者を配置すると、課題の早期発見と解決がスムーズに進むでしょう。
責任体制を明確にすることでプロジェクト全体に一貫性と推進力が生まれ、社内の理解や協力も得やすくなります。
推進体制が整った段階で、ようやくデジタルツールの導入に移行します。ここでは、自社の業務特性にフィットしたツールを選ぶことが重要です。
例えば、営業支援にはCRM(顧客関係管理)ツール、バックオフィス業務にはRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)、顧客との対話にはチャットボットやオンライン面談ツールなど用途に応じて最適な選択肢があります。
ツールの導入に際しては、全従業員が段階的に慣れていけるようスモールスタートで展開していきましょう。一部の営業チームに限定して新ツールを先行導入し、効果検証とフィードバックを経て全社展開につなげる方法がおすすめです。
このように、現場の理解と納得を得ながら導入するプロセスが、定着と効果を高めるカギとなります。
DXは、一度推進を始めれば終わりではありません。継続的に改善を重ねていく姿勢が求められます。
具体的には、定期的にKPIをモニタリングし、効果が出ているかを数値で確認しながら運用方法の見直しや新機能の追加など柔軟に対応していくことが重要です。
例えば、オンライン面談システムを導入した後に利用者から「接続が不安定」といった声が出た場合には、インフラの見直しやサポート体制の強化など素早く対応する必要があります。
また、定期的に現場と管理部門、経営層が意見交換する場を設けることで、組織全体の視点から改善サイクルを回せます。
こうしたPDCAを地道に回し続けることでDXの効果を最大化し、企業競争力の強化へとつなげられるのです。
実際にDXを推進し成果を上げている企業の事例は、これから取り組む企業にとって貴重な参考になります。それぞれの企業が直面した課題と、それにどう対応したかを見ていくと成功のカギや注意すべきポイントが明確になるでしょう。
ここでは、金融業界で注目を集めている3つの企業の取り組みを紹介します。
ふくおかフィナンシャルグループは、国内初のデジタルバンク「みんなの銀行」を立ち上げたことで注目を集めました。
背景には、従来の銀行サービスが持つ煩雑さや若年層との接点不足といった課題がありました。これに対して同社はゼロベースで銀行の在り方を再構築し、スマートフォン完結型のUX(ユーザー体験)を実現しています。
例えば、口座開設から資金管理、入出金確認まですべての操作をアプリ上で完結できるようにしたことで、従来の銀行利用にあった「面倒」「時間がかかる」といったハードルを一気に解消しました。
また、社内にはデジタル人材を多く登用し、従来の銀行文化との融合にも時間をかけて取り組んでいます。技術導入だけでなく、文化と人材の改革を同時に進めた点が成功要因といえるでしょう。
ゴールドマン・サックス証券では、AI技術を駆使した市場分析とコード生成の自動化に取り組んでいます。特に、金融工学と機械学習を融合させることで高度な市場予測を可能にしました。
この動きの背景には、従来型のアナリスト業務だけでは膨大なデータを処理しきれず、判断の精度に限界があるという課題がありました。AIの導入により、データ収集から分析、さらにはレポート生成までの時間を短縮しています。
実際に新たに開発したAIシステムでは、自然言語処理を用いてニュースや経済レポートから市場への影響を即時に抽出し、リスク予測を自動で提示できるようになりました。
この取り組みにより、業務の効率化だけでなくクライアントへの提案力強化という付加価値も実現しています。AI活用の可能性をいち早く見極めた点が、他社との差別化につながっているのです。
北國銀行は、2024年に国内で初めてフルバンキングシステムをクラウド化するという大胆な決断を下しました。このプロジェクトは単なるシステム更改ではなく、組織運営全体のデジタル化を意識したものでした。
導入の動機には、老朽化した基幹システムの維持管理コストの増大や柔軟なサービス開発の難しさといった課題がありました。従来型システムから脱却し、オープンAPIを活用できる環境を整えたことで、他業種との連携も進みやすくなっています。
例えば、口座管理や送金業務など、従来は複雑な手続きが必要だった分野においてもスマートフォンアプリと連携することでユーザー利便性を向上させました。
さらに注目すべき点は、行内での情報共有や業務連携のスピードが上がったことです。DXの進展によって、単なるサービスの刷新ではなく組織全体の機動力向上にもつながっています。
参考:株式会社北國銀行
証券業界におけるDX推進は単なるシステム導入にとどまらず、企業体質や働き方そのものの見直しが求められます。そこで重要なのは、社内の特性やリソースに応じた戦略的なアプローチです。
ここでは、DXを成功させるための4つの実践的なポイントを解説します。
初期段階から大規模な改革を試みると、現場の混乱や失敗への恐れから反発を招く可能性があります。成功への第一歩は、小さな改善から始めて徐々にステップアップする姿勢です。
例えば、営業支援ツールの導入や書類の電子化といった業務改善から着手することで、現場の負担を減らしながらデジタル活用への理解を促せます。こうした取り組みによって「できる」「便利だ」と感じる成功体験が積み上がれば、次のフェーズへの移行もスムーズになるでしょう。
いきなり全体最適を目指すのではなく、現場ごとの課題に応じた小規模な改善を繰り返すことが最終的な全社DXの達成へとつながるのです。
DX推進が現場に定着しない最大の理由は、使いづらさや現実とのズレにあります。ツールや仕組みを選定する際には、現場の声を取り入れる姿勢が欠かせません。
例えば、営業担当や事務スタッフの業務フローを丁寧にヒアリングし、実際の業務プロセスに合ったツールを選ぶことで、推進後の活用率が向上するでしょう。また、UIや操作性に配慮した設計にすることで属人的な業務を標準化しやすくなるというメリットもあります。
一方的なトップダウン型ではなく、現場と経営層が双方向でコミュニケーションを取りながら設計する姿勢が現実的で効果的なDXを実現します。
デジタル化を推進する上で、専門的な知識を持った人材は欠かせません。しかしながら、既存の金融人材だけでは十分な技術力やマネジメントスキルが不足している場合もあります。
そのため、社内での人材育成と外部人材の確保の両面から早期に取り組む必要があります。例えば、外部の研修機関やeラーニングを活用し、既存従業員に対してリスキリング(再教育)を施す方法は効果的です。また、デジタル技術に強い人材をプロジェクトベースで登用することで、内部にノウハウを蓄積しながら徐々に社内人材を育てる体制を整えましょう。
早期の人材戦略こそが、継続的なDX推進の基盤を支えることになります。
DXの本質は部署ごとに閉じた最適化ではなく、企業全体の業務連携とデータ統合にあります。そのためには、部門間の壁を越えて協力できる体制づくりが不可欠です。
例えば、営業部門・IT部門・バックオフィスが共通の目標に向かって情報を共有できるよう、定例会議やプロジェクトチームを設置する取り組みが挙げられます。こうした横断的な体制を設けることで、システム導入時の不整合や業務プロセスの断絶を未然に防ぐことが可能です。
また、経営陣が自らコミットして部門間の調整をリードする姿勢を示すことで、全社的なDX推進に対する一体感が生まれます。結果として、短期的な成果にとどまらない、中長期的な変革へとつながっていきます。

証券業界におけるDXは単なるデジタル化ではなく、企業文化や顧客体験を変える戦略的な取り組みです。成功している企業に共通するのは、現場の実情を理解した上で段階的に施策を進め、人材や体制に対する投資を惜しまない姿勢です。
一方で、課題に直面した際には「誰が推進するのか」「どのツールが適しているのか」「組織としてどう変わるべきか」といった問いに正面から向き合う必要があります。これを怠ると形だけのDXに終わり、逆に業務効率や顧客満足度を損なうリスクもあります。
そのため、戦略の立案からツールの選定・人材育成・現場の巻き込みまでを一体的に考えることが、円滑な推進につながります。本記事を参考に必要に応じて、外部の視点やノウハウを取り入れながら、自社に合った進め方を模索してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
