証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

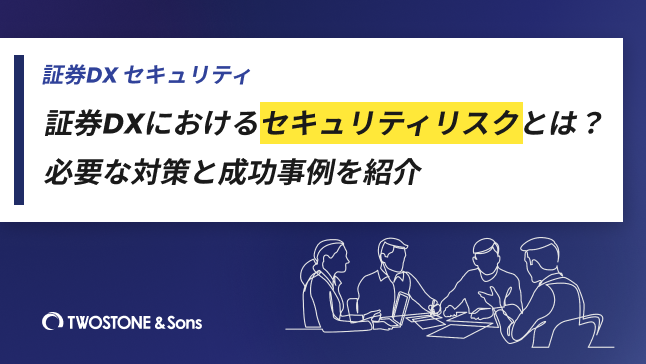
証券DXを推進する際に重要となるセキュリティ対策について、ゼロトラストやSSL通信などの基本的な技術要素に加え、企業の成功事例も交えて丁寧に解説しています。DXとセキュリティを両立させたい方にとって、実践的なヒントが得られる内容です。
デジタル技術の進化によって、証券業界にもDX(デジタル・トランスフォーメーション)の波が押し寄せています。業務効率の向上や顧客体験の最適化を目指してさまざまな企業がシステムの刷新やデータ活用を進めていますが、同時に見過ごせないのが情報セキュリティの問題です。特に証券業界では顧客の個人情報や資産データを扱うため、わずかなセキュリティのほころびが深刻なトラブルを引き起こしかねません。
では証券DXにおいて、どのような情報セキュリティの観点を重視すべきなのでしょうか。本記事では、セキュリティリスクの本質を「4つの基本要素」に分けてわかりやすく解説します。さらに、こうした観点に基づくセキュリティ対策の重要性や実際に成功している企業事例についても紹介します。これを読むことで、自社のDX推進におけるリスク管理のヒントを得られるでしょう。

証券業界のDXでは、システムのデジタル化によって大量のデータがリアルタイムでやり取りされるようになります。その一方で、サイバー攻撃や内部不正といったセキュリティ上のリスクも複雑化しています。こうした背景を踏まえ、情報セキュリティを守る上で基礎となるのが、「機密性」「完全性」「真正性」「責任追跡性」の4つの概念です。
ここでは、それぞれの意味と具体的なリスク、対策の考え方を解説します。
機密性とは、情報が許可された人物のみに閲覧されるよう保護されている状態を指します。証券業界では、顧客の個人情報、資産状況、取引履歴などが該当します。
この機密性が損なわれると、不正アクセスによって第三者に情報が流出し、信用失墜や法的責任に発展するおそれがあります。特にクラウド環境への移行や社外とのAPI連携が進む中では、情報の漏えいリスクが高まっているといえるでしょう。
対策としては、多要素認証や通信の暗号化、アクセス権限の細分化などが効果的です。社内でも業務範囲に応じて閲覧可能な情報を制限すると、不必要な情報接触を減らせるでしょう。
完全性は、情報が正確で改ざんされていない状態を維持することを意味します。金融取引ではわずかなデータの改変が損害につながるため、情報の整合性は重要です。
不正な手段で取引データが改ざんされると、顧客への誤報や不適切な投資判断につながるだけでなく内部監査や外部調査で深刻な問題として指摘されるリスクもあります。
そのため、情報の履歴管理やチェックサムの導入、変更履歴の自動記録といった技術的な対策が求められます。ログ情報をリアルタイムで監視すると、異常な更新が発生した場合に即座に検知できるでしょう。
真正性は、情報の発信者が確かに本人であるかどうか、またその情報が正当な手段で作成されたものであるかを保証する考え方です。
証券取引では、注文情報や取引記録が真正であるかどうかが常に問われます。なりすましによる不正注文や内部の不正取引などが発生した場合、企業の信頼性は揺らぎます。
このリスクを防ぐには電子署名やデジタル証明書を活用し、取引の発信元や書類の真正性を担保する必要があるでしょう。また社内システムへのアクセスには個別IDとパスワードだけでなく、生体認証などを併用するとなりすまし防止の精度が高まります。
責任追跡性とは、情報の作成・変更・削除に関わった人物やその操作の時間・内容を明確に記録し、追跡可能にする仕組みを指します。
この仕組みが整っていれば、万が一不正な操作や情報漏えいが起きた際に、原因の特定や責任の所在を迅速に明らかにできます。逆に記録が不十分だと、対応が後手に回り、損害の拡大や組織内の混乱を招く可能性があるのです。
対策としては、操作ログの保存、アクセス権の明確化、監査ツールの導入です。操作ごとの履歴を自動記録して定期的にレビューを行うことで、内部統制の強化にもつながるでしょう。

証券DXの推進は、業務効率化や利便性の向上といったメリットをもたらします。しかしその一方で、技術の導入によって新たなセキュリティリスクが顕在化しやすくなるのも事実です。これらのリスクは既存の業務プロセスやシステムとの相互作用によって複雑化し、従来の対策では対応しきれない場合があります。
ここでは証券DXにおいて特に生じやすい4つの代表的なセキュリティリスクについて、それぞれの背景と影響、さらに考えられる対処法を詳しく見ていきます。
証券業界では、多くの顧客データを保有・管理しています。氏名、住所、電話番号、口座情報、さらには過去の取引履歴まで、その情報の範囲は広範です。これらの個人情報が漏えいすれば金融犯罪に悪用されるリスクが高く、企業の信頼性にも深刻なダメージを与えかねません。
このリスクの主な原因は、情報管理体制の不備や外部との連携部分にあるセキュリティホールです。例えば、外部委託先とのデータ共有時に暗号化を施していないケースや退職者のアカウントが削除されずに残っている状態などが該当します。
対策としては、まずデータの分類と取り扱い基準を明確にすることです。その上で機密性の高い情報には厳格なアクセス制御を設け、不要なデータの削除の定期的な実施が求められます。加えてログ管理や内部監査の体制を強化すると、情報漏えいの兆候を早期に察知できるようになるでしょう。
インターネットを介した業務システムの利用が一般化する中、不正アクセスやなりすましによるシステム侵入のリスクも高まっています。攻撃者は巧妙なフィッシングメールやマルウェアを使い、従業員の認証情報を不正に入手しようとします。
このような攻撃を受けると社内システムへの不正ログインや情報の持ち出しが発生し、深刻な情報損失につながりかねません。さらに不正取引の実行など、直接的な金銭的被害が生じる場合もあります。
このリスクに対する有効な対策として、金融庁が出している「サイバーセキュリティに関するガイドライン」で紹介しているような多要素認証の導入があります。IDとパスワードに加えてスマートフォンによるワンタイムパスコードや顔認証を組み合わせることで、不正なログインを抑制できるでしょう。また認証ログのモニタリングによって、異常なアクセス傾向をリアルタイムで検知する体制を整えることも効果的です。
参考:金融庁
DXの一環としてクラウドサービスの活用は急速に広まっていますが、その導入において十分な整備がなされていないケースも少なくありません。クラウド環境では、設定ミスや権限管理の不備が思わぬセキュリティ事故を引き起こす原因となります。
例えば、公開範囲の設定を誤り、機密ファイルがインターネット上から誰でも閲覧可能な状態になってしまう事例は後を絶ちません。また、クラウド事業者との契約内容が不明確であると、事故発生時の責任の所在が不透明になる可能性もあります。
対処方法としては、まず利用するクラウドサービスに対してセキュリティポリシーとガイドラインを明確に設定し、社内で周知徹底する必要があります。その上で定期的に設定の見直しを実施し、セキュリティ監査や脆弱性診断も併用することが望ましいです。さらに、バックアップ体制を整えておくことで、万が一のデータ消失にも迅速に対応できるでしょう。
証券会社の多くは、長年にわたって使い続けてきた基幹系システム、いわゆるレガシーシステムを保有しています。DX推進時にはこれらの既存システムと新しいクラウド基盤やアプリケーションとの連携が求められますが、そこにセキュリティ上の落とし穴が潜んでいます。
レガシーシステムは設計時点で現在のサイバー脅威を想定していないため、セキュリティ機能が十分でないことが多いです。例えば、通信の暗号化が施されていなかったりサポートが終了しているソフトウェアが稼働していたりする状況では、外部からの攻撃を防ぎきれないでしょう。
この課題に対処するためには、まずレガシーシステムの現状を正確に把握する必要があります。その上で、システムの更新やセキュアなAPIゲートウェイの設置などを検討することが現実的な解決策となります。また、段階的なモダナイゼーションを進めながらシステム間の境界にファイアウォールやIDS(侵入検知システム)を導入し、防御の層を強化する戦略が有効です。
証券業界におけるDX推進は単なるデジタル技術の導入にとどまらず、企業の根幹をなす情報資産の保護体制を再構築する意味も持ちます。急速に進化するサイバー脅威に対応するには、従来型の境界防御では限界があります。特に金融業界は、常に攻撃の標的になりやすいため、先手を打ったセキュリティ対策が求められるためです。
ここでは、証券DXにおいて優先的に導入すべき7つの具体的なセキュリティ対策について、背景と導入のポイントを解説します。
まず注目すべきは、「ゼロトラスト」アーキテクチャの導入です。これは「誰も信用しない」という前提のもと、社内・社外を問わずすべてのアクセスを常に検証するセキュリティモデルです。
証券業界では顧客データや取引情報など、機密性の高い情報が日常的に扱われます。従来のようにネットワーク境界内を信頼する方式では、内部侵入者やリモートアクセスによる脅威を防ぎきれません。例えばVPNで社内ネットワークに入れた場合、その先のシステムに簡単にアクセスできてしまう構成では万一の侵害が被害に直結する可能性も高いでしょう。
そこでゼロトラストを導入すると、ユーザーごとのアクセス権を最小限に制御し、デバイスの状態やログイン位置、行動パターンも含めて動的な評価が可能になります。証券会社がゼロトラストを適用する際は、アイデンティティ管理とネットワークのセグメンテーションを連携させることが重要です。
次に重要なのが、多要素認証(MFA)の実装です。IDとパスワードだけではサイバー攻撃者にとって突破は容易であり、内部システムへの不正アクセスを許してしまいます。
例えばフィッシング攻撃やパスワードリスト型攻撃によってID情報が漏れた場合でも、MFAを導入していれば追加認証がなければアクセスは成立しません。証券業界のシステムでは、特に営業担当者やオペレーションスタッフが業務アプリケーションにアクセスする際にスマートフォンによるワンタイムコードや生体認証を併用することで、実効性の高い防御が可能になります。
導入に際してはユーザーの利便性とのバランスを考慮し、ログイン頻度や利用時間帯に応じた柔軟な運用設計が求められます。
多要素認証と併せて導入したいのが、シングルサインオン(SSO)です。これは1回のログインで複数の業務システムに安全にアクセスできる仕組みで、ユーザーの操作性を向上させながらセキュリティの一元管理を可能にします。
証券会社では、営業支援ツール、顧客管理システム、証券取引アプリケーションなど、複数のサービスを日常的に利用します。その都度IDとパスワードを入力させるのは煩雑な上、同一パスワードの使い回しが発生しやすくなります。
そこでSSOを導入してAzure ADやOktaなどの認証基盤と連携させれば、ユーザーは一度の認証で複数のシステムへスムーズにアクセスでき、しかもセッション管理やログ記録も中央で統制できるため、万一のインシデントにも迅速に対応できます。
DXの進行に伴い、システム間連携にはAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)が不可欠になります。ただしAPIは、その柔軟性ゆえに攻撃対象にもなりやすいという側面があるのです。
証券DXでは、取引システムと顧客ポータルサイト、CRMや外部金融サービスとの連携にAPIが多用されます。アクセス制限が不十分なAPIを通じて、第三者が不正に顧客データへアクセスする可能性もあるでしょう。
これを防ぐためには、APIゲートウェイを設置し、トークン認証やレート制限、暗号化通信を適用する必要があります。加えて、APIのバージョン管理や監査ログの保存などAPI全体のライフサイクルを管理する体制が求められます。
サイバー攻撃はより一層巧妙かつ高速になっており、インシデント発生後に対応するだけでは間に合わない時代です。そのため、リアルタイムでの監視体制を整えることが不可欠です。
例えば、SIEM(Security Information and Event Management)やSOAR(Security Orchestration, Automation and Response)を活用することで、ログを自動収集・分析し、異常な挙動を即座に検出できます。証券取引のように秒単位での正確性が求められる業界では、侵入の兆候をいかに早く見つけ、対処するかが被害の規模を左右します。
また、監視体制の構築には人材の育成と外部ベンダーとの協力が重要です。SOC(セキュリティ・オペレーション・センター)の導入や、24時間体制での対応準備も検討する必要があるでしょう。
クラウド環境はスケーラビリティやコスト面での利点がある一方、設定ミスや権限管理の不備による情報漏えいリスクも高まります。特にIaaSやPaaSを活用する証券業務においては、クラウドサービス提供者と利用企業の責任範囲が明確でないと想定外のトラブルを招きかねません。
例えば、ストレージの公開設定が意図せず「誰でもアクセス可」になっていた場合、重大な漏えいにつながることがあります。このような事故を防ぐためにCSPM(Cloud Security Posture Management)を導入し、構成の不備やセキュリティポリシー違反を継続的に検出するようにしましょう。
また、クラウド上での暗号化、IAM(Identity and Access Management)の適正化、バックアップの多重化も併せて実施すべきです。
最後に注目すべきなのが、内部不正に対する備えです。セキュリティ対策というと外部攻撃に目が向きがちですが、実際には内部関係者による情報漏えいや不正アクセスも多くの被害を生んでいます。
証券業界においては限られた担当者が機密データにアクセスできる体制がある一方、アクセス権の棚卸しや操作ログの精査が十分でない場合があります。退職者や異動者のアカウントが残存したままになっていると、悪意ある第三者に利用される可能性が出てくるでしょう。
そのため、RBAC(Role Based Access Control)による最小権限の原則を徹底し、業務内容に応じたアクセス権限を柔軟に設定する必要があります。また、データ操作の監査ログを継続的に確認し、不審な行動があれば即時に検知・遮断できる仕組みを整えておく必要があります。
証券DXを進める上で、セキュリティ対策との両立は欠かせません。実際に各証券会社が導入している具体的な取り組みは、今後の方針を考える上で大いに参考になります。
ここでは、実践的な3つの事例を紹介します。
ゼロトラストセキュリティの導入により、大和証券株式会社は社内外の境界を問わずあらゆるアクセスを検証対象としました。背景には、リモートワークの普及や多様化する働き方に対応するための必要性がありました。
この取り組みにより、従業員がどの端末からアクセスしてもアクセス権限の適正確認が行われ、セキュリティ事故の予防が徹底されました。特に、ネットワークの内部・外部を問わず一貫したセキュリティポリシーを適用できる点が成果です。
業務効率を保ちながら堅牢なセキュリティ体制を整備できたことは、今後の証券DXにおけるモデルケースとして注目されています。
参考:大和証券株式会社
株式会社SBI証券ではユーザーとサーバー間の通信を暗号化するため、EV SSL証明書を導入しました。ウェブブラウザのアドレスバーに企業名が表示されることで、利用者に対してサイトの信頼性を視覚的に伝える効果があるものです。
この取り組みは、フィッシング詐欺の抑止や中間者攻撃の防止につながっています。特にオンライン取引において通信の安全性は顧客信頼を左右するため、EV SSLの導入は顧客との接点における安心感の提供という意味でも極めて有効です。
ユーザー側の心理的な安心感を醸成しつつ具体的なセキュリティレベルも引き上げたこの事例は、証券会社にとって通信セキュリティの強化がいかに重要であるかを示しています。
参考:株式会社SBI証券
松井証券株式会社では早くから128ビットSSL暗号化通信を導入し、オンラインサービスの安全性を高めてきました。この方式は、クライアントとサーバー間のすべてのデータを暗号化し、第三者による情報の傍受を困難にします。
導入の背景には、個人投資家の利用増加に伴うサイバー攻撃リスクの上昇がありました。特に金融取引情報は漏えいによる影響が大きいため、通信経路の暗号化は基本対策として必須です。
このように、暗号化通信の強化によって安全な顧客体験を提供し、信頼性の高い取引プラットフォームを維持できています。
参考:松井証券株式会社

証券業界におけるDX推進は、競争力の維持や顧客満足度の向上に直結する重要な取り組みです。しかし、デジタル化が進むほどセキュリティリスクは多様化し、より複雑な対応が求められます。
例えば、本記事で紹介した事例のように、ゼロトラストや暗号化通信、多要素認証などの対策を適切に導入することで、DXとセキュリティを高い次元での両立が可能です。重要なのは、単なる技術導入に留まらず社内の運用体制や人材教育まで含めた包括的な視点で取り組むことです。
また、対応に不安がある場合や社内だけでは推進が難しいと感じる企業は、外部の知見を取り入れることも有効な手段の一つです。客観的な視点や実務に基づいたアドバイスを受けることで、より確実な前進が期待できるでしょう。
まずは本記事を参考にしながら、自社の状況に合ったセキュリティ対策とDX戦略を見直してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
