証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

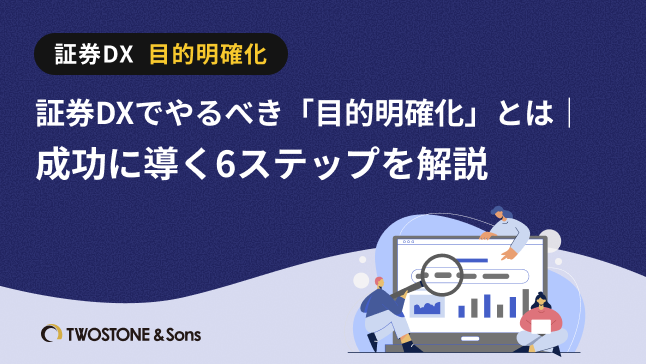
証券DXを成功に導くためには、目的の明確化が欠かせません。課題の分析からKPI設定、ロードマップ作成までの具体的なステップを詳しく解説し、実際の成功事例も紹介します。これにより、効果的なDX推進の方法が理解できる内容です。
証券業界におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)は、単なるITの導入ではなく、業務の抜本的な見直しと顧客体験の向上を目指す取り組みです。特にペーパーレス化の推進は業務効率化とコスト削減だけでなく、スピーディーな対応やセキュリティ向上といった観点からも注目されています。
一方で、DXに取り組みながらも具体的な成果を上げられない企業が少なくありません。原因の多くは、目的が曖昧なまま進めてしまう点にあります。
本記事では、証券DXを推進する中で目的が不明確な場合にどのような課題が生じるのかを深掘りし、避けるべきポイントを解説します。

デジタル化が叫ばれる中、証券会社におけるDXの推進はもはや避けて通れない道です。しかし推進の目的が曖昧なまま進めると、結果的に業務改善どころか現場の混乱やコストの増大を招くケースもあります。
ここでは、目的不明瞭なDX推進が招く具体的な問題を解説します。
多くの企業が陥る代表的な落とし穴は、DXの推進が目的化してしまうケースです。デジタル化を進めることそのものがゴールになり、業務改善や顧客価値の向上といった本来の目的が見失われがちです。
例えば、ペーパーレス化の一環として電子署名やクラウドストレージを導入しても、業務フローが変わらなければ紙の書類をスキャンして保存しているだけにとどまり、作業時間も短縮されません。これでは従来と何も変わらず、投資対効果も不透明になります。
DXを進める際には、まず「なぜDXが必要なのか」「何を変えたいのか」という課題意識を明確に持つ必要があります。その上でテクノロジーはあくまで手段であると捉え、目的との整合性を重視することが重要です。
目的が不明確な場合、組織全体でDXに向けた行動がとれなくなります。特に証券業界のように業務分担が細分化されている環境では、現場の理解と協力がなければデジタル化による改善効果は得られません。
例えばシステム部門がクラウド型CRMを導入しても、営業部門が従来の紙ベースの記録に固執すればツールの活用は進みません。結果としてDX施策が部分最適に終わり、全体最適が実現できないままです。
このような事態を避けるためには、組織横断的な理解と協働体制が不可欠です。現場の声を吸い上げる仕組みを整え、部門ごとの目的意識をすり合わせることで推進力のあるDXへとつなげられます。
目的が曖昧なDX施策では、進捗や成果を測るためのKPI(重要業績評価指標)やロードマップの設計が困難になります。数値化できない目標に向かって進むことは、目的地のわからない旅に出るようなものです。
例えば証券口座開設のデジタル化を目指す場合、「オンライン申請の完了率を〇%にする」「処理時間を〇日短縮する」など、具体的な指標がなければ施策の効果を可視化できません。また、関係部署にとっても改善へのモチベーションが生まれにくくなります。
明確なKPIを定めるには、まず業務プロセスの可視化が欠かせません。現状を把握し、どこにボトルネックがあるのかを分析することで、目指すべき方向とその評価方法が明確になります。
DX推進にあたっては社内だけで完結するケースは少なく、ベンダーや外部パートナーとの連携が不可欠です。しかし、目的が明確でなければ相手に対して具体的な要望や要件を提示できず、プロジェクトが迷走する可能性もあります。
例えば、デジタル証券の管理システムを導入する際に社内の業務フローや改善目的が定まっていなければ、ベンダー側も適切な設計や提案ができません。その結果、機能が現場ニーズと離れ、使い勝手の悪いツールになってしまうこともあります。
このような問題を回避するためには、社内で十分に課題と目的を共有して要件を具体化した上で外部と連携する姿勢が求められます。ベンダーを単なる委託先と考えるのではなく、共に価値を創出するパートナーとして関係性を構築することが重要です。
目的が不明瞭なままDXを進めると、実行後にどの程度効果があったかを測る指標が定まらず必要な改善や軌道修正が難しくなります。特に証券業務のように法規制や顧客対応の厳格さが求められる分野では、効果の検証が疎かになるとリスクも高まります。
例えばペーパーレス化によって帳票管理の手間を削減したい場合でも、定量的な成果が追えていなければ目標とのギャップが把握できません。さらに失敗の要因も曖昧になるため、次のアクションに反映させることが困難になります。
継続的なPDCAサイクルを回すには、最初から評価指標を定め、それに基づいたデータ収集と分析が必要です。また、定期的に見直す機会を設けることで、柔軟に方向修正しながらDXの質を高められます。
証券DXを成功に導くためには、取り組みの目的を明確にして組織全体で共有することが重要です。目的が曖昧なまま進めると方針がブレたり、現場の混乱を招いたりする可能性が高まるでしょう。では、目的を明確にするとはどういうことなのでしょうか。
ここでは、証券DXにおける代表的な目的と、その具体例を紹介します。
顧客接点のデジタル化は、証券会社の競争力を高める要素です。デジタルチャネルを通じた、スムーズでストレスのない体験の提供が求められています。
例えば、従来は店舗やコールセンターを経由して行っていた手続きや相談をスマートフォンアプリやオンラインチャットで完結できるようにする、という取り組みがあります。このような機能を導入することで顧客の利便性は高まり、満足度向上に直結するでしょう。またUX(ユーザーエクスペリエンス)デザインの観点から、見やすく操作しやすいインターフェースの構築も重要です。
顧客との接点をオンライン化するだけでなく、パーソナライズされた情報提供を行うことでより深い関係性を築くことが可能になります。取引履歴や関心銘柄に基づいた通知やレコメンドを活用した、顧客一人ひとりに寄り添った体験の提供がカギです。
証券業務には多くの手続きと確認作業が伴い、人的リソースを大きく消費します。その負担を軽減し、より高付加価値な業務に集中できる環境を整えるために、業務プロセスの効率化と自動化は不可欠です。
例えば、口座開設時の本人確認や書類チェックをAI-OCRやeKYC(電子的本人確認)を用いて自動化すると、作業のスピードと正確性が向上するでしょう。さらにRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用すると、定型業務を自動化して人的ミスの削減や業務時間の短縮が実現できます。
このような改革により、社員の業務負荷を軽減しながらサービス提供のスピードも向上します。結果として、顧客満足の向上にもつながる好循環が生まれます。
金融業界では、情報漏えいや不正アクセスといったリスクへの対策が常に求められています。特に証券業務では個人情報や取引情報などの機密性が高いため、セキュリティとコンプライアンスの強化はDX推進の中心的テーマです。
実際に今、ゼロトラストモデルを導入し、アクセス制御を厳格にする方法が注目されています。従来の境界型セキュリティから脱却し、すべてのアクセスに対して都度認証を行うアプローチによって内部不正や外部からの攻撃リスクを低減できます。
加えて、ログ管理の高度化や監査機能の強化により不正行為の兆候を早期に察知する体制を構築することが可能となります。さらに、電子帳簿保存法や金融商品取引法に準拠したシステム設計により、法令順守をシステム的に支援できます。
証券業界では、膨大な取引データや顧客行動データが日々蓄積されています。これらのデータを分析し、経営判断や戦略立案に活かすことがDXの目的の1つです。
例えば、BIツールやダッシュボードを用いてリアルタイムでKPIを可視化する仕組みを導入すれば、経営層は迅速な意思決定が可能になります。また、AIによる予測分析を活用することで市場動向を先取りしやすくなり、商品開発やマーケティング施策に有効なインサイトを得られます。
顧客ごとのライフステージや資産背景を基にしたパーソナライズ戦略の立案にも、データの活用が欠かせません。従来は感覚に頼っていた営業活動も、データドリブンな手法に切り替えることで成果の再現性が高まります。
デジタル化が進む中で、フィンテック企業との連携は証券業界に新たな可能性をもたらしています。既存の枠組みにとらわれずに柔軟な発想で新しいサービスを生み出すためには、外部の知見やテクノロジーを取り入れる姿勢が必要です。
例えば、ロボアドバイザーを活用した投資支援やブロックチェーンを用いたセキュリティトークンの発行など、証券ビジネスの在り方そのものを変えるイノベーションが次々と登場しています。こうした動きに迅速に対応し、協業やAPI連携による共創を進めることで、他社との差別化が可能になります。
また、モバイル証券やアプリ内での投資相談といった、ミレニアル世代やZ世代をターゲットにした新たなチャネルの構築も有望です。今後、証券会社は単なる金融商品提供者ではなく、顧客のライフプランを包括的に支援する存在としての進化が求められるでしょう。

証券業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を実効的に進めるには、単にデジタル化やIT化にとどまらず、戦略的な意図を持って取り組むことが不可欠です。そのカギとなるのが目的の明確化です。曖昧な目的設定では社内での理解も得られず、DXの価値を発揮できません。
ここでは目的を整理するためのヒントとなる5つの視点を紹介します。
最初に考えるべきは、なぜこのタイミングでDXに取り組む必要があるのかという視点です。この問いに明確に答えられるかどうかが、プロジェクトの推進力を左右します。
例えば、非対面チャネルへのニーズが高まっている背景には、コロナ禍を契機とした生活様式の変化や若年層の投資参入があります。市場の変化に即応するために今こそ業務改革が求められているという認識があれば、DXは単なるブームではなく戦略的課題として定義されるでしょう。
また、老朽化した基幹システムや紙中心の業務運用がボトルネックとなり、成長の足かせになっている場合、それを解消するタイミングとしてDXを位置付けることもできます。内外の要因を俯瞰しながら、自社にとっての「今」の意味を見極めることが重要です。
DXの目的の1つとして欠かせないのが、顧客体験(CX)の変革です。具体的に、どの顧客層に対して、どのような場面で、どのような新しい価値を提供したいのかを明確にしましょう。
例えば、アプリ上でのスムーズな取引導線を整える、顧客ごとの投資傾向を分析して最適な情報をレコメンドするなどタッチポイントを見直すことがCX改善の第一歩になります。変革の方向性が明確であれば、テクノロジーの選定やUI/UX設計にもブレが生じません。
また既存顧客だけでなく、将来的なターゲット層へのアプローチも視野に入れる必要があります。ミレニアル世代やZ世代など、デジタルネイティブ層の投資行動を念頭に置いたサービス設計が今後の競争優位性を左右します。
次に着目したいのは、現場業務の中でDXによって本質的に変えるべき領域の特定です。すべての業務を一度にデジタル化することは非現実的ですので、優先順位を明確にする必要があります。
例えば口座開設や本人確認といった手続きの自動化は、顧客・企業双方にとっての負担軽減につながります。また営業支援においては、顧客属性や行動履歴に基づくアプローチの最適化が有効です。これにより営業効率が向上し、提案の質も高まります。
さらに、バックオフィス業務の効率化も見逃せません。書類処理や監査対応などの定型業務をRPAやAIで自動化すると、専門性の高い分析や戦略業務にリソースを集中させられます。何を変えるべきかを明確にすることが、成功への近道です。
市場において存在感を発揮するためには、単なる模倣ではなく自社独自の強みを活かしたDX戦略が求められます。そのためには、競合との差別化につながる資産やノウハウを見極める視点が不可欠です。
例えば、長年蓄積してきた顧客データを活かした精緻な資産形成アドバイスや信頼性の高いコンサルティング力をデジタルで補完するアプローチは、他社にはない独自の価値になり得ます。テクノロジーそのものではなく、どう活かすかが差別化の要になります。
また地域密着型のビジネスを展開している場合、地元コミュニティとの連携を強化するデジタル施策を展開することで、他の大手証券会社との差異を明確にできるでしょう。自社らしさを再定義し、それをDXと融合させる視点が求められます。
最後に意識したいのが、DXによって企業が目指す未来像です。ただ便利になる、コストが下がるという表面的な効果だけでなく、DXが企業や顧客にもたらす価値の本質を描くことが重要です。
例えば、従来の金融機関という枠を超えて顧客の資産形成全体をサポートするライフパートナーへと進化する姿を掲げれば、DXの方向性に一貫性が生まれるでしょう。その未来像が明確であればあるほど経営陣から現場までの意識が統一され、プロジェクトの軸がぶれにくくなります。
さらに、未来像は単に理想論にとどまらず、中長期の数値目標やロードマップとして具体化することが望まれます。将来的にどのようなポジションを確立したいのか、そのためにどの機能を、どのフェーズで実現していくのか、逆算思考で描かれた未来像はDX推進の羅針盤となるのです。
証券DXに取り組む上で技術導入やシステム構築に目が向きがちですが、重要なのは「何を実現したいのか」という目的を明確にすることです。この目的が曖昧なままではプロジェクトは途中で迷走し、リソースの浪費につながります。
ここでは、DXの成功を左右する目的明確化のための具体的なステップを紹介します。
まず着手すべきは、自社の現状を正しく把握することです。現状を曖昧に捉えたままでは、DXの出発点も定まりません。
例えば、口座開設や取引にかかる時間が長い、カスタマーサポートの応対が属人的で一貫性に欠ける、といった具体的な課題がある場合、それを数値や事例で可視化すると課題の輪郭が明確になります。分析にあたっては、定量データだけでなく現場社員や顧客からのフィードバックを取り入れると実情が見えやすくなります。
このプロセスは、今後のDX施策が「どこを変えるのか」という基礎を築く上で欠かせません。
現状分析の結果を基に、DXで解決すべき課題を洗い出します。このステップでは、単なる問題の羅列ではなく課題を構造化しながら整理する視点が求められます。
例えば、「営業プロセスが非効率」という課題に対しては、どの部分が手作業に依存しているのか、情報共有に遅延が生じているのか、さらに細分化して把握する必要があります。単一の課題の背後には複数の要因が複雑に絡み合っていることが多いため、それらを分解して言語化する作業が効果的です。
また、洗い出された課題が単なる業務改善で済むのか、戦略レベルの変革が必要なのかを見極めることで、後続の目的設定が精緻になります。
次に行うべきは、洗い出した課題から導き出される目的に優先順位をつけることです。複数の目的を同時に追い求めるとDXの焦点がぼやけてしまい、現場での実行が難しくなります。
例えば、顧客接点の強化、業務の効率化、社員の働き方改革といった目的が並んでいる場合、どれを最も重視するかを決定しましょう。その優先順位は、経営戦略と整合性を取る形で整理すると納得感が得られやすくなります。
特に証券業界では、金融商品取引法の遵守や内部統制の堅牢性が求められるため、リスクとリターンのバランスを考慮した目的設定が欠かせません。明確な優先順位付けによって、施策の選定とリソース配分が効率的に行えるようになります。
目的が固まったら、それを定量的に測定できるようKPI(重要業績評価指標)を設定し、達成までのロードマップを描きます。ここで重要なのは、曖昧な指標ではなく進捗を客観的に判断できる具体的な数値目標を設定することです。
例えば、「口座開設のリードタイムを30%短縮する」「アクティブユーザー数を1年で1.5倍にする」など、期限と数値がセットになった目標が適切です。これにより、PDCAサイクルを回す際の基準が明確になります。
さらにロードマップの策定では、短期的な施策と中長期的な施策を組み合わせて計画します。初期フェーズでは既存業務のデジタル化を進め、中期には顧客接点の高度化、長期では新しいビジネスモデルの創出を目指すといった構成が現実的です。段階的なステップが整理されていれば、関係者の納得も得やすくなります。
DXは一部の部署や担当者だけで推進できるものではなく、社内外の多様なステークホルダーを巻き込む必要があります。そのためには、目的や方向性について関係者全体の合意を形成するプロセスが不可欠です。
例えば、経営陣には中長期的な収益性と戦略性を、現場には業務効率や負荷軽減といった即効性を、それぞれの視点からDXの価値を説明する工夫が必要です。ここで丁寧なコミュニケーションを怠ると誤解や抵抗が生まれ、プロジェクトの停滞につながります。
また、社外ステークホルダー、特にシステムベンダーやパートナー企業とも早い段階から連携を図り、共通のゴールを認識しておくことが後工程でのトラブルを回避する上で有効です。
最後のステップとして、定義された目的を組織全体に浸透させることが重要です。戦略やKPIを策定しただけでは不十分で、それが各部門の具体的な行動に反映されて初めてDXは進展します。
例えば、社内ポータルやワークショップを活用してDXの意義を共有したり、業務単位で小さな成功体験を積み上げる仕組みを導入したりすることで、目的の理解と定着が進むでしょう。トップダウンだけでなく現場からのボトムアップの発信も促すことで、DXが会社全体の動きとして認識されるようになります。
また、目的が変化していくことを前提に定期的な見直しと再定義の仕組みを設けましょう。時代の変化に応じて目的がアップデートされる柔軟性こそが、持続可能なDXのカギになります。
これまでに述べたように、DX成功のカギは単なるデジタル技術の導入ではなく、企業の目的を明確に定めてそれに基づいた戦略を展開することにあります。
ここでは実際に目的を明確化し、証券DXを成功に導いた代表的な企業の事例を紹介します。
野村ホールディングスは、顧客体験の質を向上させることを最大の目的にDXを推進しました。AIやビッグデータ解析を活用し、個々の顧客に最適化された金融商品やサービスの提案を実現したのです。これらを活用することで顧客の投資履歴や市場動向をリアルタイムに分析し、パーソナライズされたアドバイスを提供するシステムを導入しました。
この取り組みによって、顧客満足度の向上とリテンション率の改善に成功しています。野村HDは目的を「顧客視点のサービス向上」と明確化し、それに沿った技術活用を徹底することでDXを加速させました。
みずほフィナンシャルグループは、業務効率化を中心に据えたDX戦略を展開しています。AI技術を活用して大量のデータ処理や帳票作成などのルーティン業務を自動化し、社員の生産性向上を目指しました。実際に、生成系AIを活用した文書作成支援や問い合わせ対応の自動化により、業務の迅速化とミスの削減が達成されています。
目的を「効率的な業務プロセスの構築」と定めたことでDX推進のための優先課題が明確化され、投資対効果の高い施策に集中できました。みずほFGのケースは、目的設定がDXの成功に直結する好例です。
岡三証券グループは業務の効率化とミス削減を目指し、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用しました。人手による定型的な業務を自動化し、ヒューマンエラーの低減と業務時間の短縮を実現しています。実際に顧客情報の入力や照合作業をRPAに任せることで、社員はより高度な業務に集中できる環境が整いました。
この取り組みでは、「正確かつ迅速な業務遂行」がDX推進の核心的な目的として設定されていたため、ツール選定から導入まで一貫して戦略的に進められています。岡三証券の事例は、目的が現場の具体的な課題に根ざしている点が成功のポイントです。
参考:株式会社岡三証券グループ
アイザワ証券グループは、顧客情報の保護とシステムの安全性向上をDXの中心目的に据えました。サイバー攻撃が高度化する中で、セキュリティ対策の強化は不可欠です。実際に、最新の脅威検知システムや多要素認証の導入を推進し、顧客の信頼獲得に成功しました。
こうした取り組みでは単に技術を導入するだけでなく、セキュリティポリシーの見直しや社員教育も並行して行い、企業全体でのリスク意識を高めています。目的を「安心・安全の提供」と明確にしたことでDX施策の方向性が一貫し、顧客基盤の強化につながっています。
SBI証券は、個人投資家の資産形成支援を軸にマーケティングDXを推進しました。膨大な顧客データを活用して顧客ニーズを詳細に分析し、適切なタイミングで情報発信や商品提案を行う仕組みを構築しています。実際に、AIによる顧客の投資傾向分析に基づいて最適な金融商品のレコメンドを実施し、投資意欲の向上を促しました。
目的を「顧客の資産形成支援」と明確に定めたことで、マーケティング活動の精度が高まり、他社との差別化に成功しています。SBI証券の事例は、顧客価値を起点にしたDX戦略の典型です。
参考:株式会社SBI証券

証券業界のDXは、単にデジタル技術を取り入れるだけでは十分な成果を得られません。自社の目的や課題を慎重に見極め、目指すべきゴールを明確にすることが、成功への第一歩です。
こうした取り組みは短期間で完結するものではなく、綿密な計画の策定や社内外の関係者との連携、目的意識の共有といった地道な積み重ねが求められます。また、導入フェーズごとに柔軟な判断や調整も必要になるでしょう。
本記事で紹介した内容をもとに、DXに取り組む目的や必要なアプローチは何かを改めて見直してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
