証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

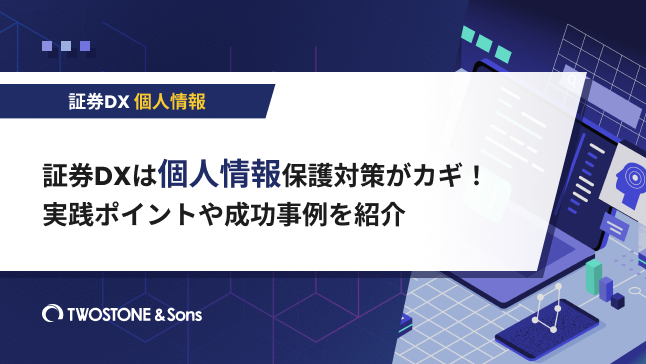
証券DXの推進において個人情報保護は重要です。具体的な先進企業の取り組みを基に、成功につながるポイントをわかりやすく解説しています。これを読めば、安全で信頼性の高いサービス構築のためのヒントが得られます。
証券DXが進む現代において、個人情報の保護は企業にとって避けて通れない重要な課題となっています。多くの企業がデジタル技術を活用して業務効率や顧客体験を向上させる中で、同時に個人情報漏えいのリスクも増大しているため、しっかりとした対策が不可欠です。
この記事では、証券DXにおける個人情報の特徴と関連法規について詳しく解説し、法律に準拠しながら安全にデータ活用を進めるためのポイントも紹介します。証券DXに取り組む方にとって、安心・安全なサービス提供のヒントを得られる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

証券DXでは、顧客の投資履歴や資産状況、取引内容といったセンシティブな個人情報を取り扱います。これらの情報は高度なプライバシーが求められ、誤った管理は信頼失墜や法的トラブルを招きかねません。特にリアルタイムで取引データを処理するシステムでは、多種多様なデータが膨大に流通するため、情報の管理体制に抜け漏れがないかを厳格に見直す必要があります。
例えば外部からの不正アクセスや内部の情報漏えいといったリスクを低減するためには、アクセス権限の細分化や暗号化技術の導入が効果的です。また、取引の透明性を保つため、ログの詳細な記録と監査体制の整備も重要なポイントとなります。こうした特徴を踏まえて、証券DXの個人情報は一般的な顧客情報以上に慎重な取り扱いが求められます。
証券業界のデジタルトランスフォーメーションにおいては、法律を遵守しつつ効果的なデータ活用を実現するバランスが求められます。
個人情報保護法では、個人情報の収集・利用に際して「利用目的の特定」と「本人の同意取得」が義務付けられており、特に顧客の属性データや取引履歴をマーケティングやリスク管理に活用する場合には、事前に明確な説明と同意を得る必要があります。また、取得した個人情報は漏えい・改ざん・不正アクセスから守るための「安全管理措置」が求められており、アクセス権限の適切な管理やログの記録、暗号化などの技術的・組織的な対応が必須です。
ここでは代表的な法律である個人情報保護法と金融商品取引法の概要を押さえ、具体的な対応策に役立てましょう。
参考:厚生労働省|個人情報保護
個人情報保護法は、顧客の個人情報を適切に管理し、無断利用や漏えいを防ぐための基本的な枠組みを示しています。証券DXの現場では、顧客の氏名や住所、連絡先に加え、投資履歴や金融資産に関するデータも個人情報として扱われます。法律に従い、これらのデータを収集・利用する際は利用目的を明確にし、本人の同意を得ることが必要です。
例えば、マーケティングやサービス改善のためにデータを活用する場合でもその範囲や内容を顧客に説明し、同意なしに情報を第三者に提供することはできません。
またデータの安全管理措置として、アクセス制御や情報の暗号化が義務付けられています。これにより、不正アクセスや情報漏えいのリスクを最小限に抑えられます。
参考:厚生労働省
金融商品取引法は、証券会社や金融機関が適正な取引を行うために必要なルールです。特に個人情報の取り扱いに関しては、顧客の資産保護や不正行為防止に重点が置かれています。例えば、顧客の取引情報や資産状況を含むデータは適切に管理されることが義務付けられており、不正利用や流出を防ぐための内部統制体制が求められています。
また法令遵守の観点から、定期的なリスク評価や監査の実施も必要です。証券DXによりデータの一元管理やリアルタイム分析が可能になる一方で、これらの法律を踏まえたセキュリティ対策を同時に進めなければなりません。不正取引を検知するためのシステム導入や、疑わしい取引に対する迅速な対応体制が求められます。
証券DXは業務効率の向上や顧客サービスの高度化を可能にしますが、個人情報対策を怠ると深刻なリスクが生じます。個人情報は企業の信用や経営基盤を支える重要な資産であり、適切な管理を行わなければ顧客や取引先からの信頼を失い、法的な問題に発展する恐れがあります。
特に、個人情報保護法や金融商品取引法に違反した場合には、行政指導や業務改善命令、さらには業務停止命令や過料などの厳しい行政処分・罰則が科される可能性があります。また、DXによりシステム化・クラウド化が進むなかで、サイバー攻撃や不正アクセス、システム障害などによる情報漏えいやサービス停止のリスクも無視できません。これらのインシデントは、単なる金銭的損失にとどまらず、企業のブランド価値の毀損や訴訟リスクにもつながります。
ここからは、具体的にどのようなリスクがあるかを詳しく見ていきます。
参考:IPA情報処理推進機構|情報セキュリティ10大脅威 2024
個人情報の漏えいは、顧客との信頼関係を根底から揺るがせるリスクです。証券DXで扱うデータは氏名や住所だけでなく、投資状況や取引履歴といった機密性の高い情報が含まれています。これらの情報が外部に流出すれば顧客は不安を感じ、サービスの利用を停止する可能性が高まりかねません。
実際に過去には、情報漏えいが発覚した金融機関が大規模な顧客離れを経験し、その後の回復に長期間を要した事例もあります。したがって日々の運用においては、厳格なアクセス管理や情報の暗号化といった対策を徹底する必要があります。漏えいを防ぐための教育や訓練も欠かせず、社員一人ひとりの意識向上が信頼維持のカギとなります。
個人情報保護に関する法律は厳格であり、違反が認められると行政処分や罰則が科されるリスクも無視できません。例えば個人情報保護法や金融商品取引法に違反した場合、金融庁や厚生労働省から業務改善命令や業務停止命令が出される可能性があります。これらの行政処分は企業の信用に大きなダメージを与え、事業継続にも影響を及ぼすことがあります。
また、違反内容が重大であれば罰金や刑事罰が科される場合もあるため、法律の遵守は経営リスクを回避する上で不可欠です。法律の専門家と連携して日々の業務が法令に適合しているかを定期的にチェックし、迅速な対応を行う体制を整えることが重要となります。
証券DXのシステムは高度なITインフラを基盤としていますが、その分サイバー攻撃やシステム障害のリスクがつきまといます。実際に、ランサムウェアやフィッシング攻撃によって重要データが暗号化されたり、不正アクセスによりシステムが停止したりするケースが増加しています。業務が一時的に停止すると、取引の遅延や顧客対応の混乱が生じるだけでなく、取引機会の損失やペナルティ発生につながる可能性もあります。
したがって、事前に多層的な防御策を導入し、万一の障害時には迅速に復旧できる体制を構築する必要があります。例えば、定期的なバックアップや脆弱性診断を実施し、インシデント対応マニュアルの整備も進めることが望ましいです。
個人情報の管理不備は企業の信用低下を招き、結果として顧客や取引先の離反を引き起こします。特に証券業界では信頼が重要な資産であり、情報漏えいや不正利用が明らかになると多くの顧客が他社へ移行する傾向にあります。競合他社が安全対策を強化している中で、自社の管理体制に不安を感じる顧客はサービスから離れ、収益基盤が弱まることは避けられません。
さらに取引先との取引停止や新規契約の減少も生じ、企業全体の業績に深刻な悪影響を及ぼします。こうした事態を防ぐには日常的にリスクを把握し、顧客ニーズに応じた透明性の高い情報管理を行うことが求められます。
個人情報漏えいが原因で損害が発生すると、顧客や取引先から損害賠償請求を受ける可能性があります。例えば、漏えいした情報が不正利用されて経済的被害が生じた場合、企業はその補償責任を負うことになります。賠償額が高額になるケースも多く、保険である程度のリスクヘッジは可能ですが、経営へのダメージは避けられません。さらに、裁判や和解にかかる時間とコストも企業負担となり、経営資源を消耗するでしょう。
したがって、事前にリスク管理体制を強化しトラブル発生時には速やかに対応できる準備が重要です。これに加え、損害賠償リスクを軽減するための法務体制や保険の見直しも検討すべきでしょう。
個人情報漏えいや法令違反が明るみに出ると、メディア報道を通じて社会的な注目を集め、ブランドイメージが著しく損なわれます。例えば、大規模な情報漏えい事件が報じられた企業は、一時的な信用喪失だけでなく、長期的にブランド価値が低下し続ける可能性もあります。ブランドの毀損は新規顧客の獲得を難しくし既存顧客の離脱を加速させるため、結果的に売上減少を招きます。
また、社会的責任を問われることで株価にも悪影響を与え、株主からの信頼を失う可能性もあります。こうした悪循環を防ぐために日頃から危機管理体制を整え、透明性の高い情報公開と迅速な対応を心掛けることが重要です。

証券DXの推進にあたり、個人情報管理は最優先の課題となります。適切な管理を実践しなければ、前述のようなリスクが現実のものとなるでしょう。
そこでここでは、証券DXにおいて具体的に実施すべき個人情報管理のポイントを順を追って解説します。これらの対策を体系的に導入することで情報漏えいを防ぎ、顧客や取引先からの信頼を維持しやすくなるでしょう。
個人情報の取り扱いで重要なのは、利用目的の明示と顧客からの同意取得です。透明性が確保されていなければ利用者は不安を抱き、信頼関係が崩れる可能性が高まります。実際に顧客の投資履歴を分析するためにデータを収集する際には、どのような目的で使用されるのかを具体的に説明し、同意を得る必要があります。
これにより、顧客は安心してサービスを利用できるようになり、企業側も法令遵守を果たせるのです。利用目的の記載は契約書やウェブサイトのプライバシーポリシーに盛り込み、わかりやすい言葉で説明することが大切です。
個人情報の収集は、必要最低限に抑えることがリスク軽減の基本です。多くのデータを集めすぎると管理の負担が増え、漏えいリスクも比例して高まります。例えば、顧客の本人確認に必要な情報に絞って収集し、不要なデータは取らない姿勢が求められます。こうした「データミニマリズム」の原則に従うことで、情報漏えいの被害範囲を最小限に抑えることが可能となります。
また、不要なデータは速やかに廃棄するか匿名化処理を施し、保管期間を定めて管理することが望ましいです。これにより、管理コストの削減と同時にセキュリティリスクの低減が可能となります。
個人情報にアクセスできる社員の範囲を厳格に限定し、必要な権限のみを付与することが不可欠です。例えば、営業担当者は顧客の基本情報にアクセスできても、詳細な取引履歴にはアクセスできないように制限を行うことが考えられます。
このようなアクセス制御を導入すると、内部からの情報漏えいリスクを減らせるでしょう。アクセス権限の設定は役職や業務内容に応じて細かく管理し、定期的に見直すことが求められます。
また、ログ管理システムを活用して誰がいつどの情報にアクセスしたかを記録し、不正利用が疑われる場合には速やかに調査ができる体制を構築する必要があります。
証券DXにおける個人情報の安全性を確保するためには、技術的な対策も欠かせません。特に、データの暗号化と多要素認証(MFA)は重要なセキュリティ強化手段となります。顧客情報を保管するサーバーやクラウド上のデータはすべて暗号化し、万が一の不正アクセス時に情報が読み取られないようにしましょう。
また社員や顧客がシステムにログインする際には、パスワードに加えてスマートフォンの認証コードなど複数の要素を用いる多要素認証を必須とすることで、不正ログインのリスクを抑えられます。これらの技術を適切に組み込むことで、セキュリティレベルを高められるのです。
個人情報管理の強化は一度の対策で終わりではありません。定期的なセキュリティ監査や脆弱性診断を通じてシステムの安全性を継続的に評価し、問題点を速やかに改善する仕組みが求められます。例えば、専門の外部機関に依頼してペネトレーションテストを実施し、不正侵入の可能性をチェックする方法があります。これにより、未知の脆弱性を早期に発見でき、攻撃に先手を打つことが可能になります。
また、内部監査も欠かさず行い、運用ルールの遵守状況やアクセス権限の適正を検証し、組織全体のセキュリティ体制を強化しましょう。こうしたPDCAサイクルを回すことで、継続的な安全対策が実現します。
証券DXの個人情報管理を組織として確実に推進するためには、個人情報保護責任者(CPO:Chief Privacy Officer)の設置が効果的です。CPOは個人情報保護に関する戦略立案や運用監督を担い、社内外の関係者と連携しながら管理体制の維持・改善に努めます。CPOが定期的に管理状況をレビューし、法令改正や新たなリスクに応じて対応策をアップデートすることで、柔軟かつ迅速な運用が可能となるのです。
さらにCPOが社内教育や啓発活動をリードすれば、社員の意識向上も促進されます。責任者の明確化はリスク対応の迅速化や組織全体の統制強化につながるため、積極的に設置しましょう。
参考:個人情報保護委員会|個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置 に関する事例集
どんなに優れたシステムを導入しても、社員の意識や知識が不足していると個人情報の漏えいリスクはなくなりません。証券DXの安全運用には、社員一人ひとりが情報セキュリティの重要性を理解し、適切な行動を取ることが不可欠です。
例えば、定期的に実施するセキュリティ研修やeラーニングを通じて、最新の脅威や対策方法を学ぶ機会を整えましょう。これにより、フィッシングメールへの対応やパスワード管理の徹底など、日常業務の中での具体的な注意点が浸透しやすくなります。
また、教育内容は階層別や職務別にカスタマイズし、実務に即した内容にすることで理解度が高まります。教育の効果を定期的に評価し、改善を続けることも重要です。
最後に、リスクアセスメントは証券DXにおける個人情報管理を継続的に改善する上で欠かせないプロセスです。リスクの特定、評価、対応策の検討を定期的に行い、現状の管理体制の弱点を明確にします。
例えば、新規システム導入や業務プロセスの変更に伴い、新たに発生するリスクを洗い出して対策を講じる必要があります。こうした評価は経営層を巻き込みながら実施し、対策の優先順位やリソース配分を効果的に行いましょう。
また、リスクアセスメントの結果は社内に共有し、全社員が現状認識を共有することで組織全体のリスク意識が高まります。定量的な評価指標を用いながらPDCAサイクルを回すことで、持続可能な情報管理体制の構築を目指せます。
証券業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中で、個人情報の保護は欠かせない課題となっています。実際に先進的な取り組みを行う企業の事例を参考にし、個人情報管理の具体的な方法や工夫を知ることが重要です。
ここでは、証券DXを推進しつつ個人情報保護を徹底している代表的な3社の取り組みを解説します。
東洋証券株式会社は統合管理ソフトウェアを導入して、個人情報を一元的かつ厳格に管理しています。この取り組みは、複数のシステムに散在していた情報を集約することで管理体制を強化し、リスクの可視化を可能にしました。
まず、統合管理ソフトウェアの導入によりデータの取扱状況をリアルタイムで監視できるようになりました。これにより、情報漏えいや不正アクセスの早期発見につながっています。
さらにこのソフトウェアはアクセス権限の細分化を実現し、担当者ごとに必要な情報だけにアクセスできるように設計されています。この権限管理の徹底により、社内からの情報漏えいリスクを減少させました。
こうしたシステム的な対策に加え、社員向けに定期的な個人情報保護の研修も実施し、技術面と人的面の両面からセキュリティを強化しています。結果として東洋証券は顧客の信頼を獲得し、安心して取引できる環境を提供し続けています。
参考:東洋証券株式会社
三菱UFJ eスマート証券株式会社は、証券DXの推進にあたりシステムの「サイジング」に注力しました。サイジングとはシステムの規模や処理能力を最適化することを指しますが、同時にセキュリティ要件を踏まえた設計も含まれています。
この企業は顧客データの安全性を第一に考え、システムの負荷状況やアクセス量を細かく分析しながら必要なリソースを確保しました。実際に、負荷が高まった際にもシステムが安定稼働するようにクラウド環境の活用と自動スケーリングを導入しています。
これにより不正アクセスやサービス停止のリスクを軽減し、個人情報を守るための防御層を厚くしました。特に多要素認証やIPアドレス制限など、アクセス管理の強化を実現した点が特徴的です。
さらに、定期的なセキュリティテストと脆弱性診断を実施し、システムの弱点を早期に発見し改善を図っています。こうした包括的なセキュリティ対策により、顧客が安心して利用できる証券サービスを提供しています。
野村證券株式会社は個人情報保護指針を全社的に可視化し、徹底したポリシーづくりを推進しています。このアプローチは、社員一人ひとりが個人情報保護の重要性を理解し、具体的な行動に移せる環境を整備することに焦点を当てています。
具体的には、個人情報の取扱いに関するルールやガイドラインを分かりやすく文書化し、イントラネットや研修での周知を強化しました。ここでは、どのような情報が個人情報に該当し、どのように管理すべきかが明確に示されています。
また、実際の業務に即したシナリオ形式の教育コンテンツを用意し、社員が現場で適切に対応できるよう工夫しました。これにより、意図しない情報漏えいの防止に成功しました。
参考:野村證券株式会社

証券DXは、業務の効率化や顧客サービスの向上に寄与する一方で、個人情報の保護にも十分な配慮が求められます。特にDXの進展により、取り扱うデータの量や範囲は拡大しており、適切な管理体制の構築がこれまで以上に重要視されています。
そのため、利用目的の明確化・必要最低限のデータ収集・アクセス権限の厳格な管理に加え、暗号化や多要素認証といった技術的な対策も欠かせないでしょう。これらの対応が不十分な場合、情報漏えいや顧客からの信頼喪失につながり、結果として企業の経営リスクを高める恐れがあります。
証券DXを推進する際は、利便性や業務効率の向上だけでなく、個人情報保護を含めたバランスの取れた取り組みが欠かせません。この記事を参考に、自社の対策が万全かどうか、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
