証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

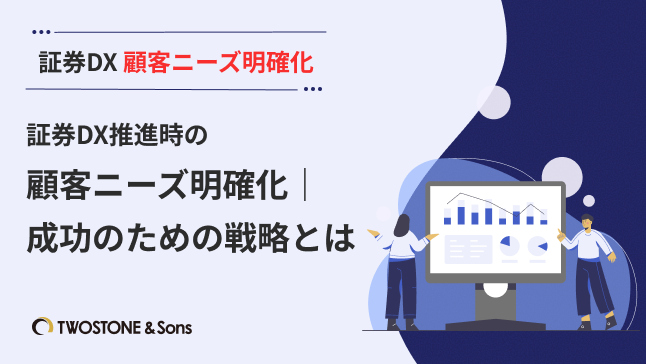
証券DXを成功に導くには、顧客ニーズ明確化が重要です。そのためには、定量・定性の両面から顧客情報を収集し、ペルソナや顧客体験マップを用いて行動や心理を可視化し、継続的な改善につなげる体制づくりが不可欠です。
近年、証券業界ではデジタル技術の導入が加速し、多くの企業が証券DXへの対応を進めています。しかしその一方で、顧客ニーズの把握が不十分なままではせっかくの取り組みも成果につながりにくくなります。特に個人情報を取り扱う金融業界においては信頼の獲得が不可欠であり、その基盤となるのが「顧客の本音を正しく理解する姿勢」です。
本記事では証券DXにおいて顧客ニーズを明確にする重要性を掘り下げ、社会背景から具体的な実践理由まで丁寧に解説します。最後まで読むと、DXを成功へ導くために何をすべきかが明確になるでしょう。

証券DXを推進する上で、多くの企業が直面するのが顧客ニーズの可視化です。業務の効率化や新サービスの展開を進めても、顧客が求める価値からずれていれば成果は得られません。
ここではまず、証券DXとは何か、そしてなぜ今その必要性が高まっているのかを整理します。
証券DXとは、証券業界におけるデジタルトランスフォーメーションのことを指します。具体的には、以下のような多岐にわたる技術革新を活用して、ビジネスモデルの変革を目指す取り組みです。
従来の紙ベースの業務から脱却し、顧客体験の質を向上させながら効率性と安全性の両立を図る点が特徴といえます。
これらの技術導入が進むことで顧客との接点はリアルからデジタルへと移行し、顧客行動のデータ収集が可能になります。収集した情報を活用するためにも、顧客が何を期待しているのかを正確に把握する姿勢が欠かせません。
証券DXが加速する背景には、いくつかの社会的な要因があります。
第一に、非対面取引の需要が急速に拡大している点が挙げられます。パンデミックを契機にオンラインでの資産運用ニーズが高まり、多くの証券会社がデジタル対応を迫られるようになりました。
次に、若年層を中心とした新たな投資層の登場です。スマートフォンを通じて金融商品にアクセスする層が増える中、従来の営業スタイルでは対応が難しくなりつつあります。さらに金融庁をはじめとする規制機関も、DXの推進によって透明性と利便性の向上を求めています。
特に2021年には、「金融商品取引契約に係る顧客交付書面の電子提供に関するガイドライン」が整備され、ペーパーレス化・電子交付の促進が正式に認められるなど、制度面でもデジタル化が後押しされています。また、金融庁が公表する「金融サービスのデジタライゼーションに関する方針」では、証券業務における顧客中心の業務運営や、データ活用の高度化といった方向性が明示されており、証券DXは政策的にも支援されています。
こうした背景の基で顧客の属性や行動パターンが多様化する中、顧客ニーズの精度を高めることが競争力の源泉になっています。
参考:金融庁|金融商品取引契約に係る顧客交付書面のデジタル化について
顧客ニーズを明確にすることは単なるサービス設計の一部ではなく、企業の成長戦略に直結する重要な要素です。ここではその理由を3つの観点から整理します。
顧客満足度を向上させるためには、顧客が求めているものと企業が提供する価値が一致していなければなりません。証券DXによって多様なサービス展開が可能になっても、顧客の本質的な期待とズレてしまえば利用継続にはつながらないためです。
例えば、初心者投資家が求めているのは手厚いサポートやわかりやすい操作性であるのに対し、企業が高機能な分析ツールに注力しても、かえって使いにくいと感じる可能性があります。このようなミスマッチを防ぐためには、ニーズの可視化と定期的な見直しが必要です。
顧客データを蓄積し分析することで、個別のニーズに応じた提案が可能になります。年齢・投資経験・リスク許容度・ライフステージなどに応じて適切なアプローチを取ることで、より深い信頼関係が生まれます。
これらのデータを効率的に活用できれば、リタイア目前の層には安定性を重視した商品提案、20代には積極的な成長型資産の紹介といった具合に、顧客像に合わせた情報提供が実現するでしょう。パーソナライズが進めば、企業へのロイヤリティも自然と高まります。
このようにデータドリブンのアプローチを成功させるには、前提として顧客ニーズの把握が不可欠です。表面的な属性情報ではなく、行動データや問い合わせ内容など多面的な情報から洞察を得る努力が求められます。
一度サービスを利用した顧客に継続的な価値を感じてもらうためには、ニーズに即した体験を提供し続ける必要があります。対応が的確であれば、顧客はその企業を「信頼できるパートナー」として捉えるようになるでしょう。
例えば、投資に不安を抱えている顧客に対して適時のサポートやリスクに配慮した提案があることで、心理的な安心感が生まれます。それにより離脱率を下げるとともに、家族や知人への紹介につながるケースもあります。
また顧客との信頼関係が構築されていれば、将来的なクロスセルや新サービスへの移行もスムーズです。信頼は数値で表せない資産であり、ニーズの理解と対応がその基盤となります。
証券DXを進める上で不可欠なのが、顧客の潜在ニーズを正確に把握する取り組みです。顕在化している要望に対応するだけではなく、本人すら明確に言語化していない期待や不安を読み取り、提案やサービスへと結びつける力が求められます。
ここでは、そのニーズを掘り起こすために有効な一般的なアプローチを紹介します。
潜在ニーズを探る出発点として、SNSや外部データの活用が挙げられます。証券会社の顧客が普段どのような情報に関心を持ち、何に悩みを感じているかを知るためには、リアルタイムなデジタルデータが有用です。
例えば、X(旧Twitter)やFacebook上で発信される投稿内容、検索エンジンのトレンドデータ、証券や投資関連の口コミサイトのレビューなどを分析することで、サービスに対する不満や要望の傾向が見えてきます。この情報を体系的に収集し、AIや自然言語処理技術を使って可視化すると、まだ顧客が口にしていないニーズを読み取る手がかりとなるでしょう。
こうした分析結果をマーケティング施策や商品設計に落とし込めば、先回りしてニーズに応える提案が可能になります。
顧客の意図を把握するには、営業現場のデータを積極的に活用する必要があります。営業支援ツール(SFA)やCRMを導入することで、担当者の経験に頼らず、組織全体で顧客の動向を管理できます。
例えば、以下の情報を一元的に把握すると、表面化していない課題に気付くチャンスが生まれるでしょう。
ある顧客が複数回にわたって特定の投資ジャンルの質問をしている場合、それは潜在的な関心の表れかもしれません。
こうした細かな兆候を見逃さず拾い上げる仕組みを構築すると、個別最適化された提案やサポートが実現でき、結果的に顧客との信頼構築にもつながります。
同じ商品やサービスでも、顧客によって価値の感じ方は異なります。そのため、属性やライフステージに応じてメッセージを最適化することが重要です。細分化によって、ターゲットごとの潜在ニーズを絞り込むことが可能になります。
例えば、20代の投資初心者と定年後の資産運用を意識するシニア層では、重視する要素が大きく異なります。前者にはリスクを抑えた商品や学びながら投資できるコンテンツ、後者には安定的なリターンや相続対策を軸とした提案が適しているでしょう。
セグメントごとの訴求軸を明確に設定するとターゲットの共感を得やすくなり、潜在的なニーズを表面化させやすくなります。また、無駄なコミュニケーションを減らすことにもつながり、効率的なマーケティングが可能になります。
テクノロジーの活用だけでなく、アナログな手法も見直す価値があります。中でも、ヒアリングの質を高めることは顧客の心の内を探る上で有効です。
例えば、商品説明や提案に終始するのではなく、顧客のライフプラン、将来への不安、過去の失敗体験などをじっくりと聞き出すことで、本人も気づいていないニーズが見えてくることがあります。そのためには信頼関係の構築が前提となるため、一方的な情報提供ではなく、双方向の対話を意識する必要があります。
また、定期的なヒアリングによって顧客の価値観や状況の変化にもいち早く対応できるようになるでしょう。これにより、サービスの柔軟性や対応力が高まり、顧客満足度の向上につながるのです。
最後に仮説に基づくアプローチの有効性を検証する手段として、ABテストの実施があります。これは、異なるメッセージやコンテンツを用意し、どちらがより良い反応を得られるかを比較する手法です。
例えば同じ投資信託を紹介する際に、「資産形成の第一歩」と伝えるパターンと、「老後の安心を支える選択」と伝えるパターンを用意し、それぞれの反応率を比較します。その結果どの訴求がより強く響いているかをデータで把握できるため、感覚に頼らず効果的な改善が可能になります。
ABテストの成果は、他の施策にも活かせます。一度有効と証明されたメッセージは、他の顧客セグメントやチャネルに展開することでより多くのニーズを掘り起こすきっかけになります。

証券業界が急速にデジタル化を進める中で、従来の対面営業だけでは把握できなかった顧客の行動や感情がテクノロジーを通じて可視化されるようになっています。とりわけ、DXの進展によって取得可能となった多様なデータを統合・分析することで、顧客の潜在的なニーズを捉えやすくなってきました。
ここでは、証券DXがどのように顧客理解を深め、サービス向上につながるかについて代表的な5つのアプローチを取り上げます。
CRM(顧客関係管理)システムは、証券会社にとって顧客情報を一元管理する基盤です。過去の取引履歴、面談記録、問い合わせ内容などを集約し、顧客ごとの投資傾向や興味関心を浮き彫りにする役割を果たします。
例えばある顧客が特定の投資商品に対して定期的に資料請求している場合、それは将来的な購入意欲の現れと考えられます。こうしたデータを担当者が見逃さずに把握できれば、タイミングを見た提案が可能になります。さらにCRM内の行動データを分析すれば、類似の顧客に対して同様のニーズを仮説立てることもできます。
CRMの活用は営業活動の質を高めるだけでなく、顧客との接点を最適化し、満足度向上にもつながる重要なステップです。
顧客の声を直接拾う手段として、アンケートの実施とそのデータ分析も有効です。特に、オンライン上で収集した回答を定量的に処理すれば、顧客層全体の傾向を把握しやすくなります。
例えば、投資に対する不安点や情報提供に対する満足度などの項目について意見を集めれば、商品設計やコンテンツ戦略に反映できる示唆が得られます。さらに、自由記述の回答を自然言語処理で分析すれば、数値化されにくいニーズも拾いやすくなるでしょう。
このようにアンケートは一見シンプルな手法でありながら、設問設計と分析手法を工夫することで、奥深いインサイトを得られます。短期的な反応を確認する目的だけでなく、中長期的な戦略にも活かせる点が魅力です。
現場の営業担当者が得る顧客のリアルな反応や要望は、ニーズの発掘において重要です。ただし属人的な情報にとどまってしまうと、組織全体で活用するのが難しくなります。そこで、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)の導入が効果を発揮します。
CDPは、社内に点在する顧客データを一元的に統合し、顧客ごとに包括的なプロフィールを構築できる仕組みです。営業日報や商談メモなどの定性情報も取り込めば、担当者の気づきをデータ化し組織全体で共有可能になります。
例えば、複数の営業担当者が同一の顧客に「保守的な姿勢」「長期運用志向」といった共通認識を持っていた場合、それは個別の感覚ではなく、確度の高いインサイトとして捉えるべきです。このように定性的なフィードバックを構造化することで、企業としての対応力を高められます。
顧客の属性や行動パターンに応じた情報提供を自動化する手段として、AIのパーソナライゼーション技術は有効です。特に、証券業界では情報の過多が顧客の意思決定を妨げる要因になることが多く、適切な情報を適切なタイミングで届ける工夫が求められます。
例えば、AIが顧客の閲覧履歴や取引傾向を基に興味を持ちそうな金融商品の情報を自動配信する仕組みを構築すれば、営業機会の創出につながるでしょう。また、個別のリスク許容度に応じたポートフォリオ提案も可能になります。
AIによるパーソナライズは一人ひとりに対する理解の深度を高めると同時に、人的リソースの効率化にも貢献します。無理に全顧客へ同一の施策を展開するのではなく、より精度の高いアプローチを実現できる点が魅力です。
顧客の意思決定の背景には、さまざまな行動パターンがあります。これを定量的に捉えるために、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールの活用が注目されています。BIツールは、取引履歴やアクセスログ、キャンペーンの反応など多様なデータを可視化・分析するための基盤になるのです。
例えば特定のキャンペーンに反応した顧客の特徴を分析すれば、今後どのような属性の顧客が同様の反応を示すかを予測できます。また、ログイン頻度や特定ページの閲覧数が高い顧客に対しては、能動的なアプローチをかける判断材料になるでしょう。
BIツールの利点は、直感に頼らずにデータに基づいた判断ができる点にあります。定期的なダッシュボードのモニタリングによって顧客の動向をリアルタイムで把握し、施策の効果検証にも役立てられます。
顧客理解の深化は単なるデータ分析だけでなく、実際の施策へとつなげる運用力によって成果が現れます。証券各社はDX推進を通じてそれぞれ独自の手法で顧客ニーズに応えており、その取り組みは実務に活かせるヒントにあふれています。
ここでは、先進的な事例を3社紹介し、実際にどのように顧客中心のアプローチが成果を上げているかを見ていきましょう。
大和証券グループでは、AIを活用した顧客対応モデルの高度化に取り組んでいます。AIが過去の取引履歴やチャネル別の接点データを分析し、顧客が次にどのようなアクションを起こすかを予測する仕組みが整備されました。
例えば特定の銘柄に関心を示した顧客が数日以内に投資行動へ移る傾向がある場合、AIはその兆候を検出し、担当者へアラートを出します。これにより、最適なタイミングで商品提案が可能となり、成約率の向上に直結しています。
さらにAIモデルの運用はブラックボックスにならないよう、ガバナンス体制も強化されています。公平性や透明性を担保しながら、個々の顧客に合わせたサービスを実現する姿勢が評価されています。
参考:大和証券グループ本社
マネックス証券では、顧客の声を迅速にサービス改善へ反映する体制が整っています。特に力を入れているのが、リアルタイムのフィードバック収集とそれに基づくユーザーエクスペリエンス(UX)の最適化です。
例えばログイン後の画面に設置された意見投稿フォームから、ユーザーは簡単に機能に対する感想や要望を伝えられます。その情報は即時に社内の分析チームへ共有され、改善案の検討が始まります。
実際に、注文画面のレイアウトや分析ツールの項目配置といった細かな修正が短期間で実施されており、ユーザーの満足度向上につながっています。こうした小さな改善を積み重ねる姿勢が、信頼感とブランド価値の向上を支えています。
参考:マネックス証券株式会社
楽天証券はユーザーインターフェース(UI)の定期的な見直しにより、投資初心者の定着と継続的な利用を促進しています。ITに不慣れな層でも直感的に操作できるよう、情報設計や導線の最適化が繰り返し実施されています。
例えば、スマートフォンアプリのホーム画面を刷新し最もよく使われる機能を優先的に配置することで、ユーザーのストレスを軽減しました。加えて、投資に関する解説コンテンツを初心者向けに分かりやすく表示する仕組みも導入され、学習と実践の両面から利用継続を支援しています。
また、UI改善の判断にはユーザーデータとABテスト結果が活用され、改善の成果を数値で検証する仕組みも整っています。こうした地道な努力が、ユーザーの信頼獲得と市場シェアの拡大へとつながっています。
参考:楽天証券株式会社
顧客ニーズを正確に把握して終わりではありません。証券業界ではその理解を出発点として、長期にわたり信頼を育む関係性の構築が必要です。特に資産形成層の拡大が続く中で、個別の状況に応じた対応が求められています。
ここでは、顧客との関係を持続的に深めていくための具体的なアプローチを紹介します。
資産形成を目的とする層は投資リテラシーや金融商品への関心が徐々に変化していくため、その変化を見越した継続的なアプローチがカギとなります。
例えば、若年層に対しては「つみたてNISA」や「iDeCo」など、少額から始められる制度を起点にした提案が有効です。中長期での資産形成シミュレーションを提示すると、自分事として捉えてもらいやすくなります。
定期的な情報提供やポートフォリオの見直し支援に加えて、ライフステージの変化に合わせたコミュニケーションを継続することがリテンション率の向上につながります。テンプレート化された提案ではなく、段階に応じた柔軟な支援設計が求められます。
参考:金融庁|つみたてNISAについて
参考:iDeCo|iDeCo公式サイト
顧客の人生には、就職・結婚・出産・住宅購入・退職などさまざまなライフイベントが訪れます。それぞれのタイミングで必要となる金融ニーズを把握し、適切なサービスを準備しておくことが顧客満足の向上につながります。
例えば子どもの誕生を機に学資保険や教育資金の積立を検討する家庭には、将来の教育費と運用プランをセットで提示するのが有効です。また、退職期には資産の取り崩しや相続対策といった新たな関心が生まれるでしょう。
こうしたイベントを契機としたタッチポイントの設計により、「この証券会社なら、将来のことも安心して相談できる」という信頼感が育ちます。
顧客の声を継続的に拾い上げるためには、定量的な指標としてNPS(ネット・プロモーター・スコア)の導入が効果的です。NPSは「自社を他人に勧めたいか」という質問を軸に、ロイヤルティを測定できる仕組みです。
例えば、顧客が証券口座を開設して半年後にNPS調査を行うことで、初期体験の満足度を把握できます。加えて、口座維持期間が長い顧客を対象に定期的な調査を行えば、長期にわたる関係性の質の変化も捉えやすくなります。
NPSの結果は単なるスコアにとどまらず、推奨者・中立者・批判者に分類し、それぞれに対してアクションを最適化することが重要です。特に批判者の声はサービス改善の起点となるため、フィードバック体制の整備と迅速な対応が成果に直結します。
資産運用は一度きりではなく、継続的な意思決定が必要な分野です。そのため、長期的な視点で顧客を育成する戦略を立てることが、関係性の深化に不可欠です。
例えば、投資初心者には基礎講座や実践ワークショップを通じて金融リテラシーを高める支援が求められるでしょう。一方、中級者には相場変動への対応力を養う分析コンテンツが喜ばれます。
また、保有資産や取引履歴を元にしたカスタマイズコンテンツの提供やライフプランに応じた投資方針の再設計支援が行えると、顧客の学びと行動が一致する機会が増えます。短期的な成果を追うのではなく、顧客の金融自立をサポートする姿勢が信頼関係の土台になるのです。
近年では、サービスを提供する側と受ける側という二項対立ではなく、共に創り上げていく「共創」の視点が注目されています。顧客と長く良好な関係を築くには、意見を反映できるプラットフォームの存在が効果を発揮するでしょう
例えば、アプリの機能改善に関する要望を募るオンラインフォーラムやサービス設計に顧客を巻き込むユーザー委員会などがその一例です。こうした取り組みにより、顧客は自身がサービスの一部であると感じやすくなります。
また、投資家コミュニティの形成も有効です。同じ関心を持つ仲間とのつながりが顧客のロイヤルティを高め、自社サービスを起点とした情報の循環が生まれます。企業が一方的にリードするのではなく、顧客とともに市場やサービスを育てていく文化を醸成することが持続的な関係性の強化につながります。
顧客との長期的な信頼関係を築くには、顧客理解を起点としたDX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠です。特に証券業界では、顧客ごとの投資目的や金融リテラシーの差を踏まえたデジタル施策が求められます。
ここでは、顧客ニーズを正確に捉えるための証券DXの具体的な推進手順を解説します。
まず取り組むべきは、定量的な顧客データの収集と分析です。アクセスログ、取引履歴、閲覧ページ、クリック数など顧客の行動を数値で可視化することで、潜在的な関心や行動パターンが見えてきます。
例えば、特定の銘柄情報ページに頻繁にアクセスしているが実際の購入には至っていない場合、その顧客は情報不足やリスクに対する不安を感じている可能性があります。このようなデータに基づいてより具体的なコンテンツやレコメンドの出し分けを行うことが、最適な顧客体験の提供につながるのです。
また、AIやBIツールを活用すればセグメントごとの特徴を抽出しやすくなり、効果的なマーケティング戦略の土台が整います。
数値では捉えきれない顧客心理や背景を理解するには、直接的なヒアリングが欠かせません。アンケート、インタビュー、カスタマーサポート対応などの接点を通じて、本音や潜在ニーズに触れることが可能です。
例えばある顧客が「アプリの使い方がわかりにくい」と感じていた場合、操作性の改善が重要課題になります。表面的な不満の裏側にある「自己解決できない不安」などを読み解く視点が必要です。
このプロセスではヒアリング結果を属人的に扱うのではなく、社内で横展開できるようフォーマットを統一し、全体課題として共有することがDX推進の基盤となります。
データ分析とヒアリングから得られた情報を基に、代表的な顧客像(ペルソナ)を設定しましょう。ペルソナは、年齢、職業、投資経験、資産規模、価値観などを具体的に描写すると、マーケティングやUX設計の軸になります。
例えば、「30代前半・未婚・年収600万円・投資歴1年未満で将来のために資産形成を意識している女性」など、詳細なペルソナを設定すれば、彼女が求める情報、使いやすい導線、適した商品構成などが見えてきます。
このような顧客視点を全社で共有すると、開発・営業・サポートの施策が統一され、組織全体が「誰のためのDXなのか」を意識しながら動けるようになるでしょう。
顧客接点で生じる課題を整理するには、顧客体験マップ(CXマップ)の作成が効果的です。これは、顧客が自社サービスをどのように知り、接し、利用し、評価していくかを時系列で可視化するフレームワークです。
例えば、「アプリで口座開設→初回入金→運用開始→定期レポート確認→問い合わせ」といったプロセスにおいて、どこで離脱が発生しやすいかを特定します。その上で、離脱要因となる課題を明確にし、対応策を設計すると、CXの質が向上するのです。
また、CXマップを定期的に更新すると、変化する顧客行動にも柔軟に対応できる体制が整うでしょう。
DXは一度推進を始めて終わるものではありません。改善のサイクルを内在化させるフィードバックループの構築が不可欠です。顧客から得たフィードバックを分析し、課題の仮説検証を行い、改善を実装した上で再度ユーザーに評価してもらう循環が重要です。
例えば、あるアプリ機能の改善案をABテストで実施し、エンゲージメント率や離脱率に変化があったかを比較すると、施策の有効性を検証できるでしょう。その結果に応じて次のアクションを調整することで、PDCAサイクルが機能し始めます。
この継続的な改善の文化が社内に根づけば、DXの進化は止まらず顧客にとって価値のある体験が積み重なっていきます。

証券DXの本質はテクノロジーの導入に留まらず、顧客理解を軸とした持続的な価値提供にあります。データと対話を両輪として顧客の期待に応え、サービス全体を最適化していく姿勢が他社との差別化を生み出すでしょう。
定量分析による行動把握、ヒアリングを通じた内面の理解、そしてその結果から導き出すペルソナ設計と体験マップは、すべてが一貫した顧客起点のDX戦略です。さらに、フィードバックループを組み込み、施策の有効性を定期的に検証することで顧客に寄り添い続けることが可能になります。
まずは本記事の内容を参考に、顧客ニーズを整理してみてください。そのうえで、具体的かつ実行可能な戦略を構築すれば、証券DXを着実に前進させることができるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
