証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

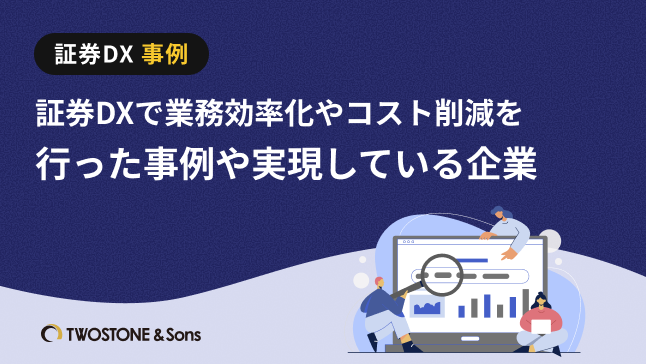
証券業界におけるDX推進にはAIやRPA、クラウドといった先端技術の導入が欠かせません。この記事では業務効率化や意思決定の迅速化を実現した成功事例を基に、具体的な活用方法や導入のポイントを詳しくご紹介しています。
急速なデジタル化の波は、証券業界にも変革をもたらしています。これまで紙ベースや手作業で行われていた業務の多くが、今やデジタル技術によって効率化されつつあるのです。
しかし、ただ新しいシステムを導入するだけでは意味がありません。企業全体としての運用体制や目的を明確にしなければ、コスト削減にも収益向上にもつながりにくいのが現実です。証券DXとは単なるIT化ではなく、業務プロセスの抜本的な見直しを伴う取り組みです。
この記事では、証券業界におけるDXの必要性を整理した上で実際に社内業務の改善を実現し、成果を上げている企業の事例を紹介します。ここで説明するシステムの内容や背景、それによって得られた効果までの詳細な解説を自社の課題解決のヒントとして活用いただけるはずです。

証券業界では取引の高度化や多様化、顧客ニーズの変化に対応するために業務のデジタル化が急務となっています。金融庁による規制強化や市場のボラティリティ増加など、外部環境の変化も業界全体にプレッシャーをかけています。このような背景から従来のアナログな業務フローでは効率性や正確性、そしてスピードが求められる現代の市場に対応しきれないという課題が顕在化しているのです。
さらに、コスト構造の見直しも避けては通れません。限られた人員で高いパフォーマンスを発揮し、かつミスを最小限に抑えるにはAIやRPA、ブロックチェーンといった先進技術の活用が不可欠です。証券DXはこうした課題を解消し、業務全体の質を向上させるための有効な手段となり得ます。
証券DXを効果的に推進することで、実際に業務の効率化やコスト削減を実現している企業は増加傾向にあります。
ここで紹介するのは、特に注目されている3つの企業事例です。どの企業も、それぞれの課題に応じた戦略的なDXを推進しています。
野村ホールディングスでは業務のなかでも煩雑になりやすい契約書管理の効率化を目指し、電子契約システム「CONTRACTHUB」を導入しました。
これまで紙ベースで運用されていた契約書類は保管場所の確保や情報検索の手間が大きく、業務効率を阻害する要因となっていたのですが、「CONTRACTHUB」の活用により契約文書の電子化が実現され、社内での情報共有や検索が迅速になっただけでなくセキュリティ面でも強化が図られています。
例えばアクセス権限の細かな設定やログ管理によって、内部統制の強化にもつながっています。この取り組みにより時間とコストの両面で効率が向上し、業務の生産性が高まりました。
岡三証券グループでは事務業務の集約と、自動化による効率化に注力しています。具体的に進められたのは事務集中センターの新設、及びRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入です。これにより従来各支店で個別に対応していた処理を一本化し、標準化された業務フローのもとで作業の質を均一に保つことが可能となりました。
RPAの導入は特に、定型業務の削減に貢献しています。例えば日次の報告資料作成や帳票の転記作業など、人の手を介していた作業を自動化することで人的ミスの削減と作業スピードの向上が同時に実現されました。その結果として社員はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が底上げされています。
参考:株式会社岡三証券グループ
丸井グループでは、証券事業の一環として個人投資家向けに新たな投資手法を提供するため、ブロックチェーン技術を活用したデジタル債を導入しました。これは応援したい企業や団体に対して個人が少額から投資できる新しいスキームであり、従来の金融商品とは異なる付加価値を提供するものです。
ブロックチェーンの技術によって投資履歴や契約情報の改ざんリスクが軽減され、取引の透明性が確保されました。また発行や流通にかかる事務処理の簡素化が図られたため、業務効率も改善されています。
例えば従来必要だった書類のやりとりが不要になり、コスト削減に寄与しました。投資家にとっても利便性が向上し、企業にとっても新たな資金調達手段として注目されています。
参考:株式会社丸井グループ
証券業界では現在、顧客との接点やサポート体制を抜本的に見直す必要に迫られています。特にデジタルネイティブ世代の台頭によりオンラインで完結する利便性やスピード、パーソナライズされた対応が求められるようになっています。
ここでは顧客対応を中心にDXを推進し、実際に成果を上げた企業の事例を紹介します。
野村ホールディングスはOMO(Online Merges with Offline)戦略を軸に、顧客接点の多様化を進めています。具体的には、リアル店舗とオンラインチャネルの融合によってこれまでアプローチが難しかった若年層や地方在住の顧客にもサービスを届ける、といった仕組みを構築しました。
この戦略により物理的な制限に縛られない柔軟な営業が可能となり、接点の拡大に成功しています。例えば顧客がスマートフォンで取引を行いながら、必要に応じて近隣店舗やコールセンターでサポートを受けられる環境が整えられています。
結果として既存顧客のロイヤルティを維持しながら、新たな層へのリーチを実現しました。
みずほ証券では顧客からの問い合わせ対応にAI音声ボットを導入し、コールセンター業務の効率化を進めています。従来は人手に頼る体制だったため、繁忙期には待ち時間の増加や応対品質のばらつきが課題となっていました。
AIを活用することでよくある問い合わせに対しては自動で即時対応が可能となり、オペレーターは複雑な相談対応に集中できる体制が整いました。例えば株価照会や手数料に関する質問はボイスボットが自動処理し、個別相談は専門担当者が対応するといった役割分担が行われています。
この取り組みによって、顧客満足度と業務生産性の双方が向上しました。
参考:みずほ証券株式会社
SBI証券は、AIによる資産運用アドバイスを提供する「ROBOPRO for SBI証券」を導入しました。このサービスは相場予測アルゴリズムを搭載したロボアドバイザーであり、データドリブンな投資戦略をサポートします。
これは世界経済の各種指標を基に市場動向を予測し、最適なポートフォリオを提案する仕組みです。例えば市場のボラティリティが高まる局面では、リスク回避型の資産配分に自動で調整する機能を備えています。これにより投資初心者や時間の取れない個人投資家でも、納得感のある運用ができるようになりました。
参考:株式会社SBI証券
アイザワ証券では口座開設時の本人確認プロセスにおいて、デジタル身分証システムを導入しました。従来の郵送や対面による確認は手間と時間がかかり、離脱率の高さが問題視されていました。
この新システムでは、スマートフォンのカメラで本人の顔と運転免許証などの身分証を撮影し、AIが自動で照合する方式が採用されています。
例えば夜間や休日でも本人確認が即時に完了し、最短当日中に口座開設が完了するケースも確認され始めています。この変革により顧客の利便性が向上し、成約率の改善にも寄与しています。
参考:アイザワ証券株式会社
東海東京フィナンシャル・ホールディングスは営業活動の最適化を図るため、AIによる顧客分析システムを導入しました。このシステムは過去の取引履歴や行動ログを基に、顧客ごとの購入意欲や関心度を数値化します。
例えば頻繁に特定の銘柄をチェックしている顧客には関連する金融商品の案内を自動で行うなど、パーソナライズされた営業が可能となりました。営業担当者はこのスコアを基にアプローチ先を選定できるため、効率的な訪問・提案活動が実現しています。
結果として、営業成約率の上昇や業務の無駄の削減につながっています。
りそなホールディングスは顧客の利便性向上を目指し、証券関連手続きをスマートフォンアプリ内で完結できるように整備しました。これにより取引や残高確認、書類提出といった一連の業務がオンラインで完了するようになりました。
例えば従来は店頭で行っていた住所変更手続きも、アプリ上で本人確認と併せて実行できるようになっています。これによって働き世代や地方在住者など多忙な顧客層にも対応可能となり、利用率の向上と顧客満足度の改善が見られました。

証券DXの進展は業務効率化を推進する上で、不可欠な要素です。特に既存の業務フローにデジタル技術を取り入れることで人的負荷を軽減し、業務のスピードと正確性を両立させる動きが加速しています。
ここでは各社の取り組みから導き出された、業務効率化のカギとなる要素を解説します。
業務プロセスを見直し自動化と標準化を進めることはDXの第一歩といえるでしょう。これは属人化された作業が多い証券業務では、業務効率にばらつきが発生するためです。
例えばAIによる音声自動応答システムを導入したみずほ証券の事例では、問い合わせ対応の平均応答時間を短縮することに成功しました。これによりオペレーターの負担が軽減され、より高度な対応に集中できる環境が整備されています。
このような自動化の導入は日常的な業務の正確性を高めるだけでなく、品質管理にも好影響を及ぼします。継続的に業務標準を整備する姿勢が、DXを成功させるカギとなるのです。
次に挙げられるのが、紙ベースの手続きを廃止し、情報管理をデジタルで完結させる取り組みです。紙媒体を介さないことで保存・検索・共有が効率化され、業務スピードが向上します。
例えばアイザワ証券が導入した「デジタル身分証システム」は、口座開設時の本人確認作業をオンラインで完結させています。これにより窓口での書類処理が不要になり、手続き時間の短縮を実現しました。
このようにペーパーレス化は単なる業務効率化だけでなく、セキュリティやコンプライアンス面でも効果を発揮します。将来的な拡張性や他システムとの連携も視野に入れ、導入を進めるべきです。
業務効率化をさらに進めるには、レガシーシステムからの脱却が避けて通れません。そのカギを握るのがクラウド化とAPI連携です。
例えばSBI証券では、AIを活用した資産運用支援サービス「ROBOPRO」をAPI経由で複数システムと連携させています。これにより新サービスの展開スピードを向上させ、迅速な顧客対応が可能となりました。
クラウド環境を活用すれば拡張性と柔軟性を確保しつつ、コストパフォーマンスにも優れたインフラ整備が実現できます。APIによるデータ連携を前提に設計されたシステムは、変化の激しい市場環境においても迅速な対応が可能です。
DXの進展によって蓄積される膨大なデータを活用することで、迅速かつ的確な意思決定が実現します。定量的なデータ分析に基づく判断は、従来の経験則に頼る業務フローに革新をもたらすことでしょう。
例えば、東海東京フィナンシャル・ホールディングスでは顧客の購買行動をAIで分析し、商品提案の精度を高めています。この仕組みは営業担当者の直感だけに頼る提案方法から脱却し、データドリブンな営業体制へと転換しています。
データを収集・分析するだけではなく、それをビジネスに応用する仕組みを構築することが重要です。ダッシュボードやBIツールの活用によりリアルタイムで状況を把握し、素早い判断を下せるようになります。
証券業界においては業務効率と同時にコンプライアンスやリスクマネジメントの強化も求められています。これらを高い水準で維持するためにも、DXは有効な手段となるのです。
例えばりそなホールディングスでは、アプリ内で取引や本人確認、手続き完了までを一貫して行えるように整備しています。これにより不正防止やトレーサビリティの確保がしやすくなり、監査対応もスムーズになりました。
業務フローにセキュリティと監視機能を組み込むことで透明性と信頼性が高まり、顧客からの信頼獲得にもつながります。DXの推進は単なる業務効率化にとどまらず、企業の信用を守るための基盤にもなり得るのです。
証券業界でDXが加速する中、成功事例には一定の技術的傾向が見受けられます。特にAIやブロックチェーン、RPAといった先端技術を効果的に活用することでサービスの質を高めつつ、業務の効率化とコスト削減を両立させているのです。
ここでは実際の取り組みを踏まえて、各技術の具体的な効果と導入の意義を紹介します。
近年ではAIや機械学習を活用した顧客分析が進み、証券営業におけるアプローチが大きく変化しています。これは膨大な顧客データを基にしたニーズ分析が、個別の最適な提案につながるためです。
例えば野村證券では、AIを用いて顧客の過去の取引履歴や相談内容を解析し、投資傾向に合わせた商品を自動提案する仕組みを構築しました。これにより営業担当者が個別に資料を作成する手間が省かれ、接客の質も向上しています。
AIを業務に組み込むことで経験や勘に頼らずに一貫した対応が可能になり、顧客満足度と成約率の双方が改善されます。今後はチャットボットや音声認識技術との連携を含め、より高度なサポートが求められるでしょう。
証券取引における信頼性、及びトレーサビリティの確保は業界全体の安定性に直結します。その点で注目されているのがブロックチェーン技術の活用です。
例えばSBIホールディングスでは、ブロックチェーンを基盤とした株式取引システムを一部導入しており、決済過程の情報がリアルタイムで共有される仕組みを実現しています。これにより取引内容の改ざんリスクが低減され、監査にも対応しやすくなりました。
このようにブロックチェーンは単なる決済手段にとどまらず、業務全体の透明性や信頼性を高める基盤技術として位置づけられています。導入時には既存の業務フローや法的要件との整合性が問われますが、長期的には不可欠なインフラとなる可能性が高いです。
定型業務の自動化による業務負担の軽減も、DX成功の重要な要素といえるでしょう。その中で注目されているのがRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)です。
例えば大和証券ではRPAを活用して、バックオフィス業務のうち約300以上の業務プロセスを自動化しました。その結果として年間で数千時間分の作業工数が削減され、人員を戦略部門へと再配置できるようになっています。
RPAの強みは既存システムを変更せずに導入できる点にあり、初期費用が比較的低く短期間で成果を出しやすいことから多くの証券会社で導入が進んでいます。ただし長期的な視点で見た場合、保守・運用体制の整備も重要になる点には注意が必要でしょう。
証券DXの推進が進まない場合、業務上の非効率や競争力の低下といった深刻な課題が発生する可能性があります。特に以下のようなリスクは、早急な対応が求められる領域です。
業務が特定の担当者に依存している状態が続くと、組織全体の柔軟性が損なわれます。なぜなら情報の共有が進まず、代替要員が育たないからです。
例えば、アナログな管理が中心の企業ではベテラン社員の退職とともにノウハウが失われ、業務に支障をきたすケースが散見されます。DXによって業務プロセスを標準化・デジタル化することで、こうした属人化のリスクを抑制できるのです。
今後人材不足がより深刻化すると予測される中で、DXを通じて再現性のある業務体制を構築することが持続的な成長のカギとなります。
DXが進んでいない企業はテクノロジーを活用した他社との競争に遅れを取る危険性があり、その結果として顧客離れや収益性の悪化につながるといった事態が考えられます。
例えば、オンライン証券会社が提供する高速な取引やスマートフォン対応のインターフェースは、既に従来型の営業体制に依存する企業との差別化要因となっています。こうした差はやがて、経営成績に直結する問題となります。
競争環境の変化に迅速に対応するには、先を見据えたテクノロジー導入が欠かせません。意思決定のスピードと実行力が、企業の存続を左右する局面も増えていくでしょう。
デジタル化が進まないことで日常業務における非効率が蓄積し、長期的に見ると運用コストが増加する傾向があります。紙ベースの処理や二重入力、確認作業の手間が放置されると人的ミスの発生率も高まることでしょう。
例えばRPAを活用している企業では、単純作業の自動化により数千時間分の工数を削減できたという事例もあります。一方で手動処理が続く企業では時間的損失、及び人件費の圧迫が経営の足かせになっているケースも珍しくありません。
生産性を高め、限られたリソースを有効に活用するためには業務プロセスの見直しとデジタルツールの積極活用が求められます。

証券業界におけるDXは単なる技術導入にとどまらず、業務構造の抜本的な改革を意味します。成功事例から、明確な目的設定と段階的な取り組みが効果的であるとおわかり頂けたと思います。
例えばAIによる営業支援やRPAを用いた事務処理の自動化、クラウド基盤の導入など取り組むべき領域は多岐にわたります。ただし闇雲にツールを導入するだけでは、真の改革にはつながりません。
重要なのは自社の課題や目標に合致したアプローチを設計し、持続的に改善していく体制を築くことです。その際、外部の知見を取り入れることも有効です。この記事を参考に客観的な視点や専門的なノウハウを活用すれば、DXの取り組みをより確かな成果へとつなげていけるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
