証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

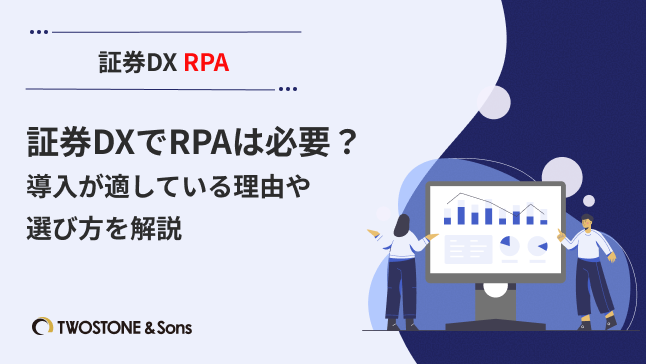
証券DX推進にあたりRPAを導入すれば、バックオフィス業務を自動化できるためヒューマンミスを削減し、コンプライアンスの強化も可能です。導入にあたっては、導入目的を明確にしたうえでスモールスタートで進めましょう。セキュリティ対策も大切です。
証券業界のDX推進において、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は業務効率化をサポートする存在です。
RPAとは、これまで人が行っていた定型的なPC操作や事務作業を、ソフトウェアロボットが自動で代行する技術を指します。
RPAにより一部の業務を自動化すれば、従業員を顧客対応など高付加価値業務へ再配置し、真のデジタル変革へと踏み出す体制の整備が可能です。
本記事では、証券会社にRPA導入が適している理由や導入の注意点などを詳しく解説します。

証券業界のDXを推進するうえで、RPAはデジタル化の起点として機能します。
口座開設や約定照合、レポート作成など従来は人手で行っていたバックオフィス処理を、RPAが終日進めることで、処理速度を飛躍的に高めつつコストを削減可能です。
これにより、人員をフロント業務や顧客体験の向上に再配置でき、真のデジタル変革へ踏み出す体制が整います。
また、RPAはAPIやAIと連携しやすいため、段階的にAI分析やチャットボットといったさまざまなDXソリューションへ拡張しやすい点も魅力です。
証券会社にRPA導入が適している理由は以下のとおりです。
それぞれの理由について詳しく解説します。
証券会社のバックオフィスには、以下のように分単位で発生するルーティンワークが数多く存在しています。
RPAはこれらの業務を一括処理できるため、担当者は分析や顧客対応など付加価値の高い業務に集中できるでしょう。
結果として、一人あたりの処理件数が向上し、残業の削減も期待できます。
オペレーターが数値を手入力する取引登録や、複雑なコードを含む銘柄情報の貼り付けは、人為的なタイプミスを招く主要因です。
特に証券業務では1桁の誤りが重大な損失や顧客クレームにつながります。
RPAなら同じ手順を厳密に再現し続けるため、誤登録の発生確率を削減可能です。
さらに操作ログが自動で残るため、原因究明や監査対応も容易になり、全社的な品質保証体制の底上げにつながります。
結果として、システム障害や取引停止に伴う機会損失を防ぎ、ブランドイメージの毀損リスクを低減し、顧客満足度向上も期待できるでしょう。
金融商品取引法や自主規制に基づき、証券会社は取引記録の保全、インサイダー情報の隔離、マネーロンダリング対策など膨大なチェックを求められます。
例えば、金融庁が公表している「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、内部管理体制の確立や顧客情報の管理、不公正取引の防止などに関する詳細な規定が設けられています。
RPAによってこれらの膨大なチェック業務を効率化できるため、コンプライアンス強化が可能です。
具体的には、本人確認書類の突合・疑わしい取引パターンの迅速な抽出・チェックリストと証跡の自動生成などが可能です。
これにより内部監査の準備時間を短縮し、コンプライアンス違反のリスクを回避、さらには投資家からの信頼向上が期待できます。
また、各ステップには時刻スタンプ付きで記録されるため、第三者検証に耐えうる透明性を確保可能です。
RPAは以下の3つの種類に分けられます。
それぞれの特徴について解説します。
デスクトップ型は、各従業員のパソコンにRPAを入れて、日々の細かな作業を代わりにこなしてもらう仕組みです。例えば、営業担当が顧客管理ソフトやブラウザを開き、必要な数字をコピーしてExcelに貼り付けるといった数分の作業を、RPAが画面上のボタンや入力欄を自動でクリックしながら進めてくれます。
代表的なデスクトップ型のRPAには「Robo-Pat DX」や「オークファンロボ」があります。これらのツールは、個別のパソコンで動作し、少人数のチームで手軽に導入可能です。特に、現場で即座に試用でき、直感的な操作で運用を始められる点が魅力です。
また、導入費用が安く、現場の人だけで設定を試せるため、思い立ったらすぐに改善できます。ただし、不特定多数のデスクトップにRPAを導入すると、誰が何を自動化しているのか分からないという事態になりやすいので、社内でルールを決めて整理しておくことが大切です。
サーバー型は、社内のサーバーにRPAを導入し、夜中など人が少ない時間帯に作業を進められます。毎日発生する取引データの取り込みや異常チェック、帳票作成のように重たい処理であっても夜間に完了するため、大量の取引を扱う証券会社でもシステムが遅くなりにくくなります。
代表的なサーバー型のRPAツールとして挙げられるのが「BizRobo!」や「WinActor」です。これらのツールは、サーバー上で動作し、企業全体の業務を一元管理できます。管理者は、どの業務がどの時間帯に処理されたかを把握しやすく、監査対応やセキュリティ対策を強化可能です。
また、RPAの動きを一元化管理できるため、監査対応やセキュリティ対策もしやすいのが特徴です。しかし、導入や運用にかかる費用はかさむ傾向にあるため、どこまで自動化すると投資効果が出るか、計画を立ててから進めましょう。
クラウド型はオンラインで利用するRPAで、ブラウザを開くだけで開発や作業を実行できます。
サーバーを自社で用意する必要がないためスピーディに導入でき、新規口座開設や本人確認(KYC)など、繁忙期だけ利用するといったスポット対応も可能です。
「UTORO」や「Automation 360」は、代表的なクラウド型のRPAツールで、特にインターネットを通じて簡単にアクセスできるため、場所を問わず利用可能です。
これらのツールは、生成AIやOCRを活用し、紙の書類を読み取りながらレポート作成まで自動で進められる機能を備えているため、人手不足の解消が期待できるでしょう。
しかし、クラウド型は情報漏えいリスクがあるため、使用にあたっては金融業界向けのセキュリティ基準を満たしているかの確認が欠かせません。

証券DXにおけるRPAは、以下のようなポイントから選びましょう。
それぞれのポイントについて解説します。
RPAツールは製品ごとに得意分野が異なります。
例えば、従業員の貼り付け作業を代行するといった場合、デスクトップ型が向いているのに対して、夜間に大量データを処理したい場合はサーバー型、急な繁忙期にライセンスを柔軟に増やしたいならクラウド型が有効です。
まずは自社が自動化したい業務リストを洗い出し、その業務フローで必要となる機能やワークフロー連携、API呼び出しなどの機能が標準で備わっているかを確認しましょう。
証券ビジネスは顧客資産やインサイダー情報を扱うため、堅牢なセキュリティが必須です。
ツール選定時には、以下のような点をチェックしましょう。
上記は金融庁「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」が推奨しているセキュリティ対策です。
同ガイドラインでは、経営陣を含むすべての役職員に対して、セキュリティの意識向上につながる教育・研修を定期的に実施することも推奨しています。
参考:金融庁 | 金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン
RPAを導入しても、操作方法が複雑だと形骸化しかねないため、ベンダーのサポート体制を必ず確認しましょう。
具体的には以下のような点を確認します。
さらに、シナリオ作成の実践例や障害時の原因分析を支援するドキュメントが充実していれば、内製化のハードルを下げられます。
証券DXを進めるうえでは、基幹システムやCRM(顧客関係管理)など多様なシステムの活用が欠かせません。
RPAがこれらとスムーズに連携できるのか、次のような点をチェックしましょう。
連携範囲が広いほど運用コストを抑えて自動化対象の拡大につなげられます。
市販のRPAツールが自社の特定のニーズに合わない場合、独自のRPAシステムを構築することを検討するのも有効な選択肢です。
自社の業務フローやシステム要件にぴったり合わせたツールを開発することで、運用面での柔軟性や効率をより高められる可能性があるでしょう。
自社独自の構築には一定のコストがかかりますが、長期的に見ると、より高い投資効果を得られることも少なくありません。
証券DX推進のためにRPAを導入する場合、事前に次のような準備を進めておきましょう。
それぞれの準備について解説します。
業務をRPAに置き換える前に、現場担当者はどのように業務を進めているのか、業務フローを時系列で詳細に書き出しましょう。
総務省「デジタル・ガバメント実行計画」においても、RPA の活用にあたっては、プロセスを定型化して処理手順を定義することが推奨されています。
業務フローをマニュアルに落とし込む際は、流れを書き出し、異常発生時の上長確認といった判断が発生するパターンには注釈を付記します。
注釈を付記しておくことで、RPAで対応する際に、該当業務の保留や例外処理が可能です。
さらに各手順の件数と所要時間を明記し、関連する法令や社内規定の番号を紐づけましょう。
RPAは導入して終わりではなく、業務変更やシステム更新のたびにシナリオを手直しする保守担当が欠かせません。
「RPA 導入実践ガイドブック」では、米国連邦政府の例を出し、人材育成の重要性を解説しています。
RPAの運用にあたっては、業務知識とITスキルを兼ね備えたハイブリッド人材が求められます。
ハイブリッド人材の確保や育成が困難であれば、まずは業務部門と情報システム部の混成チームで役割を分担し、ノーコード開発ツール研修を実施しましょう。
社内コミュニティで事例共有を行えば定着率が上がります。
評価制度に貢献度を反映するとモチベーションも維持できます。
参考:内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室 | RPA 導入実践ガイドブック
自社でRPAを開発できる体制を整えると、業務やルールが変わるたびにベンダーへ依頼するという手間や費用を削減可能です。
自社で開発をする場合、まずは操作が単純で成果を実感しやすい作業をひとつ選び、ベンダーの支援を受けながら小規模に試験導入して開発の流れをつかみましょう。
その過程で業務担当者と情報システム部の混成チームを作り、ノーコード/ローコードツールの使い方を習得します。
次に、部品化できる処理や変数の命名ルールを社内で統一し、どのRPAにも再利用できるテンプレートを整備しましょう。
こうして開発・修正を少しずつ社内へ移管していけば、最終的には設計から実装まで自社で対応できるというレベルにつながります。
なお、総務省が自治体向けに発表した「自治体における RPA導入ガイドブック」では、必要な時に外部事業者のサポートを受けられる体制作りを推奨しています。
証券会社も同様に、自社内でRPAを開発する際は、トラブル発生時などに備えて外部事業者のサポートを受けられるようにしておきましょう。
RPAを導入する際は、次のような点に注意しましょう。
それぞれの注意点について解説します。
RPAは、なぜ導入するのか目的を明確にしておきましょう。
例えば、残業を減らしたいといったような目的は、RPAでなくても達成できます。
目的は自動化対象業務、削減したい工数、遵守すべき規制などを具体的に数値化し、経営層と現場が同じゴールイメージを共有しましょう。
目的を言語化しておくと、導入後の評価軸もブレず、追加開発の優先順位づけも容易になります。
書面に落とし込んだ目的シートを掲示し、プロジェクト開始時に全員で再確認すると意思決定がぶれません。
最初から全社一括展開を目指すと、期待する成果が得られず頓挫しかねません。
まずは処理時間と人為ミスが多い単純業務をひとつ選び、PoCで効果を検証しましょう。
成功体験を作れば社内の賛同者が増え、横展開の際に部門間調整がスムーズになります。
小さな成功例を社内ポータルで共有し、数値とコメントを添えて可視化することで、次に自動化すべき業務も判断しやすくなるでしょう。
RPA導入にあたっては投資対効果(ROI)を検証しましょう。
導入費用だけでなく、サーバー維持費や保守工数など発生するのであれば費用を合算し、削減できる人件費やミス削減による損失防止額と比較します。
投資対効果がプラスになるラインを設定し、四半期ごとに実数字でモニタリングすれば、経営層の同意も得やすくなるでしょう。
加えて、品質向上など数字に現れにくい効果も定性的指標としてレポートすると、より立体的な評価が可能になります。
RPAは従業員の理解を得たうえで導入しましょう。
従業員によってはRPAに仕事を奪われると誤解している可能性があります。
このような誤解を放置していると、マニュアル更新や例外処理の協力が得られず現場定着が進みません。
説明会やデモ動画で、RPAは単純作業を肩代わりし、人は分析や提案に時間を使えることを伝えましょう。
業務担当者を設計フェーズから参画させれば、愛着が生まれ運用トラブルも減ります。
例えば、現場からの改善案を受け付ける専用チャットを設ければ、活用アイデアが自然と集まり、RPAの価値をさらに高められます。
実際にRPAを導入して証券DXを実現した企業事例として挙げられるのが以下の2社です。
それぞれの事例を解説します。
株式会社日本取引所グループでは、RPA推進事務局が各部署と連携し、入力照合や報告書作成を自動化しました。
その結果、積極的に利用した部署においては、「非常に満足」もしくは「満足」の割合が80.6%、一般利用部署では 68.4%と高評価で、業務時間削減と生産性向上を実感できました。
RPAにより従業員の業務負荷が軽減されたことで、他の業務に時間を割けるようになっています。
参考:株式会社日本取引所グループ | RPA の本格導入に向けた実証実験及びプロジェクト推進の一事例 -日本取引所グループの取組について-
PWM日本証券株式会社は、事務作業効率化を目的に2020年12月からRPAを導入し口座開設のための入力業務や営業計数メール送信など約30業務を自動化しました。
その結果、年間約1,500時間(月間125時間)の工数削減と入力ミスゼロを達成できています。
RPAにより従業員の業務負荷が軽減され、夜間自動稼働で日中は高付加価値業務に時間を割けるようになっています。

証券DXを進めるにあたり、RPAは業務効率化と顧客体験向上のために有効なツールです。
RPAにはデスクトップ型・サーバー型・クラウド型の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
導入を成功させるためには、自社の目的や自動化したい業務内容に合わせて最適な種類を選び、セキュリティ対策やサポート体制、他システムとの連携性を十分に確認しておくのがポイントです。
本記事を参考に、RPAを活用して証券DXの推進につなげましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
