証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

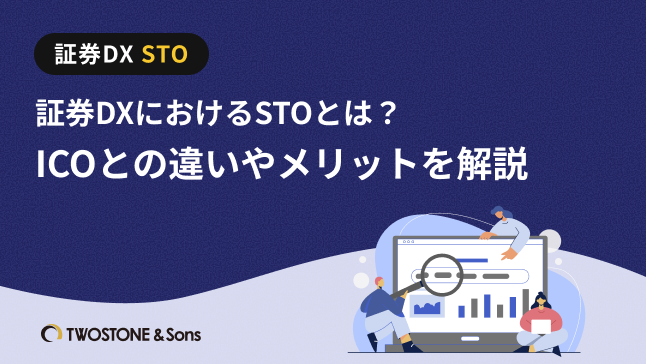
証券業界のDX促進にあたりSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)導入が注目されています。ブロックチェーン技術を活用すれば取引の透明性や決済速度が向上し、従来の証券発行にかかるコストを削減可能です。STOの概要やメリットを実現する方法を解説します。
証券業界は急速に変化し、競争の激化と収益性の圧迫が生じかねません。
特に、ネット証券や手数料の自由化により、利益率の低下が顕著になりつつあります。
こうした背景の中で、証券会社はデジタル技術を活用した業務プロセスの変革が欠かせません。
本記事では、証券DXの一環として、STO(セキュリティ・トークン・オファリング)を導入することで、証券取引の効率化とコスト削減を実現する方法について解説します。

STOは、証券のデジタル化を進める新しい資金調達手法です。
これは、有価証券の権利情報をブロックチェーン上でトークン化することで、資産の発行から流通・管理までを効率的に行う仕組みです。
世界有数の経営コンサルティングファームであるボストンコンサルティンググループによると、世界のSTO発行額は2024年末で約20億ドルでした。
一方、株式会社BOOSTRYの発表によれば国内の2024年度STO発行額は464億円でした。
トークンとは株式や債券、不動産など、現実世界の資産や権利を、ブロックチェーン上で管理できるデジタルの証券といえます。
特に、不動産などの実物資産を裏付けにしたデジタル証券の発行が注目されています。
STOにより、従来の証券取引のプロセスがデジタル化され、決済速度の向上や透明性の確保を実現できるでしょう。
ここでは近年注目されているSTOの基本概念やST・IPO・ICOの違いについて解説します。
参考:Boston Consulting Group | Tokenized Funds: The Third Revolution in Asset Management Decoded
参考:株式会社BOOSTRY | 日本のセキュリティ・トークン市場総括レポート(2024年度)を公表~累計公募発行金額は1,600億円を突破し、2025年度の飛躍が期待される~
STOは、セキュリティトークンを利用した資金調達の手法です。
発行者はその事業計画や資産裏付けを開示したうえで、投資家に対して証券を販売します。
この際、活用されるのがスマートコントラクトという自動実行プログラムです。
自動実行プログラムによってトークンの譲渡や権利の管理を効率的に行います。
その結果、名義変更や配当の計算といった従来の証券管理業務を省力化でき、手間を削減可能です。
また、STOはプライベートブロックチェーンを利用するため、投資家情報の安全性やAML(アンチマネーロンダリング)対応も担保できます。
これにより、従来の証券市場における取引の遅延やリスクを軽減し、よりスムーズで安全な取引を提供できるようになっています。
STOにおいて発行されるトークンは、通常の証券と同じ法的義務を伴い、金融商品取引法の規制下にあるため、信頼性を確保できるでしょう。
STOは新たな資金調達方法として注目が高まっています。
証券会社がSTOを活用する際は、以下の関連機関の対応状況を確認しましょう。
関連機関 | 概要 |
|---|---|
一般社団法人 日本STO協会 | 金融商品取引法に基づく自主規制団体として、セキュリティトークンの取引に関するルールを策定し、投資家保護と市場の健全な発展に努めている |
金融庁 | デジタル・分散型金融への対応を強化しており、研究会を設置して適切な規制のあり方について検討を進めている |
STO市場の健全な成長には、日本STO協会による自主規制の整備と金融庁による法制度面の支援が欠かせません。証券会社はこれらの動向を継続的に注視し、適切な対応を心がけましょう。
参考:金融庁 | デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会
ST(Security Token)とSTOはしばしば混同されがちですが、それぞれ異なる概念です。
STは有価証券をデジタル化したトークン自体を指し、これは証券の価値をデジタルで表現するものです。
一方、STOはそのSTを活用して資金調達を行うプロセス全体を指します。
簡単に言えば、STは商品であり、STOはその商品を活用する取引のスキームという関係です。
STは証券としての価値を持つデジタルトークンであり、証券会社はこのSTを発行し、保管するためのカストディ体制を整える必要があります。
そして、STOはそのSTを使って資金調達を行うための一連の手続きやサービスを指し、発行者が資金調達のために実行する具体的な活動を示します。
したがって、STは物理的な株券や債券のデジタル版であり、STOはその取引方法やフローを管理する仕組みです。
IPO(Initial Public Offering)では、企業が株式を公開市場で販売し、広範な投資家から資金を調達します。
IPOは、証券取引所に上場し、引受シンジケートを通じて株式を販売するのが一般的です。
そのプロセスには多くのステップが含まれており、規模の大きな資金調達を行う際に利用されます。
一方、STOはブロックチェーン技術を活用してデジタル証券を発行する手法であり、IPOに比べて手続きがシンプルで、発行コストも低く抑えられます。
STOの特徴は、証券をトークンとしてデジタル化することで、発行から取引、決済までの流れをプログラムによって効率化できる点です。
これにより、株式を公開する際に必要な複雑な手続きやコストを削減できます。
さらに、STOは従来の証券取引所に上場せずとも、分散型のプラットフォームで取引されるため、取引の柔軟性も向上します。
ICO(Initial Coin Offering)は、ユーティリティトークンを発行して資金調達を行う手法です。
ユーティリティトークンとは、特定のプラットフォームやサービス内で利用できるデジタル資産のことです。
これらのトークンは、一般的に投資対象としての価値を持つのではなく、特定のサービスや製品を使用するための「通貨」として機能します。
つまりICOでは、トークンを所有すれば、特定のサービスの利用権や参加権を獲得可能です。
一方、STOは証券として法的権利(配当や議決権)を伴うデジタルトークンを発行します。
STOは、有価証券として扱われるため、ICOとは異なり、金融商品取引法の規制を受けます。
不動産STOは、不動産から得られる賃料収入や売却益をトークンとして販売する仕組みです。
これにより、物件情報や分配状況が透明になり、権利譲渡もブロックチェーン上で即座に行えます。
証券会社は物件評価や適格性を審査し、トークンの発行と市場流通を支援します。
少額からの投資が可能になるため、富裕層以外にも不動産投資の機会を提供可能です。
不動産STOにおいて、不動産事業者と連携して物件の評価を行い、その資産をトークン化して投資家に販売するのが証券会社の役割です。
また、取引プラットフォームを運営し、投資家情報の確認やトークン管理を行います。
さらに、投資家向けに分配金の自動送金や税務レポート作成を提供することで、投資後の顧客体験向上につなげます。
REITは投資法人が運用する不動産のポートフォリオに投資する商品です。
REITは上場しており、流動性が高く、情報開示も制度化されています。
不動産STOは個別の物件に投資するため、投資先がわかりやすく、分配金の自動化が可能です。
ただし、市場規模や価格透明性の面ではREITに劣ります。
証券会社は、これらの違いを顧客に説明し、リスク許容度に応じた提案が必要です。
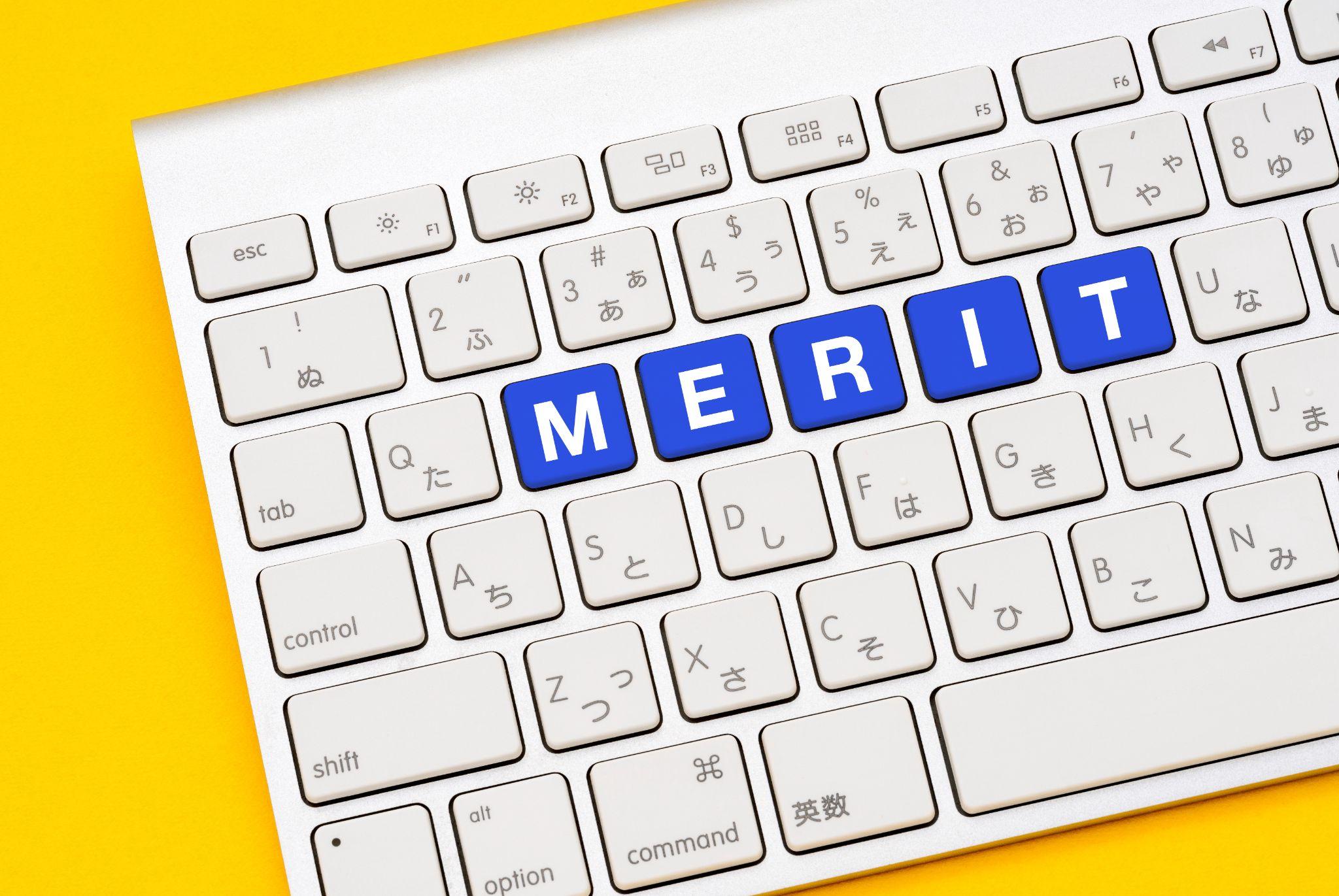
証券DXの一環として、STOを活用することは、証券業界にとって多くのメリットをもたらします。
STOは、証券のデジタル化を進める手段として、従来の証券市場に新たな価値を提供します。
具体的には、取引の透明性、効率性、そしてセキュリティの向上が期待され、証券会社はこれらのメリットを活かして、業務の効率化とコスト削減を実現できるでしょう。
ここではSTOを活用するメリットを詳しく解説します。
STOを活用すれば、顧客は24時間365日、世界中のどこからでも証券取引を行えるようになります。
証券会社にとっては、従来の営業時間に制限されることなく、取引を継続的に提供可能です。
取引の自由度が高まることで、顧客満足度が向上し、証券会社のサービス競争力も強化されるでしょう。
特に、証券取引の市場は時差の影響を受けやすいため、24時間取引可能な仕組みがあれば、顧客の利便性が向上します。
STOでは、ブロックチェーン技術を利用して、取引手数料や手続きが簡素化されます。
その結果、従来の証券取引にかかる手数料や複雑な手続きが削減され、顧客はより簡単に証券取引が可能です。
証券会社にとっても、手続きが効率化されることで、事務作業の負担が軽減され、コスト削減につながります。
また、手続きの簡素化により、取引のリスクが低減され、誤操作や不正行為のリスクを抑えることができます。
STOにより、顧客は小口での投資が可能です。
これまで大きな資金が必要だった証券取引に比べ、少額で投資を始められるため、以前は証券取引に参加できなかった新たな顧客層を獲得するチャンスが広がります。
例えば、小口投資の導入により、より多くの個人投資家や企業が市場に参入し、証券会社の顧客基盤の拡大が期待できるでしょう。
特に、若年層や投資初心者をターゲットにすれば、証券会社の売上増加が見込まれます。
証券DXの進展により、業務全体がデジタル化されることで、業務効率が向上します。
例えば、取引の処理が自動化され、手作業によるミスや時間の浪費減少が期待できるでしょう。
また、デジタル化により、証券会社の顧客データや取引履歴を効率的に管理できるため、データ解析を通じてより的確な意思決定が行えるようになります。
このような業務の効率化は、コスト削減に寄与するとともに、より迅速かつ高精度なサービスを提供可能です。
証券DXの一環としてSTOを導入すれば、証券会社は数多くのメリットを享受できる一方、次のようなデメリットにつながりかねません。
これらのデメリットを十分に理解し、事前にリスク管理や対策を講じることが、STOの導入において成功を収めるためには不可欠です。
それぞれのデメリットを解説します。
STO市場は、現在のところまだ発展途上にあり、株式市場や債券市場に比べると参加者の数が少ない現状です。
そのため、STOを導入しても、投資家や取引の規模が限られている可能性があります。
特に、初期段階では取引量が少なく、証券会社の収益に対するインパクトが小さいことが考えられます。
また、マーケットの成長には時間がかかるため、証券会社にとっては短期的な利益を期待するのが難しい場合もあるでしょう。
取引の流動性が低いため、顧客にとってはスムーズな取引が難しく、顧客満足度が低下する恐れもあります。
このような問題を解決するためには、市場の拡大を促進する施策や投資家の参加を積極的に呼びかける取り組みが必要です。
STOはブロックチェーン技術を活用しているため、システムの信頼性やセキュリティ対策が極めて重要です。
万が一、技術的な障害が発生したり、不正アクセスが行われたりすると、証券会社の信頼性に影響を与える可能性があります。
これにより、顧客が取引に対して不安を抱え、証券会社からの離脱が進みかねません。
そのため、証券会社は最新のセキュリティ技術を導入し、システムの堅牢性を確保する必要があります。
例えば、金融庁が公表している「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」が示しているように、以下のようなセキュリティ対策を講じましょう。
さらに、万が一のトラブルに備えて、バックアップ体制や障害発生時の対応フローを整備することが求められます。
不正アクセス防止に対する投資や監視体制の強化も必要であり、これらに関連するコストが証券会社にとっての負担となることも考慮しなければなりません。
参考:金融庁 | 金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン
STOの導入は、証券会社に新たな技術的要件を生み出します。
従来の証券業務とは異なり、STOはブロックチェーンやデジタル資産に関する高度な知識が求められます。
そのため、証券会社の従業員は、新しい技術に関するトレーニング受講が必要です。
しかし、トレーニングには時間とコストがかかるため、従業員教育に対するリソースが求められます。
また、専門的な知識を持つ人材を確保するために、リクルーティング活動や人材育成プログラムの強化が不可欠となります。
従業員が新しい技術に適応できるよう、サポート体制や研修の充実を図りましょう。
STOは、デジタル証券の一形態であり、証券DXの重要な要素となります。
日本の金融商品取引法においては、STOは特定の要件を満たすことで有価証券として法的に認められます。
証券DXの一環としてSTOを導入するのであれば、日本における法的な位置づけを把握しておきましょう。
ここではSTO導入にあたって把握しておきたい電子記録移転権利、電子記録移転有価証券表示権利等について解説します。
電子記録移転権利とは、日本の金融商品取引法第2条第2項各号で定められている、特定の要件を満たしたデジタル化された証券を指します。
特定の要件を満たすことで物理的な証券の取引に必要な手間を省き、取引コストを削減可能です。
具体的な要件は次のとおりです。
また、従来の紙の証券をデジタル化するため、保管コストや紛失リスクも低減し、証券の管理を効率化できます。
これにより、証券会社は業務の効率化とコスト削減につなげられるでしょう。
参考:金融庁 | セキュリティトークンに関する現状等について
電子記録移転有価証券表示権利等は、デジタル証券の法的表現に関する概念であり、日本の金融商品取引法に基づいています。
特定の要件として、デジタル証券はブロックチェーン等の技術を利用して、所有権の移転や表示が透明かつ記録されることが求められます。
また、発行者が日本の金融庁に認可を受けた企業であることも要件です。
デジタル証券は、従来の紙の証券に代わる形式として、証券取引を効率化する重要な手段となるでしょう。
証券会社がSTOを活用する事例は次のとおり海外に豊富に存在しています。
それぞれの事例を解説します。
Blockstack社は、米国初の一般投資家向けSTOを実施した企業です。
同社はSTOを活用することで、従来のIPOに比べて低コストで資金調達を実現しました。
特に、従来の証券発行手続きにおける法的手続きや手数料を削減しました。
これにより、証券取引の透明性が高まり、効率的な資金調達が可能となっただけでなく、発行後の管理コスト低減にもつながっています。
STOを活用したことで、証券会社や発行企業にとって、コスト削減とともに業務の効率化が実現されています。
参考:株式会社野村資本市場研究所 | 新たな資金調達手法として期待されるSTOー海外の事例と日本における可能性ー
ドイツのBitbond社は、欧州初の登録STOを実施した企業であり、STOを活用した資金調達により従来の資金調達方法に比べてコスト削減を実現しました。
STOによって、物理的証券発行にかかるコストや管理費用が削減され、取引がブロックチェーン上で行われるため、従来のシステムと比較して高い効率性を実現しました。
また、Bitbond社は、STOによる資金調達を通じて、投資家に対して透明性の高い取引環境を提供し、信頼性の向上にもつながっています。
参考:株式会社野村資本市場研究所 | 新たな資金調達手法として期待されるSTOー海外の事例と日本における可能性ー

STOは、証券DXを進め、効率的な資金調達を可能にします。
ブロックチェーン技術を活用しているため、取引の透明性や決済速度が向上し、従来の証券発行にかかるコストを削減できるでしょう。
一方、市場の規模や参加者の数が少ない、従業員に専門的な知識が求められるなどのデメリットも存在します。
STOを導入する際には、本記事の内容を参考にしながらメリットとデメリットの両面を正しく把握してください。そのうえで、自社に合った形で証券DXを進めていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
