証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

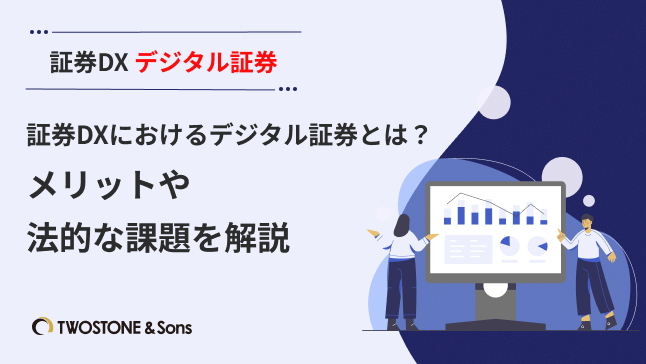
ブロックチェーン技術を活かしたデジタル証券は、発行・管理・取引を効率化しコスト削減を実現します。デジタル証券のメリットや課題と対応策を解説。証券DX推進の一環としてデジタル証券を導入して業務効率化と新たな収益機会の創出を目指しましょう。
デジタル証券は、ブロックチェーン技術を活用し、証券をデジタルデータとして取引する革新的な仕組みです。
従来の紙や物理的な証券と異なり、発行・管理・取引が迅速かつ効率的に行え、手数料やコストの削減が期待できます。
そのため、証券会社はコスト削減と業務効率化を両立可能です。
証券業務の効率化を進めたいと考えている方は導入を検討してみましょう。
この記事では証券DX推進に有効なデジタル証券について、メリットや課題、対応策などを解説します。

デジタル証券は、ブロックチェーン技術を活用して、証券をデジタル化したものです。
従来の証券とは異なり、紙ベースや物理的な証券ではなく、デジタルデータとして取引されます。
これにより、証券の発行、管理、取引が迅速かつ効率的に行えるようになり、手数料や取引コストの削減が期待できます。
また、デジタル証券は、分散型台帳技術によってセキュリティが強化されており、信頼性の向上も実現可能です。
FISC(金融情報システムセンター)が策定する「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」は、デジタル証券を扱う金融情報システムのセキュリティ確保において重要な指針です。
この基準に準拠することで、システム全体の信頼性を高められます。
さらに、ブロックチェーン上での取引履歴が透明性を確保し、不正行為のリスクを従来よりも抑えられるため、より安心して取引ができる環境を提供できます。
参考:金融情報システムセンター | 金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準
従来の証券は、証券会社や金融機関を通じて発行・取引される物理的な証券が主流でした。しかし、デジタル証券はブロックチェーン技術により、電子的に発行・取引されます。
従来の証券は、管理手数料や発行コスト、取引の時間的な制約が課題でしたが、デジタル証券はこれらのコストを削減することが可能です。
さらに、取引の透明性が向上し、即時決済が可能となるため、従来の証券に比べて効率性が格段に向上します。
デジタル証券は国際的な取引を容易にし、グローバルな投資家へのアプローチも可能です。
デジタル証券は、ブロックチェーン上でスマートコントラクトを利用して発行されます。
これにより、発行プロセスは自動化され、証券管理の簡素化を実現可能です。
従来の証券では、発行者は証券を証券会社や金融機関を通じて物理的に発行する必要がありました。
しかし、デジタル証券はブロックチェーン技術によってオンラインで即座に発行できます。このプロセスは、発行手数料や時間を削減し、証券の取り扱いを効率化するため、コスト削減に直結します。
また、証券のトレーサビリティが向上し、不正取引のリスクが低減するため、セキュリティ面におけるメリットも証券会社は享受できるでしょう。
証券DXの一環としたデジタル証券の採用は、証券業界にメリットをもたらす取り組みです。
主なメリットは、コスト削減と業務の効率化です。
従来の証券取引に比べ、発行、管理、取引が迅速かつ自動化されるため、手数料や事務作業が削減されます。
これにより、業務全体のコストが抑えられるだけでなく、時間的な余裕も生まれ、より多くの取引を処理することが可能となります。
デジタル証券の導入により、証券会社は発行手数料や管理コスト、取引手数料を削減可能です。
従来の証券では、発行や管理のために物理的なインフラや人員が必要でした。
しかし、デジタル証券ではそのようなコストが削減されます。
その結果、証券会社はより効率的な収益構造を実現し、コストを削減しつつ利益をより高めることが可能になります。
また、取引のスピード向上により、より多くの取引を迅速に処理できるため、収益機会の増加も期待できるでしょう。
デジタル証券が証券会社にもたらすメリットのひとつが、取引のスピードが向上することです。
ブロックチェーン技術により、証券の取引はリアルタイムで行われるため、従来の証券取引における決済期間の遅延や煩雑な手続きを排除できます。
このようなスピード向上により、証券会社はより迅速に取引を処理できるようになり、業務効率を向上可能です。
これにより、顧客のニーズに迅速に対応でき、競争力を強化できます。
即時決済により、資金の回転率が改善し、より多くの取引を短時間で実現できるため、収益機会をより向上させられるでしょう。
デジタル証券は、物理的な制約を排除し、グローバル市場に向けた新たな顧客へのアプローチを可能にします。
ブロックチェーン技術により、国境を越えた取引が容易になり、証券会社は新たな市場に進出しやすくなるでしょう。
従来の証券取引で海外市場で取引しようとすると、手続きの煩雑さや高い手数料がネックになるケースがありました。
一方、デジタル証券を活用することでこれらの課題が解消され、国際的な取引コストの削減と市場の拡大が可能になります。
デジタル証券を利用することで、不動産やアートなど、これまで証券化が難しかった非流動資産の証券化が可能になります。
従来、非流動資産は流動性が低く、投資家が手に入れるのが難しい資産とされていました。しかし、デジタル証券により、これらの資産を小口化して、投資家が少額で投資できるようになります。
これにより、証券会社は新たな投資家層を取り込むことができ、収益源の多様化を実現できるでしょう。
非流動資産に投資することで、これまでアクセスできなかった市場にも参加できるため、投資家にとっての選択肢が広がります。
その結果、証券会社はより魅力的な投資機会を提供可能です。
証券DXにおいてデジタル証券を導入する際には、いくつかの課題が存在します。
これらの課題を克服することが、効果的なコスト削減と証券取引の効率化を実現するために必要です。
特に法的・規制的な制約、技術的な問題、顧客教育などが障害となり得ます。これらの課題に対処するためには、関係者全体での協力と技術的なアップデートが求められるでしょう。
加えて、導入過程において新たなリスクや不確実性が生じる可能性もあり、その管理も重要な課題となります。
デジタル証券の導入において把握しておくべき課題のひとつが、法的および規制の問題です。
各国の証券法や金融規制は伝統的な証券に基づいて構築されているため、デジタル証券に対応した新しい法整備が必要です。
特に、デジタル証券の発行・取引に関する規制はまだ整備されていない国が多く、法的なリスクが存在します。
日本も金融庁が「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」を設置し、デジタル証券を含む新たな金融技術がもたらす課題やリスク、そして適切な規制のあり方について議論を進めています。
デジタル証券を扱う証券会社は、適法に取引を進めるために、新たな規制対応を行う必要があり、規制に従うことでコストが増加しかねません。
参考:金融庁 | デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会
デジタル証券を導入する際には、技術的な課題も多く存在するため事前に把握しておきましょう。
特に、ブロックチェーン技術やスマートコントラクトを用いた新しい技術の導入には、高度な専門知識と技術基盤が求められます。
これらの技術に対する理解が不足している場合、システムの導入が遅れ、コスト増加につながりかねません。
さらに、技術的な知識を持つ人材の不足も問題であり、社内での教育や外部専門家の活用が必要となる場合があります。
このような状況では、計画的にリソースを確保し、適切なタイムラインを設定することが重要です。
デジタル証券は、インターネットを介して取引が行われるため、セキュリティの問題を孕んでいます。
特に、ブロックチェーン技術を活用する場合でも、ハッキングや不正アクセスのリスクが存在します。
証券取引をデジタル化することで、サイバー攻撃やデータ漏洩といったリスクが高まりかねません。
これらのリスクを防ぐためには、最新のセキュリティ技術を導入し、信頼性の高いシステムを維持する必要があり、それに伴うコストが発生してしまうことも把握しておきましょう。
デジタル証券を導入するためには、企業内でブロックチェーンやスマートコントラクトに関する高度な技術的な知識が必要です。
しかし、これらの技術に精通した人材は限られており、企業が導入を進める際には、その人材を確保するためのコストがかかります。
加えて、既存の従業員に対しても新しい技術の教育を行う必要があり、これには時間とリソースがかかります。
このような技術的な知識の不足は、デジタル証券の導入の障害となり、企業の運営コストが増加する要因となりかねません。
デジタル証券の導入に際しては、顧客教育も重要な課題です。
従来の証券取引と異なり、デジタル証券はブロックチェーン技術を活用しているため、顧客にとっては理解しづらい場合があります。
顧客がデジタル証券を利用するためには、そのメリットや使い方、リスクについて十分に理解してもらう必要があります。
しかし、教育や情報提供には時間と費用がかかり、これが導入の障壁となりかねません。
顧客教育が十分でない場合、デジタル証券の利用者が増えず、予想した収益やコスト削減の効果を得られない可能性があります。

デジタル証券の導入に伴う課題として挙げられるのは、以下のとおりです。
これらの課題を克服するためには、外部専門家のサポートを活用し、法規制や技術的な課題、顧客教育の問題に対して適切な対応を行うことが重要です。
これにより、証券会社は効率的に課題を解決し、コスト削減につながります。
具体的な対応策を講じることで、スムーズなデジタル証券導入と市場への対応が可能になります。
デジタル証券の導入における法規制や自主規制への課題に対しては、外部専門家のサポートの活用が効果的です。
例えば日本STO協会では、私設取引システムにおけるデジタル証券の取扱いについて独自の規定を設けています。
外部専門家のサポートを受ければ、このような自主規制や法規制に対応できます。
これにより、法的リスクを抑えつつ、効率的に証券取引を進めることが可能となり、規制対応のコストを削減可能です。
また、外部専門家は最新の法改正にも対応しており、長期的な安定性を確保するために重要な役割を果たします。
参考:一般社団法人 日本STO協会 | 定款・自主規制規則等・諸規則
技術的な課題を解決するためには、定期監査を実施し、技術的なインフラとシステムを継続的に見直すことが重要です。
定期的に監査を行うことで、セキュリティの脆弱性やシステムの不具合を早期に発見し、改善策を講じることができます。
また、技術的な知識を持った人材の育成にも力を入れることが必要です。
社内で技術者を育成するために、専門家のサポートを借りたトレーニングを提供すれば、デジタル証券を扱うためのスキルを社内で確保できます。
これにより、外部依存を減らし、コスト削減につながるでしょう。
顧客教育の課題に対しては、非対面でも学べるオンラインコンテンツを活用して顧客の理解を深めることが効果的です。
動画、ウェビナー、インタラクティブなガイドなどを提供し、デジタル証券の特徴や利点、リスクについてわかりやすく説明できます。
これにより、顧客は自分のペースで情報を学び、理解を深めることができるため、デジタル証券の導入をスムーズに進められるでしょう。
オンラインコンテンツは、低コストで多くの顧客にアプローチできるため、コスト削減にも寄与します。
また、顧客の理解が進むことで、利用率の向上も期待できるでしょう。
証券DXでデジタル証券を導入している企業は、次のとおりです。
それぞれの事例を解説します。
これらの企業は、デジタル証券を通じて不動産市場における流動性を向上させ、投資家に対して新たな投資機会を提供しています。
また、DX化により取引コストの削減やスピード向上が実現され、効率的な市場運営を推進できるというのも特徴です。
みずほ証券株式会社は、スターツコーポレーションと共同で、不動産を裏付けとした公募型デジタル証券の発行を開始しました。
これは、不動産の所有権を小口化し、個人投資家や事業法人に販売する取り組みです。
従来は私募のみだったデジタル証券の公募はみずほ証券株式会社の取り組みが初めてでした。
スターツ証券が主に個人向けに1口1万円(最低投資金額10万円)から販売し、みずほ証券は法人向けの販売を担当します。
動産の所有権を小口化したことで、将来的には不動産取引のある富裕層などを中心に個人の投資家層の拡大が期待できます。
参考:日本経済新聞 | みずほ証券、スターツと公募の不動産デジタル証券 投資家層を拡大へ
2021年から不動産デジタル証券を取り扱っているのが野村證券株式会社です。
近年では、2024年3月に約97億円の「ホテルトークン 悠洛・京都三条」、2024年2月に約115億円の「那須・アウトレットモール」、2023年8月に約134億円の「月島 – リバーシティ21 イーストタワーズII」といった大型案件の販売実績を誇っています。
これらは、不動産をデジタル証券化したからこそ、新たな投資機会と効率的な資金調達を提供できたケースといえます。
参考:野村不動産ソリューションズ株式会社 | 不動産のデジタル証券化の最近の動向

デジタル証券はブロックチェーン技術を活用し、証券をデジタル化することで、発行・管理・取引の効率化とコスト削減を実現可能です。
従来の証券とは異なり、高い透明性と決済時間の短縮につながります。
デジタル証券導入にあたっては法規制や技術、顧客教育といった課題はありますが、専門家のサポート、継続的な人材育成、オンラインコンテンツの活用で克服できます。
この記事を参考にデジタル証券を活用して証券DXを加速させ、コスト削減による収益構造の効率化、取引スピードの向上などにつなげましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
