証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

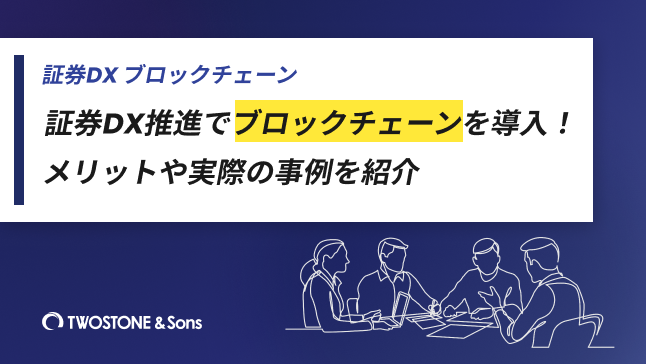
ブロックチェーン技術が証券業界でどのように活用されているのか、導入事例を交えて丁寧に解説しています。証券DXを推進したい企業担当者に向け、実際の利活用シーンや導入時に気をつけたい法規制・運用面の留意点についても詳しく紹介します。
証券業界では近年、デジタル化の波が急速に押し寄せています。特にブロックチェーン技術は、従来の業務プロセスを大きく変える可能性を秘めた革新的なテクノロジーとして注目されています。しかし多くの企業が、導入の意義や具体的なメリットのわかりにくさ、技術的なハードルの高さなどを感じているのも事実です。
この記事では、証券DXを推進する上でブロックチェーン技術が果たす役割とその導入によって得られる具体的なメリットについて詳しくご紹介します。取引の透明性や決済スピードの向上、コスト削減、さらには柔軟な資金調達手段としてのSTOの活用など、証券業務に変革をもたらすヒントが満載です。この記事を読むことで、証券業界におけるブロックチェーンの可能性と自社にとっての有効な活用法が見えてくることでしょう。
証券業界では従来のシステム構造が複雑で非効率な面があり、取引や決済に時間とコストがかかっていました。こうした課題に対して、ブロックチェーン技術が有効な解決手段となっています。ブロックチェーンは分散型台帳として機能し、あらゆる取引情報を一元管理できるため改ざんリスクの軽減や業務効率の向上につながるのです。
例えば、複数の仲介業者を介することで生じる情報のタイムラグや整合性の問題も、ブロックチェーン上でリアルタイムに情報共有が行えるようになれば解消されやすくなります。証券取引の透明性やトレーサビリティを高めることで投資家との信頼関係を構築しやすくなり、業界全体の健全性も向上することが期待されます。
このようにブロックチェーンは単なる技術革新にとどまらず、証券業務の在り方そのものを根本から変える力を持っているのです。

証券DXを推進する上で、ブロックチェーンの導入は多くの利点を企業にもたらします。
ここでは主な5つのメリットに注目し、それぞれの内容と期待できる効果を解説します。
ブロックチェーンの特徴は、全ての取引履歴がネットワーク上に記録され、関係者間で常に同じ情報を共有できるというものです。これによって、誰がいつどのような取引を行ったのか、明確に把握することが可能となります。この透明性は特に、不正取引の抑制や内部統制の強化に役立ちます。
これは、不正アクセスによるデータの改ざんや誤情報の流布を防ぎ、コンプライアンスの観点でも有効です。これは証券会社にとっては顧客からの信頼を維持・向上させる上で、大きなアドバンテージとなるでしょう。
証券取引の決済・清算には通常数日を要するものですが、ブロックチェーンを用いたスマートコントラクトを活用すれば、そのプロセスを自動化・即時化することが可能になります。
例えば、取引成立と同時に資金と証券の交換が自動で実行される仕組みを整えることで、T+0(取引日当日決済)を実現することも視野に入ります。これによって決済リスクの軽減や流動性の向上が見込まれ、機関投資家の取引環境にも変化をもたらすのです。
ブロックチェーンの導入によって仲介業者やバックオフィス業務が削減され、運用コストの削減が可能となります。これは分散型台帳により各ステークホルダーが同一の情報を共有することで、重複作業や確認作業が不要になるためです。
例えば紙ベースの契約書作成や郵送業務、手動での記録更新といった業務が不要となり、人件費や事務コストが圧縮されます。また決済エラーや手入力ミスの削減により、業務の信頼性も高まるでしょう。
STO(Security Token Offering)は証券としての性質を持つデジタル資産をブロックチェーン上で発行する手法であり、新しい資金調達の形として注目されています。これにより非上場企業でも、多様な投資家からの出資を受けやすくなるのです。
例えば不動産やベンチャー企業の持分といった、流動性の低い資産をトークン化することで小口での投資を可能にして資金の流動性を高められます。さらに発行・管理プロセスの効率化によって、従来の証券発行よりもスピーディーな資金調達が実現可能です。
ブロックチェーンはスマートコントラクトを活用し、事前に設定した条件に基づいた処理を自動で実行することによって人為的ミスを抑えることが可能となります。
例えば取引完了後の契約履行や手数料の自動計算、通知の送信などこれまで人手に頼っていた業務をシステムが代替することで、業務精度の向上が可能です。特に複雑な金融商品を扱う場面では、誤処理のリスクを軽減できる点が大きなメリットになります。
証券業界でブロックチェーン技術が注目される背景には、従来のシステムが抱える非効率性や不透明性への対応が求められている現状があります。そんな中においてデジタル化が進み、ブロックチェーンの特性を活かした具体的な活用シーンが拡大しつつあるのです。
ここでは、証券分野での代表的な活用例を紹介します。
セキュリティトークン(Security Token Offering、STO)は、証券に該当するトークンをブロックチェーン上で発行・管理する仕組みです。従来の株式や社債と同様に法的保護を受けながら、デジタル技術によって流動性や透明性を高めることが可能です。
例えば非上場企業がSTOを活用すれば、発行コストを抑えつつ少額からの投資を受け入れることができ、資金調達の間口が広がります。また発行後もスマートコントラクトにより権利の管理が自動化され、分配や譲渡の手続きが簡略化されます。
このような手段はスタートアップや中堅企業にとって、銀行融資やIPO以外の資金調達ルートとして期待が高まっており、実際に日本国内でも事例が増加しているのです。
従来、株式や債券の発行には多くの書類作成や関係機関との調整が必要でした。特に債券の利払い、満期償還などの運用時にも人的作業が多く介在していました。しかしブロックチェーンを導入すれば、これらの業務をスマートコントラクトによって自動化することが可能です。
例えば、一定の条件を満たした際に自動で利息の支払いが行われたり、名義変更が瞬時に反映されたりなど、投資家や発行体の負担を軽減できます。これによって人的ミスのリスクが減少し、取引の正確性も向上します。
さらに保有者情報もリアルタイムで更新できるため、IR活動や株主総会の通知など後続業務にもスムーズに連携が取れるのが強みです。
証券取引では、売買成立後の決済・清算に数日かかることが一般的です。この間に発生する信用リスクや管理コストは、関係機関にとって大きな負担となっています。そこでブロックチェーンを導入すると、これらの課題を解消する手段として機能するのです。
この技術は分散型台帳上で取引の成立から決済までを一気通貫で処理することができ、即時決済が現実のものになります。決済確認や資金移動がブロックチェーン上でリアルタイムに行われるため、従来必要だった第三者の仲介や照合作業も不要です。
これにより業務の簡素化とコストの削減が同時に達成され、特に国際間取引においては大きな利点となるでしょう。
証券業界において、口座開設時の本人確認(Know Your Customer:KYC)やマネーロンダリング対策(Anti-Money Laundering:AML)の徹底が法令で義務づけられています。従来は個別の金融機関が重複して情報を収集し審査を行っていましたが、ブロックチェーンを活用することでこのプロセスの最適化が期待されているのです。
ブロックチェーン技術を活用すると、KYC情報を暗号化した上でブロックチェーンに登録し、本人の同意を得て他機関と共有することが可能になります。これによって情報の正確性を担保しながら重複作業を省略でき、顧客にとっても手続きの簡略化という利点が生まれるのです。
AMLについても、取引履歴や資金の流れが記録された台帳を活用することで異常なパターンを検知しやすくなり、不正行為への早期対応が可能になります。こうした取り組みは、金融業界全体の信頼性向上にも寄与するといえるでしょう。
参考:金融庁|マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン

証券業界でのブロックチェーン活用が進む一方、導入にはいくつかの乗り越えるべき課題があります。技術的な魅力だけに目を奪われず、制度的・運用的な観点からも慎重な対応が重要です。
ここでは特に注意すべき、3つのポイントについて解説します。
まず大きな課題として挙げられるのが、法規制とガバナンスの整備です。ブロックチェーン技術は国境を越えた運用が可能ですが、証券取引には各国で異なる法律や監督機関のルールが存在します。特にSTOのように資金調達に関わる取り組みでは、金融商品取引法や電子記録移転権利法との整合性が重要になるのです。
金融商品取引法では、有価証券に該当するトークンを取り扱う場合、発行者や取扱業者に対して第一種金融商品取引業の登録が求められます。また、募集や売出しの際には目論見書の作成と提出義務が発生するため、STOが適用対象となるか否かの法的判断が極めて重要です。
一方、電子記録移転権利法は、株式などの権利をブロックチェーン上で移転可能な電子的な方法により表現・管理できるようにする法律で、STOで発行されるトークンが同法の対象となるかどうかも、法的スキームを構築するうえでの鍵を握ります。とりわけ、「電子記録移転有価証券表示権利等」としての法的位置づけが不明確な場合、事業者は証券保管振替機構との制度上の整合性や法的解釈を確認する必要があります。
参考:金融庁|金融商品取引法について
参考:金融庁|日本STO協会「電子記録移転権利法」
ブロックチェーン単体ではなく、既存の証券システムや業務基盤とのスムーズな連携も重要な要素です。現場で使用されている基幹システムとブロックチェーンが適切に連動しなければ、業務が分断され、効率化どころか混乱を招く恐れもあります。
そこで、取引履歴をブロックチェーンに記録するだけでなく、取引所の管理システムや顧客管理(CRM)、リスク管理ツールともデータを連携させる必要があります。その際フォーマットの違いや更新頻度のズレがトラブルの原因になることもあるため、整合性を保つための設計が不可欠です。
また誤ったデータが一度記録されると改ざんが難しいブロックチェーンの性質上、訂正が容易ではありません。そのため初期段階での入力精度を高めるだけでなく、事前の検証フローや承認プロセスを強化しておくと運用上のリスクを低減できます。
最後に、証券業界全体での標準化と相互運用性の確保が課題として浮上しています。個別企業が独自にブロックチェーンシステムを構築しても、業界全体で足並みが揃っていなければネットワークの価値は限定的になってしまうのです。
例えば、異なるブロックチェーン基盤間でトークンの送受信ができない、もしくは取引情報の共有ができない状況では、シームレスな取引の実現は困難でしょう。この問題を解決するためには業界横断での標準仕様策定、技術連携の推進などが不可欠です。
さらに、グローバルに展開する金融機関との連携も視野に入れる必要があります。日本国内だけで完結するスキームではなく、海外市場とも互換性のある設計を行うことが今後の成長には欠かせない要素となるのです。
ブロックチェーン技術を証券業務に活用する動きは、国内の大手金融機関にも広がりを見せています。実際の導入事例を確認することにより、どのような目的で技術が活用されているのか導入効果のイメージをつかみやすくなることでしょう。
ここでは、3つの代表的な取り組みを紹介します。
三菱UFJ信託銀行は、ブロックチェーン基盤のデジタル証券プラットフォーム「Progmat(プログマ)」を通じ、新たな資金調達の手段を提供しています。これは従来の社債や株式に比べて発行手続きが簡素化され、かつ透明性が高まる仕組みです。
実際に、従来必要とされた紙ベースでの手続きや煩雑な証券会社とのやりとりを削減し、より少人数のチームでも効率よく資金調達を行える体制が整います。またスマートコントラクトを用いることで、利払いや満期償還といった業務の自動化も可能です。
これによって企業側の事務負担が軽減され、投資家にとっても信頼性のある情報がタイムリーに提供される環境が実現しています。
SBIホールディングスでは、ブロックチェーンの活用によるNFT取引市場への参入を進めています。金融機関としての信頼性を背景に、デジタル資産を活用した新たな投資機会の提供を目指したものです。
実際に、アートや音楽、IPコンテンツなどのNFTを売買できるプラットフォームを整備することで、証券とは異なる分野の投資層の獲得に成功しています。NFTが証券としての側面を持つ場合は該当する法的整備や取引管理も必要となりますが、SBIはその法的な適合性にも配慮しつつ事業を推進しているのです。
これは、既存の金融ノウハウとWeb3の融合で新市場を開拓する好例といえるでしょう。
野村證券では、不動産投資における小口化の取り組みにブロックチェーン技術を活用しています。具体的には、分散型台帳を活用して不動産の所有権や収益権をデジタル化し、それらを少額単位で個人投資家へ販売するモデルを構築しました。
例えば数万円から参加可能な不動産投資商品を提供することで、従来アクセスが難しかった不動産市場への参入ハードルを下げています。また、分散型台帳上での権利移転は透明性が高く二次流通にも対応しやすいため、投資商品の流動性を高める効果も期待されています。
このような活用事例は資産運用の多様化と新たな投資体験の創出につながっており、証券業界全体にとっても有望な方向性を示しているのです。
参考:野村證券株式会社

ブロックチェーン技術は証券業務における透明性や効率性、セキュリティの向上を実現する強力なツールです。実際に国内大手企業がさまざまな目的で導入しており、その成果は徐々に明らかになっています。とはいえ制度や技術の整備、業界全体の連携といった課題も存在し、単独での導入には慎重な判断が必要です。そのため、自社の状況を見極めたうえで、この記事を参考に検討を進めてみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
