証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

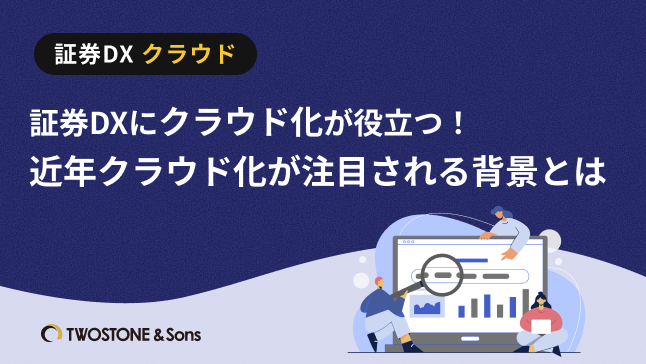
証券DXを推進するためのクラウド導入事例を紹介し、業務効率化やシステムの高度化について解説しています。また専門的な支援を活用し、証券業界のクラウド化を円滑に進めるための最適なソリューションを提案しています。
近年、証券業界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進展しています。その中でクラウド技術の活用が注目を集めているのは、多様化する顧客ニーズや働き方の変化、そして既存システムの限界が背景にあります。多くの証券会社が従来のオンプレミス環境からクラウドへと移行する理由を理解することで、業務効率化や顧客体験の向上を実現しやすくなるのです。
この記事では、証券DXにおいてクラウド活用が求められている背景を詳しく解説し、そのメリットを見据えた取り組みの方向性を示します。クラウド化の本質を把握することで、自社のDX推進に役立てられる情報を提供します。

クラウド技術は単なるITインフラの変革にとどまらず、業務プロセスの革新やサービスの質向上に直結しているのです。証券業界が抱える課題に対処し、未来の競争力を高めるためにクラウドの導入は欠かせません。
ここではクラウド活用が急速に注目される、3つの大きな背景について掘り下げます。
日本社会は現在、急速な少子高齢化によって労働力不足が深刻化しています。
証券業界でもこれは例外でなく、熟練社員の退職や人材確保の難しさが業務運営の課題となっているのです。この環境下でテレワークやフレックスタイム制など多様な働き方の導入が進んでいますが、従来のオンプレミスシステムでは場所や端末に縛られることが多く、柔軟な対応が難しい場合があることでしょう。
例えば、クラウド基盤を活用すればどこからでも安全にアクセスでき、業務の継続性と生産性の両立を図れます。クラウドはリモート環境の整備と労働効率向上の両面で貢献し、減少する労働人口に対応した働き方改革を支援します。
投資家や取引顧客のニーズは多様化・高度化しており、迅速かつパーソナライズされたサービス提供が求められているのが現状です。この状況で従来の一斉対応型サービスでは、細分化された顧客要求に応じるのは困難といえるでしょう。
例えばリアルタイムでの市場データ提供や取引状況の可視化、AIによる資産運用アドバイスなど高度な機能を提供するには、大量データの高速処理や柔軟なシステム連携が必要です。クラウド基盤はスケーラブルで拡張性が高く、新たなサービス展開を支える環境を整えやすいメリットがあります。
これにより顧客満足度の向上を実現し、競争優位性を高める手段として注目されています。
多くの証券会社で依然利用され続けている長年運用されてきたレガシーシステムですが、これらは機能拡張や他システムとの連携が困難なため効率的なデータ活用を阻害しています。
今の証券会社では、膨大な取引データや顧客情報をリアルタイムで分析し、経営判断やリスク管理に活かすには柔軟なデータアクセス環境が不可欠です。
こういったケースでも、クラウド導入によってデータを一元管理しつつ高度な分析基盤を構築しやすくなり、デジタル技術を駆使した新たな金融商品開発やマーケティング施策を可能とすることで業務革新の加速が期待されます。
参考:経済産業省|DX推進指標
証券業界でクラウド導入を検討する際には、まずクラウドの基本的な種類や特徴を理解することが欠かせません。特に、インフラを提供するIaaS(Infrastructure as a Service)、開発基盤を提供するPaaS(Platform as a Service)、業務アプリケーションを提供するSaaS(Software as a Service)といった分類の違いを把握しておくことが重要です。これにより、業務ニーズやセキュリティ要件に最適なクラウド環境を選択しやすくなります。多様なクラウドサービスの中で自社に合った形態を見極めることが、DXの成功を左右するポイントです。
ここではクラウドの種類とオンプレミスとの違い、さらに代表的なクラウド形式について解説し、証券業界特有の視点も交えて説明します。
クラウドサービスは大きく3種類に分類され、使い方や管理の仕組みが異なります。
まずプライベートクラウドは自社専用の環境であり、セキュリティや運用管理を自分たちでコントロールできるメリットがあります。証券会社のように顧客データや取引情報の保護が重要な業界では、プライベートクラウドを選択するケースが多いことでしょう。
次にパブリッククラウドは、AWSやAzure、Google Cloudなどの大手事業者が提供する共用環境で、コスト効率やスケーラビリティに優れています。急速に変化する市場環境に対応するため、必要なリソースを柔軟に拡大縮小できる点が強みです。
最後にハイブリッドクラウドは、プライベートとパブリックの両方を組み合わせ、データの機密性と運用効率のバランスを追求する方式です。例えば取引の核心部分はプライベートクラウドで安全に管理しながら、分析やバックアップの一部をパブリッククラウドに委ねるケースが典型的といえます。
この3種類を理解し、業務に合ったクラウド選択が重要となります。
クラウドとオンプレミスの違いは主に、インフラの所有と管理方法にあります。
オンプレミスは自社でサーバーやネットワーク機器を保有し、社内に設置して運用する方式です。これに対してクラウドは外部のデータセンターに設置されたリソースを、インターネット経由で利用するモデルです。
証券会社においてオンプレミスは、高いセキュリティと物理的な管理が可能という強みを持つのですが、設備投資や運用コストが膨大になりがちで変化に対する柔軟性が低いという問題も抱えています。実際に市場の急激な拡大に応じて新しいシステムを導入する際には、サーバーの増設や保守作業が大きな負担となるケースが多いです。
一方でクラウドは、初期コストを抑えつつ必要な分だけリソースを利用可能で、システムの拡張や縮小が短時間で行えます。繁忙期の取引量増加にもスムーズに対応できるため、業務の継続性と効率性が向上するのです。ただし、情報漏えいや規制対応などのセキュリティ面では慎重な設計と管理が求められるため、注意が必要です。
クラウドの基本的な種類に加え、さらに詳しく代表的な形式を理解することが不可欠です。証券業界でよく用いられるプライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウドの特徴を順に見ていきましょう。
プライベートクラウドは特定の企業専用に設計されるため、セキュリティやコンプライアンスの観点から高いレベルの管理が可能です。証券業務では顧客の個人情報や取引履歴を厳重に守る必要があるため、この形式が好まれます。
例えば自社データセンター内にクラウド環境を構築し、アクセス制御や監査ログの管理を徹底することで外部リスクを低減できます。
また自社の要望に合わせてシステムカスタマイズが可能で、独自の業務フローに適応しやすい点も魅力です。ただし初期投資や運用負荷が大きい点がデメリットであり、専門のIT人材が求められます。
パブリッククラウドは多数の利用者が共通のインフラを共有する形態であり、コストパフォーマンスが高いのが特徴です。証券会社が新規サービスをスピーディーに展開したい場合や、分析基盤を短期間で構築したい場合に適しています。
例えばビッグデータ分析やAIによる市場予測など、計算リソースを大量に必要とする処理に活用できます。ただし共有環境のためデータ分離やセキュリティ対策が課題となるため、クラウド事業者と協力し暗号化やアクセス管理を強化することが不可欠です。
ハイブリッドクラウドはプライベートとパブリックの利点を組み合わせ、リスク管理とコスト効率を両立します。証券業界では取引や顧客データはプライベートクラウドに置き、分析やシステムバックアップはパブリッククラウドに任せる運用が一般的です。
例えば取引システムの安全性を確保しつつ、市場データのリアルタイム処理や外部との連携部分で柔軟性を持たせるといった使い分けが可能です。この形態により変動するビジネス要件に対応しやすく、将来的な拡張にも柔軟に備えられます。

証券業界におけるクラウド導入は単なるITインフラの移行に留まらず、業務効率の向上や新しいビジネスチャンスの創出に直結します。
ここで紹介するのは、具体的に証券会社がクラウドを活用することで得られる代表的な6つのメリットです。これらを理解すればクラウド導入の意義がより明確になり、自社の戦略に役立てやすくなるでしょう。
クラウド導入によって業務環境が大きく変わり、証券会社は変化に即応する柔軟性を獲得できます。これは市場の変動が激しい証券業界において重要です。
従来のオンプレミス環境では新たなシステムやサービスの導入に、数ヶ月単位の準備期間が必要でした。しかしクラウド環境なら必要なリソースをすぐに確保でき、システム構築やアップデートも迅速に行えます。
例えば新しい金融商品の取扱いや規制変更に対応するシステム改修を短期間で実施し、競争優位を保てます。またテレワークやモバイルアクセスもクラウドで容易になり、業務の場所や時間に縛られない柔軟な働き方を実現します。
これにより社員の生産性向上やワークライフバランスの改善にもつながるのです。
クラウドの利用は初期投資を抑えられるだけでなく、運用コストの効率化にも寄与します。
オンプレミスではサーバーやネットワーク機器の購入、設置、保守に多額の費用がかかってしまい、特に設備更新の際には大規模な資金投入が必要となります。それに対してクラウドは、必要な分だけ利用料を支払う従量課金型が主流であり、不要なリソースを抱えずに済むのです。
例えば取引が少ない閑散期はリソースを縮小し、繁忙期はスムーズに拡張できるため無駄なコストを抑制可能です。さらにシステム管理や運用業務の一部をクラウド事業者に委託でき、社内のITリソースをコア業務に集中させられます。
結果としてトータルコストの最適化が実現し、経営資源の効率的配分が促されるのです。
証券市場の動向や新たな事業展開に対応するためには、システムのスケーラビリティが欠かせません。クラウドの大きな強みはこのスケーラビリティを柔軟、かつ迅速に確保できる点です。
従来のオンプレミスでは設備投資の制約や調達時間の問題で、急激な需要増加に対応しにくい側面がありました。一方でクラウドはサーバーやストレージを即座に増強でき、ピーク時のトラフィック増加にも問題なく対応可能です。
例えば株価の大幅変動時には取引量が急増するものですが、クラウドのスケーラブルな設計なら遅延やシステムダウンのリスクを減らし、顧客満足度を維持できます。
拡張性があることで将来的な成長や新サービス開発の基盤も整います。
証券会社にとって膨大な市場データや顧客情報を効果的に活用することは、競争力の源泉です。クラウドは大量のデータを効率よく蓄積し、分析するための強力な基盤を提供します。特にビッグデータ解析や機械学習、AI活用といった高度なデータ処理はクラウドのスケーラブルな計算リソースが不可欠です。
例えば、リアルタイムで市場の動向を分析して投資判断を支援する仕組みを構築する際には、クラウドのデータ分析プラットフォームが役立ちます。
また複数のデータソースを統合して一元管理することも可能になり、情報の鮮度と精度が向上します。これによって新たな金融商品の企画やリスク管理の高度化を実現できるため、戦略的な意思決定が加速するのです。
証券業界は個人情報保護や金融規制など、多くの厳格なセキュリティ要件に直面しています。クラウドはこれらの要求に応えるための最新セキュリティ技術、コンプライアンス対応などを迅速に導入できるメリットがあるのです。多くのクラウド事業者は高度な暗号化技術や多層防御システムを実装し、監査ログの自動収集・管理なども提供しています。
例えば顧客データのアクセス権限を細かく設定し、不正アクセスや情報漏えいのリスクを最小限に抑えられます。さらに、金融庁の規制や国際的な標準規格に準拠した環境構築も支援されており、自社での対応負担を軽減しつつ安全性を高められるのです。
継続的なセキュリティ監視とインシデント対応もクラウドなら効率化されるため、リスクマネジメントが強化されます。
参考:金融庁|金融検査マニュアル
参考:日本証券業界|システムリスク管理態勢について
昨今の証券業界では、フィンテック企業や外部サービスとの連携が不可欠となっています。クラウド環境はAPI連携やデータ交換が柔軟に行えるため、他社サービスとの統合がスムーズです。
例えばスマートフォン向けの投資アプリやロボアドバイザー、AIによる資産運用サポートなど、外部の先進技術を取り込みやすくなります。これによって顧客に新たな価値を提供し、競争力を強化できるのです。
また、マルチクラウドやハイブリッドクラウドの活用によって多様なパートナーシップを築きやすい環境が整い、クラウドのオープンな仕組みを活かして業界全体のエコシステム形成にも貢献します。
証券業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、クラウド導入によって大きな成果を上げています。
ここで紹介するのは、実際にクラウド活用によって業務効率化や新たなサービス展開に成功した企業の事例です。これらの具体例はクラウドの有効性を理解し、導入検討の参考になるでしょう。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)はデジタルバンク設立の基盤として、Google Cloudを積極的に採用しています。MUFGは従来の金融サービスに加え、デジタル技術を融合させることで新たな顧客体験の創出を目指しました。
Google Cloudの活用によって柔軟なシステム構築と高速なデータ処理が可能になり、顧客のニーズに即応できる環境が整いました。特にデータ分析基盤の強化が実現し、リスク管理やマーケティング戦略の精緻化に貢献しています。
これによって迅速かつ安全な金融サービスの提供が可能となり、デジタルバンクとしての競争力を大きく高めています。
SBI証券は国内株式のオンライン取引システムをクラウド化することで、システムの可用性と拡張性を向上させました。
従来のオンプレミス環境ではシステムの拡張に時間がかかるという課題がありましたが、クラウド基盤の採用により需要に応じて迅速にリソースを調整できる体制を構築しました。これによって取引が集中する時間帯でもシステムダウンを防ぎ、顧客の取引体験を損なわずに済んでいます。
さらにクラウドの特性を活かして機械学習を活用した投資分析ツールの導入も推進されており、顧客の投資判断を支援する仕組みが強化されています。
参考:株式会社SBI証券
SMBC日興証券では複雑な金融工学計算の高速化を目的に、クラウドサービスを活用しています。従来は社内のサーバー資源に限界があり大量の計算処理に時間を要していましたが、クラウド導入によって必要な計算資源を柔軟に確保できるようになりました。これによってリスク評価やポートフォリオ最適化のスピードが改善され、投資判断の迅速化につながっています。
またクラウドの冗長性を活かしてシステムの安定稼働も実現されており、金融商品開発のスピードアップに貢献しています。
参考:SMBC日興証券株式会社

証券業界のDX推進はクラウド活用によって変革を遂げつつあります。業務の柔軟性やスピードの向上、運用コストの最適化、そして高度なセキュリティ対応が実現し、競争力を維持・強化する上で欠かせない要素となりました。
今回紹介した企業の事例からもクラウド導入が単なる技術刷新に留まらず、業務効率化や新サービス創出に直結していることが見て取れることでしょう。
クラウドを軸としたDXは、今後ますます重要性を増していくと考えられます。この記事を参考にして、自社にとってどのようなクラウド活用が最適なのかを見直し、より柔軟かつ戦略的に取り組んでみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
