証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

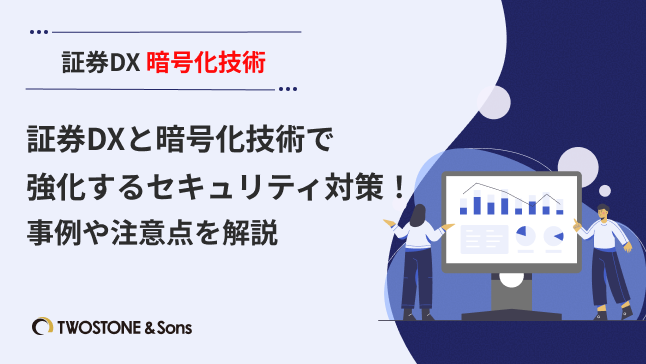
証券業界で暗号化技術を導入すると、情報セキュリティの確保と業務の信頼性向上に大きく寄与します。本記事では証券DX推進に関連する暗号化技術の種類や実際の導入事例、そして導入に際して注意すべきポイントを詳しく解説しています。
デジタル化の加速とともに証券業界でも業務の効率化や利便性向上を目指し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が進んでいます。
しかし便利さが増す一方で、サイバー攻撃や情報漏えいといったリスクも増加し、セキュリティ対策の重要性がこれまで以上に高まっているのが現状です。特に暗号化技術は顧客の資産や個人情報を守るための基盤として注目されており、導入の有無が企業の信頼性にも直結します。
本記事では、証券DXの推進に伴って求められるセキュリティ対策の背景と、その中核をなす暗号化技術について事例を交えてわかりやすく解説します。これを読むことで、証券DXを安心・安全に進めるために必要な視点と対策が見えてくるでしょう。

証券業界がDXを進める中でなぜ暗号化技術の強化が不可欠なのか、背景にはさまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは主な理由を挙げ、具体的に掘り下げていきます。
まず挙げられるのが、サイバー攻撃、内部不正などの脅威への対処です。近年では金融機関を標的としたフィッシング詐欺やマルウェア感染が急増しており、外部からの不正アクセスによって顧客データが流出する事件が後を絶ちません。さらに、関係者による情報持ち出しといった内部の不正も無視できないリスクです。このような状況では通信経路やデータの保存環境に対し、強固な暗号化を施すことが不可欠となるでしょう。
実際、警察庁が公表した「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によれば、令和5年におけるフィッシングの報告件数は119万6,390件(前年比で23.5%増)と過去最多となり、特に金融関連を装ったフィッシング詐欺が顕著に増加していると報告されています。また、ランサムウェア被害の届出件数も1年間で159件にのぼり、重要インフラや企業の基幹システムを狙った攻撃が深刻化している実態も浮き彫りになっています。
例えばTLS(Transport Layer Security)を用いた通信の暗号化、AES(Advanced Encryption Standard)によるデータの暗号保存などが有効な手段となります。技術的な防御を固めることで、仮にアクセスが発生しても情報が解読されるリスクを最小限に抑えることが可能なのです。
参考:警視庁|令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
DXの推進に伴いクラウドサービスやAPI連携、モバイルアプリなどの新たな技術が次々と導入されています。しかしこれらは業務の効率化やユーザー体験の向上に貢献する一方、新たな脆弱性をもたらすリスクも内在しているのです。
APIの認証設定が不十分であれば、不正なリクエストによる情報取得が可能になってしまう場合があるでしょう。また、クラウド環境では適切なアクセス制御や暗号化が行われていない場合、外部の第三者から簡単に情報へアクセスされる危険もあります。そのため、技術導入と並行してセキュリティの強化が求められるのです。
証券業界において顧客データは単なる記録情報ではなく、企業にとって戦略的な資産としての重要性が年々高まっています。個人の投資履歴や資産状況といった情報はサービスのパーソナライズや営業戦略に活用される一方、外部に漏れると信用失墜につながりかねません。そのため、こうした機密性の高い情報にはデータベースレベルでの暗号化や鍵管理の徹底が必要です。
顧客情報に対して行レベルやカラムレベルで暗号化を施すと、不正アクセスが発生した場合にも情報の読み取りを防止することが可能になるでしょう。
従来の境界型セキュリティでは社内と社外を明確に分けて内部を信頼するという前提がありましたが、DXの推進によってネットワークの境界が曖昧になりつつある昨今では、その前提自体が成り立たなくなっています。このような状況を背景に注目されているのが、ゼロトラスト・セキュリティの考え方です。ゼロトラストとはすべてのアクセスを「信頼しない」ことを前提にしてユーザー認証や通信の暗号化、行動ログの監視を徹底するアプローチです。
例えば社員が自宅から社内システムにアクセスする場合でも、多要素認証やVPNを通じてアクセスを管理して通信内容全ての暗号化を要する、といった設計がDXのリスクを抑えるカギとなります。
昨今の証券業界は大手企業に加え、フィンテックベンチャーなど多様なプレイヤーが参入することで競争環境が大きく変わってきています。顧客はより利便性の高いサービスを求める一方、セキュリティ面の信頼性も厳しくチェックするようになってきました。こうした中で企業が他社と差別化を図るには、利便性と安全性を両立させる設計が不可欠です。
例えばログインから取引、口座情報の閲覧に至るまですべての通信経路に暗号化を適用し、顧客の情報保護に万全を期することが選ばれる証券サービスの条件となるでしょう。
証券業界では日々、大量の個人情報や取引データが扱われています。これらの情報を安全に保護するため、暗号化技術が重要な役割を担っているのです。暗号化は単なるデータ変換ではなく、複数の技術要素が連携することで強固なセキュリティを実現しています。
ここでは暗号化技術の基本的な仕組みについて、3つの観点から解説します。
まず暗号化技術の中核を担うのが、情報そのものを変換するプロセスです。これは平文と呼ばれる人間が読めるデータを、第三者が理解できない暗号文へと変換する工程を指します。
例えば、顧客の取引履歴やログイン情報などをそのままサーバーに保存すると、仮に不正アクセスを受けた際に情報がすぐに読み取られてしまう危険があります。これに対して、AES(Advanced Encryption Standard)やRSA(Rivest–Shamir–Adleman)といった暗号アルゴリズムを用いてデータを暗号化しておくと、情報の内容を把握するには復号用の鍵が必要となるのです。
これによって万が一アクセスされた場合でも、情報漏えいのリスク軽減が可能になります。さらに最近ではデータベース全体ではなく、特定のカラムだけを暗号化する「カラムレベル暗号化」も活用されており、セキュリティとパフォーマンスの両立が図られています。
参考:IPA独立行政法人情報処理推進機構|米国連邦政府での暗号標準利用の ためのガイドライン
暗号化された情報を安全に復号するためには、鍵の存在が不可欠です。つまり暗号技術の強度は鍵の生成、及び管理体制に大きく依存します。
例えばAES方式では同一の鍵で暗号化と復号が行われるため、鍵が流出した場合には重大なリスクが生じます。そのため鍵の生成には乱数生成器を用いた高強度な手法が採用され、管理にはHSM(Hardware Security Module)などの専用装置が使われるのです。
また証券業界では鍵のライフサイクル管理も重要です。鍵の定期的な更新やアクセスログの記録、複数ユーザーによる権限の分離などを組み合わせることで内部不正への対策としても有効な管理体制が構築されています。
暗号化された情報を実用化するためには、復号化のプロセスも必要不可欠です。復号化とは暗号文を元の平文に戻す処理であり、正しい鍵を持つ者のみが実行できる仕組みです。
例えば顧客が自身の証券口座にログインした際、保存されている暗号化済みの氏名や取引履歴をリアルタイムで復号することでサービスを滞りなく利用できるようにしています。ここでは処理速度と安全性のバランスが重視され、復号処理が遅すぎるとUX(ユーザー体験)に悪影響を与えるため効率的な実装が求められるでしょう。
復号化では鍵が正しく使用された場合に限り、正しい情報が取り出せるよう設計されています。これにより攻撃者がデータにアクセスしても、情報を読み取ることはできません。このプロセスがあることで、暗号化の効果が最大限に発揮されるのです。
暗号化技術は単にセキュリティを高める手段ではなく、業務全体に対して多角的なメリットをもたらします。特に証券業界においては暗号化の導入・強化によって、ここで紹介する5つの重要な成果が期待されています。
明確なメリットは情報漏えい、不正取得などを防ぐセキュリティの強化です。暗号化された情報はたとえ外部からの攻撃で入手されたとしても、鍵がなければ意味を持ちません。
取引データや顧客の個人情報がすべて暗号化されていれば、システムに侵入された場合でも情報の内容までは読み取られないのです。これにより、組織全体のセキュリティレベルが向上します。暗号化は外部攻撃だけでなく、内部関係者による情報流出の抑止力にもつながるのです。
金融業界ではFISC安全対策基準や個人情報保護法、金融庁ガイドラインなど厳格なルールの遵守が求められています。暗号化技術の導入により、これらの法的要件を確実に満たす体制を構築しやすくなります。
実際に、金融庁が定める「システム管理態勢の高度化」においても暗号化の実装が明確に求められており、企業としての信頼性を維持する上でも欠かせません。コンプライアンス強化は監査対応をスムーズにし、経営上のリスクを軽減する意味でも重要です。
参考:個人情報保護委員会|金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
セキュリティ対策が強化されているサービスは、顧客からの信頼を得やすくなります。個人情報が適切に保護されていると感じられれば、利用継続の動機づけにもつながるでしょう。
実際に、ログイン時に暗号化されたパスワードが使用されて通信もTLSで保護されていることが明示されていれば、安心して取引を行えると感じるユーザーは多いです。こうした細部の対応がサービス全体の利便性向上にもつながり、長期的な顧客満足度の向上に寄与します。
暗号化技術の強化は、攻撃者にとっての障壁を高くするという観点からも効果的です。仮に侵入されても、情報を解読できない環境であればそのモチベーション自体を下げられるのです。
データが暗号化されており、さらに通信がVPNとSSLで二重に保護されていれば攻撃コストが上昇します。こうしたセキュリティ設計を採用することで組織全体が標的とされにくくなり、平常時からの抑止力として機能するのです。
最後に、暗号化は業務の効率化とコスト削減にもつながる点は意外と見落とされがちではないでしょうか。従来の物理的な管理手法や紙媒体での記録・保存に比べ、デジタル化された暗号化環境は圧倒的に管理がしやすくなります。
例えばオンライン上での本人確認や電子署名を導入すると、書類の送付や印鑑の押印が不要となり、処理時間の短縮と運用コストの削減が可能になるでしょう。また誤送信や情報紛失といった人的ミスも減少し、結果として全体のオペレーションの信頼性が向上するのです。

証券業界におけるDXでは情報の安全性を担保する技術として、暗号化技術が中心的な役割を果たしています。近年では単なる暗号化だけでなく、先進的な技術と組み合わせた統合的なセキュリティ対策が進められているのです。
ここでは実際に導入が進んでいる、代表的な暗号化技術について紹介します。
量子暗号通信は量子力学の原理を応用し、絶対的な安全性を実現する通信方式です。量子鍵配送(QKD)技術によって、盗聴が理論的に不可能な暗号鍵のやり取りが可能となります。
この技術を活用すれば仮に通信が傍受されても、鍵そのものの改ざんや解読はできません。
実際に東芝デジタルソリューションズ株式会社では、光ファイバー網を通じた都市間通信においてQKDの長距離実証に成功し、商用レベルの適用可能性を広げています。こうした技術が証券取引に導入されることで、膨大な資産情報や機密文書の完全な保護が期待できます。
AES(Advanced Encryption Standard)はアメリカ国立標準技術研究所(NIST)によって制定された暗号化方式で、現在もっとも広く利用されている対称鍵暗号の1つです。AESは暗号強度が高く、処理速度も優れているため証券会社のサーバー間通信やオンラインバンキングなど多くのシステムで採用されています。
実際に金融庁のガイドラインにおいてもAESは安全性が高い方式として明示されており、セキュリティ対策のベースラインとして位置づけられています。証券DXの進展においてはAESによる暗号化に加え、鍵管理や多層防御との連携が求められるのです。
ブロックチェーンは分散型台帳技術として、改ざん耐性と透明性を併せ持つ点が大きな特徴です。特定の管理者を持たないネットワーク上でデータを共有し、取引の信頼性を保証できます。
日本電気株式会社(NEC)では独自のコンセンサスアルゴリズムを導入し、高速かつ高スループットなブロックチェーンプラットフォームを開発しています。証券取引においては株式の発行から売買、清算に至る一連のプロセスをブロックチェーン上で記録・管理することで不正や誤記録を防止し、業務効率の向上にも貢献するのです。
参考:日本電気株式会社
証券業界では、既に多くの企業が暗号化技術を積極的に導入しています。それぞれの企業が自社の特性やニーズに応じて先端技術を取り入れており、具体的な活用例からもその効果や可能性が見て取れることでしょう。
大和証券グループ本社は量子暗号通信と秘密分散技術を活用し、音声データのセキュリティ対策を強化しています。特にコールセンターで扱う顧客との通話内容には高い機密性が求められますが、これまでの暗号化では盗聴リスクを完全に排除することが困難でした。
そこで、量子鍵配送を用いた暗号鍵を活用することで通話データはリアルタイムで暗号化され、さらに複数のサーバーに分割保存する「秘密分散技術」を導入することで仮に一部のデータが漏えいしても完全な復元ができないよう設計されました。これにより顧客情報の保護だけでなく、業務上の透明性も向上しているのです。
三菱UFJ信託銀行株式会社ではデジタル証券の発行、及び管理にブロックチェーン技術を活用しています。従来の証券では権利移転の確認や照合に時間を要し、手続きの複雑さが課題となっていました。
ブロックチェーン技術を導入することで、証券の発行から権利移転、配当の記録まで一貫した管理が可能になり、すべての取引履歴が改ざん不可な形で記録されます。投資家の所有権が即座に確認でき、透明性の高い金融取引が実現されるとともに管理コストの削減も実現しています。
野村ホールディングス株式会社では、使い捨てパスワード(OTP:One Time Password)をベースとした高度な暗号通信の実証実験を行いました。OTPは一度限りの使い捨て鍵を用いるため、仮に通信が傍受されても同じ鍵が再利用されない仕組みとなっており、安全性が高いとされています。
この実証ではNICT(情報通信研究機構)と連携し、OTPによるリアルタイム通信に成功しました。これにより高速性と秘匿性を両立する、新しいセキュリティ基盤の構築に一歩近づいたと評価されています。金融市場の変化が激しい中、こうした迅速かつ安全な通信手段は大きなアドバンテージとなるのです。
証券DXの加速に伴い、高度な暗号化技術の導入が不可欠になっています。ただしその導入にあたっては技術面や制度面の課題をあらかじめ洗い出し、慎重に対応することが求められるのです。
ここでは導入時に留意すべき、重要なポイントを挙げます。
まず確認すべきは、導入する技術が現行の法令や業界ガイドラインに準拠しているかどうかです。証券業界は、金融商品取引法をはじめとする複数の法律によって厳格に管理されており、情報の取り扱いや通信方法にも高い透明性と信頼性が求められます。
例えば顧客情報を含む通信内容を暗号化する場合でも、その暗号化方式が政府や業界団体によって推奨されているものである必要があります。また海外ベンダーが提供する暗号化技術を導入する際には、国外への情報漏えいの懸念にも配慮するべきです。
コンプライアンス部門との連携を密にして、法的な適合性を逐一確認しましょう。
次に重要なのは、既存の業務システムとの互換性です。高度な暗号化を施すことで通信の安全性が向上する一方、従来のシステムとの非互換や処理速度の低下が新たな課題として浮上する可能性があります。
例えばブロックチェーン技術を用いたトランザクション管理を新たに導入する場合、その台帳システムと既存の顧客管理システム、取引報告システムとの間に不整合が生じるリスクもあります。導入前にPoC(概念実証)を行い、全体の技術アーキテクチャを見直すことが重要です。さらに今後のスケーラビリティも考慮し、将来的なアップデートに対応できる構成を設計する必要があります。
暗号化技術は導入して終わりではなく、継続的な運用と厳格な管理が必要です。特に復号プロセスにおいては、アクセス権限の管理や復号鍵の保護体制が企業の信頼性を左右します。
量子暗号通信などは極めて安全性が高い一方、専用のハードウェアと運用知識が不可欠です。このため、導入後は社内に専任のセキュリティチームを配置し、定期的なトレーニングと監査を実施することで暗号化体制の品質を維持しましょう。災害時や障害発生時の復旧プロセスも事前に策定しておくと、万が一の際にも柔軟に対応できます。
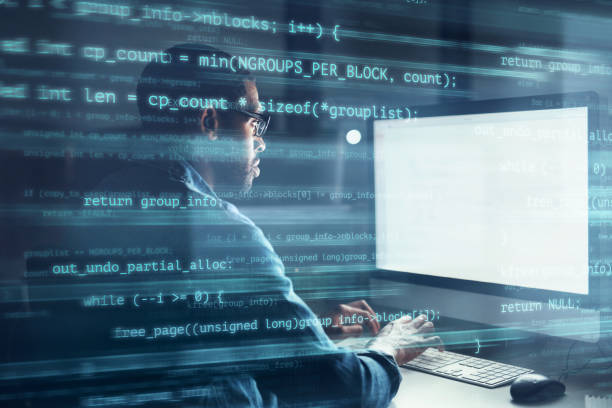
暗号化技術は、これからの証券業界において情報の安全性と業務の信頼性を両立させるカギとなります。量子暗号通信やAES、ブロックチェーンなどの各技術はそれぞれに特性があり、導入先のニーズやシステム構成に応じた選定が不可欠です。
あわせて、法令順守・システム間の互換性・運用管理といった導入後の課題にも目を向ける必要があります。これらを事前に考慮することで、安定した運用を実現できるでしょう。
今後、証券DXをさらに効果的に進めていくには、暗号化技術の選定から実装、そして運用体制の構築に至るまで、一貫した戦略をもって取り組みましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
