証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

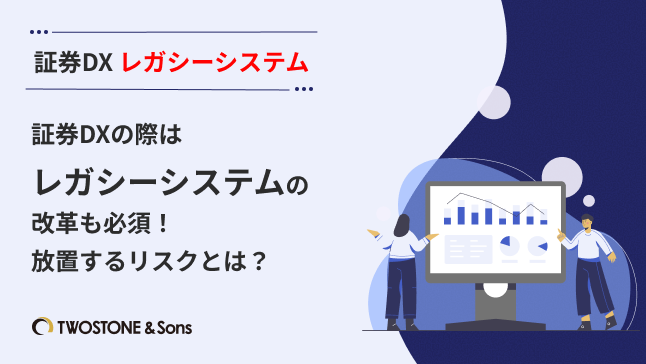
証券DX成功のためには、レガシーシステムに依存した業務プロセスの抜本的な見直しが欠かせません。本記事では業務継続性を確保しながら段階的にシステムを移行する方法や厳格なセキュリティ要件への対応など、具体的な取り組みポイントを詳しく解説しています。
証券業界でDXを進める企業が増えていますが、現場では古い基幹システムが足かせになっているケースも少なくありません。業務効率化やデータ活用を目指して最先端のテクノロジーを導入しても、既存のレガシーシステムがその足を引っ張ってしまうのです。このような背景から、DX推進の成否を左右するカギとして「レガシーシステムの改革」が注目されています。
本記事では証券DXにおいてなぜレガシーシステムが障壁となるのか、その理由を深掘りして放置した場合のリスクについても具体的に解説します。読み進めることで、自社のDX推進を成功させるための課題とその解決の糸口をつかめるでしょう。

証券業界のDXでは取引の自動化やデータの一元管理、顧客サービスの高度化など、さまざまな改革が求められています。これらを実現するには最新技術の導入が不可欠ですが、そこに立ちはだかるのが長年使われてきたレガシーシステムです。
まずは証券DXの概要とレガシーシステムの意味を整理し、両者の関係性を明確にしましょう。
証券DXとは、証券業務全体にわたってデジタル技術導入等を行い、業務プロセスの効率化や顧客体験の向上、新たなビジネスモデルの創出を図る取り組みを指します。オンライン取引の利便性向上やAIを活用したリスク分析、RPAによる定型業務の自動化などがその一例です。これによって迅速な意思決定や精度の高い運用支援が可能になり、顧客満足度と業務効率を同時に高める効果が期待されています。
証券DXでは社内に蓄積された多種多様なデータを活用し、リアルタイムな判断が求められます。したがって、システム間の連携やデータの統合基盤が重要となるのです。ところがここで障壁となるのが、既存のレガシーシステムの存在です。
レガシーシステムとは、企業が長年にわたり使用してきた旧式の基幹システムを指します。多くの場合はカスタマイズを重ねてきた独自仕様で構築されており、古いプログラミング言語やハードウェアに依存しているケースが多いでしょう。表面的には稼働していても内部の保守や改修には専門知識が必要となり、運用コストやリスクが高まっています。
特に証券会社では取引データや顧客情報など機密性の高い情報を扱うため、レガシーシステムが担う役割は依然として大きいです。新しいクラウド型システムやAIツールと連携させるには、多くの制約があるのも事実でしょう。そのためDXの推進には、レガシーシステムの見直しが不可欠となっています。
証券DXの実行フェーズにおいて、レガシーシステムの存在が技術的・組織的な障害として浮かび上がることが多くあります。ここではその主な理由を、2つの視点から具体的に見ていきましょう。
第一にレガシーシステムは構造が硬直化しており、最新技術との連携が困難であるという問題が挙げられます。
例えば、クラウドベースのデータ管理プラットフォームを導入しようとしても、既存システムがAPI連携に対応していない場合はリアルタイムデータの活用が制限されてしまいます。
またデータ形式が独自仕様で統一されていない場合、分析用のデータ抽出や変換に多くの工数が必要となります。結果としてプロジェクト全体の開発スピードが落ち、ビジネスチャンスを逃すリスクも高まるでしょう。
柔軟性のないシステムではユーザー要望に即応することが難しく、顧客体験の向上にも限界があります。特にスマートフォンアプリやオンラインプラットフォームとの統合を進める場面では、レガシーシステムの制約が足を引っ張る要因になります。
もう1つの障壁は、レガシーシステムの保守にかかるコストと属人化の問題です。古い技術を理解できるエンジニアが限られており、特定の担当者にしかメンテナンスができない状態は、技術的負債の蓄積を意味します。
実際にレガシーシステムは、プログラムの一部を改修する際に全体構造が不明瞭でリスクが高いため、作業の遅延やバグが発生する可能性が高まります。また現行の業務要件に合わせた改修が難しく、システム更新を行うたびにコストが発生するのです。
このような状況が続くとDX推進のための予算が保守費用に圧迫され、新規開発に回す余力がなくなります。結果として、業界のデジタル化の流れに取り残される危険性が高くなるでしょう。属人化が進めば進むほどシステムトラブル時の対応にも時間がかかり、業務停止リスクも上昇します。
証券DXを推進する上で、旧来のレガシーシステムが深刻なボトルネックになる場面は少なくありません。技術的な制約だけでなくビジネスの俊敏性や法令対応、さらには顧客体験にも悪影響を与えているのが実情です。
ここでは証券業界における、レガシーシステムの問題点を具体的に紐解いていきます。
多くの証券会社では、長年使われてきた基幹システムがそのまま稼働しています。これらのシステムは当初の設計思想や時代背景に強く依存しており、変化の速い市場環境に追従するのが困難です。
例えば新たな金融商品やサービスを迅速に市場投入する際、既存システムでは対応モジュールの追加や連携が容易でなく、結果として機会損失を招く可能性があります。柔軟なAPI連携やマイクロサービスアーキテクチャを採用していないシステムでは、新規チャネルとの接続にも多大な時間とコストを要します。
さらにベンダー依存度が高いシステムではカスタマイズの自由度が限られ、ユーザー部門からの要望にスピーディーに応えるのが難しくなるでしょう。こうした構造は業務のボトルネックを生み、DX推進を鈍化させる要因になりかねません。
金融業界は高度なセキュリティと、厳格な法令対応が求められる分野です。しかし、レガシーシステムではセキュリティ対策が現代の脅威に対応しきれていない、といったケースが多く見受けられます。
例えば暗号化技術やログ管理機能が不十分なシステムでは、サイバー攻撃に対する脆弱性が残りやすく、情報漏えいやシステム停止のリスクが常につきまといます。加えてOSやミドルウェアのサポート終了に伴い、パッチの適用も難しくなるためゼロデイ攻撃への備えも不完全になりやすい状況です。
また法改正への迅速な対応が求められる場面でも、硬直したシステム構成では修正作業が煩雑になり、結果としてコンプライアンス違反のリスクが増大します。金融庁のガイドライン変更やFATF(金融活動作業部会)による勧告など、国際的な枠組みに対応するためにも柔軟に変更を受け入れられる基盤が不可欠です。
参考:金融庁|金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン
顧客体験の高度化やパーソナライズされた金融サービスの提供には、データの活用が欠かせません。しかしレガシーシステムではデータが部署ごと、あるいは機能ごとに分断されて保存されているため統合的な分析が難しい状況にあります。
例えば口座情報や取引履歴、問い合わせ履歴などが異なるシステムに分散している場合、それぞれを統合して活用するには複雑なETL処理やマスターデータの再構築が必要です。これによりBIツールやAI分析の導入が後回しになり、顧客ニーズをリアルタイムで把握する体制が整わなくなってしまうのです。
また非構造化データ(音声記録・チャットログなど)の蓄積が進んでいても、分析に活用するにはフォーマット変換や自然言語処理の仕組みが必要であり、従来の基幹システムではそれに対応できない場合もあるでしょう。こうした分断されたデータ環境は、DXの根幹である「データドリブン経営」への移行を阻害しかねないのです。
システムが老朽化し、担当者の異動や退職によってノウハウが継承されないままになると業務全体が「なぜそうなっているのかわからない」というブラックボックス状態に陥ります。この状況は、業務改革や自動化を進める際に障害になりかねません。
既存フローの最適化を試みた際に、特定のバッチ処理や独自ルールがドキュメント化されておらず、業務担当者すらその詳細を把握していない、といったケースも同様です。こうしたケースでは修正を加えるリスクが高いため、DXプロジェクト自体が停滞しがちになるでしょう。
さらにブラックボックス化された業務では、内部統制の観点でも問題が生じます。トラブル発生時に原因追跡が難しくなり、顧客や監査機関への説明責任を果たすのが困難になります。信頼性が重視される証券業界において、これは信用リスクを伴うでしょう。
証券業界では、金融商品や市場環境の変化に迅速に対応する能力が競争力に直結します。しかしレガシーシステムがボトルネックとなっている場合、新規サービスの立ち上げや業務改善のスピードが著しく低下するのです。
例えば、スマートフォンアプリでの新機能追加やチャットボットの導入といった顧客接点の強化を行う際、基幹システムとの連携が取れないと表層的な改善にとどまり真のUX向上にはつながりません。またキャンペーン施策やレポート機能の拡充においても、実装スピードが遅ければ競合に後れを取ることになります。
さらに内部業務においても手続きの電子化やワークフローの効率化が進まなければ、人的リソースの負荷が高いままとなり、結果としてサービス提供全体に遅延が発生します。このような状態が続けば、顧客満足度の低下や離反の原因にもつながるでしょう。

レガシーシステムがもたらす多面的な課題を克服するには、単なる技術刷新にとどまらず、経営・業務・ITの三位一体で進める包括的なDX戦略が求められます。特に証券業界では顧客との接点や取引スピード、法令遵守などが厳しく問われるため、刷新の手順や手法を精緻に設計してリスクを最小化しながら段階的に移行するアプローチが不可欠です。
ここでは証券DXを推進する、具体的な方法を7つの視点から解説します。
証券システムは多層的であり、すべてを一気に刷新するのは現実的ではありません。フェーズごとに段階的な移行戦略を採用することで、システム停止やサービス影響のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
例えば非コア業務領域(顧客ポータルや照会システムなど)からまずクラウド化・モダナイゼーションを進め、その後順次基幹系業務に移行していく、といった手法が有効です。この際に影響範囲やデータ依存関係を洗い出し、マイルストーンごとに検証を重ねながら実施すると安定性と柔軟性の両立が実現できるでしょう。
また段階移行を成功させるには、PoC(概念実証)とモック開発を組み合わせることも有効です。初期フェーズで得られた知見を次のフェーズへ活かす循環構造を設けることで、全体最適なDXが加速するでしょう。
レガシー刷新の中核となる考え方の1つが、システム構造のマイクロサービス化です。これは機能ごとに独立したサービス群として設計し、変更や拡張を容易にするアーキテクチャです。
例えば口座開設や入出金、注文処理などを独立したサービスとして実装することで、ある一部の改修が他の機能に波及しにくくなります。結果として、サービス単位での迅速な改善やスケーリングが可能になるのです。さらにCI/CD(継続的インテグレーションと継続的デリバリー)の仕組みを組み合わせることで、短いサイクルでの機能リリースも現実的になるでしょう。
一方でマイクロサービス化には組織体制や運用スキルの転換も求められるため、既存のSI体制を再構築する必要があります。システムだけでなく、人材育成やプロジェクトマネジメントの仕組みにも目を向ける必要があるでしょう。
レガシー刷新を急ぐあまり既存システムと断絶してしまうと、業務継続性や顧客利便性に支障を来すおそれがあります。そこで有効なのが、APIを介した既存システムとのブリッジングです。
例えば新たに開発した顧客管理機能を旧来の取引システムとAPI連携させると、データ連携と操作性の両立を図ることが可能です。またバックエンドシステムの刷新が完了していない段階でも、フロントエンドの改善を先行させる戦略が取りやすくなります。
API設計においてはRESTfulアーキテクチャやGraphQLなど、モダンな技術選定が求められます。同時にセキュリティや認証方式(OAuth2.0など)にも十分、配慮することが不可欠です。APIガバナンスの整備も並行して行うことで、スムーズなシステム間連携が実現します。
証券業務におけるシステム基盤は、かつてオンプレミス環境が主流でした。しかし近年では、クラウド移行がセキュリティ・コスト・拡張性の観点からも主流となりつつあります。
そこでAWSやAzureといったパブリッククラウドを活用すると、インフラの初期投資を抑えつつ需要に応じたスケーリングが可能となります。BCP(事業継続計画)やDR(災害復旧)対策においても、クラウドは有効な選択肢となるでしょう。
ただし証券業界はFISCガイドラインなどの規制に基づく、セキュリティ要件が厳格です。そのため、クラウドベンダーとの契約条件やデータの所在(リージョン選定)にも慎重な検討が求められます。さらにハイブリッドクラウド構成による段階的な移行も視野に入れることで、安定運用と柔軟性を両立できるでしょう。
既存システムの見直しにおいては全機能を一から作り直す「リビルド」ではなく、必要な部分だけを再構築する「リファクタリング」を適切に使い分ける判断力が求められます。
例えばビジネスロジックが成熟しており既に安定稼働している部分については、コードの最適化やモジュールの整理だけでも十分な改善効果が得られます。一方で顧客ニーズや業務要件が変化している領域では、スクラッチ開発によるリビルドの方が合理的な場合もあるでしょう。
この判断を誤ると開発期間や予算が膨張し、DXの進行が滞ってしまいます。定量的な指標(バグ発生率、保守コスト、ユーザー満足度など)を基に、リファクタとリビルドを戦略的に選択することが重要です。
システム刷新のプロジェクトでは、IT部門と業務部門の分断が障壁といえます。真に業務に即したシステムを実現するには、両部門の協働体制が不可欠です。
例えば新たな注文処理システムの開発を行う場合、業務部門から具体的な業務フローや課題を共有してもらうことで実態に即した機能設計が可能になります。一方でIT部門からも技術的制約や実現手段を説明し、相互理解を深める必要があるでしょう。
このような連携を促進するにはBizDevOps的なアプローチを導入し、要件定義から検証までを一体化したプロジェクト運営が効果的です。またデザインスプリントやユーザーストーリーマッピングなどの手法を取り入れることで、現場の声を反映したプロダクト開発が実現できるでしょう。
レガシー刷新の中でも特に慎重な対応が求められるのが、データ移行と整備です。取引履歴や顧客情報は金融業務における根幹であり、一部でも欠損や不整合が生じれば重大なトラブルに発展します。
例えば顧客IDの形式が旧システムと新システムで異なる場合、マッピング作業において齟齬が生じやすくなるでしょう。こうしたリスクを避けるためには事前にデータクレンジングを実施し、整合性の高いマスターデータの構築が重要です。
さらに移行後のデータ検証(バリデーション)を複数段階で行うと、システム移行の信頼性を担保できるでしょう。ETLツールの活用やデータ移行専用のプロジェクトチーム設置も、円滑な移行に寄与します。加えて移行対象の優先順位や影響範囲を整理することで、全体的なプロジェクト計画の精度が高まるのです。
実際に証券DXを推進し、レガシーシステムの刷新を成し遂げた企業の取り組みからは多くの示唆が得られます。
ここでは、大手証券会社がどのようにDX戦略を具体化し、システム統合や業務効率化を進めたのかを3つの事例として紹介します。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、長年の課題であった部門ごとの分断された業務システムを「SCM(セキュリティ・コントロール・マネジメント)」によって統合しました。この取り組みは社内の情報共有を活性化させると同時に、顧客対応のスピードと精度を高めることに直結しています。
背景には、旧来のシステムが個別最適で構築されていて情報の一元管理が困難だった、という課題がありました。そこで段階的に新たなシステムを導入し、共通プラットフォーム上での運用に切り替えることで全社的な業務改革を実現したのです。
営業部門とリスク管理部門が同じデータベースを参照できるようになったことで、意思決定の迅速化にもつながりました。SCMを軸に据えた統合戦略は、他の証券会社にとっても有用なDXの参考モデルといえるでしょう。
みずほ証券では、リテール業務の基幹システムを全面的に刷新する、という大規模なDXプロジェクトを実行しました。目的は顧客対応力と業務効率の両立を図るため、より柔軟で堅牢なシステム基盤を構築することでした。
特に注目すべきは、ITと業務部門が密接に連携しながら要件定義から開発、テストに至るまで一貫して推進された点です。過去のシステムでは業務の現場とIT開発部門の間に溝があり、仕様の乖離が問題視されていました。
今回の刷新により、顧客の資産状況や取引履歴をリアルタイムで照会できる新機能が導入され、営業担当者の提案力向上にもつながっています。プロジェクト全体は長期にわたる取り組みでしたが、段階ごとにマイルストーンを設けることで進捗を可視化し着実に成果を積み重ねてきました。
参考:みずほ証券株式会社
楽天証券では基幹システムのリプレイスを行う際に、既存システムを完全に切り替えるのではなく、一定期間は並行稼働させるというハイブリッド型の移行戦略を採用しました。この方式により、移行中のトラブルリスクを最小限に抑えつつ新機能の検証と導入を効率的に進められました。
旧システムは長年にわたり業務に深く根付いていたため、突然の切り替えはユーザーの混乱を招く恐れがありました。そこで、段階的に利用シーンを分けて新システムへと移行し、業務に支障が出ないよう細心の注意を払いながら移行プロセスを設計しました。
新システム上では高頻度取引に対応できるレスポンス性能が向上し、取引エラーの減少にも寄与しています。これによりトレーダーや個人投資家からの信頼も高まり、結果として顧客基盤の拡大へとつながりました。
参考:楽天証券株式会社
証券業界におけるDX推進では、レガシーシステムの刷新が避けて通れない課題です。しかし、単純にシステムを新しくすれば良いわけではありません。現行業務への影響を抑えつつ安定的かつ効率的に刷新を実現するには、複数の視点から注意を払う必要があります。
ここでは、代表的な3つのポイントを解説します。
システム刷新の最大のリスクは、業務停止やサービス障害を引き起こすことです。そのためいきなり全体を切り替えるのではなく、段階的な移行が求められます。
まずは周辺システムを新しいアーキテクチャに移行し、影響範囲を限定しながら稼働テストを実施しましょう。その後コア機能の移行を段階的に進めることで、トラブル発生時にも影響範囲を最小限にとどめることが可能になるのです。
さらに、旧システムとの並行稼働期間を設けることで移行中の業務の安定性を維持できます。技術的な対策と同時に現場への説明や教育のタイミングも見極めることが、スムーズな刷新を実現するカギとなるのです。
証券業界では金融商品取引法やマネーロンダリング対策、個人情報保護法など遵守すべき法規制が数多く存在します。システム刷新においては、それらの要件を満たすことが前提となります。
特にデータの暗号化やアクセス権限の厳格な管理、改ざん検知機能の導入などが必須でしょう。またクラウドを利用する場合には、リージョン選定や通信の暗号化、監査ログの整備などにも注意が必要です。
例えば取引データが第三者に漏えいするリスクを想定し、二重認証やゼロトラストネットワークの導入を検討する企業も増えています。刷新に際しては、セキュリティポリシーの再設計とその実装状況の検証も欠かせなくなってきているのです。
参考:個人情報保護委員会|金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
レガシーシステムは長年の運用の中で業務そのものに組み込まれているケースが多く存在します。システムを刷新する際には、その周辺業務も合わせて見直す必要があるでしょう。
例えば紙ベースで行われていた承認フローや属人化した手作業が残っている場合、それらを機能的に再設計することで業務の標準化と効率化を図れるでしょう。このように、システムだけでなくプロセス全体を最適化する視点が求められるのです。
レガシー依存の業務構造を可視化してどの部分が本質的な価値を持ち、どこが非効率であるのかを分析すると、刷新の目的が明確になります。IT部門だけでなく、業務部門との対話を通じてプロセス改善を同時に行うことが重要なのです。

証券業界でのDX推進において、レガシーシステムの刷新は重要なテーマです。しかし技術の置き換えだけでは、本質的な変革にはなりません。段階的な移行戦略の構築や厳格なセキュリティ対応、業務プロセスの最適化を同時に進めることが成功のカギとなります。
例えば、クラウド移行だけを目的としたプロジェクトでは期待された業務効率化が実現できず、かえって負荷が増す場合もあるでしょう。だからこそ、刷新を円滑に進めるためには、関係部署と連携しながら、全体像を俯瞰したうえで取り組むことが大切でしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
