証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

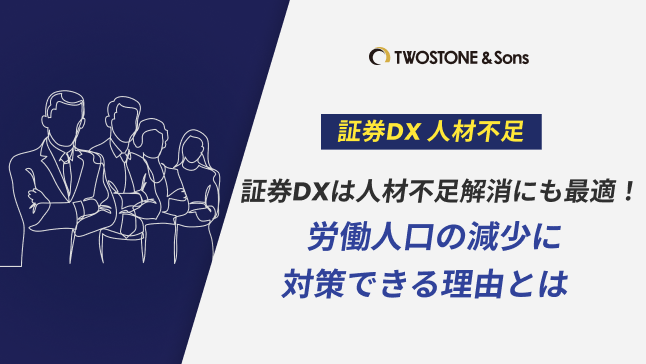
証券業界における人材不足は深刻な課題ですが、DXの推進によって効率的な業務運営が可能になるのです。3つの事例を基に効率的なDX推進のポイントも紹介し、証券業界の未来を支える施策を丁寧にご案内します。
近年、証券業界では慢性的な人材不足が経営課題となっています。高齢化による熟練人材の引退や若手人材の確保難、さらに高度化する業務への対応といった複合的な要因が企業の成長を阻む要素として深刻化しています。こうした中で注目を集めているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務の効率化と自動化です。
本記事では、なぜDXが証券業界における人材不足の解消に貢献できるのか、その具体的な背景と要因を解説していきます。読み進めることで、今後の経営判断や業務改革に役立つ視点が得られるでしょう。

証券業界における人材不足は単なる労働力の減少にとどまらず、業務継続や競争力の維持にも直接的な影響を及ぼします。そのような状況下でDXは、業務の自動化やプロセスの最適化を通じ、少人数でもパフォーマンスを維持・向上できる手段として注目されています。
ここではDXの必要性を浮き彫りにする、3つの背景を見ていきましょう。
最初の課題は、ベテラン人材の大量退職に伴う専門知識の喪失です。証券業務には長年の経験に基づく判断や独自の取引ノウハウが求められる、といった場面が多くあります。しかしこれまで現場で蓄積されてきたノウハウの多くが、マニュアル化やデジタル化されないまま個人に依存しているケースが目立つのが現状です。
こうした知識の属人化が進むと退職と同時にノウハウも失われ、業務の継続性が危ぶまれるリスクが高まります。そこでDXを活用して業務プロセスを見える化し、ナレッジをシステム上に蓄積することで退職者の知見を組織内に残すことが可能になります。
次に挙げられるのが、若手人材の獲得難と業界のイメージ問題です。証券業務は専門性が高く繁忙期には長時間労働が発生することも多いため、若年層からは敬遠されがちな傾向があります。
このような職場環境は、若手にとって「古くてついていけない業界」という印象につながり、採用活動の障壁になります。そこで重要なのがDXを通じた業務のモダナイズです。業務フローの自動化やペーパーレス化、クラウド活用による柔軟な働き方の推進などデジタル化は、職場環境そのものの魅力を高める役割を果たすでしょう。
人手が限られている中で求められるのが、業務の徹底的な効率化と再構築です。証券業務では、取引データの管理やリスク分析、顧客対応といった多岐にわたる作業が日常的に発生します。従来はそれらを複数の担当者で分担しながらこなしていましたが、少人数体制ではそれが難しくなるでしょう。この課題に対応するには、業務の選別と自動化がカギになります。
例えば、AIによる取引分析やチャットボットによる顧客対応、ダッシュボードによる可視化は属人的な業務の削減に効果的です。さらにマイクロサービスやAPIを活用したシステム連携を進めれば、業務ごとに最適なツールを組み合わせて柔軟な運用が可能になります。
証券業界におけるDXの取り組みは、人材不足の対策としても効果的です。証券DXは業務の効率化にとどまらず、限られたリソースを最大限に活かす体制を構築できるため今後の競争環境を生き抜く上でも重要な施策といえます。
ここからはDXが具体的にどのように人材不足の課題を解決するのか、見ていきましょう。
人材が不足している現場において時間と労力を多く割かれる定型業務は、従業員にとって負担になります。特に証券業務では、口座開設の手続きや顧客データの更新、帳票の作成など反復的で単調な業務が多く、これらに人手を割くことで本来注力すべき業務が後回しになってしまうという課題があります。この問題に対して有効なのが、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIを活用した業務の自動化です。
こうした仕組みを取り入れることで、これまで人手に頼っていた作業を効率的に処理できるようになります。
DXによって業務効率が高まると、不要な作業時間やミスによる手戻りが削減され、運用コストも下がっていきます。これにより、企業は浮いたコストを戦略的に再配分する余地を得られます。特に有効なのが、人材関連の費用に再投資するというアプローチです。
例えば浮いたコストを、採用活動の強化や社員のスキルアップのための教育研修、定着率向上に向けた福利厚生の充実といった施策にあてれば、人材確保と定着の両面で成果を出すことが期待できます。
人材不足の状況下では、各担当者の判断の質が全体の成果を左右します。従来は経験や直感を頼りにした意思決定が一般的でしたが、それでは属人化が避けられず業務の再現性や精度にばらつきが出るリスクが高まることでしょう。この課題に対しては、データ分析の導入が有効です。
データ分析を導入すると、取引履歴や市場データを統合して分析することで顧客ごとの投資傾向を把握したり、リスクの兆候を早期に察知したり、といったことが可能になります。こうした仕組みによって現場では数値に基づいた判断が可能となり、人的リソースに頼らない業務運用が実現するのです。
近年は多様な働き方を求める人材が増加しており、企業にとっても柔軟な雇用モデルを整えることが求められています。特に人材不足が深刻な状況では常勤の正社員だけでなく、副業人材やリモートワーカーなど外部人材の活用が重要な選択肢となるでしょう。このような柔軟な働き方を実現するためには、業務のデジタル化が不可欠です。
例えばクラウドシステムを導入してどこからでもアクセス可能な環境を整備すれば、地理的制約にとらわれずに優秀な人材を採用できるでしょう。結果として人手不足を補いながら、専門性の高いスキルを持つ人材を柔軟に活用できる体制が整うのです。

証券業界が抱える構造的な人材不足の問題に真正面から向き合わなければ、DX推進どころか業務全体の継続性にすら悪影響を及ぼしかねません。テクノロジーの導入に注目が集まりがちですが、それを支える人材が確保できていなければいかに優れたシステムを導入してもその効果を引き出すことはできません。
ここからは人材不足への対策を怠った場合にどのようなリスクが生じるのか、具体的に見ていきましょう。
DXの取り組みが進まない最大の理由の1つが、現場の人材不足です。新しいシステムの導入や業務プロセスの見直しには通常業務とは異なり、専門的な知識や時間が必要です。しかし慢性的に人手が足りない現場では、こうしたプロジェクトに十分なリソースを割けないケースが多く見受けられます。
実際にプロジェクトチームを立ち上げても専任担当者を確保できず、片手間での対応に終始してしまうと十分な議論も設計も行われないままに結論だけが先行してしまいます。その結果、理想と現実のギャップが埋まらずプロジェクトは停滞してしまうのです。
このような状態では現場からの信頼も得られず、改革へのモチベーションも低下します。つまり人的資源を確保しない限り、DXの取り組みは絵に描いた餅に終わってしまうのです。
人材が不足している状況で新たな施策を進めようとすると、既存の社員に過大な負荷がかかりがちです。通常業務に加えてシステム導入や研修対応まで担う必要が出てくると、肉体的にも精神的にも疲弊し離職リスクが高まります。
例えば、数名で多数の顧客対応をこなす中、システム移行に関する検証作業やマニュアル作成まで行うようなケースでは業務時間の確保すら困難になります。これによって、業務の質が落ちるだけでなく社員のモチベーションも低下し、最終的には転職や退職といった選択に至る可能性が高まるのです。
こうした事態が続くとさらに人手が減り、残された人により大きな負担がのしかかるという悪循環が生まれます。結果として、DXの定着どころか日常業務すら回らなくなるリスクがあるのです。
テクノロジーの導入はあくまでも手段であり、それを有効に活用できる体制が整っていなければその投資は無意味に終わります。特に人材が不足している状況では新しいツールの導入に対する教育やサポートが不十分になり、せっかくの機能が活かされないまま放置されてしまうケースも少なくありません。
例えばCRMやマーケティングオートメーションツールを導入しても、実際に運用できる人材がいなければシステムは稼働せず、使われないまま年月だけが過ぎていきます。
このようにツールの導入と人材体制が噛み合わなければ、どれだけ高度な技術を採用しても意味をなしません。投資の回収が見込めないどころか、企業全体のDX推進に対する不信感にもつながりかねないのです。
社内のリソースが不足していると、外部のベンダーやフリーランスに依存する機会が増えます。もちろん専門性の高い外部人材を活用することには一定のメリットがありますが、それが過度になると、企業の中核的な知見や運用能力が外部に流出してしまう恐れがあるのです。
例えば、基幹システムの構築から運用保守までをすべてベンダー任せにしていると、トラブルが起きた際に社内で対処できず、対応が遅れてしまうことがあるでしょう。ノウハウが社内に蓄積されないため後任者の育成もままならず、同じ業務で再び外部依存するという悪循環に陥るのです。安易な外注依存を避けるためにも、社内人材の育成と確保が不可欠です。
人材不足が深刻な状況では、育成よりも即戦力を求める傾向が強くなりがちです。しかし、それでは中長期的な人材戦略が機能しません。特に若手社員に対する教育の機会が失われると業務理解やスキルの蓄積が進まず、将来的なリーダー人材の不足に直結します。
新入社員が入社しても、教育担当者が現場対応に追われておりOJTすら満足に行えない、といったケースでは、業務を理解できないまま現場に放り出され、やがて離職してしまうことになりかねません。
このように若手育成をおろそかにすると、企業の将来を担う人材の土台が築けません。結果として人的資産の蓄積が止まり、組織全体が短期的な対応に終始するようになります。
証券業界のDX推進において、人材不足は避けて通れない課題です。しかし単なる人手の補充だけでなく、技術や組織の変革を通じて持続可能な体制を構築すれば、限られた人材でも効率的に成果を出せます。
ここでは人材不足対策として、特に効果的な5つの施策を紹介します。
即効性のある手段としてまず挙げられるのが、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIの活用です。これらの自動化ツールはルーティン業務やデータ処理、分析などの作業を効率化し人的リソースを戦略的な業務へ振り向ける環境を整えます。
例えば口座開設や取引報告の入力作業、顧客情報の更新といった繰り返し作業をRPAで自動化すれば担当者の作業時間は削減されるでしょう。またAIを活用した顧客データの分析は、営業活動やリスク管理において迅速かつ精度の高い判断を支援します。
これらのツールを利用することで人的ミスの減少や業務スピードの向上が見込まれるため、限られた人材でより高度な業務に注力できるようになります。
次に注目すべきは、クラウドサービスへの移行によるインフラ運用の効率化です。従来のオンプレミス環境ではサーバーの管理やシステムの保守に多くの人手が必要でしたが、クラウドを活用すればこれらの負担を軽減できます。
例えばAWSやAzureといったパブリッククラウドを導入すると、インフラの自動スケーリングや運用の自動化が可能になるでしょう。
またクラウドは迅速なシステムの導入やアップデートが行えるため、ビジネスの変化に柔軟に対応できるメリットもあります。インフラ面のDX推進は、現場の業務効率化と並行して人材不足の緩和に貢献するのです。
人材不足の深刻化に対応するためには、多様なスキルを持つ「越境人材」の育成が不可欠です。越境人材とは専門分野の枠にとらわれず、ITと金融の知識や経験を横断的に活用できる人材を指します。
例えば、営業部門で金融商品に詳しい社員がITスキルを身に付けることで、デジタルツールの活用やデータ分析に積極的に関われるようになります。
越境人材は組織の柔軟性を高める効果もあり、変化の激しい証券業界においては貴重な存在です。したがって研修プログラムの充実や異動制度の活用など、計画的に越境人材を育てる体制づくりが求められます。
組織の内製化を進めるには、DX推進に必要な知識や経験を備えた人材の採用が欠かせません。特に証券業界特有の業務知識とITスキルを兼ね備えた人材は市場での需要も高く、戦略的に確保することが企業競争力の源泉となります。
例えば、フィンテック関連のプロジェクト経験を持つエンジニアや証券業界でのデジタル戦略に携わったコンサルタントを採用すれば、即戦力としてDXを加速させられるでしょう。
このような戦略的人材採用は短期的な人手不足の解消に留まらず、長期的な組織力強化に直結します。適切な人材を迎え入れることで、DX推進の質と速度が向上するでしょう。
最後に紹介するのは、専門性の高い外部パートナーの活用です。前述の通り過度な外注依存はリスクを伴うのですが、戦略的かつ限定的なパートナーシップは証券DXを成功に導く重要な要素となります。
例えば、AIやデータ分析の高度な技術を持つITベンダー、業界に精通したコンサルティングファームを活用すれば、自社に不足するノウハウやリソースを補完できるでしょう。
この際外部パートナーとは、単なる委託先ではなく、共に価値創造を目指す協働者として位置付けることがポイントです。そうすることでノウハウの共有や人材育成の支援も期待でき、持続可能なDX推進が実現するのです。
証券業界では、DX推進が人材不足の解消に役割を果たしています。実際に多くの企業がデジタル技術を活用し、業務効率を高めつつ限られた人材で最大の成果を出しています。
ここでは具体的な成功事例を3社紹介し、それぞれの特徴と効果を見ていきましょう。
楽天証券は、紙ベースでの発注書や検収書の処理を全面的に電子化しました。この取り組みは、社内業務のスピードアップに直結しています。
以前は手作業で処理していた発注関連の書類が電子システム上で一元管理されるようになったことで、承認や確認にかかる時間が短縮されました。その結果業務全体の流れがスムーズになり、社員の負担軽減に寄与しています。
加えて、ペーパーレス化は書類の紛失リスクを減らし、コンプライアンス強化にもつながっています。このような効率化は人材不足の影響を抑えつつ、業務品質の向上を可能にした好例です。
参考:楽天証券株式会社
大和総研は自社開発の証券ソリューションサービスを導入し、トレーディングやリスク管理などの業務効率を改善しました。
複雑なデータ連携や分析処理を自動化することで、これまで多くの担当者が手作業で行っていた作業を削減したのです。これにより、社員はより付加価値の高い業務に注力できる環境が整いました。
さらに証券市場の変動に迅速に対応できる体制も構築され、業務の柔軟性とスピードが向上しています。こうしたシステムの活用は少数精鋭での業務推進を実現し、人材不足をカバーする効果が顕著です。
参考:株式会社大和総研
みずほフィナンシャルグループでは生成AIを活用した社内文書検索システムを導入し、膨大な社内資料の効率的な活用を実現しました。
今では社員は、検索システムを使うことで必要な情報を瞬時に引き出せるため、調査やレポート作成にかかる時間が短縮されたのです。これによって情報探索に費やしていた工数を削減し、業務の質を向上させています。
さらにAIが関連情報を自動で提示するため、社員の知見の広がりや新たな発見も促進される仕組みです。この先進的な取り組みは人材不足の中でも、効率的かつ高度な業務遂行を可能にしています。

証券業界では人材不足が今後ますます深刻化することが予測されますが、DXの活用によってその課題に柔軟に対応することが可能でしょう。
業務の自動化やリモート環境の整備、データ活用による意思決定の高度化などにより、限られた人員でも高い生産性を維持できる仕組みが構築できます。自社の業務特性や人材課題を見直したうえで、現実的かつ持続的なDX施策を推進することが、人手不足の解消と組織力の向上につながるでしょう。
ぜひ、本記事を参考にして、今後の取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
