証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

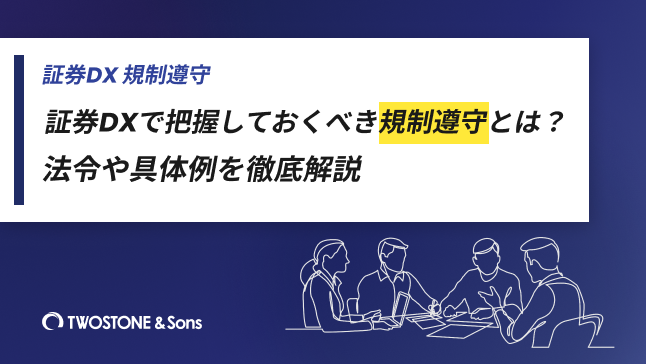
証券業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進において、規制遵守は成功の鍵を握る重要な要素です。金融商品取引法、個人情報保護法、サイバーセキュリティガイドラインなど、複雑化する法令・規制に適切に対応しながら、効率的なデジタル化を実現することが求められています。
本記事では、証券DXで把握すべき主要な法令・規制から、RegTechを活用した実践的な対応策、実際の企業成功事例まで、規制遵守とDX推進を両立させるための具体的な方法を徹底解説します。
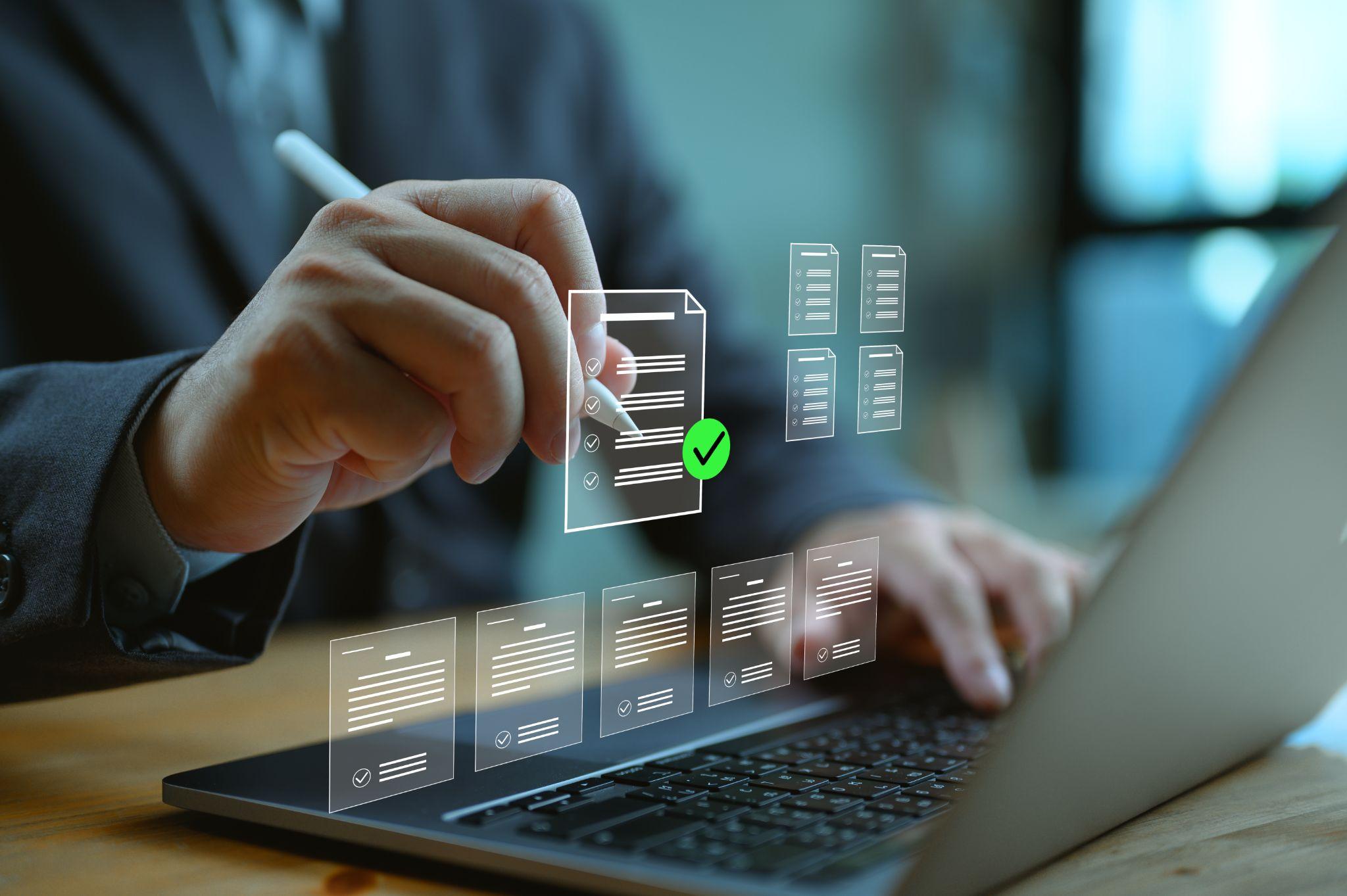
金融業界は他業界と比較して厳格な法令や規制に従う必要があり、DXを進める際も必ずコンプライアンス要件を満たす必要があります。特に証券業界では、投資家保護や市場の健全性を維持するため、金融商品取引法をはじめとする多様な規制が存在し、これらを遵守しながらデジタル化を進めることが求められているのです。
また、近年のサイバー攻撃の高度化や個人情報保護法の改正など、規制環境の変化にも適切に対応する必要があります。
近年、金融商品取引法の改正、個人情報保護法の強化、マネーロンダリング対策の厳格化など、対応すべき規制は年々増加し、その内容も詳細化しています。従来の手動による管理では、これらの複雑な要件を満たすことが困難になってきており、システム化やデジタル技術を活用した効率的な対応が不可欠です。
また、国際的な規制調和の流れもあり、海外展開を行う証券会社では複数の法域における規制遵守が求められるため、より高度なコンプライアンス体制の構築が必要となっています。さらに、規制当局による監督の厳格化により、形式的な遵守だけでなく実質的な効果を重視した対応が求められるようになっており、企業には継続的な改善と高度化が要求されています。
証券DXの推進により、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが大幅に増加しています。証券業界では、顧客の個人情報や取引データ、市場情報など機密性の高い情報を大量に扱うため、外部漏洩時の影響は甚大です。ランサムウェア攻撃、標的型攻撃、内部不正など多様な脅威に対し、技術的・組織的な包括的なセキュリティ体制の構築が求められています。
金融庁ガイドラインへの対応も必須で、規制遵守とセキュリティ対策を両立させることが証券DX成功の鍵となっています。クラウド利用拡大やAPI連携により、従来の境界防御モデルでは対応できない新たなリスクも生まれており、ゼロトラストセキュリティなどの新しいアプローチも必要です。
参考:金融庁|金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン
証券業界でDXを推進する際に対応すべき主要な法令や規制について、その概要と要求事項を詳しく解説します。これらの規制を適切に理解し、システム設計や業務プロセスに反映させることが、健全なDX推進の基盤となります。
特に、金融商品取引法、個人情報保護法、電子記録移転権利制度、サイバーセキュリティガイドライン、FISC安全対策基準は、証券会社のデジタル化において法令・規制への適切な対応が企業の競争力向上にも直結するのです。
金融商品取引法は、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保および金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指して制定された法律です。証券業界のDX推進において最も基本的かつ重要な法令として位置づけられており、以下の4つの柱で構成されています。
DX推進においては、顧客情報の適切な管理・取引記録の保存義務・不公正取引の監視体制・利益相反管理などの要件をシステムに反映させなければなりません。そのため、AI技術を活用したサービスにおいては、その透明性と説明責任を確保するための仕組みが求められるのです。
個人情報保護法は、令和4年4月1日に改正が施行され、証券DXにおいて顧客データを取り扱う上で遵守すべき重要な法令です。改正により、個人情報保護委員会が法を一元的に所管し、行政機関、地方公共団体、民間事業者を統一的に監視・監督する体制が整備されました。
証券会社では、顧客の投資行動データやリスク許容度など機微な個人情報を扱うため、データガバナンス体制の構築が不可欠です。特に重要なのは、プライバシー・バイ・デザインの考え方に基づくシステム設計、PIA(個人情報保護評価)の実施、CPO(最高プライバシー責任者)の設置などです。
また、仮名加工情報制度の活用により、個人を識別できない形でのデータ分析が可能となり、マーケティングやサービス改善に活用できます。越境データ移転については、外国の個人情報保護制度等に関する情報提供義務が強化されており、特にクラウドサービス利用時の適切な管理が求められます。
電子記録移転権利制度は、2020年5月に施行された改正金融商品取引法により創設された、ブロックチェーン技術を活用したデジタル証券に関する法的枠組みです。集団投資スキーム持分や信託受益権などの第二項有価証券をトークン化したものを「電子記録移転権利」として第一項有価証券に格上げし、より厳格な規制の下で流通性の向上を図っています。
証券会社がセキュリティトークン(ST)を取り扱う際は、適合性原則の徹底、広告等の規制、契約締結前交付書面での注意喚起、分別管理の徹底などが必要です。特に分別管理においては、トークンの移転に必要な秘密鍵をコールド・ウォレット等で適切に管理することが義務付けられています。また、STの販売・勧誘には専門の外務員資格が必要で、プラットフォームの安全性に関する継続的なモニタリングも求められます。
参考:一般社団法人日本STO協会|セキュリティトークンに関する
令和6年10月4日に金融庁が策定した「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」は、証券会社におけるサイバーセキュリティ管理体制の確立を求める最新の指針です。このガイドラインでは、経営陣のリーダーシップによるガバナンス確立、リスクベース・アプローチによる対応、サードパーティリスク管理の強化など、従来以上に包括的な要件が詳細に規定されています。
証券DXの推進においては、「基本的な対応事項」として、サイバーセキュリティ管理の基本方針策定、CISO等の責任者任命、年次レビューの実施、セキュリティ・バイ・デザインの実践などが必須です。また、「対応が望ましい事項」として、3線防衛態勢の構築、外部専門家の活用、脅威ベースのペネトレーションテスト(TLPT)の実施、常時監視体制の確立などが推奨されています。
FISC(金融情報システムセンター)安全対策基準は、現在第13版が最新版として公表されており、金融機関のシステムセキュリティに関する業界標準として広く採用されています。証券会社のDXプロジェクトにおいては、新システムの設計・開発・運用の各段階でFISC基準への適合の確認が必要です。
特に重要なのは、クラウドサービス利用時の「金融機関等におけるクラウド導入・運用に関する解説書」や、RPA導入時の「RPA導入にあたっての解説書」など、最新技術に対応した個別ガイドラインの活用です。
また、TLPT(脅威ベースのペネトレーションテスト)実施にあたっての手引書やコンティンジェンシープラン策定手引書(第5版)など、実践的な対応策も提供されており、データの機密性・完全性・可用性を確保するための適切な管理策の実装が求められます。
参考:金融情報システムセンター|FISCガイドラインPDF版
証券業界では適切な規制遵守体制の構築により、多方面にわたって具体的な効果を得ることができます。コスト削減と業務効率の向上、リスク管理体制の強化、人的ミスの低減、監査対応の迅速化など、短期的な効果から長期的な競争優位性の確保まで、幅広いメリットが期待できます。
また、デジタル技術を活用した規制遵守により、従来のマニュアル対応では実現できなかった高度な分析や予測が可能となり、戦略的な意思決定にも貢献できるのです。
従来手動で行っていた監査対応や報告書作成業務の自動化により、人件費の削減と処理時間の短縮が可能となります。また、規制要件に対応したシステム設計により、重複業務の排除や業務プロセスの標準化が進み、全社的な生産性向上につながります。特に、複数の規制要件を統合的に管理するシステムの導入により、個別対応によるコストを大幅に削減可能です。
さらに、リアルタイムでの監視やアラート機能により、問題の早期発見と迅速な対応が可能となり、重大な規制違反を未然に防ぐことで、将来的な制裁金やレピュテーション損失を回避できます。ROI(投資収益率)の観点からも、初期投資を上回る長期的なコスト削減効果が期待でき、企業の財務体質強化にも大きく貢献します。
包括的な規制遵守体制の構築により、企業のリスク管理能力が大幅に向上します。モニタリングシステムや内部統制の整備により、市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクなどを早期発見し適切に対応できます。リアルタイム監視・分析による精度の高いリスク評価に加え、収集データは経営判断の向上と戦略的意思決定もサポート可能です。
災害やシステム障害時の事業継続性も規制要件に基づく準備により確保され、機械学習やAI技術を活用したリスク予測モデルにより、従来困難だった複雑なリスクパターンの特定も可能となり、より高度なリスク管理を実現できます。
システム化と自動化により、人的ミスによる規制違反やオペレーショナルリスクを大幅に削減可能です。手動処理を自動化することで、計算ミスや入力ミス、確認漏れなどの人為的エラーを排除し、業務品質の向上と一貫性を確保できます。自動チェック機能やワークフロー管理により業務プロセスが標準化され、従業員は定型作業から解放されて付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。
トレーサビリティの向上により問題発生時の原因究明と再発防止が迅速に行え、デジタル化による業務の可視化は潜在的問題の早期発見を可能にします。これらにより予防的な品質管理体制が構築され、最終的に顧客満足度向上と企業の信頼性強化が実現可能です。
システム化された規制遵守体制は、監査証跡や報告資料の自動生成により監査準備の時間と労力を大幅に削減し、担当者の負担を軽減します。データの一元管理と検索機能により監査人への迅速で正確な回答が可能となり、リアルタイム内部監査機能で外部監査前の事前チェックと問題の早期解決を実現します。
継続的な監視により日常的な内部統制の維持・改善が可能となり、監査対応を通常業務の一部として効率化できるのです。ダッシュボード機能による可視化で監査人との円滑なコミュニケーションを実現し、監査プロセス全体の質的向上と担当者の精神的負担軽減を図れます。

証券業界において効果的な規制遵守体制を構築するためには、テクノロジーの活用から組織体制の整備まで、多角的なアプローチが必要です。RegTechの導入、社内業務のデジタル化、データガバナンス体制の構築、継続的な教育・研修、外部専門家の活用など、それぞれの取り組みを戦略的に組み合わせることで、効率的かつ効果的な規制遵守が実現できます。
特に重要なのは、単発的な対応ではなく、継続的な改善サイクルを構築し、変化する規制環境に柔軟に対応できる体制を整備することです。
RegTech(Regulatory Technology)は、AI、機械学習、ビッグデータ分析などの最新技術を活用して、金融機関の規制遵守業務を効率化・自動化する革新的なソリューションです。顧客向けサービス革新を目指すFinTechとは異なり、RegTechは内部統制やリスク管理の効率化に特化しています。
主な機能として、AI技術による不正取引検知システムが大量の取引データからパターン分析を行い、疑わしい取引を自動識別します。また、自然言語処理技術を用いた規制変更の自動監視により、新しい法令や改正情報をリアルタイムで収集・分析し、迅速な対応策策定が可能です。クラウドベースのソリューション導入により、初期投資を抑えながら最新の規制要件に対応できる柔軟なシステム環境の構築が実現できます。
法規制遵守の効率化には、社内業務プロセスのデジタル化と標準化が重要です。紙ベースの業務をデジタル化することで、データの一元管理と自動処理が実現し、人的ミスの削減と処理速度向上が期待できます。ワークフロー管理システムにより承認プロセスを可視化・標準化し、内部統制強化と業務効率向上を両立できます。RPA技術を活用した定型業務の自動化により、監査対応や報告書作成を大幅に効率化し、電子署名・電子承認システムでリモートワーク環境でも適切な内部統制を維持可能です。
API連携による外部システムとの自動データ交換で手動入力を排除し、正確性と効率性を向上させます。業務可視化によりボトルネックの特定と改善が容易になり、継続的な業務改善サイクルの構築が可能です。
規制遵守を実現するためには、適切なデータガバナンス体制の構築が不可欠です。データ品質管理フレームワークにより、システム内データの正確性・完全性・一貫性を継続的に維持し、データライフサイクル管理で収集から廃棄まで一貫したポリシーを適用します。マスターデータ管理システムは顧客・商品情報の一元管理と整合性を確保し、規制報告の精度向上に寄与します。
データアクセス制御とログ管理の強化により、不正アクセスを防止し監査証跡を確保し、データ分類・タグ付けの体系化で機密情報や個人情報を適切に識別・管理し、情報漏洩リスクを少なくできるでしょう。さらにデータリネージュ管理により、データの出所や変更履歴を追跡でき、品質問題発生時の迅速な原因究明が可能となります。
規制遵守の成功には全社員の理解と協力が必要であり、継続的な教育・研修プログラムが重要な役割を果たします。法令・規制の最新動向に関する定期的な研修により、社員の知識を常に最新状態に保ち、ロールベース研修で各部門に特化した実践的教育を提供できます。eラーニングシステムの活用により、時間と場所の制約なく効率的な学習環境を構築し、理解度テストやケーススタディを通じて実践的スキルの向上を図れるのです。
規制違反事例を用いたケーススタディにより、具体的なリスク理解と予防意識の向上を促進し、継続的なフォローアップとスキル評価で研修効果を測定します。必要に応じて追加教育プログラムを実施し、マイクロラーニングの導入により日常業務での効率的学習も可能となり、組織全体の規制遵守能力を継続的に強化できます。
複雑化する規制環境への対応には、外部専門家との連携が不可欠です。法律事務所やコンサルティング会社からは最新の法令解釈や業界動向に関する専門的助言を、RegTechベンダーからは効率的な規制遵守システムの技術支援を受けられます。監査法人との協力により内部統制の専門的支援と監査品質向上を図り、業界団体への参加を通じて同業他社とのベストプラクティス共有が可能です。
外部専門家による定期的なアセスメントにより、客観的視点から規制遵守体制を評価し継続改善を実現できます。これらの外部リソース活用により、限られた社内リソースを最大限に活用しつつ、高度な規制遵守能力の構築が実現します。
企業の証券DXとRegTech活用の成功事例を通じて、規制遵守とデジタル化の両立による具体的効果と実装ポイントを解説します。事例では理論に加え、実践的な導入プロセス、効果測定方法、課題解決策を示し、同様の取り組みを検討する企業の参考資料となるでしょう。
導入前の課題からソリューション選択、実装プロセス、効果、今後の展開まで具体的に説明し、証券DXの実現可能性を実証しています。技術面のみならず組織変革や人材育成も含めた包括的分析により、成功要因を明確化しています。
大和証券グループは、投資家層拡大とHFT(高頻度取引)による市場の複雑化に対応するため、不公正取引監視にAIソリューションを導入しました。2023年3月にはNECの「AI不正・リスク検知サービス for 証券」を導入し、説明可能AIの「異種混合学習技術」により全取引データを高精度でスコアリングし、判定理由も明確化しました。
2024年4月からは大和総研開発の「AI不公正取引検知モデル」を開始し、機械学習と深層学習モデルを組み合わせ、独自のデータオーグメンテーション技術を適用しています。これにより従来の人手審査では困難だった複雑な不正取引パターンの検知が可能となり、審査業務の効率化と精度向上を実現しました。
参考:NEC(Japan)|売買審査業務における人工知能(AI)活用の取組みについて
SBI証券は、コンプライアンス強化を目的として網屋の「ALog ConVerter for EMC」と「Resource Athlete」を導入しました。背景として監査でファイルサーバの重要情報・個人情報に対するログ取得が指摘され、従来の非効率なログ管理の改善が必要でした。ALog ConVerter for EMCによりエージェントレスで全ファイルアクセスログの取得・管理が可能となり、直感的なインターフェースで効率的な検索・分析を実現します。
Resource Athleteで共有フォルダのデータ量やアクセス権が可視化され管理効率が向上しました。両製品により「いつ誰がアクセスしたか」「どこをどう変更したか」の詳細把握が可能となり、年次共有フォルダ棚卸のレポーティング自動化で業務効率化を実現しています。
参考:ALogシリーズ | 株式会社 網屋|株式会社SBI証券 | 導入事例
三菱UFJ銀行は株式会社ラックと共同で、ATM不正利用対策としてAI不正取引検知システムの概念実証実験を実施し、94%の検知率を達成しました。背景として、年間285.2億円の特殊詐欺被害が発生し、高齢者を狙った預貯金詐欺やキャッシュカード詐欺盗によるATM経由の不正引き出し被害が多発しています。従来のルールベースシステムでは新手口への対応が遅く、検知レベルを上げると正規利用の誤検知が増加する課題があったのです。
ラックのAIシステムは、金融犯罪対策センターの専門知見を特徴量エンジニアリングに活用し、超不均衡データに対してラック独自のAI技術を適用することで精度を大幅改善しました。従来システムと比べ誤検知率を抑制しつつ検知精度を向上させ、運用コスト削減と金融機関のセキュリティ強化を両立しています。
参考:株式会社ラック|ラックと三菱UFJ銀行、ATM不正出金の検知率94%をAIを利用した不正取引検知実証実験で実現~特殊詐欺やサイバー犯罪など金融犯罪被害の抑止に貢献~
証券DXと規制遵守の成功には、技術面だけでなく組織・運用面での配慮が不可欠です。規制環境の変化への対応力と既存システム統合という主要課題に対し、事前準備と段階的アプローチが重要となります。技術革新のスピードと規制対応のバランスを保ちながら、持続可能なDX戦略を策定する必要があります。
また、ステークホルダーとの継続的なコミュニケーションと変更管理プロセスの確立も、プロジェクト成功の鍵となる要素です。
規制環境は絶えず変化するため、新法制定や既存規制改正に迅速対応できる体制構築が不可欠です。情報収集から影響分析、対応策策定・実装まで一連プロセスの標準化により、組織的な効率対応を実現する必要があります。専門人材の確保育成と外部専門家との連携体制により、複雑な規制要件の適切な解釈・実装が可能です。システム設計段階から規制変更対応を考慮し、柔軟性・拡張性を確保することで将来変更にも効率的に対応できます。
定期的な規制遵守評価とギャップ分析で潜在リスクを早期識別し、継続的改善を実施します。社内外コミュニケーション体制確立により関係者間の情報共有・連携を円滑化し、クラウドファースト戦略採用でシステムの柔軟性・拡張性を確保にも有効です。
証券会社では長年蓄積されたレガシーシステムと新しいDXソリューションとの統合が課題となっています。段階的な移行計画により業務継続性を確保し、API連携やデータ変換ツールを活用してシステム間のデータ交換を自動化することで運用負荷を軽減できます。データ品質の確保とマイグレーション時の整合性チェックにより規制遵守に必要なデータの正確性を維持し、テスト環境での十分な検証を経て本番環境への影響を最小限に抑えた移行が重要です。
また、従業員への教育・訓練により運用上の混乱を防止し、レガシーシステムの段階的モダナイゼーションを通じて技術的負債を解消しながら計画的な技術移行の実現が効果的な戦略となります。

証券業界のDX推進では、規制遵守は制約ではなく持続可能な成長の基盤となります。適切な規制遵守体制により、リスク管理強化、業務効率向上、コスト削減が同時に実現可能です。RegTechの活用や業務デジタル化を通じて、複雑化する規制要件に効率的に対応しながら競争優位性を獲得できます。
成功事例が示すように、技術と規制遵守の両立は適切な戦略と実装により大きな成果をもたらします。変化し続ける規制環境への対応には、柔軟性を持った体制づくりと継続的改善が成功の鍵です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
