証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

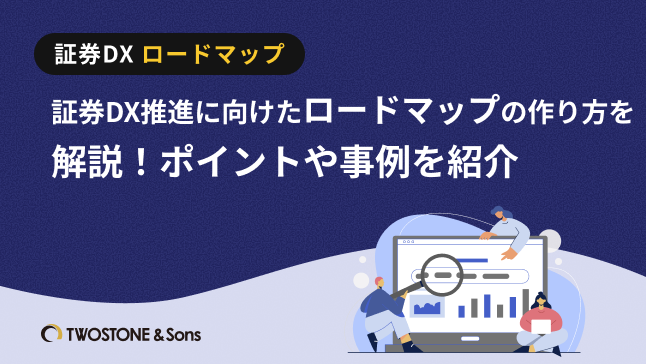
証券業界でDX推進を検討しているものの、「何から始めればよいかわからない」「具体的な進め方が見えない」と悩んでいませんか?
レガシーシステムや厳格な規制要件を抱える証券業界では、戦略的なロードマップ策定が成功の鍵となります。適切なロードマップがあれば、現状の課題を整理し、段階的かつ効率的にデジタル変革を実現することが可能です。
本記事では、証券DXロードマップの基本概念から具体的な作成手順、成功事例まで詳しく解説します。読み終える頃には、自社に最適なDX戦略の描き方と実践的な進め方が明確になるでしょう。

証券DXロードマップとは、証券業界でのDXを推進する具体的な道筋を示す戦略的計画書です。レガシーシステムや規制要件などの業界特有の課題を解決し、顧客価値向上と業務効率化を実現するための実行計画となります。
フィンテック企業の台頭により競争環境が激変する中、体系的なロードマップに基づくDX推進が経営上の重要課題となっています。以下より、証券DXロードマップの具体的な定義と組織における役割から詳しく見ていきましょう。
証券DXロードマップとは、証券会社がDXを推進するための時系列に沿った包括的な行動計画です。現状の課題分析から始まり、将来のあるべき姿までの道筋を明確にするとともに、各段階での具体的な施策と成果指標を定めたものです。
証券DXロードマップは単なる計画書ではなく、組織全体の変革意識を統一し、部門間での連携を促進する重要な役割を担っています。また、限られた経営資源を効率的に配分し、投資の優先順位を明確化します。
経営層から現場まで一貫したビジョンを共有することで、組織全体のDX取り組みへの意欲を向上させる効果も期待できるでしょう。
従来のシステム導入は、特定業務の効率化や既存機能の単純な置き換えが中心であり、「部分最適」の発想に基づくものでした。一方、証券DXロードマップは組織全体の包括的なビジネスモデル変革を目指す「全体最適」を採用しています。
根本的に異なる点は、単発的なIT投資ではなく、連続的かつ戦略的なデジタル活用という点です。顧客接点の革新、新たな価値創造、競争優位性の確立を追求し、組織文化の変革、人材育成、業務プロセスの再設計を含んだ包括的なアプローチが特徴です。
従来の「システムありき」の発想から「顧客価値創造ありき」への転換が重要なポイントとなります。
ロードマップの策定により、DX推進の優先順位が明確化され、限られた資源を最適配分した計画的なDX推進が可能です。段階的なアプローチにより、技術的リスクや運用リスクを最小化しながら、着実な成果を積み重ねることができます。
関係者間での目標共有とコミュニケーションも促進され、部門を超えた組織一丸となった取り組みが実現できます。投資対効果の可視化により、経営層の理解と継続的な支援も得やすくなり、持続的なDX推進が可能です。
さらに、明確な成果指標の設定により、進捗状況を定量的に把握でき、必要に応じた軌道修正も迅速に行えるため、より確実なDX推進ができるでしょう。
ロードマップ作成は体系的なアプローチが重要です。現状把握から継続的改善まで、5つの段階を経て効果的なロードマップを構築していきます。
各段階では具体的な成果物を設定し、次のステップへの橋渡しを行います。証券業界特有の課題である規制要件への対応やレガシーシステムとの共存も考慮しながら、段階的かつ確実にDXを推進することが成功の鍵です。
適切な手順に従うことで、リスクを最小化しながら最大の効果を得られるロードマップを策定することが可能です。以下よりその手順を見ていきましょう。
まず、証券会社の現状を客観的に分析し、DX推進を阻む課題を特定しましょう。レガシーシステムの実態調査では、システム構成や技術的負債を詳細に把握します。次に、業務プロセスの可視化では各部門の業務フローを分析して非効率な作業やボトルネックを特定します。
証券業界では、1980年代から蓄積された巨大システムの複雑化、印鑑・書面依存のアナログ業務、規制要件による制約が共通課題です。これらを定量的・定性的に整理し、影響度と緊急度を評価することで戦略的改善計画の基盤を構築します。
組織が目指すべき将来像を具体的かつ実現可能な形で描きます。顧客体験の向上、業務効率化、新規事業創出など、DXによって実現したい価値を明確に定義し、全社的に合意を得ましょう。経営陣、現場管理者、実務担当者など多様な関係者を巻き込むことが重要です。
証券業界では「顧客一人ひとりに最適化された資産運用サービス」「リアルタイムでの市場情報分析と投資判断支援」などの業界特有の価値提案を含めます。抽象的理念ではなく具体的な行動指針として機能するレベルまで詳細化しましょう。
DXの進捗と成果を測定するための具体的かつ測定可能な指標を設定します。顧客満足度、業務処理時間、デジタル取引比率、システム稼働率、コスト削減効果など、ビジョン実現に直結する多面的な指標を選定します。
さらに、各KPIに応じて現状値、目標値、測定方法、責任部署を明確に定義しましょう。目標値は、計測可能で現実的な目標値を定め、短期・中期・長期の段階的目標を設けます。
リーディング指標(先行指標)とラギング指標(結果指標)のバランスを考慮することで、プロセス改善と最終成果の両方を評価できる体系を整備しましょう。定期的な見直しにより柔軟に調整することも大切です。
概念実証(PoC)を通じて、DX施策に対する技術的な実現の可能性と事業的な有効性を検証しましょう。リスク評価とリターン分析を実施し、影響度と実現の容易性を軸として施策の優先順位を決定します。
PoCでは小規模な実証実験を行い、技術的課題、運用上の問題点、期待効果を検証します。証券業界では金融商品取引法をはじめとする厳格な規制要件があるため、コンプライアンス観点からの慎重な検討が必要です。
規制リスクが低く効果が見込める領域からPoCを実施し、成功体験を積み重ねながら段階的に適用範囲を拡大していきましょう。
ロードマップは策定して終わりではありません。定期的な進捗確認と成果評価を行い、計画と実績の乖離を分析し、必要に応じて計画修正や追加施策を検討していくことが大切です。
月次・四半期・年次の評価サイクルを設定し、短期的な軌道修正と中長期的な戦略見直しを適切に組み合わせましょう。市場環境や技術動向の変化、規制要件の改正、競合他社の動向に応じて柔軟にロードマップを更新することが重要です。
成功・失敗事例を組織内で共有し、ナレッジマネジメントの仕組みを構築することで、持続的な改善の文化を醸成していきましょう。

効果的なロードマップ作成には、体系的な分析フレームワークの活用が不可欠です。証券業界では金融規制の動向、市場環境の変化、競合他社の動き、顧客ニーズの多様化など複雑で変化の激しい環境要因を考慮した分析が重要となります。
フレームワークを活用することで分析の抜け漏れを防ぎ、客観的な現状把握が可能です。以下で紹介する4つのフレームワーク(PEST分析・3C分析・SWOT分析・VC分析)は異なる視点から証券DXの戦略策定を支援します。
PEST分析は、政治(Politics)・経済(Economy)・社会(Society)・技術(Technology)の4つの外部環境要因を分析するフレームワークです。証券業界では規制環境の変化が事業に大きな影響を与えるため特に重要です。
政治面では金融規制の動向、経済面では市場環境や金利動向、社会面では投資家の行動変容、技術面ではフィンテックの進展などを分析します。これらの要因が自社のDX戦略にどのような影響を与えるかを予測し、対応策を検討することが重要です。
3C分析は、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの要素から市場環境を分析するフレームワークです。証券業界における競争優位性の源泉を特定するのに有効です。
顧客分析では投資家のニーズやデジタル化への期待を把握し、競合分析では他社のDX取り組み状況や差別化ポイントを調査します。自社分析では保有する技術力や人材、資金力などの経営資源を客観的に評価し、DX推進における強みと弱みを明確にします。
SWOT分析は、自社の強み(Strength)と弱み(Weakness)、外部環境の機会(Opportunity)と脅威(Threat)を4つの象限で整理するフレームワークです。証券DXの戦略策定に直結する分析手法です。
強みと機会を組み合わせた積極的戦略、強みで脅威に対抗する差別化戦略、弱みを改善して機会を活かす改善戦略、弱みと脅威を最小化する防御戦略の4つの戦略方向性を導き出すことができます。各象限の分析結果を基に、最適なDX戦略を選択します。
バリューチェーン(VC)分析は、企業の事業活動を価値創造の連鎖として捉え、各工程での付加価値を分析するフレームワークです。証券業務の各プロセスでの価値創出ポイントの特定が可能です。
証券業務では、調査・分析、商品企画、営業・販売、取引執行、決済・管理、アフターサービスなどの主活動と、システム基盤、人材管理、リスク管理などの支援活動に分けて分析します。各工程でのデジタル化の可能性と効果を評価し、DX投資の優先順位を決定します。
国内証券大手各社のDX推進事例を分析すると、成功の背景には共通の戦略的アプローチが存在しています。
野村ホールディングス、大和証券グループ、SBI証券の各社は、それぞれ独自の強みを活かしながらデジタル変革を推進し、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現しています。
野村ホールディングスは、デジタル戦略を経営戦略の中核に位置付け、包括的なビジネス変革を推進しています。同社の取り組みで特に注目されるのは、顧客接点のデジタル化と新規事業領域への挑戦です。
全資産ポートフォリオ管理ツール「Nomura Navigation」の導入により、顧客の資産状況を一元的に可視化し、パートナーの業務効率を大幅に向上させました。また、中堅・中小企業向け事業推進支援プラットフォーム「Trynibus」では、登録会員企業が1,000社を突破し、新たな顧客セグメントの開拓に成功しています。
さらに、デジタル・アセット分野では「Laser Digital Holdings」を新設し、ブロックチェーン技術を活用したSTO案件の取扱いを拡大するなど、次世代金融サービスの基盤構築を進めています。
参考:野村ホールディングス|Presentation at Nomura Investment Forum 2022 戦略アップデート~これまでの成果と環境変化を見据えた今後の取り組み
大和証券グループは、段階的なDX推進戦略により着実な成果を上げています。DX1.0として会社風土のデジタル化、DX2.0として業務プロセスの変革を経て、現在はDX3.0として生成AIを活用したビジネスモデル変革に取り組んでいます。
2024年10月には国内大手金融機関初となるAIオペレーターサービスを開始し、顧客の待ち時間ゼロでマーケット情報照会や手続き関連の問い合わせに対応できる体制を構築しました。
また、「デジタルITマスター認定制度」により社内のDX人材育成を強化し、900名を超える応募者を集めるなど、組織全体のデジタル変革への意識改革に成功しています。AIガバナンス指針の策定により、生成AI活用における安全性と実用性のバランスを適切に管理している点も評価されています。
SBI証券は、データ分析・AI専門企業であるALBERTとの戦略的パートナーシップにより、マーケティングDXの高度化を実現しています。2021年12月に実装されたマーケティング最適化AIモデルは、従来の短期的施策評価から中長期的な顧客関係構築を前提とした最適化へと発想を転換しました。
同社の膨大な顧客データと取引データを活用したビッグデータ解析により、顧客の資産形成パターンをクラスタリング分析し、各クラスターに最適なマーケティング施策を展開しています。
新規口座開設者100万人超のうち約6割が20代・30代、約8割が株式投資未経験者という状況において、一人ひとりの投資意向に合わせたパーソナライズマーケティングを実現し、顧客の中長期的な資産形成支援を強化しています。
参考:SBI証券|ALBERTとマーケティングDXの取組みを強化
ロードマップの成功には、策定だけでなく実行段階での適切な取り組みが重要です。証券業界では厳格な規制要件や複雑なレガシーシステムなど、DX実行時に特有の課題が存在します。
これらを克服し持続的な変革を実現するには、組織全体の変革意識、技術基盤の整備、人材育成、外部連携の4つの要素をバランスよく推進することが不可欠です。各要素は相互に関連し合っており、総合的な推進が成功の鍵となります。
DXの成功には経営層の強いコミットメントと現場の積極的な参画が不可欠です。変革の必要性と将来ビジョンを組織全体で共有し、一体感を醸成することが重要な基盤となります。
経営層は変革のリーダーとして自ら率先してデジタル活用を実践し、その姿勢を組織全体に示しましょう。定期的な社内セミナーや成功事例の共有、タウンホールミーティングを通じてDXの意義と効果を継続発信し、部門横断的なプロジェクトチームで組織の縦割りを超えた協働体制を構築します。
変革への貢献を適切に評価しインセンティブ制度に反映することで、組織全体のモチベーション向上を図ります。
証券業界では高いセキュリティレベルと可用性が求められるため、DXを支える堅牢なITインフラの構築が必要不可欠です。
クラウド技術の戦略的活用により、柔軟性と拡張性を確保しながらコスト効率性も実現します。金融業界特有の規制要件を満たすため、プライベートクラウドやハイブリッドクラウドの採用も検討すべきです。
レガシーシステムからの段階的移行を慎重に計画し、業務継続性を確保しながらモダナイゼーションを進めます。API連携基盤の整備により外部サービスとの接続性を高め、サイバーセキュリティ対策の強化、災害対策システムの整備など包括的なインフラ設計が求められます。
DXの推進には、デジタル技術を理解し活用できる人材が必要です。既存従業員のスキルアップと新たな人材獲得を並行して進める必要があります。
証券業界の専門知識とデジタル技術の両方を理解する人材育成が特に重要で、これらの人材が組織のDX推進の核となるでしょう。社内研修プログラムでは基礎的なデジタルリテラシーから高度な技術スキルまで段階的なカリキュラムを整備し、外部セミナーや資格取得、eラーニングを通じて継続的な学習文化を醸成します。
実践的な学習機会の提供・メンタリング制度・キャリアパスの明確化により、デジタル人材の育成と定着を図ります。
証券業界特有の規制要件や高度な技術的課題に対応するため、専門知識を持つ外部パートナーとの戦略的連携が効果的です。フィンテック企業・ITベンダー・コンサルティング会社など各分野の専門家との協業により、迅速かつ確実な技術導入が可能となります。
パートナー選定では証券業界での豊富な実績と規制対応能力を重視し、長期的な戦略パートナーとして関係構築することが重要です。知識移転やスキル共有を含む包括的なパートナーシップにより内部人材の成長も促進し、適切な役割分担とガバナンス体制を構築してリスク管理を行いながら効率的なDX推進を実現します。
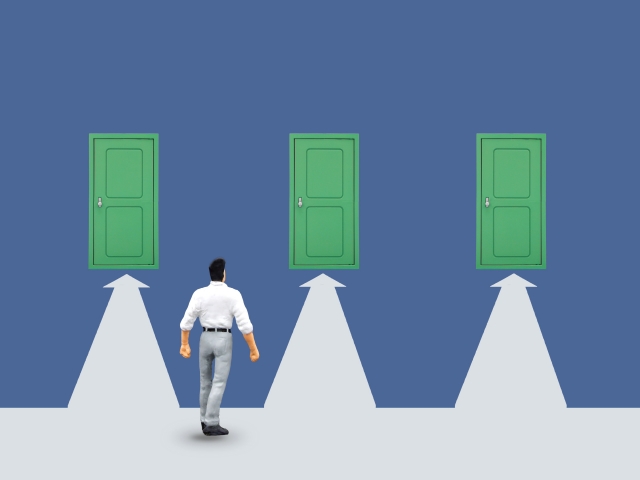
証券業界におけるDX推進は、レガシーシステムや規制要件といった特有の課題を抱える中でも、適切なロードマップ策定により確実な成果を生み出せます。
本記事で解説した現状把握からPDCAまでの5段階手順と、PEST・3C・SWOT・VC分析の4つのフレームワークを活用することで、自社の強みを活かした戦略的なDX推進が可能です。
国内大手各社の成功事例が示すとおり、組織一丸となった取り組みと適切な外部パートナーとの連携が成功の鍵となります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
