証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

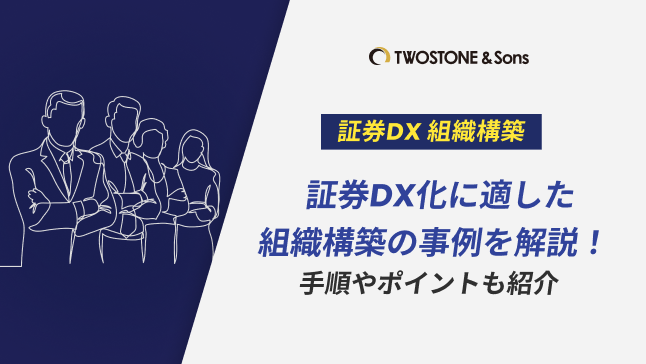
証券DXを成功に導くためには、戦略的な組織構築が不可欠です。本記事ではDX推進の目的設定や経営戦略との整合性、人材育成、予算確保までを一貫して解説しており、組織体制の再設計に取り組む際の実践的なヒントや指針を提供しています。
証券業界では業務の高度化と人材不足への対応を背景に、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の必要性が急速に高まっています。しかしDXの成果を最大限に引き出すためには技術導入だけでなく、それを受け止める組織体制の再構築が不可欠です。現場と経営層の連携や柔軟な組織文化、ITリテラシーの向上など取り組むべき課題は多岐にわたります。
この記事では、証券DXを推進する上で適した組織の特徴や阻害要因となる文化、変革に向けたステップを詳しく紹介します。読み進めることで自社にとって必要な組織改革の方向性、及び実行ポイントが明確になるでしょう。

証券業界でDXを成功させるためには、技術だけでなく組織全体の体制整備が必要です。新たなツールを導入しても、既存の文化や構造が変わらなければ現場に浸透せず、効果が限定的になります。業務のスピード感を損なわず、変化に柔軟に対応できる体制づくりが不可欠です。
証券DXとは、証券業務におけるITやデジタル技術の活用を通じて業務効率の向上や顧客体験の向上、新たなサービス提供を目指す取り組みです。
具体的には、クラウド基盤の導入やRPAによる定型業務の自動化、顧客データの分析によるマーケティング最適化などが挙げられます。これらを実現するには、テクノロジーを活用できるだけの組織体制と社員のマインドセットの変化が求められます。
DX推進には技術的な知識やシステム構築だけでなく、現場の理解と協力が欠かせません。ところが、多くの証券会社では従来型の組織文化が障壁となり、DXの浸透が進まないケースも見受けられます。
証券業界は長年の慣習や独自のノウハウが根づいており、変化に対して慎重な傾向があります。過去の成功体験に基づく保守的な姿勢が、新しい技術や働き方の導入を妨げる原因です。
例えば新システムを提案しても現場が既存のフローに固執してしまい、実行フェーズに移らないケースが見受けられます。このような文化が続けば、他業界との競争で遅れを取るリスクが高まるでしょう。
さらに、現場担当者が変化を拒むだけでなく組織全体に横断的なコミュニケーションが不足している場合、イノベーションの種は芽を出す前に摘まれてしまいます。変革を推進するにはまず内向きの思考を打破し、変化を恐れず柔軟に対応できる風土をつくることが求められます。
信頼関係を前提にした現場との対話や、成功事例の社内共有などが効果的です。
組織の方向性を決める経営層やミドルマネジメント層の多くが、ITやDXに関する知識や関心が不足しているケースも見られます。
例えば、新たなデジタル戦略に対して投資対効果を正しく評価できず導入判断が遅れたり、断念されたり、といったことがあるでしょう。このように、現場がDX推進に意欲を持ったとしてもトップの理解がないばかりにプロジェクトが前に進まない、そんな事態を改善するためには経営層自身の学習と巻き込みが不可欠です。
加えて、ITやデジタルに対するアレルギーを払拭できないまま全体を統括しようとすると、現場との温度差が拡大し方向性に一貫性がなくなります。経営陣が自らデジタルの基本を学び現場と議論できる関係性を築くことが、DXの初期フェーズにおいては重要です。意識改革と並行し、社内にITリテラシーを高める機会を増やす必要があるでしょう。
既存の業務プロセスや評価制度にこだわるあまり、DX推進に必要な柔軟性が欠けている場合もあります。
例えば属人的な業務を改善するためにRPAを導入しようとしても、手作業を重視する文化が根強く残っていれば活用されず効果が発揮されません。制度やフローの見直しを前提とした変革が必要です。
証券DXを本格的に進める上では、システム導入や業務のデジタル化だけでなく、それを支える組織構築が欠かせません。組織の体制や文化が変われば、プロジェクトの進行速度や定着率にも明確な違いが生まれるでしょう。
そこでまず挙げられるのは、業務の意思決定スピードが加速することです。部門を横断するDXチームやITとビジネスを橋渡しできる人材が配置されることで、社内での合意形成がスムーズになります。
また、現場主導による改善提案の活性化も見逃せません。デジタルを前提とした業務環境で働くことで、従業員が自らの手で業務改善や新サービスのアイデアを実行に移しやすくなることがあるでしょう。
さらに組織横断的な人材育成やスキルの平準化などにもつながるため、従来のような属人化や部門間の情報分断が減少して社内のリソースを柔軟に活用できる体制が整います。
このように証券DXに適した組織づくりは企業全体の変革力を高め、持続的な競争優位性を築く礎になります。
続いては実際に証券DX推進のために組織体制を見直し、変革を進めた企業の事例を紹介します。各社の戦略や工夫から、自社にも応用できるヒントが見えてくるはずです。
みずほフィナンシャルグループでは全社的なIT戦略を策定し、DXを実行するための基盤整備に注力しています。
特徴的なのはデジタル人材の育成、及び採用の両輪による推進体制です。社内で育てるだけでなく即戦力となる外部の専門人材も積極的に受け入れ、多様な視点と技術を組織に取り込んでいます。
例えば社内IT部門に「エンジニア・イネーブルメント推進部」を設置し、継続的にスキル研修を行っています。このような育成・補強の両面からのアプローチにより、DXプロジェクトの実行力が高まりました。
野村ホールディングスは伝統的な証券業界の枠組みにとらわれず、変革を先導する組織設計を進めています。
同社が導入したのは、部門横断型・連邦型組織です。これは複数の部門が独立性を保ちながらも、共通のDX戦略に基づいて連携する体制です。結果として意思決定が迅速になり、各部門が現場の課題を起点に施策を実行できるようになりました。
今でも営業・IT・マーケティングが一体となったプロジェクトチームが顧客体験向上を目的とし、アプリ開発に取り組んでいます。このような柔軟な連携が、イノベーション創出につながるといえるでしょう。
大和証券グループではDXを一過性の施策で終わらせず、継続的な改善活動として根付かせるための専任組織を立ち上げました。
専任チームは「ビジネストランスフォーメーション部」として設置され、技術部門と現場の橋渡し役を担っています。ここでは社員の声を起点としたプロジェクトを推進し、ボトムアップ型のDX推進が実現しています。
例えば紙ベースで行っていた社内報告や承認プロセスをデジタル化し、作業時間の短縮に成功しました。専任部門があることで、DXが全社的な取り組みとして継続されています。
みんなの銀行は設立当初から、デジタルバンクとしての機能に特化した組織設計を行っています。
特徴的なのは、現場と経営層が密に連携する体制です。一般的には経営と現場が分断されがちですが、同社ではプロジェクト単位で経営陣が議論に参加し迅速な意思決定を行っています。
また若手社員がアイデアを自由に発信できる環境が整っており、新規サービスのアイデアも現場から数多く生まれています。トップダウンとボトムアップの融合が、同社の大きな強みです。
参考:株式会社みんなの銀行

証券DXの成功には戦略的な組織構築と、それを支える明確な意識が欠かせません。技術を導入するだけではなく、それを機能させる人材・組織・文化の整備が変革を持続させるカギになります。
ここでは証券業界がDXを組織的に推進する際に意識すべき、4つの視点を整理します。
自社だけでDXを進めるのは、体制・ノウハウ・人材の観点からも限界があります。特に証券業界のような規制業種では、専門的な知識と経験が不可欠です。こうした場合には、外部パートナーの支援を活用してプロジェクトを加速させる判断が有効でしょう。
例えばIT戦略の立案段階から外部コンサルタントと協働すると、短期間で方向性を明確にできるでしょう。また内製化の難しい分野では開発・運用までアウトソーシングすることにより、社内リソースをコア業務に集中させることも可能です。
一方で外部任せにするのではなく、自社内での知見を蓄積する仕組みも必要です。外部支援と内部育成のバランスをとりながら、持続可能な体制を整えることが重要といえます。
DXはシステム開発だけでなく、業務改革そのものを目的とする取り組みです。従来のIT部門では保守・運用が中心であり、DXのような全社横断型のプロジェクトとは性質が異なります。
そこで必要になるのが、デジタル推進部門の設置と役割強化です。デジタル推進部は業務部門との対話を重視し、ビジネス側の要望を技術部門とつなぐブリッジの役割を担います。
例えば新サービスの立ち上げやチャネル改革など、ビジネス起点の施策においてはITだけでなくデジタル戦略が不可欠です。そのためには従来の縦割り構造を超えて、部門間での協働体制を築くことが求められます。
デジタル推進部とIT部門が相互補完的に機能することでDX全体の統制力が強まり、組織全体の変革力も高まります。
証券DXを持続的に推進するためには、将来を担うデジタル人材の育成が不可欠です。単なるシステム利用者ではなく業務課題を発見し、技術を使って自ら解決策を提示できるような人材の存在が組織の強みになります。そのためには現場での実務経験とデジタル教育を両立させる、人材育成施策が必要です。
例えばOJTに加えて、外部のリスキリング研修や資格取得支援を行う企業も増えています。
さらに若手社員に自由な発想で業務改善を提案させる、といった文化づくりも有効です。失敗を許容し、チャレンジを称える組織風土があればデジタルネイティブ世代が本来の力を発揮しやすくなります。
人材育成は短期的な成果を求めず、時間をかけて継続的に投資していく姿勢が問われます。
最後に重要なのが、DXを推進する専任組織の立ち上げです。各部門の一部業務としてDXを進めるだけでは意思決定の遅れや優先順位の低下が生じやすく、変革が形骸化する恐れがあります。
専任組織を設けることで責任の所在が明確になり、プロジェクトの実行力も高まります。さらにDX戦略の一貫性を保ちつつ、全社横断的なガバナンスを効かせるためにも中心となる組織が不可欠です。
この組織はプロジェクトマネジメントの機能だけでなく、人材配置・評価制度の調整・外部ベンダーとの連携などの広範な役割を担う必要があります。
また経営層との距離が近い位置に配置されていれば迅速な意思決定と柔軟な予算対応が可能になり、全社を巻き込んだDX推進が実現します。
証券DXの実現には技術的な変革と並行して、組織そのものの構造を柔軟かつ戦略的に変えていく必要があります。
ここでは先進的な取り組みを通じ、組織構築の強化とDX推進を両立している企業の事例を紹介します。各社の具体的な行動から、自社に取り入れるべき要素を検討してみましょう。
SMBC日興証券では従業員から募ったビジネスアイデアを実際の事業に展開する、といった仕組みを整備しています。この取り組みによって現場の声を起点とした変革が可能となり、部門を越えた連携や自発的な提案が活発化しています。
実際に新規サービスや業務プロセス改善案などが採用され、既存体制にとらわれない柔軟な挑戦が生まれました。こうしたボトムアップ型のDXは、組織全体にイノベーション文化を浸透させる効果があります。
このように社員の主体性を活かす制度を整えることで、組織が自然と変化に強くなる環境が育ちつつあります。
参考:SMBC日興証券株式会社
岡三証券グループではリテール分野における顧客接点の再構築を進める中で、DXと組織変革を連動させています。チャネル統合や業務の効率化だけでなく営業体制そのものを見直すことで、現場に求められる能力や役割の再定義を行いました。
同社では顧客のライフステージに合わせたコンサルティング強化を目的に、柔軟に人材を配置できる体制を構築しました。またデジタルツールの活用により、経験の浅い社員でも一定水準のサービスを提供できる環境を整えられました。
このように業務戦略と組織のあり方を一体で設計することで、成果につながる変革が実現されています。
参考:株式会社岡三証券グループ
みずほ証券はグループ全体でのDX戦略を推進する中で、情報共有と意思決定のスピード向上に重点を置いています。特に注目すべきは、部署の枠を越えたコラボレーションが促進されている点です。
例えば生成AIを活用した社内文書検索システムを導入し、ナレッジの活用効率を高めています。これにより部門間での知見や成功事例の共有がスムーズになり、重複業務や無駄な調整を減らすことに成功しました。
また各チームの裁量を拡大し、意思決定の現場主導化を進めることで変化に即応できる組織構造が実現されています。
参考:みずほ証券株式会社
証券DXを本格的に推進するには技術導入や業務改善だけでなく、それらを支える柔軟かつ戦略的な組織体制の再構築が不可欠です。
ここではDXを成功に導くための組織構築における、6つのステップを紹介します。段階的に進めることで、現場と経営層の認識を揃えながら確実に前進できるようになるでしょう。
最初に行うべきは、DX推進の目的を明確に定義することです。目的が曖昧なままでは組織の方向性に一貫性が生まれず、現場が混乱しやすくなります。
例えば業務効率化を狙うのか、顧客体験の向上を目指すのか、新たな収益モデルの創出に注力するのかによってそれぞれ必要な組織構造や人材像が大きく異なります。目的が明確であれば関係者の共通理解が生まれ、具体的な施策や優先順位の設定もしやすくなります。
DXは単なるIT部門の施策ではなく、経営そのものに関わる変革です。そのため、DX推進は経営戦略と切り離して考えるべきではありません。
例えば、営業戦略の再設計やリテール部門の収益構造改革と連動させる形でDXを位置づけると、各部署にとっての自分ごととして認識されやすくなるでしょう。経営陣自らがDXの重要性を発信し、全社方針として取り組むことで組織内の理解と協力が加速します。
目的が定まり経営戦略に組み込まれたら、次はそれを実行する体制づくりです。専任のDX推進組織とリーダーの配置は不可欠です。
この際リーダーには、単なる技術的な知見だけでなく、事業理解と社内の調整力が求められます。また推進組織はプロジェクト管理だけでなく現場の課題を吸い上げ、施策として具現化する役割も担います。
例えばIT部門だけでなく業務部門の中からも人材を選出することで、実態に即した改革が実現しやすくなるでしょう。
次に進めるべきは、部門間の連携強化です。従来の縦割り組織のままでは、情報の断絶や調整コストの増大がDXの妨げになります。そのため部門横断型、または連邦型の組織体制へと進化させることが求められます。
例えば各部署にDX担当者を配置し定期的に横断的な議論や進捗共有を行うことで、全社的な連携が生まれやすくなります。
連邦型の仕組みでは各組織が独自にDXを進めながらも、統一されたビジョンとガイドラインで統制を保つことが可能です。
組織体制の整備と並行して、人材と文化の改革にも着手する必要があります。いくら制度が整っていても、現場に変革を受け入れる文化が根付いていなければDXは定着しません。そのためには社内教育や外部研修を通じたDXリテラシーの底上げに加え、挑戦を許容する風土の醸成が重要です。
例えば失敗から学ぶ姿勢を評価する仕組みや成功事例の共有を習慣化することで、社員の意識は少しずつ変わっていくでしょう。また外部からの専門人材を採用し、社内に新しい刺激を与えるのも有効です。
最後にDX組織の持続的な運営と実行には、予算の確保が欠かせません。システム導入や人材採用だけでなく教育、運用、改善など多岐にわたるコストが発生します。そのため各プロジェクトのROI(投資対効果)を明確にし、継続的な成果を見込める計画を策定する必要があります。
例えばスモールスタートで成果を出し、次の予算を確保する方式をとれば現場の負担を最小限にしながら進められます。予算配分と優先順位を戦略的に見極める力が、DXの実効性を大きく左右します。

証券DXの成功には技術導入だけでなく、組織そのものの在り方を問い直す必要があります。目的の明確化から専任体制の構築や人材育成、部門連携、そして予算の確保に至るまですべてが一貫性をもって計画されることが求められるためです。既存の組織構造にとらわれず柔軟かつスピーディーに対応できる体制を整えることで、変化する市場に即応し持続的な競争優位を確立できるようになります。
まずは本記事を参考に自社の現状と課題を客観的に捉え、段階的に変革に取り組んでみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
