証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

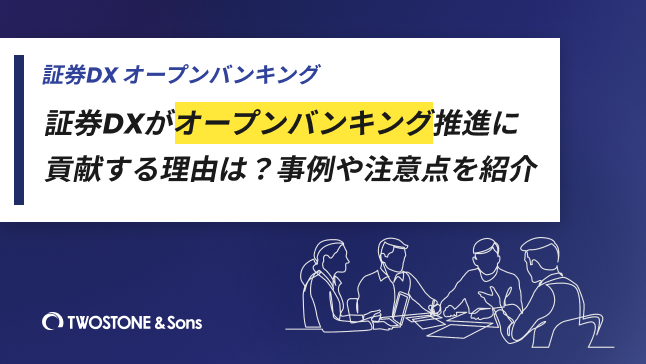
証券DXとオープンバンキングの関連性について、具体的な企業事例を交えながら解説しています。導入を検討している企業担当者に向けたセキュリティリスクや顧客の同意管理、API連携の注意点などの実務に直結する重要な観点を網羅した内容となっています。
近年の金融業界では「オープンバンキング」という、新たな潮流が注目されています。これは、金融機関が自社の持つ顧客データやサービスを外部と連携させることでより利便性の高い金融体験を提供しようとする動きです。しかしその実現には、柔軟で拡張性のあるシステム基盤が欠かせません。
ここで注目されるのが、証券業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)です。証券DXが進めばオープンバンキングの基盤として機能するインフラやデータ連携の環境が整い、銀行と証券会社の垣根を越えたサービス提供が可能になります。
本記事では、証券DXがオープンバンキングの推進にどのように寄与するのかを解説します。API連携や顧客同意の取得など基本的な仕組みから実際の連携事例、導入時に注意すべきポイントまで幅広く取り上げます。本記事を読むことで金融業界における次世代サービスの方向性や、自社が取り組むべき戦略のヒントが得られるでしょう。

テクノロジーの進化により、証券業界は従来の枠組みを超えた変革を求められています。中でもデジタル技術の導入を通じて業務を効率化し、新たな顧客価値を創出する証券DXは業界再編のカギを握る動きです。
一方で銀行を中心とするオープンバンキングは、APIの活用を軸に外部サービスとの連携を図る戦略です。これによって顧客は自身の金融情報を他のサービスとも統合して活用できるようになり、金融の利便性が高まります。
この2つの流れは個別に進んでいるようでいて、実は密接に関係しています。証券DXが進めばデータ構造やシステム基盤が整い、オープンバンキングの実現を支える土台となります。
証券DXとは証券会社がデジタル技術を活用し、業務プロセスや顧客対応を変革する取り組みです。紙中心だった申込手続きのデジタル化やAIを使った投資アドバイス、RPAによる社内業務の効率化などが挙げられます。
この動きは単なるIT導入ではなく、ビジネスモデルの転換を伴うものです。顧客行動の変化やフィンテック企業との競争に対応しつつ、スピード感のある商品・サービス提供が求められています。証券DXによって業界全体の生産性やサービス品質が高まり、オープンバンキングにも積極的に関与できる土壌が築かれます。
オープンバンキングは、銀行や証券会社が持つ顧客情報や金融サービスをAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を通じて外部に提供する仕組みです。これにより、第三者企業と連携した多様な金融サービスが実現します。
APIを活用することで口座残高や取引履歴などの情報を、外部のアプリケーションやサービスに安全かつ効率的に提供できます。これによって顧客は複数の金融機関を横断し、資産管理を行うことが可能になります。
証券業界でも取引データや投資情報をAPIで連携する動きが進んでおり、金融エコシステム全体の一体化が加速しています。
さらにこれらのデータを用いて、資産配分の自動提案や投資タイミングの分析といった高度な機能を提供する企業も増えています。こうした技術活用によって利用者の利便性はもちろん、金融業界全体の生産性も向上しているのが実情です。
オープンバンキングの前提には、顧客の明確な同意があります。個人情報や取引履歴の共有にあたっては、信頼性と透明性が重視されます。
デジタル化が進んだ証券業界ではスマートフォンやオンライン口座を通じた同意取得の仕組みが整っており、スムーズなデータ提供が可能です。顧客自身が情報活用の主体となる環境を整えることが、今後の金融サービスの質を左右します。
実際に、ワンタップで同意が完了するインターフェースやデータ提供先を可視化できる管理画面など、ユーザーの安心感と操作性を高める工夫が進められています。こうした設計は、デジタルサービスへの信頼形成に直結します。
APIを介して他社サービスと連携することで、金融サービスの幅は広がります。資産管理アプリや会計ソフト、住宅ローンシミュレーターなどの顧客が日常的に利用するサービスと証券情報を結びつける動きが広がっています。
この連携によって、ユーザーは1つのインターフェースで多様な金融機能にアクセスできるようになり、顧客体験が向上します。
また証券会社にとっては、顧客接点の拡張やサービス価値の強化につながる、といったメリットもあります。実際に他社アプリとの連携を通じてユーザーの行動データを分析し、新たなニーズの発掘やサービス改善に役立てているケースも増加しています。
証券DXはオープンバンキングの推進にとって、重要な役割を果たします。その理由は3つに整理できます。
まずDXによりシステムのAPI化が進むため、他社との連携がしやすくなる点です。これによって証券会社も金融エコシステムの中で連携プレーヤーとして、機能を発揮できるようになります。
次にデータのリアルタイム性と正確性が向上するため、外部サービスに提供する情報の品質が保証されます。金融業界においてはデータの信頼性がサービスの価値を大きく左右するため、この点は特に重要です。
最後に、証券DXは顧客中心のサービス設計を可能にします。個人投資家のニーズを詳細に把握し、パーソナライズされたサービスを他社との連携によって届けることが可能になります。これはオープンバンキングの思想そのものであり、今後の金融サービスの中核を担う動きです。
オープンバンキングの導入により、証券業界は従来の枠組みを超えた成長が期待されます。顧客体験の向上や新規プレーヤーの参入、そして法規制への対応などのさまざまな側面で新たな可能性が芽生えています。
ここからは証券業界にとってどのようなメリットがあるのか、具体的に掘り下げてみましょう。
オープンバンキングは、複数の金融機関のデータ連携を可能にするインフラです。これが証券業界に与える影響は、以下のように整理できます。
複数の金融機関の口座情報や取引履歴を統合すれば、ユーザーは1つのアプリで資産全体を把握できます。
この統合型サービスによって、顧客はスマートフォン1つで銀行口座や証券口座の残高、投資状況を確認でき利便性が向上します。統合プラットフォームは顧客の利用頻度を高めるだけでなく、企業には新サービス創出の基盤となります。
加えて企業は顧客ごとのライフステージ、金融ニーズなどに応じた提案を展開しやすくなります。これによって単なる資産管理を超えた包括的なファイナンシャルプランニングが実現し、サービス価値が高まります。
オープンバンキングによって得られる多様なデータを活用すれば、顧客ごとの収入・支出パターンや投資スタイルに基づいた提案が可能になります。これによって従来の一斉提案では見えにくかったニーズに対応し、顧客満足度と信頼性を高める結果につながります。
実際に、AIによる分析結果を活用してポートフォリオの自動調整や適切なリバランス時期の提案など、より高度な個別最適化サービスの提供が進んでいます。こうした施策は、リテンション率の向上にも寄与します。
オープンバンキングは市場構造にも変化をもたらします。新たなプレーヤーの参入や既存企業の競争環境を大きく変える可能性があります。
APIを通じた金融情報連携はFinTech企業など、新興プレーヤーにとって低コストでサービスポケットを拡大するチャンスになります。
実際に、証券口座や銀行口座のある顧客のニーズに合わせてポートフォリオ分析や投資アドバイスを提供するスタートアップが増えています。こうした新規参入者は提供価値や使いやすさで顧客を惹きつけ、大手証券会社への圧力としての役割を果たします。
さらに、既存金融機関との協業を通じた共同サービスの開発やエコシステム型のビジネスモデル構築も活発化しており、業界全体に活気と緊張感が生まれています。
オープンバンキングによってアクセス可能になるデータは、AIや機械学習による高度な分析や自動化の原動力になります。
例えば短期的な市場変動に反応した自動取引アルゴリズムの導入、高度なリスク評価ツールの開発などサービスの質を一段上に引き上げるイノベーションが相次いで生まれます。これが競争優位の源泉になるため、DXへの継続的な投資が必須とされます。
加えて、異業種との連携による新たなユースケースの創出やユーザーの金融リテラシー向上を支援するサービスの開発など、多面的な価値が期待される領域です。
サービスの多様化と市場の拡大には、同時に新たなリスクも伴います。オープンバンキングには、セキュリティやコンプライアンスの対応が欠かせません。
金融データ連携の範囲が広がると、その分リスクも高まります。APIへの不正アクセスやなりすましといった脅威は、より頻繁かつ巧妙に発生します。
証券会社は認証強化やアクセス制御、通信暗号化など多層的なセキュリティ体制を構築し、リアルタイム監視によって不正検知力を高める必要があります。またISMSやSOC(セキュリティオペレーションセンター)の整備により、運用面の信頼性も補強する必要があるでしょう。
加えて脆弱性の早期発見と修正、定期的なペネトレーションテストの実施など技術的対策を日常的に運用へ取り入れる体制が求められます。
オープンバンキングを展開するにあたって個人情報保護法や金融商品取引法、API連携ガイドラインなど多数の法令や指針への対応が求められます。
規制環境は国際的に多様で変動もあり、企業はコンプライアンス要件の継続的把握や必要な制度整備、社内教育に注力する必要があります。これが不十分だと、罰則や信頼失墜による被害が企業価値に影響してしまいます。
実際に国内外でのデータ漏えいや法令違反に起因する訴訟リスクも増しており、リーガルチェック体制や内部監査の強化も不可欠です。透明性の高いガバナンスが、顧客の安心感につながります。

証券業界では金融サービスの利便性向上や業務効率化を目的として、API連携の導入が進んでいます。特に証券DXと組み合わせることで、オープンバンキングの展開が一層加速しています。
ここでは実際にAPIを活用した企業の具体例を取り上げ、その効果と導入背景について解説します。
楽天証券は楽天銀行とのAPI連携を通じ、証券取引と銀行口座の間でリアルタイムな資金移動を実現しました。顧客が株式を購入する際に自動で銀行口座から資金が移動するため、入金の手間がかかりません。
この自動化によって投資初心者でもスムーズに取引を行える環境が整い、ユーザー層の拡大にも貢献しています。資金の移動忘れや時間的ロスがなくなることで、顧客の投資行動が活性化しています。特にシステム面ではAPI通信の安定性が高く、導入後のトラブルも少ないと評価されています。
またこのサービスは、楽天グループの強みを活かした総合金融戦略の一環として位置づけられており、銀行・証券・ポイント経済圏を横断する一体型の顧客体験を提供する基盤にもなっています。これにより、グループ全体のクロスユース率の向上にも寄与しています。
参考:楽天証券株式会社
野村證券は顧客の金融資産をより的確に把握できるよう、銀行口座情報と証券口座を統合管理できる機能を提供しています。この取り組みによって個人資産の全体像が可視化され、資産運用の最適化が図られました。
統合データに基づいた提案が可能になるため、これまで以上に細やかな投資アドバイスが実現しています。また複数口座を持つユーザーにとって、資金移動や管理が一元化される利点も大きいのです。営業担当者側の利便性も高く、顧客への提案資料やレポート作成のスピードが向上しました。
さらに、資産形成に対する意識の高まりを受けてこうした統合機能のニーズは増加傾向にあり、今後はライフイベントに連動したシミュレーション機能や教育資金・老後資金に関する自動診断などの周辺サービスの展開も視野に入れた展開が期待されています。
参考:野村證券株式会社
SBI証券は複数の銀行や金融機関と連携し、顧客が保有するすべての口座情報を統合的に取得できるAPIを構築しました。この連携によって分散していた情報が一本化され、精度の高い投資判断を支援しています。
さらにこれらの情報を基にAIが資産構成を分析し、最適な運用プランを提案する仕組みも搭載されています。ユーザーは個別相談の手間を省きながら、自分に合った投資方針を選択できます。
加えて、SBIグループ全体での情報連携によって他の保険・銀行・住宅ローンサービスとの相互活用も進められており、資産運用のトータルサポートという観点からも競争優位性が確立されつつあります。
こうした仕組みは高齢者層や投資初心者のサポートにも適しており、顧客層の拡大にも効果があります。
参考:SBI証券株式会社
三菱UFJ eスマート証券では外部開発者向けに「kabu.com API」を公開し、証券データへのアクセスを可能にしています。ユーザーはこのAPIを通じ、リアルタイムの株価情報や注文処理を外部アプリケーションで活用できます。
これにより、投資家個人が自らのニーズに合ったシステムを作る動きも見られるようになりました。独自の分析ロジックを使った取引ツールの開発も促進されており、証券取引の多様化が進んでいます。企業側もエコシステムの形成を戦略的に進めることで、長期的な顧客ロイヤルティ向上を目指しています。
さらにAPIの仕様は金融APIに特化したセキュリティ基準を満たしており、情報漏えいや不正アクセスへの対策も整備されています。外部企業との連携も円滑に進めやすく、実証実験などを通じた新サービス創出の基盤にもなっています。
マネックス証券は外部FinTech企業との連携を重視し、APIを活用したサービス拡充を積極的に進めています。
実際に資産管理アプリやライフプランニングツールと連携し、顧客に最適な金融環境を提供しました。このようなAPI連携により、証券業務が日常の延長線上に溶け込むような体験が可能となりました。利用者にとって1つのアプリケーション上で、情報取得から取引までを完結できる点は大きな魅力になったのです。
加えてオープンAPI戦略を中心とした協業モデルを展開しており、新興企業や大学などと共同でプロトタイプ開発を行う事例も増加しています。こうした取り組みにより、APIを通じた革新的なサービスが次々と生み出されています。
マネックスはFinTechの進化とともに、APIの柔軟性とセキュリティの強化にも力を入れています。
参考:マネックス証券株式会社
フィデリティ証券はWebと連携可能な独自プラットフォーム「WB4」を開発し、APIによるデータ統合を実現しています。これによって顧客は複数の金融機関情報を一括管理でき、資産の見える化がスムーズになりました。
また投資戦略に応じたダッシュボードも構築されており、UXの向上と同時に運用の精度も高めています。ログイン認証の一元化など、セキュリティ面での配慮もなされています。
さらにグローバルな金融プラットフォームとしてのポジションを強化する狙いもあり、今後はAIを活用した資産分析やリスク許容度に基づく、パーソナライズ機能の搭載も計画されています。国内外の顧客に向けて先進的な証券体験を提供しています。
フィデリティ証券の取り組みはパートナー企業との連携を通じ、サービス提供の範囲が拡張されている点も注目されています。
参考:フィデリティ証券株式会社
Jトラストグローバル証券はFinTechパートナーとの連携を前提とした、API環境「OmegaFS」を構築しました。このAPIを利用することで、外部開発者が投資アプリや分析ツールと証券口座を接続しやすくなります。
特に若年層を中心としたアクティブトレーダーに対し、自由度の高い投資支援環境を提供できる点が特徴です。また開発者向けのドキュメント整備やテスト環境も用意されており、導入のしやすさも支持されています。
加えてユーザーごとのニーズに応じたモジュール提供も実施されており、細かなカスタマイズが可能です。特定の業種向けテンプレートやAPI接続のサンプルコードなども豊富に提供され、実装工数を削減しやすい仕組みが整っています。
Jトラストグローバル証券の取り組みは、金融サービスのオープン化を推進する代表的なモデルケースとして注目されているのです。
オープンバンキングは証券業界の変革を促す一方、導入に際しては慎重な姿勢が求められます。特に金融業特有の厳格な規制環境や個人情報を扱う責任の重さから、実装段階での注意が不可欠です。
ここでは証券DXの一環としてオープンバンキングを活用する際に押さえるべき、主要なポイントを整理します。
API連携は利便性を向上させる一方、外部とつながるという特性上セキュリティリスクが高まります。金融機関が不正アクセスや情報漏えいのリスクを軽減するためには、多層的な防御策の構築が必要です。具体的には通信の暗号化や認証強化、アクセス制御の厳格化が必須となります。
特に証券業界では取引情報や残高データなどのセンシティブな情報を扱うため、少しのセキュリティインシデントが信頼失墜につながる可能性があります。そのため定期的な脆弱性診断やペネトレーションテストを行い、常に最新の脅威に対応できる体制を整えておくことが肝要です。
サードパーティとの連携では、相手側のセキュリティレベルも評価対象になります。単に自社のセキュリティを強化するだけでなく、パートナー企業のガバナンス体制の確認も不可欠です。
APIを通じた顧客データの共有には、明確かつ適切な同意プロセスの設計が必要です。ユーザーがどの範囲まで情報を共有するか、誰と共有されるのかを理解できるようにUI・UX設計の段階から透明性を重視すべきでしょう。
また、同意の取り方にも工夫が求められます。例えばワンタップで包括的な同意を取得するのではなく、カテゴリ別に明示しながら進める方式が望まれます。ユーザーが自身の意思で情報開示を管理できる設計が、長期的な信頼関係の構築につながります。
加えて取得した情報の扱いにおいても、使用目的の明確化や保存期間の制限、再利用の制御など個人情報保護法をはじめとする関連法規への準拠が必須です。これらの体制整備が不十分な場合は法的リスクだけでなく、社会的信用の毀損にもつながります。
オープンバンキングの基盤はAPIですが、そのAPIが不安定であればサービス全体の品質が低下します。安定した接続やレスポンスタイムの短縮、障害時の復旧体制は利用者の満足度に直結する要素です。
証券取引ではリアルタイム性や正確性が特に重視されるため、APIの品質管理には他業界以上の水準が求められます。そのため、開発フェーズでは負荷テストや冗長構成の設計を通じ、システム全体の堅牢性を確保する必要があります。
また、APIのメンテナンスやバージョン管理も重要なポイントです。利用者や外部ベンダーに向けたドキュメント整備、変更通知の仕組みを整備することで混乱のない運用が可能になります。
長期的にはこれらの対応が業界全体のデジタルインフラとしての信頼性を底上げし、持続可能なオープンバンキングの推進を支える土台になります。

オープンバンキングは、証券業界に新しい価値をもたらす可能性を秘めた概念です。顧客ニーズの多様化、競争環境の変化に対応する上で、API連携を軸としたデジタル戦略の推進はもはや選択肢ではなく必須の取り組みといえます。
ただし導入に際しては、セキュリティ対策やプライバシー保護、システムの安定運用といった多面的な検討が欠かせません。安易な導入はリスクを高め、顧客の信頼を損なう可能性もあるため、本記事を参考に段階的かつ慎重に検討しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
