証券DXとデジタル通貨の融合による変革とは?効果的な施策を解説
証券

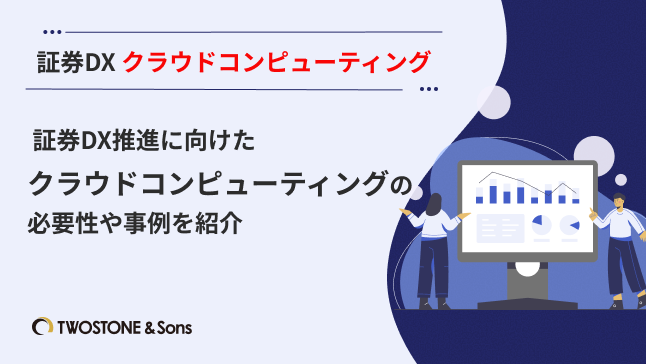
証券DXの推進に欠かせないクラウドコンピューティングの重要性や代表的なクラウドサービス、具体的な活用事例をわかりやすく解説します。またリスク管理の方法や導入時の注意点も詳しく紹介し、安全かつ効率的な証券業務の実現に役立つ情報を提供します。
証券業界では近年急速に進むデジタルシフトの波に乗り遅れないため、DX(デジタル・トランスフォーメーション)が経営課題として強く意識されています。特に、膨大なデータを扱い厳しいセキュリティ要件が課される証券業務においては、既存システムの限界を乗り越える手段が求められています。
その中でも注目されているのが、クラウドコンピューティングの活用です。クラウド環境に移行することでコストの最適化や業務の柔軟性向上、さらには顧客ニーズに即応するシステム構築が可能となります。
本記事では、証券DXを成功に導くためにクラウドコンピューティングがなぜ不可欠なのか、その理由を明確にするとともに実際の事例も交えながら具体的に解説していきます。読み終える頃にはクラウド導入による証券業務の変革可能性と、その活用に向けた視点を手に入れられるでしょう。

クラウドコンピューティングとは、従来のように自社内にサーバーやネットワーク機器を設置してシステムを構築するのではなく、インターネット経由で外部のデータセンターにある計算資源やストレージ、アプリケーションなどを利用できるサービス形態を指します。
この技術の最大の特徴は、スケーラビリティと柔軟性に優れている点です。企業は需要に応じてリソースを簡単に拡張・縮小できるため、インフラ投資を最小限に抑えながらビジネスの成長に応じたIT基盤を維持することができます。また、保守やセキュリティ対応をクラウド事業者が担うことで運用負担が軽減されるのも、利点の1つです。
さらにクラウドには「パブリッククラウド」「プライベートクラウド」「ハイブリッドクラウド」といった利用形態があり、それぞれに特徴と適した用途があります。証券業界のように高度な機密性が求められる分野ではハイブリッド型を採用し、機密情報はプライベート領域で厳重に管理しつつ汎用的な業務はパブリック領域で処理する、といった構成が選ばれる傾向となっています。
証券DXの実現には、単なるIT導入にとどまらずビジネスプロセス全体を再設計し、顧客体験や業務効率を向上させることが求められます。その中核を担うのが、クラウドコンピューティングです。
ここでは、その具体的な理由を見ていきます。
証券会社が従来のオンプレミス型システムを維持するためには、サーバーの管理やシステムのアップデート、障害対応など多くの人員と時間を要します。さらに、予測が難しいトラフィックの変動に対応するためには過剰なリソースを前提とした構成が必要となり、コスト面で非効率な運用を強いられていました。クラウド化を進めることで、こうした問題を解決できます。
例えば、取引量の増加が予想される時期にだけリソースを一時的に増やす、といった柔軟な対応によって常に最適な状態でシステムを稼働させることが可能になるでしょう。このためIT予算の最適化が図られ、人的リソースも重要なコア業務に集中させることができます。
また、クラウドは高い可用性と自動化された運用機能を備えているため、システム障害時の復旧対応や定期メンテナンスの負担も軽減されます。結果として業務全体の効率が向上し、より付加価値の高いサービス提供へとつながります。
証券業務は金融商品取引法をはじめとする各種規制に加え、個人情報保護法やマネーロンダリング防止対策など厳格な法的要件を満たす必要があります。そのため、システムには高度なセキュリティ機能、及び監査対応能力が求められるのです。
近年のクラウドサービスは業界標準に準拠したセキュリティ対策を講じており、多層的な防御構造や暗号化やアクセス制御、ログ管理などが標準で組み込まれています。
例えば、ISO27001やSOC2といった第三者認証を取得しているサービスを選択することで、規制対応の土台を整えられるでしょう。またクラウドベンダーによっては、金融機関向けに特化したセキュリティ設計やコンプライアンスサポートを提供しており、これを活用すれば自社で一から構築するよりも迅速かつ確実に法的要件に準拠した環境を整備できます。
証券DXを進めるにあたり、こうした外部リソースを活用することは支援となります。
証券会社が扱うデータは、顧客の属性情報や取引履歴、資産状況、リスク許容度など多岐にわたります。これらの情報を適切に活用し、個別のニーズに応じた商品提案や運用サポートを行うことが競争優位性のカギとなります。
クラウド環境ではビッグデータ処理やAIによる分析、リアルタイムデータ活用が可能となるため、従来よりもはるかに高度な情報処理が実現します。
例えば、クラウド上でデータレイクを構築してそこに蓄積された顧客データをAIで解析することで、行動予測や潜在ニーズの抽出が可能になります。また、クラウドでは複数システム間のデータ統合が進めやすく、顧客との接点ごとに断片化していた情報を一元管理しやすくなります。
こうした基盤を整えることで、顧客満足度の向上や営業の生産性改善に直結するデジタル戦略の実行が可能となります。
証券業界に限らず、長年使い続けてきたレガシーシステムの維持・運用には多くの課題があります。実際に、対応できる技術者の減少や他システムとの連携の困難さ、新たなサービスの立ち上げにくさ、といった制約が顕在化しています。
クラウドへの移行は、これらの制約から抜け出しアジリティとスピードを手に入れる手段です。マイクロサービスアーキテクチャを導入し、サービス単位での柔軟な開発・拡張を行うことで顧客のニーズ変化に即応できる体制を整えることができます。
またクラウドを活用したモダナイゼーションは、システムの保守性向上や運用コスト削減だけでなく新たなビジネスモデルへの対応力を強化する意味でも重要です。証券DXの実現に向けては、クラウドを起点に既存の業務や組織構造を見直し、将来を見据えたデジタル基盤を構築することが不可欠です。
証券業務の高度化とスピード向上が求められる中で、どのクラウドサービスを選定するかはDXの成否に影響します。各社が提供するクラウドには特定の分野に強みがあり、証券業界においてもそれぞれ活用が進んでいます。
ここでは代表的な3つのサービスと、その特徴を解説します。
AWSはクラウド市場で圧倒的なシェアを持つサービスであり、金融業界でも多くの導入実績を誇ります。その最大の強みはグローバル規模で展開されるデータセンターと、高い可用性を持つインフラにあります。
実際にこのサービスは、複数のリージョンとアベイラビリティゾーン(AZ)により、災害時や障害発生時でもシステムを即座に切り替える仕組みが整っています。この冗長性によって証券会社は、トレーディングシステムなどの高い稼働率が求められる業務でも、安定的にサービスを提供できます。
さらに、AWSはオンデマンドでリソースを増減できるスケーラビリティにも優れており、取引量が急増するイベント時にも柔軟に対応できます。セキュリティ面でも暗号化技術やアクセス管理、ログ監視の機能が充実しておりコンプライアンス対応も含めた導入が可能です。
Microsoft Azureは特に企業向けシステムとの親和性が高く、既存のWindowsベースの業務環境をクラウドに移行しやすいという特徴があります。証券会社においても、既存の社内システムと連携させながら段階的にクラウド化を進める上で有効です。
例えばAzureのセキュリティセンターでは、リアルタイムでの脅威検出やコンプライアンス違反のアラートが自動で通知されるなど先進的なリスク管理が可能です。またマイクロソフト独自の「Confidential Computing」技術により、データが処理中であっても暗号化された状態を保ち情報漏えいリスクを最小限に抑えられます。
さらにPower BIやMicrosoft 365など同社の他製品との連携がスムーズであるため、業務の可視化や報告書作成を効率化する仕組みも構築しやすくなります。このようにAzureは、セキュリティと業務運用を両立させたい証券企業にとって、魅力的な選択肢です。
GCPは、データ処理と機械学習に強みを持つクラウドプラットフォームであり、証券業界におけるデータドリブンな意思決定を支援します。これは、膨大な取引データや市場動向を高速、かつ高精度に分析する必要がある場面で力を発揮します。
例えば、BigQueryという高性能なデータウェアハウスを用いると数百億件のデータを瞬時に集計・可視化でき、トレンド予測やリスク評価に役立ちます。またVertex AIを活用することで、過去の投資行動から顧客ごとの最適な金融商品をレコメンドする仕組みも構築可能です。
GoogleのテクノロジーはUI・UXにも定評があり、ユーザーにとって使いやすい分析ツールを構築する点でもメリットがあります。GCPは特にAIやデータ活用を軸にDXを進めたい証券企業にとって、選択肢として検討すべきクラウドサービスの1つです。

クラウドの活用には多くの利点がある一方、証券業界のように高い信頼性と安全性が求められる分野ではリスクマネジメントが不可欠です。導入にあたってはシステムの選定だけでなく、運用体制や契約内容も含めた包括的な視点が求められます。
ここではクラウド利用にあたり、注意すべきポイントを整理します。
クラウド環境で注意すべき点としてまず挙げられるのは、情報が外部のデータセンターに保管されるため物理的な管理が自社の手を離れるという特徴です。このため、不正アクセスやデータ漏えいといったリスクに対してより一層の対策が求められます。
例えば、多要素認証やIP制限、ゼロトラストセキュリティの導入によって内部・外部からのアクセスリスクを最小限に抑えられるでしょう。また定期的な脆弱性診断とセキュリティ監査を実施することで、リスクを可視化して早期に対処する体制を整えることが重要です。
クラウド事業者によるセキュリティレベルの違いにも注意が必要であり、サービス選定時にはどのような認証を取得しているか、金融業界向けの実績があるかなどを確認すべきでしょう。
クラウドを利用するということは、自社でハードウェアを所有せず外部の環境に依存するということでもあります。したがって、クラウドサービスの障害やメンテナンスによる影響が業務全体に及ぶ可能性があります。
これに対して、システムの冗長化を設計段階から取り入れてマルチリージョン構成を採用することで、万が一の障害発生時にも迅速に切り替える体制を築く必要があります。加えて、事業継続計画(BCP)をクラウド前提で見直すことも不可欠です。
さらに、サードパーティ製ツールや自社アプリケーションとの相性によっては安定稼働が妨げられるケースもあるため、事前の検証プロセスを慎重に実施することが求められます。
クラウドは初期費用を抑えやすく、必要な分だけリソースを利用できるという特徴がありますが、運用が長期化するほどにコストが膨らむ可能性もあります。リソースの過剰利用や非効率なアーキテクチャが原因で、月次費用が予想以上になることもあります。
そこで料金ダッシュボードやアラート設定を活用し、常に使用状況と費用をモニタリングすることが重要です。特に証券業務では、月末や四半期末など一時的に負荷が集中する場面があるため、それに合わせて柔軟にリソースを調整する運用設計が求められます。
またクラウド導入初期には、無駄なリソース利用を防ぐガイドラインを整備し、開発部門や業務部門と連携してコスト最適化に取り組むことが重要です。
クラウド環境では、データの所有権や保存場所、契約終了時のデータ処理方針などを明確にしておかなければトラブルの原因となります。特に証券業界では、顧客データや取引履歴などの情報が企業の信頼性を左右するため、その取り扱いは慎重であるべきです。
そこで、契約時にサービスレベルアグリーメント(SLA)やデータ移行ポリシーを明記し、契約終了後のデータ消去手順や保管期間について事前に合意しておくことが重要です。またデータをバックアップする際には、クラウド事業者と自社の両方で対応して二重のセーフティネットを設けましょう。
このように、クラウドの利便性を最大限に活かしつつ想定されるリスクに備えた準備を進めることで、より安全で効率的な証券DXが実現可能です。
クラウドコンピューティングを活用する際は、前述したリスクを正しく認識し、適切な対策を講じることが成功のカギとなります。特に、証券業界のように高い安全性が求められる領域では、リスク回避のための具体的な取り組みが必要です。
ここからは、実務で効果的なリスク回避策を紹介します。
リスク回避にはクラウド利用の範囲を段階的に拡大する、といった方法が効果的です。いきなり全システムをクラウド化するのではなく、影響範囲の小さいシステムから試験的に移行して運用上の課題を洗い出します。
まずは社内の業務効率化を目的とした文書管理やコミュニケーションツールのクラウド化を行い、そこで得られた知見を元に重要業務へ適用範囲を広げていきましょう。こうしたステップを踏むことで、システムの安定稼働とセキュリティ対応の両立を図りやすくなります。
また社内での役割分担や権限設定を明確にし、クラウド利用に関するポリシーや手順を整備してガバナンスを強化しましょう。従業員に対しては定期的な教育や啓蒙活動を実施し、情報セキュリティ意識の向上を図ることも重要です。
クラウド環境における最大のセキュリティ対策は、アクセス権限を厳格に管理し、誰がいつどのデータにアクセスしたかを正確に記録・監査することです。
例えば多要素認証(MFA)を必須とし、業務に必要な最小限の権限だけを付与する、といった対策が挙げられます。これにより、不正アクセスや内部犯行のリスクを減らせます。
加えて、アクセスログや操作履歴の記録は必須です。こうした証跡管理は問題発生時の原因特定や早期対応に欠かせず、規制対応でも求められる要素となっています。ログの保管方法や保管期間もポリシーで定め、定期的に監査を行う体制を構築しましょう。
クラウドサービスを利用する際はその提供元だけでなく、サプライチェーン全体のリスクを把握し管理する必要があります。それは、サービスの依存関係や外部委託先のセキュリティ水準が自社のリスクに直結するからです。
例えばクラウドベンダーがサードパーティ製のソフトウェアやハードウェアを使用している場合、その安全性も評価対象としましょう。ベンダー選定時にはセキュリティ認証や監査報告書の確認を徹底し、契約書にリスク管理体制の明確化を盛り込むことが重要です。
また定期的なリスク評価と監査を通じて、新たな脅威に対する対応策をアップデートし続ける体制を整備しましょう。サプライチェーンの透明性確保は、信頼できるサービス運用の土台になります。
証券業界特有の高度なセキュリティ要件や法規制に対応するためには、社内だけで対応を完結させるのは難しいケースが多いです。そのため外部の専門家を活用し、クラウド導入や運用を支援してもらうと良いでしょう。
例えば、金融業界に精通したセキュリティコンサルタントへのリスク評価の依頼やクラウド運用の自動化、専門企業への監査機能の実装委託などが効果的です。専門家の視点は、盲点となりやすいリスクの発見や最新の技術トレンドを踏まえた最適解の提示に役立ちます。
また法令対応やガイドラインの解釈に不安がある場合も、外部のアドバイスを受けることで確実に基準を満たす体制を構築できます。結果としてクラウド導入に伴うトラブルやセキュリティ事故のリスクを減らし、安全で効率的な証券DXの実現につながるでしょう。
証券業界ではクラウドコンピューティングを導入し、業務の効率化やサービスの高度化を目指す企業が増えています。実際にクラウド技術を活用することで従来の手作業を自動化し、情報共有のスピードを上げるなどの効果を上げています。
ここでは代表的な証券会社のクラウド活用事例を、3つ紹介します。
大和証券は営業担当者が顧客との会話内容を効率的に記録するため、Google CloudのSpeech-to-Textサービスを導入しました。従来は手入力や録音データの聞き直しに時間がかかっていましたが、音声認識技術により会話内容をリアルタイムでテキスト化し入力負担を削減しています。
この取り組みにより営業担当者は記録作業にかける時間を減らし、その分顧客対応や提案活動に集中できるようになりました。さらに、テキスト化されたデータはクラウド上で一元管理され、営業チーム間での情報共有もスムーズに行われています。こうした仕組みは業務効率化だけでなく、顧客満足度向上にもつながっています。
参考:大和証券株式会社
光世証券はIBMが提供するKICSクラウドを活用し、柔軟なシステム運用を実現しました。金融業界特有の厳しい規制に対応しつつ新たな業務要件への迅速な対応が求められていた、という背景からクラウドサービスの導入に踏み切りました。
例えば新規商品の追加や業務フローの変更といった要件に対し、クラウドのスケーラブルな環境で迅速にシステムを調整してタイムリーなサービス提供を可能にしました。これによって従来のオンプレミス環境では難しかった、スピード感のある業務改善を実現しています。
またKICSクラウドの強力なセキュリティ機能によって、顧客情報の保護や規制遵守を確実に担保しながら業務効率化を進めています。この成功事例は、クラウド活用による証券業務の変革を示しています。
参考:光世証券株式会社
むさし証券は富士フイルムビジネスイノベーションの提供する「オフィスあんしん365」を導入し、社内コミュニケーションの円滑化を図りました。従来は紙ベースや個別メールによる情報共有が中心で、情報の伝達漏れや遅延が課題となっていました。
クラウドベースのコミュニケーションツールに切り替えることで文書の共有やタスク管理がリアルタイムに行えるようになり、部署間の連携が強化されています。
実際にプロジェクトごとの情報共有スペースを設け、関係者が必要な情報にいつでもアクセス可能な環境を整えています。これによって意思決定のスピードアップや業務の透明性向上に寄与し、全社的な業務改善の原動力となりました。
こうした取り組みは証券DXの現場における、クラウド活用の良い手本といえるでしょう。
参考:むさし証券株式会社

証券業界のDX推進には、業務特性や規模に適したクラウドコンピューティングの選択が重要です。今回ご紹介したようにAWSやMicrosoft Azure、Google Cloud Platformなどの各クラウドサービスにはそれぞれ強みがあり、企業のニーズに応じて最適なサービスを選ぶことができます。
さらに段階的な導入や厳格なガバナンス、アクセス管理の強化といったリスク回避策を講じることも不可欠です。リスクを適切に管理しながらクラウドを活用すれば、業務効率化や顧客サービスの高度化といった効果を実現できるでしょう。
本記事を参考に、クラウドコンピューティングの力を最大限に引き出し、自社の証券DXを加速させましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
