証券DX推進に向けたクラウドコンピューティングの必要性や事例を紹介
証券
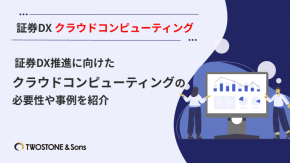
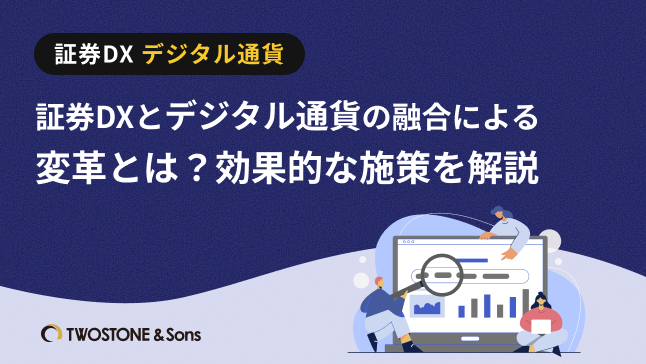
証券DXを実現する上で、デジタル通貨の導入は重要な要素です。本記事では、デジタル通貨が証券業界にもたらす影響や導入による利点に加え、実際に導入に取り組んでいる企業の具体的な事例も紹介しています。
証券業界でもデジタル化の波が加速し、金融インフラ全体に変革が求められています。その中でも近年注目を集めているのが、「デジタル通貨」の活用です。取引の透明性や決済スピードの向上を可能にするデジタル通貨は、証券業務の効率化と顧客体験の質の向上に貢献すると期待されています。
しかし一方で、新たな技術を導入する際にはリスクやコストも伴うので注意しましょう。業界特有の法規制やセキュリティ要件にどのように対応していくかは、多くの企業が直面する課題です。
本記事では、デジタル通貨の基本的な定義から、証券企業が導入することによる具体的なメリットとデメリットまでをわかりやすく解説します。導入を検討する企業にとって、自社に適した戦略を描くための手がかりとなるでしょう。
デジタル通貨がどのように業務に変革をもたらすのかを知ることで、今後のDX戦略の方向性を明確にする一助となれば幸いです。

デジタル通貨とは物理的な紙幣や硬貨とは異なり、電子的な形で発行される通貨の総称です。
主に中央銀行が発行する「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」と、民間企業などが発行する「ステーブルコイン」や「仮想通貨」に分類されます。証券業界において注目されているのは、特にCBDCや円建てのステーブルコインなど安定した価値を持っていて迅速な決済手段として機能するタイプです。
デジタル通貨は、ブロックチェーンや分散型台帳技術(DLT)を基盤とすることで信頼性や改ざん耐性を確保しています。決済プロセスを自動化できるスマートコントラクトとの親和性も高く、取引の正確性と効率を同時に実現できるという点で証券業務への導入が進められています。
例えば証券の決済や送金においてデジタル通貨を活用すれば、従来の複雑な清算フローを簡素化してリアルタイム処理を可能にする構成が実現可能です。この技術的な進化が、証券DXを推進する要素となっています。
デジタル通貨の導入は、証券業界にとって多くの利点をもたらす可能性を秘めています。一方で、慎重に検討しなければならない課題も存在します。
ここでは、導入によって得られるメリットと注意すべきデメリットをそれぞれ整理しているのでご参考ください。
デジタル通貨の最大の魅力は、決済の迅速化や業務の効率化を実現できる点にあります。これらのメリットは、証券取引の精度や速度が求められる場面で特に有効に機能します。
証券取引では取引成立から資金決済までに時間がかかる場合が多く、T+2(取引日から2営業日後の決済)といったスケジュールが一般的です。デジタル通貨を用いた場合、このプロセスをほぼリアルタイムで処理が可能になります。
例えば、スマートコントラクトを活用することで、取引と同時に自動的に決済が行われる仕組みを構築できます。これにより資金の滞留時間を短縮し、流動性の向上にもつながるのがポイントです。また取引スピードの向上は顧客満足度の向上にも寄与し、競争力のあるサービス展開が可能になります。
デジタル通貨の導入は、従来の複雑な送金処理や決済ネットワークを簡素化する役割を果たします。これによりシステム間連携や中間業者の介在が不要となるケースも増え、関連する運用コストを抑えることが可能です。
例えば、証券の受渡業務においては複数の関係機関を介した照合作業が発生しがちですが、ブロックチェーンベースのデジタル通貨を活用することでトランザクションが即座に記録されるのがポイントです。結果、正確かつ透明性のある取引が可能になります。
一方で、デジタル通貨を証券業務に取り入れる際にはいくつかのリスクやハードルも存在します。特に、技術的な安全性と法的な整備状況には注意が必要です。
デジタル通貨はインターネットを介して取引が行われるため、サイバー攻撃のリスクが以前より高くなります。ハッキングによる資金流出やスマートコントラクトの脆弱性を突いた攻撃など、金融業界にとって重大なインシデントを引き起こす可能性があります。
例えば認証機構が不十分なまま運用を始めてしまうと、不正アクセスによって顧客資産が流出するリスクも現実のものになるでしょう。そのためゼロトラストアーキテクチャの導入や多要素認証など、堅牢なセキュリティ基盤を確立する必要があります。
デジタル通貨に関する法制度は、現在も国内外で整備が進行中です。そのため、制度変更への迅速な対応が求められる場面も少なくありません。特に金融庁などの監督官庁によるガイドライン改定は、業務運用の根本的な見直しを迫るケースもあります。
例えば新たに発行される規制によって取引記録の保存方法や報告体制が変わった場合、それに対応するためのシステム改修や人材育成が必要となり、短期的にはコストや労力が増すこともあります。法制度が成熟するまでの間は、慎重な運用体制と柔軟な対応力が不可欠です。
デジタル通貨を証券業務に取り入れることで、新たなビジネスモデルの構築や業務効率化が進みつつあります。これにより、単なるシステムのデジタル化にとどまらず、取引のあり方そのものが変わり始めました。
ここでは証券DXとデジタル通貨を融合させるための具体的な施策を4つ取り上げ、それぞれの狙いや効果について説明します。
証券のデジタル化は、紙や従来の電子証券に代わり、ブロックチェーン上で発行されるセキュリティトークン(ST)を用いることで実現されます。STは株式や債券・不動産などをデジタル資産としてトークン化する技術で、金融商品そのものを透明かつ安全に管理できるという点で注目されました。
実際に、不動産ファンドをSTとして発行することで小口投資が可能になり、流動性が低かった資産にも参加しやすくなるのがポイントです。これによって個人投資家を含む幅広い層への資金調達が可能となり、新たな投資マーケットの形成にも寄与します。証券会社はこうした商品を取り扱うためのシステム整備と法令対応が求められますが、それに見合う市場拡大の可能性があります。
証券DXの中核を成すもう1つの施策が、決済に使用するデジタル通貨の発行とそれを支える決済インフラの整備です。これは単なる決済手段の拡張にとどまらず、証券取引に関わるすべてのプレイヤーがつながる共通基盤の整備という意味合いを持ちます。
例えば、企業が独自にステーブルコインを発行して証券の売買や分配金の支払いに利用すれば、金融機関を介さずに即時決済が可能です。また、ブロックチェーンを基盤にしたプラットフォームを活用すれば取引の追跡性や透明性が高まり、金融庁などの監督機関への報告業務も効率よくなります。
このような決済インフラの整備は、将来的に複数の金融サービスを1つの環境で連携させる「金融のエコシステム」形成の基盤にもなり得ます。
スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上であらかじめ定めた条件に基づき自動で処理が実行されるプログラムです。証券業務においては、売買の成立から決済・配当金の支払い・名義変更といった一連のプロセスを自動化する手段として有効です。
例えば、株式の売買契約が成立した時点で取引所のシステムと連携して即時にデジタル通貨での決済を実行し、権利の移転まで自動的に完了させるといった運用が可能になります。これにより人的ミスや不正のリスクが減少し、業務のスピードと正確性が向上します。
またスマートコントラクトを活用すれば、条件付きの投資商品や定期支払い型の証券など新たな商品設計も実現可能です。証券会社にとっては、サービスの多様化による差別化戦略にもつながります。
証券取引においては、資金と証券の引き渡しを同時に行う「Delivery Versus Payment(DVP)」の実現が重要です。DVPをデジタル通貨とブロックチェーン技術で構築することで、即時かつ安全な決済処理が可能になります。
例えば、取引所と証券会社が共通のブロックチェーン基盤上で取引を行えば、約定と同時に証券と資金の交換が実行されます。これによりいわゆる「決済失敗リスク」を解消でき、取引全体の信頼性が高まるでしょう。
金融庁が推進する決済インフラの近代化にも合致し、証券会社が国際基準に沿った運用を行う上でも意義があります。こうした仕組みは、将来的には他の金融商品との連携やクロスボーダー決済にも応用が期待されます。
これらの施策を通じて証券DXとデジタル通貨の融合が本格的に進めば、金融業務の在り方は変化します。ここからは、実際に期待される効果について3つの観点から解説するのでご参考ください。
従来、証券取引における決済には一定のタイムラグがありましたが、デジタル通貨を活用するとリアルタイムの取引が可能になります。これにより資金と資産の移動が迅速化し、業務の効率化はもちろん投資家にとってもストレスの少ない取引環境が整います。
例えば海外市場との連携においても、時差を意識することなく24時間体制での取引が現実味を帯びてくるでしょう。市場のボラティリティに即応できるスピード感が、企業の競争力にも直結します。
資産をセキュリティトークンとしてデジタル化することで、流通しづらかった資産にも投資機会が広がります。小口化された投資商品は、流動性の向上に加えてより多様な投資家の参入を促すことにもつながります。
例えば、地方の中小企業や不動産などこれまで証券化が難しかった資産をSTとして発行すれば、新たな資金調達手段を提供可能です。証券会社にとっても、扱う商品が多様化して新たな収益機会が生まれることになります。
デジタル通貨とブロックチェーンを活用すれば、為替や通貨の壁を越えて取引ができる環境が整います。国際送金にかかる時間とコストを削減し、グローバルな資金流動性を高めることが可能です。
例えば、国内外の投資家が同一のプラットフォーム上で証券を取引して即座に決済まで完了することで、国際的な投資環境のハードルが下がります。これにより証券会社は新たなマーケットを開拓し、海外投資家との取引拡大につなげられます。

デジタル通貨と証券業務の融合は、すでに実際のビジネス現場で動き始めています。
ここでは、証券DXを推進するためにデジタル通貨の発行や関連システム構築に着手した代表的な企業の取り組みを紹介しているのでチェックしてみましょう。これらの事例からは、業界全体がどのように変化しつつあるのかを把握でき、自社の戦略立案にも役立てられます。
野村證券株式会社は、2025年3月に新たなデジタル証券市場の構築に向けた取り組みを発表しました。ブロックチェーン技術を活用したセキュリティトークンの普及に合わせて、決済スキームの高度化を目指す実証実験を開始しています。
例えば、セキュリティトークンの発行と並行して決済通貨としてのステーブルコインを活用することで、即時かつ安全な資金決済を実現するモデルを構築中です。これにより現行のT+2決済からの脱却を図り、リアルタイムでの証券取引環境を整備する狙いがあります。
このような取り組みは、証券業界におけるDVP(Delivery Versus Payment)実現への布石ともなり、今後の金融インフラ全体に影響を与える可能性があります。
参考:野村證券株式会社
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は独自のデジタル通貨「Progmat Coin」を開発し、資金決済の仕組みを根本から見直す構想を進めています。このデジタル通貨は証券決済や資金移動に利用され、信頼性の高いトークンエコノミーを支える中核的な存在となるのです。
実際に金融機関同士の証券決済においてProgmat Coinを使用すれば、法定通貨と等価で担保された資産がブロックチェーン上に記録され、取引の透明性や処理のスピードが向上します。さらに、中央銀行によるCBDCの動向に対応しながら民間主導の安定的な運用が可能な設計も特徴です。
このようにMUFGは金融機関の枠を超えて他業界とも連携できるプラットフォーム構築を目指しており、金融DXを支える新しい土台を形作ろうとしています。
ソニー銀行株式会社は、デジタル証券(セキュリティトークン)を活用した新しい投資商品の提供を通じて個人投資家の資産形成支援に取り組んでいます。2023年よりST形式で提供されるファンド型商品の取り扱いを開始し、投資機会の拡大を図っています。
例えば不動産や再生可能エネルギー事業など、従来の金融商品ではアクセスが難しかった領域に対してもSTを通じて少額から投資できるようにした点が特徴です。また、分配金の支払いなども自動化されており、デジタル通貨との連携によって将来的には即時決済も視野に入れられています。
これによって顧客は多様なリターンを狙える商品に参加でき、ソニー銀行としても独自性のある金融サービスの提供を可能にしています。金融×テクノロジーの融合によって、新しい資産運用の形が確立されつつある好例として注目されました。
参考:ソニー銀行株式会社
証券DXの一環としてデジタル通貨の導入を検討する際は、期待される利便性や効率化だけでなく、慎重な対応も不可欠です。業務の根幹に関わるシステムや仕組みを変革する以上、法規制・セキュリティ・ユーザー対応といった複数の観点から準備を整える必要があります。
ここでは、導入時に意識すべき3つの重要なポイントを紹介します。
デジタル通貨に関する法律は国や地域、通貨の種類によって異なるため、証券業界で活用する場合には金融商品取引法や資金決済法、さらにはマネーロンダリング対策関連の法令など多岐にわたる法的な枠組みに目を配ることが欠かせません。
例えば、セキュリティトークンを扱う際には、発行体の開示義務や投資家保護の観点から金融庁への届出や報告が求められるケースがあります。また、デジタル通貨が証券決済手段として使用される場合には、既存のインフラとの整合性も問われます。
これらに適切に対応するためには、社内の法務・コンプライアンス部門だけでなく外部の専門家との連携体制を構築し、最新の法改正動向を注視する体制が大切です。
デジタル通貨を取り扱うシステムはインターネットを通じてアクセスされる性質上、高度なサイバーセキュリティが求められます。万が一システムが不正アクセスやデータ改ざんの被害を受けた場合、顧客資産の損失や信用低下につながりかねません。
例えば、ウォレットへの不正アクセスやスマートコントラクトの脆弱性を突かれた攻撃は、これまで実際の金融犯罪としても報告されています。そのため、定期的な脆弱性診断の実施や多層的な防御構造の設計が必要になります。
加えて、障害発生時に即座に復旧できるバックアップ体制や取引記録を分散管理するなど、可用性を高める工夫も不可欠です。信頼性の高いシステム基盤は、顧客の安心感を生むと同時に継続的な運用にも直結します。
新たなテクノロジーを取り入れる際に見落としがちなのが、顧客の理解と社内オペレーションの整備です。デジタル通貨はまだ一般化していない概念も多く、利用者側が正確に仕組みやリスクを理解していないとトラブルの原因となる場合があります。
例えば、デジタル通貨による決済の流れや資産の保有形態が従来の証券と異なることに対して十分な説明や教育が行われていなければ、問い合わせやクレームの増加につながります。
そのため、導入初期にはFAQの整備やサポート体制の拡充が欠かせません。加えて、社内のオペレーションやマニュアルの見直し、研修制度の強化を通じて業務全体としてスムーズな移行を図ることが重要です。

証券業界は、長らく続いた従来型の取引・決済モデルから、ブロックチェーンやスマートコントラクトといった新技術を取り入れた先進的な業務運用へと移行しつつあります。デジタル通貨の発行と活用は、その変革の中心的なテーマの1つです。リアルタイム決済の実現や資産の流動化、グローバルな証券取引への対応などメリットは大きく、今後も広がりが予測されます。
同時に、法制度やセキュリティ、ユーザー対応といった課題にも丁寧に向き合わなければなりません。これからデジタル通貨の導入を検討する企業にとっては、段階的かつ戦略的な対応が求められる場面が増えていくでしょう。
本記事を参考に、自社の業務に適したデジタル通貨の設計や運用の在り方を検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
