店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
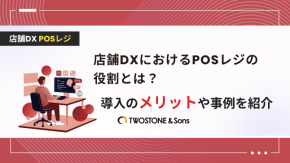
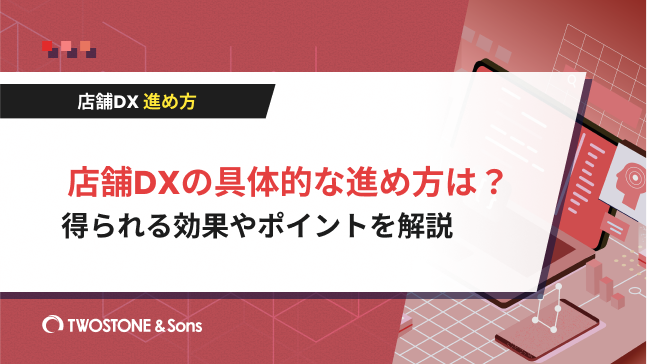
店舗DXは、単にデジタルツールを導入しただけでは進んでいかない可能性があります。デジタルツール導入だけに満足してしまい、DXそのものの効果を引き出せない恐れもあるでしょう。
店舗DXを推進するのであれば、なぜDXに取り組むのかという目的やゴールの明確化、効果検証と改善などが必要です。
本記事では、店舗DXを成功に導くための具体的な進め方をステップごとに解説します。また、DXによって得られる効果や、推進する上での重要なポイント、活用できる補助金制度についても詳しく紹介します。
具体的な進め方に沿って自社の店舗DXを効果的に推進し、データに基づいた経営判断や顧客満足度の向上、業務効率化、売上拡大へとつなげていきましょう。
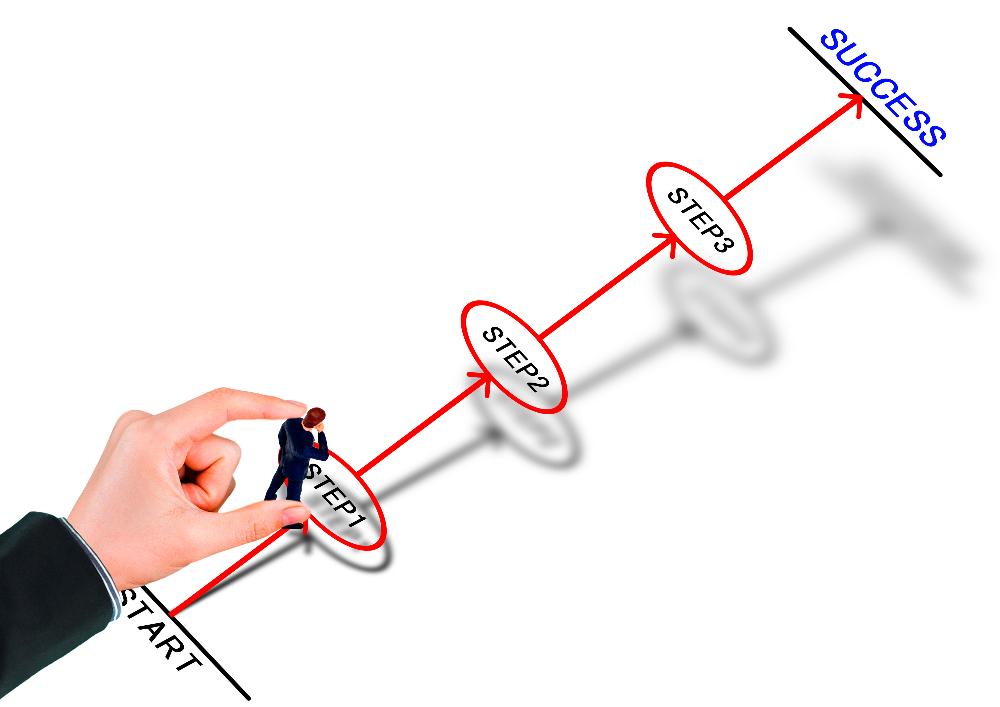
店舗DXは、単にデジタルツールを導入するだけではありません。なぜDXに取り組むのかという目的やゴールの明確化、効果検証と改善などが必要です。具体的には以下のようなステップで店舗DXを進めていきましょう。
それぞれのステップを詳しく解説します。
店舗DXを始めるにあたり、まず重要なのはその目的とゴールの明確化です。例えば、以下のように具体的な数値目標を設定しましょう。
目標設定が曖昧だと、導入するツールの選定や施策の効果検証が困難になりかねません。現状抱えている課題を深く掘り下げ、なぜDXが必要なのか、DXによって何を実現したいのかを関係者間で共通認識として持つことが大切です。
顧客満足度向上、業務効率化、売上向上など、どこに重点を置くのかによって、DXの方向性は変わります。目標達成の期日を設定することで、より具体的な行動計画を立てやすくなります。従業員全員が目標を共有し、同じ方向に向かって進む意識付けが重要です。
現在の店舗運営における業務フローを詳細に把握し、具体的な課題を洗い出します。例として挙げられるのがレジ業務での顧客待ち時間、在庫管理の煩雑さ、顧客データの散在、従業員の作業負担などです。
これらの課題は、従業員へのヒアリングや、顧客からのフィードバック、POSデータなどの分析を通じて多角的に把握します。特に、非効率な手作業や重複作業、情報の連携不足といったアナログな部分に潜む課題を見つけ出しましょう。課題を明確にすることで、本当に解決すべき問題点が浮き彫りになり、DXの導入によってどのような改善が見込めるかを具体的にイメージできます。
また、顧客視点と従業員視点の両方から課題を深掘りすれば、多角的に解決策を検討できるでしょう。
現状の課題が明確になったら、それらを解決するための具体的なソリューションとツールの検討に入ります。例えば、レジ待ち解消にはセルフレジやモバイルオーダーシステム、在庫管理の効率化にはAI(人工知能)を活用した需要予測システム、顧客体験向上にはデジタルサイネージやCRM(顧客関係管理)システムなどが考えられます。
この段階では、単に最新のツールを導入するのではなく、自社の課題と目的、予算に合致するかどうかを慎重に検討することが重要です。複数のツールを比較検討し、費用対効果や既存システムとの連携性、導入後のサポート体制なども考慮した最適な選択が求められます。
さらに、ツールの選定においては、ベンダーの導入実績や、同業他社での成功事例なども参考にするのも効果的です。
大規模なシステムを一度に導入するのではなく、まずは小規模な範囲でDXを試行するスモールスタートが効果的です。
例えば、特定の店舗や一部の業務に限定して新しいツールを導入し、その効果や課題を検証します。これにより、導入リスクを抑えつつ、現場の従業員が新しいツールやシステムに慣れる時間を確保できるでしょう。
また、スモールスタートを通じて得られたフィードバックは、本格導入時の改善点として活かせます。従業員への十分な説明とトレーニングも不可欠です。現場の理解と協力を得ることが、DX推進を成功させるための鍵となります。
初期段階での成功体験は、全社展開への弾みとなるでしょう。現場からのポジティブな意見は、他の従業員の導入への抵抗感を減らす効果も期待できます。
DXは、一度取り組んだら終わりではありません。システム導入後も継続的に効果検証を行い、改善を繰り返すことが重要です。設定した目標に対し、実際にどの程度の効果があったのかをデータに基づいて評価します。
例えば、待ち時間削減目標が達成されたか、売上や顧客単価は向上したかなどを定期的に測定します。もし目標が達成されていない場合は、原因を分析し、改善策を講じましょう。
このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることで、DXの効果を最大化し、常に変化する顧客ニーズや市場環境に適応できる店舗へと進化できます。
さらに、改善策を実行する際には、その効果を再度測定し、次のアクションへとつなげるサイクルを確立することが重要です。
店舗DXに取り組むことで得られる効果は、以下のとおりです。
ここでは店舗DXで得られるそれぞれの効果について詳しく解説します。企業によっては店舗DX推進の理解を得られない可能性があるため、期待できる効果を伝えて経営陣や従業員からの理解を得ましょう。
店舗DXは、深刻化する人手不足の解消に貢献する取り組みです。デジタルツールを導入し、これまで手作業で行っていた業務を自動化・効率化することで、従業員の負担を軽減できます。
例えば、AIを活用した自動発注システムを導入することで、在庫管理や棚卸しにかかる時間を削減でき、従業員は接客や顧客サービスの向上といった、より付加価値の高い業務に専念しやすくなるでしょう。
また、セルフオーダーシステムやキャッシュレス決済の導入は、レジ業務の混雑緩和と待ち時間の短縮につながり、最小限の人数で店舗を運営できる体制を構築します。その結果、人件費の最適化も図れるでしょう。
店舗DXは、売上向上と機会損失の削減にも影響を及ぼします。デジタルツール活用によってオンラインとオフラインを融合したOMO(Online Merges with Offline)戦略を推進すれば、顧客は店舗に足を運ぶ前からオンラインで情報を得たり、商品を予約したりできるようになります。
例えば、デジタルサイネージで商品の魅力を効果的に伝えたり、スマートフォンアプリでクーポンを配信したりすることで、来店を促し購入意欲の向上につなげられるでしょう。また、在庫状況をリアルタイムで把握し、欠品による販売機会の損失を防ぐことも可能です。
顧客の購買履歴や行動データを分析することで、パーソナライズされた提案が可能になり、顧客単価の向上にもつながります。
店舗DXによって、これまで漠然としていた店舗の状況をデータとして可視化できます。POSデータはもちろんのこと、来店客数、顧客の導線、滞在時間、購買頻度など、多岐にわたるデータを収集・分析可能です。
これにより、経験や勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて経営判断を下せるようになるでしょう。例えば、売れ筋商品の傾向や時間帯別の来店者数を分析すれば、効果的な品揃えや人員配置が可能になります。
また、プロモーションの効果測定も正確に行えるため、費用対効果の高いマーケティング戦略を立案できます。データドリブンな経営は、店舗の収益性を最大化し、持続的な成長につながるでしょう。
店舗DXに取り組むことで得られる効果のひとつが、顧客体験(CX)の向上です。デジタル技術を活用することで、顧客はよりスムーズで快適な買い物ができるようになります。例えば、モバイルオーダーやキャッシュレス決済は、顧客の待ち時間を解消し、ストレスフリーな購入体験を提供可能です。また、AIを活用したパーソナライズされたレコメンド機能や、顧客の属性に合わせた情報提供は、顧客一人ひとりに寄り添った接客を可能にします。
これにより、顧客は自分だけの特別な体験を得られ、店舗への満足度が向上し、リピーターの増加が期待できるでしょう。

店舗DXを成功に導くためには、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
店舗DXはデジタルツールを導入して、やみくもに進めても期待する効果は得られない可能性があります。ここでは、店舗DXを成功に導くために特に重要となるポイントを解説します。
店舗DXを成功させるためには、経営トップのコミットメントと、現場の従業員の協力が不可欠です。トップはDXのビジョンと目標を明確に示し、必要なリソースを確保する必要があります。
一方、現場の従業員は日々の業務に精通しており、DXによって解決すべき具体的な課題や、導入するツールの実用性について貴重な知見を持っています。トップダウンとボトムアップの両方を組み合わせ、意見交換を活発に行える推進体制を構築することが重要です。これにより、DX推進が全員で取り組むべき共通の目標として認識され、スムーズな導入と定着につながります。
店舗DXには、初期投資や運用コストがかかります。そのため、費用対効果を意識したコスト管理が不可欠です。導入を検討しているツールやシステムが、設定した目標達成にどれだけ貢献するか、具体的な数値で試算しましょう。
例えば、業務効率化によって削減できる人件費や、売上向上によって得られる利益など、定量的な効果を算出します。また、一度に全てを導入するのではなく、優先順位をつけて段階的に投資を行うスモールスタートも有効な手段です。無駄な投資を避け、より効果を引き出すための予算配分と見直しを継続的に行いましょう。
デジタル化が進む店舗DXにおいて、情報セキュリティ対策も考慮すべき事項です。顧客の個人情報や決済情報、企業の機密データなど、取り扱う情報量が増えるほど、情報漏えいやサイバー攻撃のリスクも高まります。
そのため、強固なセキュリティシステムを導入するだけでなく、従業員に対するセキュリティ教育も徹底する必要があります。パスワードの適切な管理、不審なメールやサイトへの注意喚起、定期的なシステムの脆弱性チェックなど、多角的な対策を講じましょう。
万が一の事態に備え、インシデント発生時の対応計画を策定しておくことも重要です。
DXを取り巻く技術は日々進化しています。AI、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティングなど、新たな技術が登場し、店舗運営に活用されています。これらの最新トレンドや技術動向を継続的にキャッチアップし、自社のDX戦略にどのように活かせるかを常に検討することが重要です。競合他社の動向や、異業種でのDX成功事例なども積極的に情報収集し、自社のビジネスモデルに応用できないかを考察しましょう。常に新しい情報を取り入れ、柔軟に戦略を修正していくアジャイルな姿勢が、市場の変化に対応するためのDX成功の鍵となります。
店舗DXは、あくまでビジネス目標達成のための手段であり、それ自体が目的ではありません。最新の技術を導入したい、他社が導入しているからといった理由だけで、安易にデジタルツールを導入してしまうと、「DXのためのDX」に陥りかねません。その結果、期待する効果が得られないばかりか、かえってコストや手間が増える恐れがあります。
常になぜDXを進めるのか、DXによって何を解決し、何を実現したいのかという根本的な目的を明確に持ち続けることが重要です。その目的達成に貢献しないツールや施策は、たとえ最新のものであっても導入しないという判断も時には必要になります。
店舗DXの推進には、初期投資や運用コストがかかるものの国や地方自治体では、中小企業のDXを支援するためのさまざまな補助金や助成金制度が用意されています。これらの支援制度を有効活用することで、導入コストを抑えつつ、スムーズにDXを進められるでしょう。ここでは、代表的な補助金制度とその概要について解説します。自社の状況に合った制度を見つけ、積極的に活用を検討しましょう。
国が主導する補助金制度は、店舗DX促進を後押しする制度です。中小企業の生産性向上や経営革新を目的としたものもあり、店舗DXにも幅広く適用できる可能性があります。
具体的には、以下のような補助金制度が挙げられます。
店舗DX促進にかかる費用を抑えたい場合は、それぞれの補助金制度についての理解を深めて活用を検討しましょう。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際に活用できる補助金です。業務効率化やデータ連携による生産性向上を目的とし、ソフトウェア購入費やクラウド利用料、導入関連費用などが対象となります。
例えば、POSシステム、顧客管理システム(CRM)、ECサイト構築ツールなど、店舗DXに直結する多様なITツールが対象です。デジタル化基盤導入類型では、会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなども含まれ、インボイス制度への対応も可能です。
申請には、IT導入支援事業者との連携が必要で、導入計画の策定から申請手続きまでサポートを受けられます。複数の類型があり、それぞれ異なる補助率と上限額が設定されています。
出典参照:IT導入補助金2025|サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業・小規模事業者が、革新的なサービス開発や試作品開発、生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する制度です。
店舗DXにおいては、例えば、顧客体験を向上させるための新たなデジタルサービスの開発や、効率的な店舗運営を実現するシステムの導入などが対象となりえます。具体的には、AIを活用した需要予測システムの導入や、ロボットによる自動接客システムの開発なども考えられます。
幅広い業種の中小企業が対象で、事業計画に基づき、機械装置費、システム構築費、技術導入費などが補助対象です。新製品開発や新サービス導入などに活用を検討してみましょう。
出典参照:ものづくり補助金総合サイト|全国中小企業団体中央会
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継やM&Aを契機として、新たな取り組みを行う中小企業等を支援する制度です。店舗DXにおいては、事業承継を機に既存店舗のデジタル化を一気に進めたい場合や、M&Aによって得た経営資源を活用してDXを加速させたい場合に活用できる可能性があります。
特に経営革新型では、新しい設備の導入やITシステムの構築といった、生産性向上に資する取り組みが支援対象となります。事業承継後の経営革新や、後継者による新規事業展開など、未来を見据えたDX投資の活用が検討できるでしょう。世代交代や組織再編を機に、DXを加速させる好機となり得ます。
なお、DX促進にあたり専門家に相談した場合の費用も対象となるケースもあります。
出典参照:事業承継・引継ぎ補助金|事業承継・M&A補助金事務局
国が提供する補助金以外にも、各地方自治体が独自に設けている支援制度も活用可能です。これらの制度は、地域の特性や産業構造に合わせて、中小企業のDXを促進するための補助金や融資、相談窓口などが設けられている場合が一般的です。
例えば、東京都はサイバーセキュリティ対策促進助成金として、サイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入にかかる費用の一部を助成しています。また、神奈川県横浜市では、中小企業が生産性向上のために取り組むDX、デジタル化にかかわる費用の一部を補助する中小企業デジタル化推進支援補助金を実施しています。
まずは、DX促進を図る店舗が位置する自治体で、どのような支援制度があるのかを確認してみましょう。
出典参照:サイバーセキュリティ対策促進助成金|公益財団法人 東京都中小企業振興公社
出典参照:令和7年度中小企業デジタル化推進支援補助金|横浜市
店舗DXは、企業の規模や業種に関わらず、様々な形で導入が進められています。ここでは、以下のように実際に店舗DXに取り組み、具体的な成果を上げている企業の事例を紹介します。
これらの事例は、自社のDX推進を検討する上での具体的なイメージやヒントにつながるでしょう。自社の業種や規模に近い事例があれば、参考にしてください。
イオン株式会社は、レジに並ぶ手間を解消し、顧客の買物の自由度を向上させる「どこでもレジ レジゴー」というサービスを展開しています。これは、利用客が専用の貸し出しスマートフォンや自身のスマートフォンにインストールしたアプリを使い、商品のバーコードをスキャンしながら買い物をするシステムです。買い物が終わったら、専用のレジでバーコードをかざし、支払い方法を選択すれば会計が完了します。従来のレジに並ぶ時間を短縮できるため、顧客のストレス軽減につながっています。
また、店舗側もレジ業務の効率化が図れ、従業員を他の業務に配置できる点もメリットです。これにより、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現しました。非接触での会計は、衛生面への配慮から顧客の安心感も高め、新しい買い物体験を提供できるという側面もあります。
出典参照:イオンリテールは3月より、“レジに並ばない”お買物スタイル「レジゴー」本格展開|イオン株式会社
株式会社ドトールコーヒーでは、全国の店舗で働くアルバイトスタッフのシフト調整に課題を抱えていました。シフト調整は時間がかかってしまうのが一般的です。そこで、株式会社ドトールコーヒーが導入したのが、専用のシフト管理システムです。
このシステムにより、各店舗のアルバイトスタッフはスマートフォンから自身の希望シフトを簡単に入力できるようになりました。また、店長はシステム上でスタッフの希望を一覧で確認し、最適なシフトを自動で作成できます。
これにより、シフト作成にかかる時間や手間が削減され、店長の業務負担が軽減されました。さらに、スタッフ間のコミュニケーションも円滑になり、シフト調整のトラブルも減少しました。従業員の働きやすさを向上させ、店舗運営の効率化に成功した事例です。専用のシステム導入は従業員の定着率向上も期待できるでしょう。
出典参照:「店舗と店舗の間に”道”ができた。」ドトールコーヒーが描く未来型店舗運営への挑戦。|シェアフル株式会社
株式会社三越伊勢丹ホールディングスは、新しい顧客体験の提供を目指し、メタバースアプリ「REV WORLDS(レヴ ワールズ)」での営業を開始しました。このアプリでは、利用者はアバターとなって仮想空間に再現された伊勢丹新宿店やその周辺の街を自由に散策できます。ブランドのショッピングを楽しんだり、イベントに参加したり、アバター同士でコミュニケーションを取ったりできます。
実際の店舗に行くことが難しい遠方の顧客や、新たな体験を求める顧客に対して、時間や場所にとらわれないショッピング機会を提供可能です。リアル店舗では難しい多角的な商品情報提供や、オンラインならではの体験を提供することで、顧客接点の拡大とブランド価値向上に挑戦している事例といえるでしょう。
これまでにないショッピング体験の提供によって、新たな顧客層の開拓とブランディング強化にもつながっています。
出典参照:スマートフォン向け仮想都市空間サービス「REV WORLDS」仮想伊勢丹新宿店|株式会社三越伊勢丹ホールディングス

店舗DXは、単なるデジタルツールの導入にとどまらず、顧客体験の向上や業務効率化、データに基づいた経営判断を実現し、店舗の価値を最大化する戦略的な取り組みです。
本記事で解説した具体的な進め方、得られる効果、そして成功へのポイントを押さえることが重要です。目的とゴールを明確にし、現状の課題を洗い出した上で、最適なツールを選定し、スモールスタートで着実に推進しましょう。
国や地方自治体の補助金制度を活用しつつ、効果検証と改善を繰り返すPDCAサイクルを回し続けることで、店舗の持続的な成長が期待できます。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
