店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
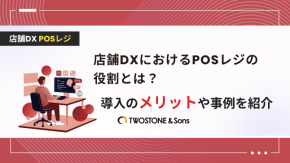
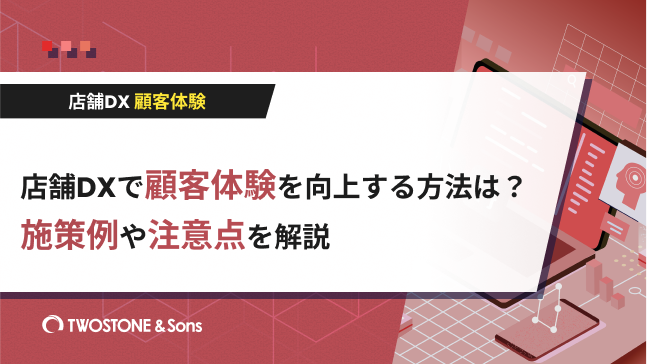
店舗DXが進む現代では、単に商品やサービスを提供するだけではなく、顧客が店舗で過ごす体験自体の質の差別化要素になりつつあります。デジタル技術の活用により、オンラインとオフラインの垣根を超えた顧客体験を設計することが求められているためです。消費者のニーズは多様化し、便利さや迅速さだけでなく、心地よさや驚き、満足感を得られる体験に高い価値が置かれるようになっています。
このような背景から、店舗DXの推進は、効率化だけでなく、顧客一人ひとりに合わせたサービス提供や購買体験の質的な向上が中心課題となってきました。
本記事では顧客体験向上に直結する具体的な施策や、その際に気を付けるべきポイントを分かりやすく解説します。店舗運営の現場で役立つヒントを多く含んでいるため、これからの店舗DX推進にぜひ参考にしてもらいたい内容です。

顧客体験(Customer Experience)は、顧客が商品やサービスに出会ってから購入、利用、そしてアフターサポートに至るまでのすべての接点において感じる印象や満足度です。近年では、単に商品を提供するだけではなく、顧客がその過程でどのような体験をするかが企業の評価や選ばれる理由に直結すると考えられるようになっています。
このような背景から、企業は顧客体験の質を高める取り組みを進めています。代表的な指標としては、顧客が他者にサービスを薦めたいと思う度合いを示すNPSや、サービスに対する満足度を測るCSAT、対応時にどれだけの労力を要したかを評価するCESなどがその一例です。こうした数値を活用することで、顧客心理を把握し、改善施策へとつなげていくことが求められています。
現代の店舗には、単なる物品の販売を超えた多面的な顧客体験の提供が求められています。デジタル技術の発展により、消費者は店舗を訪れるだけでなく、オンラインも含めたあらゆる接点で一貫したサービスを期待するようになりました。そのため、これまで以上にシームレスでパーソナライズされた接客やサービス、店舗空間での感覚的な満足を両立させる必要が出てきています。
ここでは、今顧客が店舗に求めている顧客体験について解説します。
オムニチャネルとは、オンラインや店舗、モバイルアプリなど多様なチャネルを連携させ、一貫した顧客体験を提供する考え方です。これにより、顧客はどのチャネルを通じても同じブランド体験を享受でき、購買のハードルの低下が期待されます。
例えば、顧客がオンラインで商品を確認し、そのまま店舗で受け取る「クリック&コレクト」サービスが広まりつつあります。このような施策はチャネル間の連携を強化し、顧客の利便性を高めるだけでなく、顧客満足度の向上にも寄与するでしょう。店舗DXを推進する際には、チャネルごとに分断されがちな情報やサービスを統合する設計が大切です。
デジタル技術の活用により、顧客の購買履歴や嗜好に基づいて個別対応がしやすくなっています。パーソナライズされた接客やサービスは、顧客一人ひとりに寄り添う印象を与え、再訪率やロイヤリティの向上につながるでしょう。
例えば、店舗内でのスマートフォンアプリを活用し、過去の購入履歴を基におすすめ商品を提案したり、特別な割引クーポンを配信したりする方法が挙げられます。こうした施策は、単に効率化するだけでなく、顧客が自身のニーズに合ったサービスを受けていると感じる環境を作り出します。効果的なパーソナライズには、データの正確な管理と顧客プライバシーへの配慮も欠かせません。
実店舗が持つ強みは、顧客が五感を通じて商品やサービスを体感できる点にあります。デジタル技術が発展した今でも、実際に商品を手に取ったり、店内の雰囲気を味わったりすることで得られる体験価値は依然として重要視されています。したがって、店舗DXではこのリアル空間の価値をいかに高めるかがカギです。
例えば、デジタルサイネージやAR(拡張現実)技術を活用することで、商品情報を視覚的に分かりやすく伝えたり、試着や試用の体験を拡充したりできるでしょう。また、空間のデザインを工夫して居心地の良さを追求することで、顧客の滞在時間を延ばし購買意欲を高める効果も期待されます。これらの取り組みは店舗の個性やブランドイメージの向上にもつながり、競争力の強化に寄与します。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、顧客の購買体験において非接触やスマート化のニーズが増しています。店舗DXの推進においては、キャッシュレス決済の導入やセルフレジの整備、モバイルオーダーの拡充など、接触機会を減らしつつ利便性を保つ施策が欠かせません。
これらの技術は顧客の安全安心を支えるだけでなく、待ち時間の短縮やオペレーション効率の向上にもつながるため、店舗運営側にもメリットがあります。ただし、利便性を追求するあまり使い勝手が複雑になると逆効果になることもあるため、導入時には顧客視点での操作性やサポート体制も考慮すべきでしょう。
顧客からのフィードバックをリアルタイムで収集・分析し、迅速に改善に活かす体制は顧客体験向上に不可欠です。デジタルツールを活用すれば、アンケートやレビュー、SNSでの意見を即座に確認でき、問題点の早期発見や新たなニーズの把握がしやすくなるでしょう。
例えば、タブレット端末を用いた店頭アンケートや、チャットボットによる対話型フィードバック収集が考えられます。これらの情報は店舗スタッフの対応品質の向上や、商品ラインアップの見直しにも活用できます。加えて、顧客の声を反映した改善施策を積極的に周知することが、顧客満足度をさらに高める効果につながるでしょう。
店舗DXの推進にあたり、顧客体験を向上させる施策は多様に存在します。単なるデジタル化に留まらず、顧客の行動や嗜好を踏まえた柔軟な対応が不可欠です。これらの施策は単独での効果も期待されますが、複合的に組み合わせることで、より深い顧客満足を実現し、ブランドの価値を高めることにつながります。
ここでは、店舗DXによって実現可能な具体的な5つの施策について詳しく説明します。
パーソナライズされたサービスは、顧客ごとの嗜好や過去の購買データを活用し、個別に最適化された対応を提供することを指します。店舗DXの技術を用いて、顧客の属性や行動パターンをデータベースに蓄積し、それを基に一人ひとりに合わせた情報や提案ができる環境を整えます。例えば、過去に購入した商品や閲覧履歴に応じておすすめの商品を案内したり、誕生日や記念日などに特別なサービスを提供したりする方法です。
このような施策は、顧客に対して「自分だけを大切にされている」と感じさせることができ、顧客のロイヤリティ向上やリピート率アップに貢献します。ただし、個人情報の取り扱いやプライバシー保護にも十分な配慮が必要で、データ管理の厳格化や適切な同意取得の体制づくりも必要です。また、スタッフ間で情報を共有しやすくする仕組みも、サービス品質の維持には欠かせません。
顧客の利便性を高める手段として、モバイルオーダーや事前予約システムの導入が注目されています。これらのシステムを利用すると、顧客は店舗に到着する前にスマートフォンから注文や予約を済ませられるため、店頭での待ち時間を削減できます。結果として、顧客のストレスが減り、店舗の混雑緩和にもつながるのが特徴です。
さらに、店舗側は注文情報を事前に把握しやすくなり、効率的な商品準備やスタッフ配置を実現しやすくなります。特に飲食業や美容サービス業などでは、来店予測や予約管理により運営の最適化が可能になるため、経営面でもプラスの効果が期待されます。ただし、システムの操作性やトラブル発生時の迅速な対応策も検討しておきたい点です。導入にあたっては、顧客の利用しやすさと運営側の利便性を両立させることが求められます。
AIチャットボットや音声アシスタントの活用は、顧客対応の自動化と効率化に貢献します。これらのツールは、顧客からの問い合わせに24時間応答可能なため、営業時間外や繁忙時でもスムーズな対応が可能になる点が強みです。注文受付や商品案内、FAQの解決など、多様な業務をAIがサポートすることで、スタッフの負担軽減とサービスの均質化が進みます。
加えて、AIによる対話ログの分析から顧客のニーズや問題点を抽出し、サービス改善や新たな施策開発に役立てられます。一方で、AIの応答が不十分な場合には顧客の不満につながりやすいため、人間スタッフへのスムーズな引き継ぎや補完体制を用意しましょう。これにより、顧客にとってもスタッフにとっても利便性の高い運用につながります。
店舗内の顧客体験を向上させる手段として、デジタルサイネージや拡張現実(AR)の導入が効果的です。デジタルサイネージは動画や静止画を使い、リアルタイムで商品の魅力やキャンペーン情報を発信できるため、顧客の関心を引きつけやすくなります。動的なコンテンツによって店内の雰囲気も演出され、より魅力的な空間を作り出せるでしょう。
一方、ARはスマートフォンやタブレットを通じて、商品を仮想的に試せる体験を提供します。例えば、服やアクセサリーの試着シミュレーション、家具の設置イメージなどを顧客が自宅や店内で体験できるため、購買の後押しに役立ちます。こうした技術は、単に商品の説明をするだけでなく、顧客の五感に訴えかける新たな価値を創出し、購買行動を促すツールとして注目です。導入時は設備投資やコンテンツの定期的な更新も念頭に置くとよいでしょう。
顧客の行動データを収集し、分析することで売場の改善につなげることも店舗DXの大切な施策です。来店頻度や購買履歴、店内での動線などの情報を解析し、どのエリアに顧客が集まりやすいか、逆に離脱が多いポイントはどこかを把握します。こうしたデータを基に陳列場所の変更やプロモーションの強化、スタッフの配置見直しを行うことで、顧客満足度の向上や売上アップが期待できるでしょう。
また、売場改善は在庫管理や商品補充の効率化にも役立ち、無駄なコスト削減や品切れ防止につながります。効果的に活用するためには、適切な分析ツールの選定や、現場スタッフとデータ担当者の連携体制の構築が必要です。さらに、分析結果を定期的にレビューし、迅速に対応策を実行することで、店舗運営の質を継続的に高めていくことが求められます。

店舗DXを推進している企業は、顧客体験の向上に向けて多様な独自施策を積極的に展開しています。単に最新の技術を導入するだけでなく、顧客のニーズや利用環境に即した使いやすさや付加価値の提供に重点を置く傾向が強くなっています。こうした取り組みは、顧客満足度を高めるだけでなく、ブランドの信頼性向上やリピーター獲得にもつながるでしょう。
ここでは、特に注目される国内の代表的な企業事例を取り上げ、それぞれが実施している施策の特徴や工夫点について詳しく解説していきます。
株式会社資生堂は、店舗DXの一環として、顧客が店頭で直接商品に触れることなく、化粧品のテクスチャーや使い心地を体験できる非接触技術の開発に取り組んでいます。この技術は主にセンサーやAIを活用しており、肌の状態や環境に合わせた最適な製品提案をサポートします。
コロナ禍を経て非接触での接客ニーズが高まる中、資生堂は衛生面に配慮しつつも、顧客に安心感と満足感を提供できる体験を目指しました。具体的には、専用デバイスを用いて肌の水分量や弾力を計測し、その情報を基に推奨化粧品を提示する仕組みを採用しています。これにより、顧客は店頭での滞在時間を短縮しつつ、的確な商品選択を行えるようになっています。
出典参照:資生堂とNTT、化粧品の触り心地を遠隔・非接触で体験できる技術開発に向けた共同研究を開始|株式会社資生堂
イケアジャパンは、店舗DXの推進に伴い、「インテリアスタイルラボ」という顧客参加型のプラットフォームを展開しています。このサービスは、日本の住宅事情やライフスタイルに合ったインテリア提案をデジタル技術でサポートし、顧客が自宅にいながら理想の空間づくりを体験できるよう設計されています。
具体的には、AIやAR技術を活用し、顧客の間取りデータや好みのデザインを取り込むことで、リアルタイムにコーディネート例を提示しました。これにより、来店前に家具の配置イメージを具体化でき、購入検討の効率化と満足度向上につなげています。
こうした双方向コミュニケーションは、ブランドへの愛着や顧客ロイヤリティの向上を後押しし、店舗と顧客の関係性を深化させています。
出典参照:イケア、体験型ショッピングツール「インテリアスタイルラボ」を日本初導入|イケアジャパン株式会社
株式会社良品計画は、店舗DXを通じて顧客とのつながりの強化を目指し、専用アプリを提供しています。このアプリは単なる購買履歴の管理にとどまらず、ユーザーの好みや購買行動を分析し、パーソナライズされたおすすめ商品やクーポンを提示する機能を備えています。
さらに、アプリ内で商品レビューや店舗情報の共有ができるため、顧客間のコミュニケーションを活性化できる点も同アプリの強みです。これにより、顧客の声を店舗運営に反映しやすくなり、より顧客志向のサービス向上が促される構造となっています。
良品計画のDX戦略は、顧客の利便性とエンゲージメントの両面を重視しており、リアル店舗とデジタルの連携を強化しながら顧客体験の質を高めています。アプリの利用率が上がることで、顧客のライフスタイルに寄り添った提案が継続的に実施できるようになっている点も特徴です。
出典参照:無印良品が Recommendations AI で実現する「感じ良い」個客体験|株式会社良品計画
店舗DXを推進して顧客体験を向上させる際には、単に技術を導入するだけではなく、さまざまな側面をバランスよく考慮する必要があります。
ここでは具体的に、操作性やUXの重要性、デジタル偏重のリスク、個人情報やプライバシーへの配慮、そしてチャネル間の体験の一貫性を保つ設計について詳しく解説していきます。これらのポイントを踏まえて検討を進めることで、より良い顧客体験の実現に近づくでしょう。
店舗DXの施策を成功させるには、利用者が操作しやすく直感的に理解できるユーザーインターフェースを整えることが大切です。どんなに高性能な技術でも、操作が複雑であれば利用者の離脱を招きやすく、結果として顧客体験の質を下げるリスクがあります。
具体的には、画面遷移のスムーズさや視覚的なわかりやすさ、操作手順の簡潔さを意識した設計が必要でしょう。また、さまざまな年齢層やデジタルリテラシーに差がある顧客層にも配慮し、誰でも使いやすい設計を心がけることが大切です。利用者のフィードバックを積極的に取り入れてUXを継続的に改善していくことが、顧客体験向上のカギになると考えられます。
店舗DXではデジタル技術を活用するメリットが多いものの、過度にデジタルに偏ると逆効果になることがあります。とくに、対面のコミュニケーションや人間味のあるサービスを求める顧客も多いため、デジタルとアナログのバランスを考慮することが大切です。技術を活用しつつも、従業員の接客スキルや店舗の雰囲気づくりを疎かにしないことが顧客満足度を高める要素となります。
例えば、AIチャットでの対応と有人対応を使い分けるなど、顧客のニーズに合わせた適切な接点設計を検討しましょう。デジタル化の推進は手段の一つとして捉え、顧客との心地よい関係づくりを優先した視点が求められます。
顧客データの活用が店舗DXの中心的な役割となる一方で、個人情報やプライバシー保護への配慮は不可欠です。顧客の信頼を損ねるような情報管理の不備は、ブランドイメージの低下や法的な問題を引き起こすリスクにつながります。具体的には、データの取得時に適切な同意を得ることや、収集した情報を安全に保管・管理するためのセキュリティ対策を講じることが求められます。
また、個人情報を扱う従業員に対して定期的な教育を実施し、リスクの理解と遵守意識を高めることも必要です。プライバシーを尊重しながら、顧客が安心してサービスを利用できる環境づくりを進めることが店舗DX成功の土台になるでしょう。
店舗DXでは複数の接点やチャネルが存在するため、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験が得られるような設計を求められています。チャネルごとに異なる情報やサービス提供がなされると、顧客は混乱したり不満を感じたりしやすくなります。
したがって、オンラインとオフライン、モバイルアプリや店頭端末など、あらゆるチャネルでデータ連携やサービス連携を図ることが欠かせません。統合的な顧客管理システムの活用やクロスチャネルでのコミュニケーション設計により、シームレスな顧客体験の提供を目指しましょう。チャネルの垣根を越えたつながりが顧客満足度の向上につながると考えられます。

店舗DXの推進にあたっては、顧客体験の向上を中心に据えることが重要になります。最新技術の導入だけに偏らず、操作性やUX、プライバシー保護といった基本的な要素に目を配りながら、多様なチャネルでの一貫した体験設計を進めるべきでしょう。顧客の期待やニーズに応える施策を段階的に展開し、フィードバックを活用して継続的に改善していく姿勢が求められます。
こうした観点を踏まえた店舗DXは、顧客満足度を高めると同時に、競争力の維持にもつながりやすいと考えられます。記事を参考に具体的な取り組みを検討し、より良い顧客体験を追求していきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
