店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
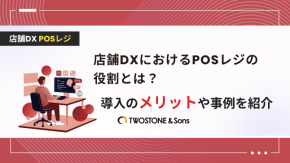
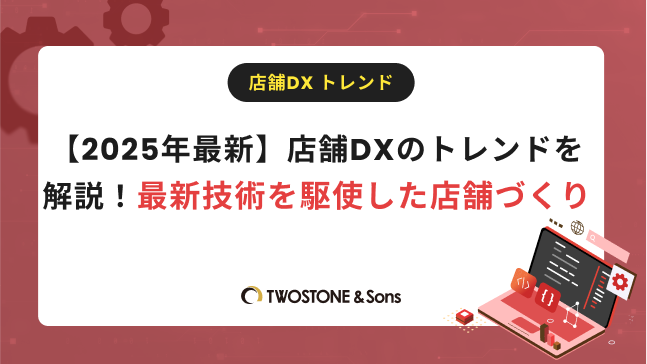
近年、店舗運営におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が加速しています。特に2025年に向けては、技術革新と消費者行動の変化が重なり、店舗の在り方そのものが問われる時代となっています。これまでデジタル化に慎重だった分野でも、業務の効率化や接客の質向上、顧客体験の強化を目的とした取り組みが次々と始まってきました。こうした流れは、小売業や飲食業といった業界にとどまらず、幅広い分野の実店舗に影響を与えています。
単なる技術導入にとどまらず、企業文化やビジネスモデル全体を再構築する視点が求められる今、どのような技術が店舗運営に変化をもたらし、どこに注目すべきなのかを把握することが必要です。本記事では、2025年に注目される店舗DXの最新トレンドと、それぞれが実店舗に与える影響を詳しく解説していきます。

2025年における店舗DXの推進では、単にデジタルツールを取り入れるだけでなく、顧客体験全体を設計し直すような包括的な変革が求められています。店舗が担う役割も「商品を売る場所」から「ブランド体験を提供する空間」へと変化しつつあります。こうした潮流の中で注目されるのが、無人化技術や生成AI、モバイルオーダーの進化など、消費者ニーズとテクノロジーが交差する領域です。
ここでは、2025年に特に注目される店舗DXのトレンド7つを具体的に紹介し、それぞれがどのように店舗運営を変えていくかを解説します。
無人店舗やスマートストアの拡大は、2025年の店舗DXにおいて重要なトレンドの1つです。特に人手不足が深刻化する中で、省人化・省力化を目的とした無人化技術の導入が進んでいます。AIカメラやセンサーを活用した来店者の行動解析、自動決済システムによるスムーズな会計体験など、従来の有人店舗では実現できなかった効率と快適さが両立できるようになりました。
例えば、大手コンビニチェーンでは深夜帯の無人営業を導入することで、労務コストの削減と売上維持の両立を実現できるでしょう。さらに、顧客データの蓄積によるパーソナライズドマーケティングへの応用も期待されています。これにより、単なる「無人化」ではなく、「より高品質な顧客体験」を提供するという次なるフェーズへと進化しています。
ChatGPTをはじめとした生成AIの進化により、接客・業務のDXが新たな段階へと進んでいます。2025年には、顧客対応チャットボットや音声アシスタントの導入がより一般的になり、24時間対応の問い合わせ処理や商品案内などがスムーズに行えるようになります。
また、AIは接客業務だけでなく、シフト作成、在庫管理、SNS投稿の自動化といったバックオフィス業務でも活躍できるでしょう。例えば、OpenAIやGoogleが提供するAPIを活用することで、顧客ごとにカスタマイズした接客フローを自動生成できます。
さらに、過去の会話ログや購買履歴と連携させることで、より高精度なレコメンドが実現し、販売機会の最大化にもつながります。今後は、人間の判断を補完するパートナーとして、生成AIが接客の質と業務効率の両方を支える存在になっていくでしょう。
コロナ禍以降、急速に普及したモバイルオーダーとモバイル決済は、今や業界標準の機能となりつつあります。2025年には、さらに多様な機能を統合し、より利便性を高めたアプリケーションの導入が進むでしょう。例えば、予約・注文・決済・ポイント管理を一元化できるプラットフォームが登場し、顧客の待ち時間削減や業務効率化に貢献し始めています。
飲食店では、席についたままスマートフォンで注文し、支払いも完了できるサービスが浸透しています。これにより、スタッフの負担軽減と回転率の向上が実現できるでしょう。また、小売業においてもレジを通さずにアプリ決済で商品を購入できる仕組みが増えており、今後はこれが当たり前の購買体験として定着するでしょう。
2025年の店舗づくりでは、デジタルサイネージの高度化と体験設計の融合が注目されています。デジタルサイネージとは、ディスプレイを活用して情報や広告をリアルタイムで表示する仕組みのことです。これにより、来店客に対して即時性のある案内や販促が行いやすくなり、紙媒体では実現できなかった柔軟な情報提供が可能になります。
さらに、タッチパネル式のインタラクティブサイネージを取り入れることで、ユーザー自身が情報を選び取る体験が生まれるでしょう。このような双方向型のコミュニケーション設計は、ブランドとのエンゲージメントを高める効果が期待されており、購買意欲にもポジティブな影響を与えるとされています。空間デザインや導線設計と連動させたデジタル演出は、店舗全体の顧客体験を底上げする要素として、今後さらに重視されていくでしょう。
リアルとオンラインの垣根が低くなる中、顧客一人ひとりの行動履歴や購買傾向を統合的に把握する仕組みが重要視されています。これにより、パーソナライズされた接客や提案がしやすくなり、顧客満足度やリピート率の向上につながるでしょう。
例えば、会員アプリやポイントカードと連動させて購買履歴を収集し、好みに応じた商品レコメンドを行う仕組みがあります。さらに、属性データと来店履歴を組み合わせることで、最適なタイミングでキャンペーンを案内することも可能になります。
こうしたデータ活用を支えるのが、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)やCRM(顧客関係管理)といったツール群です。店舗DXを推進する上で、単なる情報の蓄積ではなく、活用しやすい形に整えることが求められており、そのためのシステム連携や運用設計がカギとなっています。
店舗運営において人的リソースの効率化は避けて通れないテーマです。特に人手不足が常態化している現在、スタッフ一人ひとりの負担を軽減し、接客品質を保つためのDX推進が求められています。
その具体例として、業務支援ツールや業務自動化アプリの導入が進められています。例えば、在庫確認や発注作業をスマートフォンから行えるアプリケーションや、レジ業務を簡略化するセルフレジ・セミセルフレジの導入などがその一例です。これらは単なる省人化ではなく、スタッフが接客に集中できる環境を整えるという点で注目されています。
また、業務マニュアルや商品情報を共有するクラウド型の教育ツールも有効です。業務の属人化を防ぎ、店舗ごとのバラつきを抑える効果が期待されます。今後は、こうした仕組みの柔軟な活用が、店舗の安定運営における基盤となっていくでしょう。
店舗運営におけるサステナビリティとデジタル技術の融合も、2025年の注目すべきトレンドの1つです。環境に配慮した取り組みが社会的要請として高まる中、デジタルを活用した効率的かつ持続可能な運営モデルが必要です。
例えば、エネルギー消費の最適化に向けてIoTセンサーを活用し、空調や照明を自動制御する仕組みがあります。また、デジタルレシートの導入により紙の使用を減らす動きも進んでいます。これらは環境負荷を抑えるだけでなく、業務効率化にもつながるでしょう。
さらに、サステナビリティに関する情報を店舗内のデジタルサイネージで可視化することで、顧客との信頼関係の構築にもつながります。サステナブルな価値観を共有する体験を提供することが、これからのブランド戦略において大きな意味を持つといえるでしょう。

近年、消費者の購買行動や価値観は急速に変化しており、これに柔軟に対応するためには、単なるシステムの導入ではなく、戦略的な店舗DXの「推進」が求められています。特にリアル店舗においては、デジタル技術を用いて業務効率を高めるだけでなく、顧客体験(CX)を軸とした設計が不可欠です。オムニチャネル戦略やデータ利活用、AI・IoTの実用化、スタッフの業務支援などを含めた全体最適が必要となります。
ここでは、その具体的な推進ポイントを整理します。
顧客体験(Customer Experience:CX)を中心に店舗運営を設計することは、DX推進において必要です。顧客が来店から購入、退店に至るまでのあらゆる接点において、ストレスのないスムーズな体験を提供する必要があります。
例えば、入店時の案内をデジタルサイネージで提供したり、決済を非接触化したり、スタッフと顧客のコミュニケーションをデジタルで補完したりするなど、各工程で満足度を高める工夫が求められます。
そのためには、顧客行動を可視化し、ペルソナ設計やカスタマージャーニーマップを活用して体験全体を再設計することが必要です。技術はあくまで手段であり、CXという目的を支える存在であることを念頭に置きましょう。
現代の消費者は、オンラインとオフラインを自在に行き来しながら購買行動を取っています。そのため、店舗運営も「オムニチャネル」を前提に再構築することが必要です。例えば、ECサイトで商品を検索・比較し、実店舗で試着後にアプリケーションから注文するという行動は、今や日常的です。
こうした流れに対応するためには、在庫情報や購入履歴をリアルタイムで一元管理できるシステムの整備、チャネル横断のポイント統合、接客の連携などが求められます。
また、顧客がどのチャネルに接触しても同じ体験価値を得られるように、チャネル間のUI/UXを統一する工夫も欠かせません。オムニチャネル設計は、単なる複数チャネルの併存ではなく、シームレスな統合を指します。
店舗DXにおいて、データ活用は根幹を成す要素の1つです。購買履歴、来店頻度、滞在時間、レビュー内容などの多種多様なデータを収集・蓄積し、それを意思決定やパーソナライズ施策に活かす体制を整えることが求められます。
具体的には、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)やCRMシステムを導入し、リアルタイムでのデータ統合と分析を可能にする基盤が必要です。また、POSデータやアプリケーションから得られる行動データを組み合わせることで、顧客ごとに最適な商品提案や販促施策を展開できます。
ただし、プライバシー保護の観点からも、収集・管理に関するコンプライアンス遵守を徹底する姿勢も欠かせません。
AIやIoTの活用は、店舗DXにおける「手段」であり、決して「目的」となるものではありません。AI接客チャットボットやIoTセンサーを導入すること自体がDXではなく、それらを活用して、顧客接点の強化や業務効率化を実現するプロセスこそが本質です。
例えば、棚の在庫状況をリアルタイムで可視化するIoTセンサーは、品切れ防止に役立ちますが、目的は機会損失の最小化です。AIも、過去の購買傾向に基づくレコメンドや需要予測に使うことで、販売機会の最大化に貢献するでしょう。
導入ありきではなく、何の課題を解決するために導入するのか、常に現場のニーズと照らし合わせながら、最適な技術選定と運用が求められます。
DXを推進する際に見落とされがちなのが、店舗スタッフの視点です。スタッフは顧客との直接的な接点であり、その業務環境の改善や業務フローの最適化なくして、CXの向上は実現しにくくなります。
具体的には、タブレット端末での商品説明支援や、スマートウォッチによるタスク管理、業務マニュアルの動画化といった施策が有効です。これによりスタッフの負担を軽減しつつ、サービスの質を一定に保つことができます。
また、スタッフの意見を反映したUI設計や、定期的な運用レビューを通じて、現場に根付いたDXを実現しましょう。DXはシステムの刷新だけではなく、スタッフの働き方を変えることも含めた「現場起点の改善」が必要です。
店舗DXを積極的に推進している企業は、顧客利便性や業務効率の向上に向けてさまざまな独自施策を展開しています。最新技術を活用し、顧客の購買体験をスムーズにするためのシステム開発や、無人化・キャッシュレス決済の導入など、実際の現場に根ざした工夫が見られます。
ここでは、国内の代表的な3社の取り組みを紹介し、各社がどのようにしてDXの潮流に乗り、店舗運営の革新を実現しつつあるのかをみていきましょう。
株式会社ノジマは、店舗DXの一環として、顧客の買い物をスマートにサポートするアプリケーションを提供しています。このアプリケーションは商品検索や店舗在庫の確認、決済までを一元的に行える仕様となっており、顧客は店内での待ち時間を削減しながらスムーズに買い物ができる仕組みです。
さらに、ポイント管理やクーポン配信機能も備え、パーソナライズされたサービスを提供しています。こうした取り組みは、リアル店舗の利便性を向上させるだけでなく、オンラインとの連携によるオムニチャネル戦略の強化にもつながっています。顧客の利便性と店舗運営の効率化を両立させる工夫として注目されている事例です。
出典参照:1. QRコードを利用した注文~スムーズなお買い物をサポート|株式会社ノジマ
株式会社東急ストアは、無人決済店舗「platto」の運営を開始し、店舗DXの最前線を走っています。plattoは、入店から商品の選択、決済までを顧客自身のスマートフォンで完結できる仕組みを導入し、レジ待ちのストレスを解消します。AIや画像認識技術を活用して、商品スキャンやカゴの中身を自動で把握するシステムを採用している点が特徴です。
これにより、店舗スタッフの負担軽減にもつながり、業務効率の向上も期待されています。無人店舗の拡大は、今後の店舗運営における重要な潮流であり、消費者の利便性と店舗の運営効率の両面で価値を提供する試みといえるでしょう。
出典参照:無人決済店舗の名称が「platto」に決定!|株式会社東急ストア
株式会社ローソンは、ウォークスルー決済店舗「Lawson Go」の展開により、店舗DXの新たな形を提示しています。顧客は入店後、スマートフォンを使って専用アプリにより商品をスキャンし、そのまま店外に出るだけで決済が完了します。店舗内でのレジ待ちがなく、スムーズな買い物体験が実現されました。
また、顔認証やAI技術も取り入れ、セキュリティ面にも配慮しています。この無人レジの導入は、労働力不足の課題解決にも寄与しつつ、顧客満足度の向上を目指す取り組みとして注目されています。今後も店舗DXの代表例として注視される動向といえるでしょう。
出典参照:ウォークスルー決済導入店舗 「Lawson Go」10月11日(火)から、新たに展開開始|株式会社ローソン
店舗DXの推進にあたり、最新トレンドを追いかけることは大切ですが、話題性に偏りすぎると本質的な課題解決が後回しになる恐れがあります。目新しさや流行の技術を優先するあまり、店舗の実情や顧客ニーズに合わない施策を展開してしまうことがあるため、注意が必要です。
したがって、トレンドの活用にあたっては、店舗の具体的な課題や長期的なビジョンと照らし合わせて、取捨選択を行う姿勢が大切です。
多くの店舗がDX推進を検討する際、最新技術や流行の施策に注目しがちですが、その一方で現場での本質的な課題に目を向けることがおろそかになるケースが散見されます。例えば、無人レジやAI接客など話題性の高い技術を導入しても、店舗の実際の運営課題や顧客の不満が解消されないままだと、施策の効果は限定的です。技術を使いこなせず混乱が生じる場合もあり、これがかえって顧客体験を損ねる要因となりかねません。
こうした事態を避けるには、店舗の現状や課題を詳細に把握し、DX推進の目的を明確に定めた上で、技術を選択することが肝要です。顧客視点や現場スタッフの意見を取り入れながら、本当に役立つ施策を検討していくことが求められます。
店舗DXにおいて最新技術を導入しても、現場のスタッフが十分に使いこなせなければ、施策が定着せずに終わることが少なくありません。技術に対する理解不足や操作の煩雑さが原因となり、スタッフの負担感が増してしまう場合もあります。
結果として、ツールやシステムの利用が進まなかったり、旧来の業務プロセスに戻ってしまったりするかもしれません。こうした状況を避けるためには、導入前に現場のニーズや業務フローを丁寧にヒアリングし、操作性や実用性に配慮した選択が求められます。
さらに、スタッフへの十分な研修やマニュアル整備も欠かせません。現場の声を反映した段階的な運用開始やサポート体制の構築も、DXを継続的に推進する上で重要なポイントといえるでしょう。
最新のDXトレンドに乗ろうとするあまり、顧客の実際のニーズや購買体験に配慮しない施策が押し売りされることもあるかもしれません。例えば、無人決済やスマート店舗の導入が進んでも、顧客の年齢層や利用環境に合わないと、不便さや使いづらさを感じる場合もあるでしょう。
技術が高度になりすぎると、逆に顧客との接点が希薄になり、温かみのあるサービスが損なわれることも考えられます。また、トレンドにばかり目が向くと、店舗独自のブランド価値や強みを見失い、顧客ロイヤルティの低下を招く可能性も否めません。
したがって、店舗DXの推進にあたっては、顧客の多様なニーズを把握し、多様な利用者が快適に使える環境設計や接客スタイルの確立に配慮することが肝心です。技術と人の調和を意識した取り組みが求められます。

店舗DXを推進する上で、最新トレンドを追いかけることは確かに魅力的ですが、話題性だけに偏らず、本質的な課題解決を重視する姿勢が大切です。現場スタッフがスムーズに使いこなせるか、そして顧客体験を向上させる設計となっているかを常に意識しながら取り組むことが望ましいでしょう。これにより、顧客にとって使いやすく魅力的な店舗づくりが実現し、長期的な店舗価値の向上につながります。
記事で紹介したポイントを参考に、自店舗の状況に応じたDX推進を検討してみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
