店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
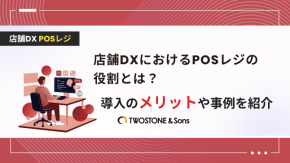
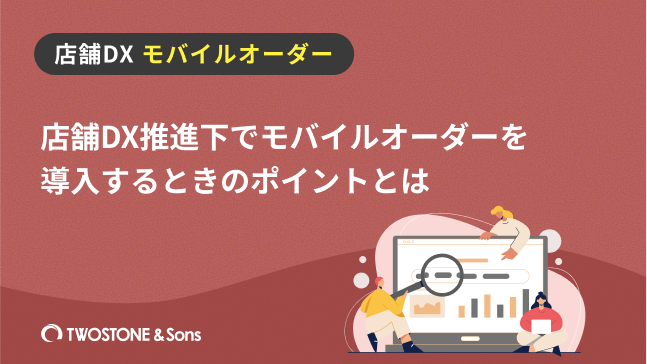
近年、店舗経営においてDX推進の重要性がますます高まっています。経産省発表によると2024年のキャッシュレス決済比率は42.8%になりました。お客様のニーズが多様化し、店舗の運営効率や顧客体験の向上が求められる中で、最新技術を活用した店舗づくりは経営のカギとなりつつあります。しかし、どのようにして技術を取り入れ、実際に成果につなげていくかは悩みの種になりがちです。
本記事では、特に注目されているモバイルオーダーシステムを中心に、その仕組みと店舗運営への影響を具体的に解説します。これにより、導入を検討する際の理解が深まり、効果的な店舗DX推進の一助になることを目指します。技術の流れを押さえ、スムーズな店舗運営と顧客満足度の向上を実現するポイントを知ることで、競争力を高めるヒントが見つかるでしょう。
出典参照:2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました|経済産業省

モバイルオーダーシステムは、スマートフォンやタブレットを利用して店舗の商品を注文できる仕組みです。このシステムの特徴は、注文から決済までのプロセスを効率化し、スタッフの負担を軽減しながら顧客の利便性を高める点にあります。店舗運営においては、注文管理のリアルタイム化や決済手続きのスムーズ化が期待できるでしょう。
ここからは、ユーザーの注文情報入力から店舗への連携、そして決済処理と注文管理までの流れを詳しく説明します。これらの要素を理解することで、導入後の効果や運用面のポイントをイメージしやすくなるでしょう。
まずユーザーは、専用のアプリやウェブサイトを通じて注文したい商品を選びます。ここでは商品情報が視覚的にわかりやすく表示されることが重要で、メニューの構成や写真、説明文が注文意欲に影響しかねません。注文内容を決めた後、ユーザーは数量やオプション、受取時間などを指定します。
これらの情報はシステムに正確に反映されなければならず、操作が直感的でストレスを感じさせない設計が必要です。注文の確定ボタンを押すと、入力されたデータは即座にサーバーに送信され、次の処理に進みます。注文情報の入力から送信までの段階で、ユーザーエクスペリエンスの質がシステムの評価を左右すると言えます。
ユーザーから送信された注文情報は、クラウド上のサーバーでリアルタイムに処理されます。これにより、店舗スタッフは常に最新の注文状況を把握できるようになるでしょう。具体的には、注文データが自動的にキッチンの調理端末やレジ端末に連携され、作業の優先順位や進捗管理に活用されます。
リアルタイム処理によって、注文の重複や取りこぼしを防ぎ、ミスの削減につながる点がメリットです。また、店舗側で在庫管理システムと連携すれば、売り切れ情報を即時反映して注文受付を制限することもできます。このようなデータ連携は店舗運営の効率化と顧客満足の両面に貢献し、システム導入の価値を高める重要な機能となっています。
注文の決済は、モバイルオーダーシステムにおいてユーザー体験を左右する重要なポイントです。システムはクレジットカードや電子マネー、QRコード決済など複数の決済手段に対応することが多く、利用者の利便性を確保できるため安心です。決済情報はセキュリティに配慮した形で処理され、不正利用のリスクを抑えるための暗号化や認証技術が用いられています。
決済が完了すると、ユーザーと店舗双方に注文確認の通知が送られます。店舗側では注文状況を管理画面でリアルタイムに把握でき、受注から商品提供までの流れをスムーズにコントロールしやすくなるでしょう。こうした仕組みが注文ミスの防止やサービス品質の向上に寄与し、店舗DX推進の中心的な役割を担うことにつながります。
店舗DX推進の一環としてモバイルオーダーを導入すると、店舗運営の質や効率に多方面から影響を与えるでしょう。実際に2024年10月のぐるなび調査ではモバイルオーダー利用経験者は62%に増加しました。注文プロセスの改善だけでなく、顧客満足度や売上の向上にもつながるため、単なる技術導入以上の効果を期待する動きが見られます。
ここでは、モバイルオーダーを活用することで得られる具体的なメリットを5つに分けて解説します。これらのポイントを把握することで、店舗経営におけるDX推進の重要性と、その実践的な価値が理解しやすくなるでしょう。
出典参照:モバイルオーダーに関する調査レポート|株式会社ぐるなび
モバイルオーダーの導入により、ユーザーは店舗での注文待ち時間を減らせるため、顧客体験が改善されやすくなります。事前に注文内容を確定し、決済まで済ませられるため、来店後の注文手続きが省略される仕組みです。結果として、店舗内の混雑緩和や注文処理の効率化につながり、回転率の向上も期待されます。
これは店舗の売上向上に直結する重要な要素であり、特にランチタイムやピーク時の混雑対策として効果的です。店舗側がスムーズに対応できる体制を整えれば、顧客満足度の向上も自然と実現しやすくなります。
近年、多くの店舗が慢性的な人手不足に悩まされています。モバイルオーダーを活用することで、注文受付や会計の業務を自動化でき、スタッフの負担を軽減することが可能になります。注文情報がデジタルで一元管理されるため、ミスの軽減や確認作業の簡略化が進み、限られた人員でも高品質なサービスを維持しやすくなるでしょう。
さらに、スタッフは顧客対応や店舗内の清掃、商品準備など、より付加価値の高い業務に注力しやすくなります。このように人手不足の課題に対して技術を活用することで、業務効率の改善や従業員の負担軽減が期待できます。
モバイルオーダーシステムでは、注文画面に関連商品やおすすめメニューを表示できるため、アップセルやクロスセルの機会が増えます。ユーザーは注文中に追加商品を検討しやすく、購入単価の向上に寄与するでしょう。
さらに、システムが過去の注文履歴を分析し、個々の顧客に合わせた提案を行うケースもあります。これにより、ただ単に注文を受けるだけでなく、積極的に売上増加を促進できる点がメリットです。こうした販売戦略をデジタルツールで支援することで、店舗の収益性向上につながると考えられます。
モバイルオーダーを通じて得られる顧客の注文履歴や行動データは、マーケティングや店舗運営の改善に役立ちます。データが蓄積されることで、人気商品の傾向や利用時間帯、顧客層の特徴などを把握しやすくなります。これを基に、効率的な仕入れ計画やキャンペーン企画が可能となり、無駄な在庫を減らしたり販促効果を高めたりできるでしょう。
さらに、顧客の嗜好に合ったサービスの提供やパーソナライズされたコミュニケーションも実現しやすくなるため、顧客満足度の向上も期待されます。このように、モバイルオーダーはデータ活用による店舗運営の高度化を促進する役割を担っています。
顧客との関係性を深める上で、リピーターの育成は欠かせません。モバイルオーダーシステムは、ポイント付与やクーポン発行、キャンペーン案内などの販促機能と連携しやすいため、顧客の再来店を促しやすくなります。これらの仕組みを活用して継続的にコミュニケーションを図ることで、店舗のブランドロイヤルティ向上につながる場合があります。
さらに、顧客の購買履歴を基にしたターゲティングも可能で、より効果的な販促施策が行われやすいです。こうした点は、競争が激しい市場環境で差別化を図るためにも注目されており、店舗DX推進の重要な側面となっています。

モバイルオーダーの導入を検討する際には、技術的な仕組みだけでなく、実際の店舗運営や顧客体験を見据えた設計が必要です。単にシステムを導入するだけでなく、ユーザーが快適に使え、店舗側も無理なく運用できる環境づくりが求められます。加えて、店舗の販促や顧客管理と連携しやすい形にすることも、効果を高めるカギとなるでしょう。
ここからは、モバイルオーダーを円滑に推進するために注目すべき具体的なポイントを解説します。これらを踏まえることで、システムの運用を通じて店舗全体のDX推進を進めやすくなります。
モバイルオーダーはユーザーが直接操作するシステムであるため、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)の設計が必要です。使いにくい画面や複雑な操作は、注文途中で離脱を招く恐れがあります。注文の選択から決済までの流れが直感的で、迷わず操作できることが求められます。
加えて、視認性の高いデザインや適切なフォントサイズ、わかりやすい説明文も不可欠です。シンプルでストレスの少ない体験を提供することが、顧客の利用率を向上させるポイントになるでしょう。こうした工夫は、リピーターの獲得にも影響しやすいため慎重に検討したい部分です。
注文受付時に商品の在庫状況がリアルタイムで反映されることは、ユーザーの満足度向上につながります。注文しても品切れで受け取れないという事態を防ぐため、システムが店舗の在庫管理と連動していることが望ましいです。
また、営業時間やピーク時間帯に応じた注文受付の調整も必要です。時間帯によって提供可能なメニューが変わる場合や、受け取り可能時間の制限があるときは、ユーザーに明確に情報を提示し誤解を避けることが大切です。こうしたリアルタイム性を持たせることで、店舗側のオペレーションもスムーズに進みやすくなります。
モバイルオーダーを導入しても、店舗のオペレーションに適合しないと効果的な運用は難しくなります。注文データの受け取り方法や調理開始のタイミング、商品の受け渡し方法までを含め、店舗の実態に合わせてシステムを設計することが大切です。
特に、スタッフが注文を確認しやすい表示形式や、キッチンとの連携体制が整っているかどうかは、業務効率に直結します。現場の声を反映しながら運用ルールを設定し、ITと現場の連動を強化することが、店舗全体のパフォーマンスを高めるためのカギとなります。
ユーザーの利便性を考える上で、注文後の受け取り方法を複数用意することは効果的です。店内での受け取りに加え、ドライブスルーやテイクアウト、場合によってはデリバリーにも対応できると選択肢が広がります。多様な受け取り方法を提供することで、利用シーンに応じた使いやすさが実現しやすくなります。
また、受け取り時の混雑緩和や顧客満足度向上にも寄与しやすいです。システム側で受け取り方法の切り替えを柔軟に設定できることが、運用のしやすさにつながるため、要件として押さえておきたいポイントです。
モバイルオーダーは単なる注文システムとしてだけでなく、販促活動や顧客管理(CRM)と連携できる設計にすることで店舗経営により効果的に活用できます。ポイント付与やクーポン配布、会員管理機能とつなげることで、顧客の再来店促進に役立ちます。
さらに、購買履歴や嗜好データを活用したパーソナライズされたメッセージ配信も実現しやすくなるでしょう。こうした連携は、単一のシステムだけでは実現が難しいこともあるため、外部の販促ツールやCRMと統合しやすいAPI連携が整っているかも重要な判断基準となります。結果として、継続的な顧客関係強化に寄与するため、戦略的に設計すべき点です。
モバイルオーダーの推進は、店舗運営の効率化や顧客満足度向上に役立つ一方で、運用方法やシステム設計が適切でなければ期待通りの効果を得られない場合があります。特に、導入後の継続的な運用や現場との連携を軽視すると、トラブルや顧客離れを招くことが多いです。導入時に陥りやすい失敗事例を把握しておくことで、課題への事前対応がしやすくなり、店舗DX推進がスムーズに進むでしょう。
ここではよく見られる失敗例を取り上げ、注意すべきポイントを詳しく解説します。
モバイルオーダーはシステムの設置だけでは本来の効果を発揮しにくい側面があります。導入後の運用体制の整備やスタッフ教育、日々の業務改善を継続して行うことが欠かせません。運用軽視の状態では、スタッフがシステムの扱いに慣れず、混乱や誤操作が生じやすくなります。
また、顧客からの問い合わせやトラブル発生時の対応が後手に回り、サービス品質の低下に直結しやすいです。さらに、注文データの分析やシステムのアップデートを行わなければ、導入効果は時間の経過とともに薄れてしまいます。成功している店舗は、導入後の運用にリソースを割き、改善活動を継続的に行っている傾向があります。
システムの機能と現場の実際のオペレーションが合致していない場合、店舗全体の効率化が阻害されてしまいます。具体的には、注文情報の伝達方法が現場スタッフの動線や作業手順に合わず、混乱を招きかねません。
例えば、キッチンスタッフが注文を確認するタイミングや方法が不適切だと、調理遅延や誤作が発生しやすくなります。こうした状況はスタッフのストレスを高め、サービス品質低下につながるため、現場の意見を取り入れたシステム設計が不可欠です。
また、スタッフのスキルや人員配置も考慮しなければ、システムと運用が乖離し、期待通りの成果に結びつかないリスクがあります。現場とITが一体となった運用体制づくりが大切です。
モバイルオーダーの利用率を高めるには、使いやすいユーザーインターフェースとスムーズな操作体験が不可欠です。操作が煩雑で注文完了までに時間がかかると、顧客が途中で利用を断念する恐れがあります。特にスマートフォンの画面サイズに合っていない設計や表示速度の遅さはストレスになります。注文内容の選択肢がわかりづらかったり、エラーメッセージが不親切だったりと混乱を招きやすいです。
また、高齢者やITに慣れていない層にも配慮した設計が求められます。こうしたユーザビリティの欠如は顧客離れを引き起こし、システムの効果を損ねることになりかねません。継続的なユーザーテストとフィードバックの活用が改善のカギとなります。
モバイルオーダーはインターネット回線やクラウドサーバーに依存するため、通信障害やサーバーダウンが発生すると、注文受付が全面的に停止してしまうリスクが存在します。こうした障害が長時間続くと、店舗の売上減少や顧客からの信頼低下を招く恐れがあります。
また、障害発生時の代替手段が準備されていないと、業務が混乱しやすいです。したがって、通信環境の冗長化やバックアップの通信経路確保、オフライン時の注文受付方法など、万が一のトラブルに備えた対策が重要になります。
さらに、システム提供側との迅速な連携や障害復旧のための手順を明確にしておくことが、被害の最小化につながるでしょう。リスク管理を怠ると店舗の評判や信頼を損なう結果となるため、注意が必要です。
実際の導入事例を確認することで、モバイルオーダーが店舗DXとどのように連携し、現場の業務効率や顧客体験に具体的な変化をもたらすのかが理解しやすくなります。特に業界大手の企業では、店舗運営の課題に対して独自の工夫を凝らし、短期的な効果だけでなく、中長期的な収益性や顧客満足度の向上までを見据えた取り組みが行われています。
ここでは、日本国内の企業によるモバイルオーダー導入の事例を通じて、その有効性や導入時に直面する課題、成功のための戦略的アプローチについて、具体的なヒントを探っていきましょう。
スターバックスでは、2019年より「Mobile Order & Pay」の名称でモバイルオーダーを本格運用し始め、順次全国の店舗に展開しました。この仕組みでは、顧客がアプリ上で商品を事前に選択し、希望する店舗で時間を調整して受け取ることができます。
ピークタイムの混雑緩和を目的として設計されており、待ち時間の短縮と店舗内の滞在時間の分散に効果を発揮しています。加えて、アプリと連動したスターバックスリワードの活用により、注文履歴や購入傾向の把握が可能となり、顧客ごとのパーソナライズされたマーケティングにもつながりました。
UI設計や利用導線のわかりやすさが評価され、都市部を中心に多くのユーザーから支持を集めています。
出典参照:事前注文決済サービス「モバイルオーダー&ペイ」が全国直営のスターバックスで対応開始|スターバックスコーヒージャパン株式会社
日本マクドナルドでは、モバイルオーダーの導入により受け取り方法の多様化を図っています。店舗カウンターの受取に加え、テーブルデリバリーやパーク&ゴー、ドライブスルー対応も用意されています。これにより、顧客がその時の状況やニーズに合わせて受け取り方法を選択できる柔軟性が生まれました。
アプリからの注文は、位置情報と連動して店舗に通知され、スタッフはそれに基づいて調理と提供準備を進めます。導線の分散化により店舗の混雑を抑えるとともに、業務効率の向上も実現しています。また、モバイルオーダー限定のキャンペーンやクーポン配信により、アプリ経由での利用促進を継続的に行っている点も特徴です。DXの一環として顧客体験の多層化に成功した事例といえます。
出典参照:マクドナルドの新サービス モバイルオーダー ついに誕生!|日本マクドナルド株式会社
吉野家は、スマートフォンからの事前注文とキャッシュレス決済に対応した「スマホオーダー」を導入し、効率的な店舗運営とサービス向上を両立しています。このサービスでは、メニュー選択から支払いまでをアプリ上で完結できるため、店頭でのやり取りを最小限に抑えられました。
さらに、注文履歴や利用頻度のデータを取得し、マーケティング施策へと活用する仕組みも整えられています。注文情報は店舗のキッチンとリアルタイムに共有され、調理から受け取りまでがスムーズに進行するよう設計されています。
顧客視点では、時間の有効活用や会計の簡略化が利点となっており、ビジネスパーソンや時間に制限のある層にとって利用価値が高まりました。テイクアウト需要の高まりに対応したDX施策として注目されています。
出典参照:「PayPay」で事前決済までできるテイクアウトスマホオーダーサービスを開始|株式会社吉野家

モバイルオーダーの導入は、単なる利便性向上にとどまらず、店舗DX推進の一環として店舗運営全体に波及効果をもたらします。注文の効率化や人手不足対策に加え、顧客データの取得と活用によるマーケティングの精度向上、そしてリピーター育成にもつながる点がポイントです。
実際の企業事例でも、ユーザビリティや現場のオペレーションとの連動性を重視した取り組みが成果を出しています。モバイルオーダーを検討する際は、単なるシステム導入に留まらず、顧客体験の再設計やスタッフの運用体制といった視点も組み込むことが効果を高める要因になります。
本記事で紹介した内容を参考に、自店舗に適した形でDXを推進していきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
