店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
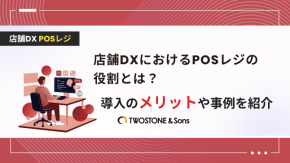
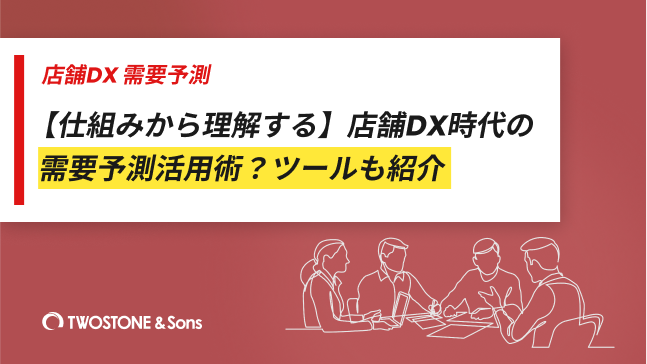
店舗運営において売上や顧客満足度を向上させるには、先を見通した計画が欠かせません。近年ではテクノロジーの進展により、需要予測を活用して効率的な運営を目指す動きが加速しています。特に、店舗DX時代にはデータを活用した需要予測が単なる売上予測を超え、在庫管理や人員配置、販促計画においても重要な役割を果たすようになりました。これによって過剰な在庫や人手不足を減らし、コスト削減や顧客体験の向上につなげることが期待されています。
本記事では、店舗運営における需要予測の仕組みや具体的な活用法を分かりやすく解説します。記事を読むことで、店舗の需要変動に柔軟に対応し、効率的な販促や人員配置を実現するヒントが得られるでしょう。

店舗経営では、季節やイベント、天候など多様な要因で需要が変動します。この変動を適切に把握し対応することが、売上の安定化やコスト管理に直結します。需要予測はこうした変動を分析し、未来の販売量や顧客数を予測する、注目の技術です。予測を活用すれば、過剰な在庫やスタッフの不足といった問題を未然に防ぎ、効率的かつ戦略的な店舗運営が見込まれます。
ここでは、需要予測が求められる3つの理由を解説します。
店舗の需要は多くの要素によって左右され、単純な過去データの延長だけでは正確に予測できません。そこで売上予測の仕組みでは、過去の販売データに加えて天候情報、イベントカレンダー、競合状況、さらには地域のトレンドやSNSの動向など、多様なデータを統合して解析することが求められます。こうした多角的なデータ分析により、需要のピークや谷を事前に把握しやすくなるでしょう。
予測モデルは機械学習や統計分析を用いて作成され、時系列解析によって将来の売上傾向を数値化します。これにより、店舗ごとの特性や曜日ごとの変動パターンなども加味した精度の高い予測が目指されます。売上の動きを前もって把握できれば、仕入れ量やキャンペーン計画の調整に役立ち、無駄なコストを抑えられるでしょう。
売上の需要ピークを的確に予測できると、そのタイミングに合わせた販促施策の効果を高めることができます。例えば季節の変わり目やイベント開催時には、商品の品揃えを最適化したり、プロモーション活動を集中的に展開したり、といったこともできるかもしれません。これにより、売り逃しを防ぎながら顧客の購買意欲を引き出す狙いが期待できます。
また、需要予測を活用することで、販促の投資対効果を評価しやすくなります。キャンペーンの効果を事前にシミュレーションし、費用対効果の低い施策を削減できるでしょう。これらは店舗の売上向上だけでなく、効率的なマーケティング資源の配分にもつながり、経営の質を向上させることに寄与します。
店舗における人員配置も需要予測の活用領域の1つです。特に来客数や購買行動のピークを予測することで、適切なスタッフ数を確保し、顧客サービスの質を落とさずに効率的な運営を実現できます。人員が不足すれば顧客対応に遅れが生じ、逆に過剰ならば人件費の無駄が増加します。
予測データを基に曜日別や時間帯別の混雑状況を分析し、シフト計画に反映することが効果的です。これにより、スタッフの負担軽減や顧客満足度の向上が期待でき、結果的にリピート率の向上にもつながります。さらに急な天候変化やイベント開催時の変動にも柔軟に対応しやすくなるため、店舗運営の安定性が高まるでしょう。
これまでの需要予測は過去の実績に頼る傾向が強く、変化の早い消費行動に対応しきれない課題がありました。しかし現在では、AI、IoT、POS、外部環境データなどの技術を活用することで、より精緻な予測が目指されています。こうした仕組みを組み合わせて構築することで、販売戦略やオペレーション全体の最適化につながるでしょう。
ここでは、それぞれの技術的アプローチと予測精度向上の関係について具体的に解説します。
AIを活用した需要予測は、単なる統計的推定を超えて、膨大なデータからパターンや異常値を検出し、学習・改善を繰り返しながら予測の精度を高めていく点が特徴です。機械学習アルゴリズムは、商品の販売傾向や顧客行動の変化を捉え、日単位・時間単位の粒度で予測するモデルを作成します。これにより、売上の微細な動きにも対応しやすくなるでしょう。
特にディープラーニングを用いたモデルでは、従来では気づきにくかった相関関係も浮かび上がり、複数の要因が複雑に絡む需要の変動に対しても柔軟に対応できます。例えば、曜日や天候といった外部要因に対しても、販売データとの関係性を解析することで、影響の大きい需要パターンを特定する手がかりになります。こうした技術の活用によって、以前よりも実態に近い売上予測ができるでしょう。
POSデータは、日々の取引から得られる貴重な情報源であり、商品ごとの販売数量や時間帯別の売上動向を詳細に把握できます。需要予測においてこのデータを活用することで、過去の傾向に基づいた予測の精度を高めるだけでなく、トレンドの早期把握にもつながります。
例えば、一定期間内に売上が急増した商品があれば、それに関連するプロモーションや季節要因との関係を調査することで、今後の販売戦略に活かせるでしょう。また、売れ筋商品や不調商品を特定することにより、品揃えの見直しや仕入れ数の調整に役立ちます。
POSデータは量が膨大であるため、分析には専用のBIツールや可視化ダッシュボードが有効です。こうしたツールによってデータの見落としを防ぎ、販売状況を俯瞰的にとらえる判断材料が増えることは、需要予測の質の向上につながります。
IoTは、センサーやカメラなどの機器を通じてリアルタイムに情報を取得し、それをクラウドに蓄積・分析する技術です。店舗運営においては、入店数、滞在時間、棚前の動きといった行動データを取得することで、来店者の動線や購買行動を視覚化する手がかりになります。
こうしたデータを需要予測に組み込むことで、特定エリアの商品前での滞在時間が長い商品は今後の購買が期待される、逆に通過が多いのに購買につながらない商品は陳列や価格に課題がある、などの仮説が立てられます。また、IoTによって在庫状況や棚卸しデータのリアルタイム取得も実現し、需要予測との連携が容易になるでしょう。
店外のデータとの連携にも注目が集まっており、例えば近隣施設の人流情報や交通状況などを組み合わせて予測に活かす取り組みも進んでいます。IoTによる可視化と連携は、データに基づいた運営判断の精度を底上げする要素として重要視されています。
需要予測において外部環境の変化は見逃せない要素です。特に天候や地域イベントといった短期的な要因は、急激な来店数の増減や特定商品の売上変動に直結することが多いため、予測モデルへの組み込みが効果的です。
気象データでは、気温や降水確率、湿度、風速などが販売に与える影響を検証できます。例えば冷たい雨の日には温かい飲料や食品の需要が高まりやすいため、事前に仕入れ量を調整する判断材料となります。逆に真夏日が続けば、冷感アイテムや飲料の売上が上昇するかもしれません。
さらに地域のイベントや祭事も需要に影響を及ぼしかねません。商業施設のセール、地域の祭り、学校の休校日などを予測に組み込むことで、通常時とは異なる来客数や購買行動を見込むことができるようになります。これにより、事前の在庫調整やスタッフ配置の最適化がしやすくなり、機会損失の軽減につながります。
現代の消費行動はオンラインとオフラインを行き来する「オムニチャネル化」が進んでおり、需要予測においても単一のデータソースでは不十分になりつつあります。ECサイト、アプリ、実店舗、SNSなど複数のチャネルから得られるデータを統合し、相互に関連づけることで、より正確な需要の動きを捉えられるようになるでしょう。
例えばオンラインでの検索トレンドやカート投入状況、レビューの動向などは、購買意欲の高まりを示す兆候として予測モデルに組み込むことがその一例です。さらにSNSでの話題やトレンドワードを分析することで、短期的な消費行動の変化も見極めやすくなります。
これらのデータを統合し、販売実績と突き合わせて分析することで、モデルの精度を高めるとともに、戦略的な意思決定にも活用が見込まれます。マルチチャネルデータの融合は、今後の需要予測において避けて通れない重要な課題といえるでしょう。

店舗DXを推進する中で、需要予測の高度化を実現するには、目的に合ったツールの選定が欠かせません。近年では、AIや機械学習を活用した予測アルゴリズムを搭載し、多様なデータをリアルタイムで処理できるツールが登場しています。業務システムやPOSとの連携が可能なツールもあり、導入のハードルを下げつつ実用性を高めている点が注目です。
ここでは、代表的な2つのツールを取り上げ、それぞれの特長と活用方法を紹介します。
Amazon Forecastは、AWSが提供する時系列データ分析に特化した機械学習ベースの需要予測サービスです。膨大な履歴データを基に、商品の販売数や来店者数などの将来の動きを予測する機能を備えており、店舗業務の最適化に役立つ設計となっています。過去の販売実績、天候、プロモーションの履歴など複数の変数を入力することで、より実態に近い予測結果を得られる点が特徴です。
このツールは、深層学習を活用したモデル選択を自動的に行い、モデルの構築やチューニングの専門知識がなくても予測機能の活用を始めやすい設計です。また、ダッシュボードやAPIを通じて出力された予測結果を他の業務ツールに連携できるため、システム間での連動にも柔軟に対応可能です。さらに、短期予測だけでなく中長期の計画にも対応できるため、仕入れや販促計画の調整に活かしやすい点も注目されています。
出典参照:Amazon Forecast|アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
Perswellは、株式会社DATAFLUCTが提供する需要予測プラットフォームで、POSデータ・気象情報・商圏データなどの外部データと自社データを統合・分析することで、精度の高い予測を目指しています。特に小売業や飲食業における現場での活用を想定して設計されており、実運用を前提とした柔軟な構成が特徴です。
このツールでは、複数のAIアルゴリズムを活用し、業態や店舗の特性に応じた最適な予測モデルを自動で構築します。これにより、予測の精度を維持しながらも、運用者の負担を減らせるでしょう。また、外部要因を動的に取り込む設計となっており、天候やイベントなど突発的な需要変動への対応力を高める仕組みが整っています。
Perswellは、単なる予測ツールにとどまらず、現場での実行可能性や可視化、意思決定支援までを包括的にサポートする点で、DX推進において実用性の高い選択肢となっています。
株式会社マルイは、需要予測の精度向上を目的として、日本IBMのAIソリューションを活用し、全店舗で需要予測の仕組みを展開しています。この取り組みの背景には、顧客ニーズの多様化や購買行動の変化がありました。
特に食品業界では、在庫の適正化が収益性に直結するため、正確な需要予測が重要な役割を担っています。マルイでは、AIが各店舗や商品カテゴリーごとの売上動向やトレンドを分析し、それをもとに店舗担当者が発注量や品揃えを調整できるようにしました。
従来は属人的な判断に頼る場面が多く見られましたが、AIによる数値的な裏付けがあることで、業務の効率化と適正在庫の維持を両立する体制が整いつつあります。今後は、さらに精度を高めた需要予測に基づき、顧客満足度向上と売上管理の最適化の両立を目指しています。
出典参照:日本IBMのAI需要予測を活用し、客数と販売予測精度の向上と発注時間の大幅な削減を実証 2024年9月から、マルイが運営するスーパーマーケット全店舗でAI需要予測の導入を決定|株式会社マルイ
需要予測の仕組みを業務に取り入れ、成果を上げている企業の事例は徐々に増えています。こうした実例を見ることで、導入のハードルや活用イメージを具体的に描くことができ、社内のDX推進に対する理解や納得感も得やすくなるでしょう。
ここでは、小売業界において実績を示している2社の事例を取り上げ、取り組みの内容と成果について紹介します。自社の課題や現状と照らし合わせながら参考にしてください。
株式会社イトーヨーカ堂は、全国の店舗においてAIを活用した需要予測型発注システムを導入し、効率的な商品供給体制を整える取り組みを進めています。これは、商品ごとの販売履歴、曜日別の販売傾向、天候やカレンダー情報などを統合して分析し、売れ筋を予測することで発注精度を向上させるシステムです。
これにより、従来は担当者の経験や勘に頼っていた発注作業の属人化を軽減し、全店舗での在庫過多や欠品のリスクを抑えることが見込まれています。
公式発表によると、導入後には発注ミスや欠品の件数が目に見えて減少したとの報告もあり、データに基づいた発注の有効性が現場レベルで実感されていることが分かります。これは、AI予測の定着とともに、全社的な業務の質向上を図る取り組みの事例といえるでしょう。
出典参照:「AI(人工知能)発注」の仕組みを全店に導入|株式会社イトーヨーカ堂
株式会社ライフコーポレーションでは、生鮮食品や日配品といった賞味期限の短い商品を対象に、自動発注システムの導入を進めています。AIによる需要予測を活用し、売上動向、天候、イベント日程などの外部要因を取り込んだ発注モデルを用いることで、精度の高い商品供給を目指しています。
この取り組みの特徴は、店舗ごとの特性を考慮しつつ、共通の発注基準を整備することによって、全体最適と現場の柔軟性を両立させている点です。発注ミスによる廃棄の発生を抑えると同時に、商品欠品による販売機会の損失を防ぐ仕組みとして、導入以降も継続的に改善が図られています。
需要予測による業務支援が、現場の生産性向上と商品ロスの削減に貢献している好例といえます。
出典参照:ライフコーポレーションと日本ユニシス共同開発のAI需要予測自動発注システムをライフ全店に導入|株式会社ライフコーポレーション
店舗DXにおける需要予測は、ツールを導入するだけで成果が得られるものではありません。予測の活用には、現場の運用体制や人材のスキル、環境要因など複数の視点を踏まえた実践が求められます。予測と実績の差異、データの変動要因、業態特性などを把握した上で、自社に合った戦略的な活用を意識することが大切です。
ここでは、需要予測を実施・運用する際に押さえておきたい視点について解説します。
どれほど精緻なモデルを用いたとしても、需要予測は常に一定の誤差を含みます。予測結果と実際の販売実績に差が生じることを前提に、柔軟な対応を行える運用体制を整える必要があります。過信せず、補正や調整を適切に実施する体制が必要です。
例えば、予測結果に依存しすぎると、予期せぬ需要変動に対応できないリスクが高まります。過去の販促効果や近隣競合の動き、急な天候変化など、モデルでは捉えきれない要素を把握する現場の視点も欠かせません。こうしたズレを認識し、早期に対応できる体制を築くことが、実運用での成功につながります。
また、店舗スタッフが予測値をどう読み取るか、どのように現場の判断に反映するかといった教育体制も含めて設計することが求められます。定期的に予測と実績の乖離を検証し、改善につなげるフィードバックサイクルの整備も不可欠です。
予測モデルの精度は、時間の経過とともに変動します。消費者の行動や市場のトレンドが変化すれば、過去のデータに基づいたモデルの有効性は低下する傾向にあります。そのため、予測の精度を維持するためには、定期的なチューニングが欠かせません。
具体的には、新しいデータの反映や季節変動のパターン更新、外部要因の重み調整などを行い、モデルを常に最新の状態に保つことが大切です。予測精度の指標(RMSE、MAPEなど)をモニタリングし、異常があれば迅速に原因を分析し修正する仕組みを整えておきましょう。
また、チューニングを現場任せにせず、専門部署やデータ分析担当者と連携する体制を構築しておくことで、属人化を避けながら安定した精度を保つことができるでしょう。精度維持の継続的な取り組みは、店舗DXを進める上で欠かせない基盤の1つといえます。
需要予測を業務に取り入れる際、現場のITスキルやデータリテラシーの水準が活用の成否を左右します。予測結果を正しく読み解き、業務判断に落とし込むには、一定のデータ理解力が求められます。特に多店舗展開している企業では、店舗ごとのスキル格差が課題になりかねません。
このような課題に対処するには、初期導入時の教育だけでなく、継続的なリテラシー強化と社内でのナレッジ共有が必要です。マニュアルや研修の整備に加え、現場からのフィードバックを活かした改善活動を積み重ねることで、徐々にスキルの底上げが期待できます。
また、ITスキルが限定される現場に対しては、わかりやすいインターフェースやガイド機能を備えたツールを活用することも有効です。予測値の可視化やアラート機能を通じて、直感的な判断支援ができる環境を整える工夫も求められます。
需要予測のモデルは、業種・業態、店舗の立地条件、客層などの違いによって予測傾向が異なります。汎用的な予測モデルをそのまま適用しただけでは、精度が不十分になりやすく、現場の実情にそぐわない結果につながりかねません。
例えば、都心部のオフィス街にある店舗と郊外の住宅地にある店舗では、来店タイミングや曜日ごとの購買傾向がまったく異なります。これらを区別せず一律で予測した場合、在庫過剰や機会損失を招くかもしれません。したがって、業態ごとに異なる特徴を反映したモデル設計が求められます。
さらに、店舗ごとにチューニングされたモデルやローカルデータを活用することで、現場の実感に応じた予測が実現できます。現場スタッフからの情報収集や、地域密着型の要素を組み入れる仕組みづくりも重要なポイントです。
需要は消費者の心理や社会状況に強く影響されるため、外部環境の変化が予測に与える影響を把握しておくことが欠かせません。突発的な天候不順、自然災害、感染症の流行、原材料価格の変動、政治経済の動向など、外的要因によって消費行動が短期的に変化するケースが少なくありません。
こうしたリスクを予測に組み込むためには、外部データとの連携や複数シナリオを想定したシミュレーション機能の活用が有効です。単一の予測結果に依存するのではなく、複数のモデルを併用することで、変動に対する耐性を高めることができます。
また、過去に起きた同様の事象から傾向を学び、将来の意思決定に活かす体制づくりも必要です。リスクを想定し、あらかじめ対応策を考えておくことで、急な変化にも柔軟に対応できる組織体制を構築していきましょう。

店舗DXを推進する上で、需要予測の高度化は中核となる要素です。AIや機械学習の活用によって、販売傾向の見える化や在庫最適化が実現し、現場の業務効率とサービス品質の向上につながります。
一方で、予測と実績の差異や外部環境の影響といったリスクにも目を向ける必要があります。継続的なチューニングや現場との連携を前提に、データに基づく判断体制を構築することが、成果につながる第一歩です。実際に成果を上げている企業の取り組みや、需要予測ツールの特徴を参考に、自社にとって最適な活用方法を検討していきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
