店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
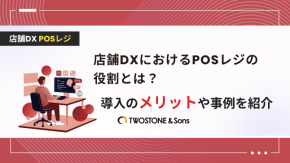
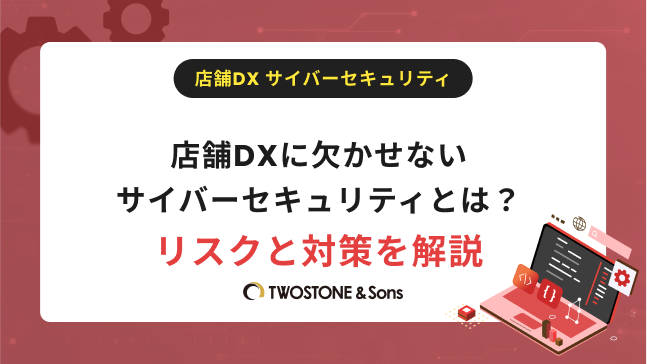
店舗運営の現場では、業務効率化や省人化を図るためにデジタル技術の活用が欠かせない状況になっています。特に店舗DXを推進することで、従来の手作業や紙管理から脱却し、迅速で正確なオペレーションを実現しやすくなります。
しかし、デジタル化が進む一方でサイバーセキュリティリスクも高まっていることを忘れてはなりません。株式会社サイバーセキュリティクラウドの調べによると、2024年の個人情報漏洩件数は約2,164万件に上り、サービス業は業界3位の漏洩数になっています。顧客情報や決済データなどの重要な情報がデジタル上で管理されることで、悪意のある攻撃者から狙われる危険性が増しています。もしセキュリティ対策が不十分だと、情報漏えいやサービス停止、さらにはブランドイメージの低下につながるかもしれません。
本記事では、店舗運営で注意すべき代表的なサイバーセキュリティリスクを取り上げ、それらに対してどのように対策を進めていくべきかを解説します。店舗経営者や管理者が今後のデジタル戦略を考える際の参考になれば幸いです。
出典参照:2024年は約3日に1回、企業や自治体でセキュリティインシデントが発生 個人情報漏洩件数は年間約2,164万件、最もインシデントが多い業種は「製造業」に|株式会社サイバーセキュリティクラウド

デジタル化が進む店舗運営では、多様なサイバーセキュリティリスクが存在します。特にPOSシステムやWi-Fi環境、メールのやり取りといった業務に直結する部分が狙われやすく、これらの脆弱性が放置されると情報漏えいや業務停止のリスクにつながりかねません。店舗はこうしたリスクの理解を深め、適切な対策を推進していく必要があります。
ここでは、店舗で注意したい代表的なリスクを具体的に解説します。
POSシステムは店舗の販売情報や決済データを扱う重要な設備であり、そのセキュリティは店舗運営の根幹に関わります。マルウェア感染によってPOSシステムが侵害されると、顧客のクレジットカード情報が不正に取得されたり、システムが停止して販売が滞ったりする恐れがあります。
攻撃者は主に脆弱なソフトウェアや外部機器を経由して感染させるため、定期的なソフトウェアの更新やアクセス制御が必要です。さらに、感染を早期に検知できる監視体制を整えることも効果的でしょう。POSシステムの安全性を維持するためには、単に技術的な対策だけでなく、従業員への啓発も欠かせません。
多くの店舗では顧客やスタッフが利用する公共Wi-Fiを提供していますが、この環境にはセキュリティ上のリスクが潜んでいます。公共Wi-Fiは暗号化が不十分な場合も多く、第三者による通信の盗聴やなりすまし攻撃が発生しやすい状況です。悪意ある第三者がネットワークに侵入すると、顧客の個人情報や決済情報が漏えいしかねません。
店舗側はWi-Fiのセキュリティ強化やVPNの活用を検討し、通信の安全性を確保する必要があります。また、スタッフに対しても公共Wi-Fi使用時の注意喚起を徹底することで、リスクの低減が期待できるでしょう。
店舗運営にかかわるメールは、業務連絡や顧客対応に欠かせないコミュニケーション手段ですが、ここにもリスクが潜んでいます。フィッシング詐欺やなりすましメールは、正規の取引先や上司を装って不正アクセスや情報漏えいを狙う手口です。
フィッシング対策協議会によると、2025年3月に寄せられたフィッシング報告件数 (海外含む) は、前月より108,713件増加し、249,936件となりました。
こうした攻撃により、重要なシステムの認証情報が盗まれたり、金銭的な被害が発生したりするリスクがあります。店舗はメールの送信元を確認する習慣をつけるとともに、怪しいメールを識別するための教育やツールの活用を進めることが大切です。セキュリティソフトの導入や多要素認証の活用も防御策として検討されます。
出典参照:月次報告書|フィッシング対策協議会
店舗のデジタル化が進む中、サイバーセキュリティ対策を怠ることは経営リスクを高める要因となります。顧客情報の管理や決済システムなど重要なデータが守られない場合、さまざまなトラブルが発生する恐れがあり、結果的に店舗の信頼性や事業継続に深刻な影響を及ぼしかねません。対策不足によるリスクは多岐にわたり、その内容と影響を正しく理解し、適切な対応を検討することが必要です。
ここでは、店舗運営で想定される代表的な危険性について詳しく解説していきます。
顧客情報の漏えいは店舗にとって深刻な問題の1つです。個人情報が外部に流出すると、顧客のプライバシーが侵害されるだけでなく、顧客からの信頼を失う事態に発展しやすいです。信頼の喪失は再訪率の低下や口コミでの悪評につながり、売上減少を招きます。情報漏えいの原因は内部のヒューマンエラーやシステムの脆弱性が多く、対策を怠ると被害は広範囲に及ぶかもしれません。
実際に、独立行政法人情報処理推進機構の調べでは、情報セキュリティ関連の被害を受けた企業の被害額は平均で73万以上、復旧までには約5.8日かかっています。
加えて、漏えいが発覚すると、社会的信用の回復に長期間かかることも少なくありません。したがって、顧客情報の厳重な管理と定期的なセキュリティ監査が不可欠になります。
出典参照:「2024年度中小企業等実態調査結果」速報版を公開|独立行政法人情報処理推進機構
店舗のPOSシステムやオンライン管理ツールに対して不正アクセスが行われると、システムが停止し業務が滞りかねません。不正アクセスは外部からの攻撃だけでなく、内部関係者によるものも含まれます。システムが利用できなくなると、決済処理ができず顧客対応に支障をきたし、結果的に機会損失や顧客満足度の低下を招きかねません。
また、停止が長引くと復旧までのコストも膨らみ、店舗運営に打撃を与えかねません。このようなリスクを軽減するためには、アクセス権限の管理強化や侵入検知システムの設置などが必要とされます。
サイバーセキュリティ対策を怠った結果、顧客情報の漏えいやシステム障害が発生すると、法律に基づく賠償金や罰金を請求されるかもしれません。個人情報保護法などの法令遵守が求められる中、違反が明らかになると企業責任が問われ、経済的な損失が生じやすいです。
これらの損失は直接的な金銭的負担だけでなく、訴訟費用や調査費用などの追加コストも含みます。賠償金や罰金の発生は店舗経営に負担を与え、事業継続にも影響を及ぼすため、法令に沿ったセキュリティ対策の推進が求められます。
個人情報保護法などの規制に違反すると、行政処分や罰則が科されるリスクもあります。行政処分には業務改善命令や公表命令などがあり、これらは企業の社会的信用を損ないかねません。さらに、悪質な場合には刑事罰が科されることもあり、経営者や担当者に直接的な責任が問われるケースもあります。
処分を受けると店舗の運営に制限がかかり、顧客離れや取引先からの信用失墜を招く恐れがあります。こうした事態を避けるために、規制への対応を徹底し、定期的な内部監査や教育を実施しましょう。
セキュリティトラブルが発生すると、ブランドイメージにダメージが及びやすいです。顧客からの信頼が揺らぎ、企業としての信用が低下することで、集客や販売に悪影響を及ぼします。SNSや口コミで情報が瞬時に拡散される現在、トラブルが表面化すると短期間で多くの人に知られ、ブランドの評価を下げてしまいかねません。
イメージ回復には時間やコストを要し、場合によっては新たな販促活動やキャンペーンが必要になる場合もあります。したがって、トラブルの未然防止に注力し、万が一発生した際には迅速かつ適切な対応を心掛けることが大切です。

店舗DXを推進する過程では、POS端末やモバイルデバイス、クラウドサービスの活用が進み、ネットワーク接続される機器の数が増加します。これに伴い、サイバー攻撃や情報漏えいといったリスクも高まりかねません。安心してDXを進めるには、IT基盤の整備と同時に、セキュリティ対策の実践が不可欠です。
特に店舗運営に関わる個人情報や決済情報を安全に扱うためには、技術的・人的な両面から対策を講じる必要があります。
ここでは、店舗で実施されている代表的な5つのセキュリティ施策について紹介します。
出典参照:令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について|警察庁サイバー警察局
店舗のネットワークを複数のセグメントに分けることで、異なるシステム間の通信を制限し、不正アクセスやマルウェアの拡散リスクを抑制できるでしょう。例えば、顧客の決済情報を扱うPOSシステムは他の端末やパブリックネットワークから分離し、アクセス権限を厳格に管理するのが効果的です。
また、アクセス制御はユーザー認証やデバイス認証を組み合わせ、許可された人や機器のみが重要な情報に触れられる仕組みを構築します。これにより、内部からの脅威も含めた多層的な防御が可能となり、店舗のサイバーセキュリティが強化されるでしょう。さらに、複数店舗を展開している場合は、中央管理によるセグメント化で効率的な運用が期待されます。
重要な顧客情報や決済データは、通信中だけでなく保存時にも暗号化されることが望ましいです。暗号化を施すことで、万が一データが外部に漏えいした際にも情報内容の解読を防止できるでしょう。例えば、クラウドに保管するデータや店舗内のサーバー上の情報は暗号化され、アクセス権限を持つ担当者のみが復号できる体制が理想的です。
通信の際もSSL/TLSなどの暗号プロトコルを利用し、ネットワークを流れる情報の安全を確保します。このように多層的に暗号化を施すことで、情報漏えいリスクを低減させ、顧客や取引先の信頼を維持しやすくなります。
店舗のIT環境においては、サイバー攻撃や不正アクセスの兆候を早期に検知する監視体制が必要です。監視システムはネットワークトラフィックやアクセスログをリアルタイムで分析し、不審な挙動や異常な通信を発見すると速やかに担当者へ通知します。これにより、被害が拡大する前に適切な対応が取りやすくなります。
また、監視結果はインシデント対応後の原因分析や将来的な対策検討にも役立つため、継続的なセキュリティ強化に資することもメリットです。店舗の規模にかかわらず、こうした監視体制は安全なオペレーションの維持に欠かせません。
店舗のサイバーセキュリティは従業員の意識と行動に左右されます。パスワードの適切な管理方法やフィッシングメールの見分け方など、具体的なリスクを理解してもらうことが大切です。定期的な研修や啓発活動を通じて、情報の取り扱いやセキュリティポリシーの遵守を徹底する体制を整えましょう。
従業員一人ひとりがリスクを認識し適切に対処できることで、ヒューマンエラーによる情報漏えいや不正アクセスのリスクを減らせます。さらに、最新の脅威情報の共有も効果的で、店舗全体のセキュリティレベルの向上につながります。
パスワードだけに頼る認証は不正アクセスのリスクを高めるため、多要素認証の活用が推奨されます。多要素認証は、パスワードに加えてスマートフォンのワンタイムパスワードや生体認証など複数の認証要素を組み合わせる方法です。
これにより、パスワードが漏えいしても他の認証要素がなければログインできず、侵入防止に効果的です。店舗では特に管理者アカウントや重要システムの利用時に導入されるケースが多く、セキュリティの強化に寄与します。導入にあたっては利用者の利便性も考慮し、適切な認証手段を選択することが望まれます。
店舗DXを推進する際に欠かせないのが、サイバーセキュリティ対策の体系的な構築です。デジタル技術の活用で業務効率化や省人化を進める一方で、情報漏えいや不正アクセスなどのリスクを適切に管理しなければなりません。
具体的には、店舗全体のセキュリティポリシーの策定からシステム面の防御策、さらには専門家の活用まで幅広い対策を段階的に進めることが必要です。こうした多角的な取り組みが安全で安定した店舗運営を支え、信頼性の向上に寄与すると考えられます。
サイバーセキュリティの強化は、まず明確なセキュリティポリシーを策定することから始まります。ポリシーには顧客情報の取り扱い基準やアクセス権限の管理方法、緊急時の対応手順などを詳細に定める必要があります。
重要なのは、策定したポリシーを店舗スタッフ全員に周知徹底し、日常業務の中で実践させることです。定期的な研修や確認テストを実施し、全員の理解度を把握する仕組みも役立ちます。こうした取り組みはヒューマンエラーの削減や、店舗全体でのセキュリティ意識の共有に有効であり、結果として組織的な防御力の強化につながる取り組みです。結果として組織的な防御力の向上につながります。
店舗ネットワークを外部からの攻撃や不正アクセスから守るために、ファイアウォールやIDS/IPS(侵入検知・防御システム)の設置は重要な施策となります。ファイアウォールは外部からの不要な通信を遮断し、店舗の内部ネットワークを保護する役割を担います。
一方、IDS/IPSはネットワーク上の異常や攻撃を検知し、自動でブロックしたり警告を発したりする仕組みです。これらのシステムを適切に設定し、常に最新の状態に保つことが必要です。店舗の規模や運用形態に合わせて最適な構成を検討し、継続的な監視とメンテナンスを行うことが、セキュリティ対策の効果を維持する上で欠かせません。
セキュリティ体制の維持には、定期的に脆弱性診断を実施してシステムの弱点を洗い出すことが必要です。脆弱性診断とは、ネットワークやアプリケーションに潜むセキュリティホールを検査し、早期に発見する作業です。診断結果を基に速やかに修正対応を行うことで、サイバー攻撃のリスクを減らせます。
店舗では定期的なスキャンやペネトレーションテストを行い、ソフトウェアのアップデートや設定変更を確実に実施する体制を整えるのが望ましいです。こうした診断はIT環境の変化に対応する上でも重要な手段となり、持続的な安全運用の基盤となります。
店舗のサイバーセキュリティ対策は高度化しており、専門的な知識や技術を必要とする場面も増えています。そこで外部のセキュリティ専門チームやコンサルタントに支援を依頼するのも有効な方法です。プロフェッショナルは最新の脅威動向を把握し、店舗の実情に合わせた最適な対策を提案したり、インシデント発生時の対応支援を行ったりします。
また、定期的な監査やトレーニングも提供してもらえるため、内部リソースの不足を補う役割も果たします。外部の専門家の知見を取り入れながら、店舗のセキュリティ体制を強化しやすくなるでしょう。
店舗DXを進める上で、サイバーセキュリティを強化するために効果的なツールの活用は重要なポイントです。多様な脅威に対応しながら、店舗の運営効率を落とさずに安全を確保するには、状況に応じた適切なツール選びが必要です。
ここでは代表的なセキュリティツールの特徴を紹介し、どのような場面で役立つかを理解してもらうことで、店舗のリスク管理の参考になればと考えています。これらのツールを組み合わせて活用することが、より堅牢なセキュリティ対策につながるでしょう。
Trend Micro Apex One™は、エンドポイントセキュリティに特化したツールで、多様なマルウェアやランサムウェア、不正アクセスに対して多層的に防御します。リアルタイムでの脅威検知と自動対応機能が特徴で、感染の拡大を抑えながら迅速な対処が期待できるツールです。
加えて、AIを活用した未知の攻撃パターンの検出や、行動監視による不審な動きを察知する仕組みが搭載されています。これにより店舗のPOS端末やPCの安全を保ち、業務の継続性を確保しやすくなります。管理コンソールから全端末の状況を一元管理でき、運用の手間を抑えられる点も評価される理由です。
出典参照:Trend Micro Apex One™ |トレンドマイクロ株式会社
Cisco Umbrellaは、クラウドベースのセキュリティプラットフォームで、不審なウェブサイトへのアクセスをブロックする役割を果たします。DNSレベルで通信を監視し、マルウェア感染やフィッシング詐欺に使われる可能性があるドメインへの接続を未然に防げるため、店舗のネットワークを安全に保ちやすくなります。
特に公共Wi-Fiを利用する店舗環境では、不特定多数のアクセスリスクを抑えられるでしょう。設定も比較的容易で、短期間で導入が進めやすいのも特徴です。また、利用状況の分析機能があるため、不審なトラフィックの傾向を把握し、継続的な改善に役立てられます。
出典参照:Cisco Umbrella|株式会社NTT DATA, Inc.
Microsoft Defender for Endpointは、マイクロソフトが提供する統合型のエンドポイント保護ソリューションです。ゼロトラストセキュリティの考え方に基づき、常にデバイスとユーザーの信頼性を検証しながら安全性を確保します。多層的な防御機能を持ち、脅威の早期検知や自動調査、レスポンスの機能が充実しているツールです。
Windows環境だけでなく、多様なOSにも対応しているため、異なる機器を混在させる店舗でも導入しやすい点が評価されます。さらにクラウドベースの管理画面を通じて、複数拠点の状況を一括して監視可能で、効率的な運用支援にもつながるのが特徴です。
出典参照:Microsoft Defender for Endpoint|日本マイクロソフト株式

店舗DXの推進では、サイバーセキュリティの確保が欠かせない課題です。デジタル化によって生まれる新たなリスクに対し、ネットワークの分割やアクセス制御、暗号化、監視体制の強化といった多様な施策を検討しながら進めることが必要です。
加えて従業員教育や多要素認証、最新のセキュリティツールを活用することで、リスクを抑えつつ効率的な店舗運営を維持しやすくなります。こうした総合的な対策が安全なDX推進を支え、店舗の信頼性や顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
