店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
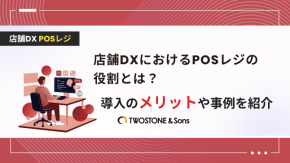
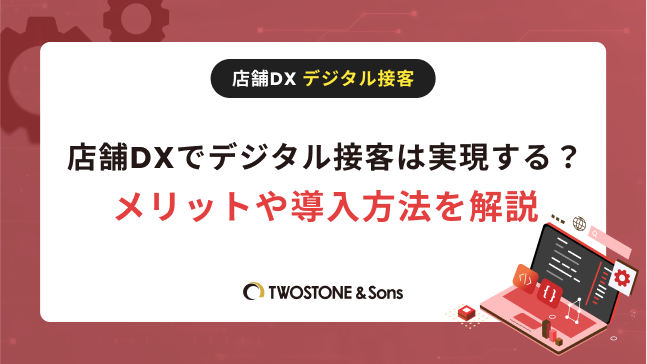
近年、店舗運営の現場ではデジタルトランスフォーメーション(DX)が重要なテーマになっています。特に接客においては、従来の人手による対応から、デジタル技術を活用した「デジタル接客」への関心が高まっている状況です。接客の質や効率を安定的に向上させるだけでなく、多様な顧客ニーズにも対応できる点が評価されているからです。
ただデジタル接客を単に導入するだけではなく、どのようなメリットが得られ、どのように実際の店舗運営に活かしていくのかを理解することが重要になります。本記事では、店舗DXの一環としてのデジタル接客の効果や具体的な導入方法をわかりやすく解説し、取り組みのヒントや成功のポイントも整理しました。
これを読むことで、効率的で質の高い接客サービスの実現に向けてどのような方向性を検討すればよいかが見えてくるでしょう。

デジタル接客は、単なる新しいツールの導入ではなく、店舗運営全体の質を向上させるための重要な要素になりつつあります。顧客との接点をデジタルで強化することで、多くの利点が生まれます。例えば、接客の質の均一化や、多店舗展開でも少人数での対応がしやすくなること、また顧客の詳細なデータを活用したパーソナライズ対応も実現可能になる点などです。
こうしたメリットを押さえることで、今後の店舗DX推進に向けた方向性を定めやすくなるでしょう。ここでは特に注目される5つのポイントを具体的に紹介します。
店舗の接客には、スタッフごとのスキルや経験の差によるばらつきが伴うものです。これが顧客満足度に影響を与えることも少なくありません。デジタル接客を取り入れることで、接客プロセスや案内内容をシステムで管理し、一定の水準を保てるようになります。
具体的には、AIチャットボットやタブレット端末を活用した案内システムが一例です。これらは、質問への回答や商品の説明などを標準化し、誰が対応しても同じ質のサービスを提供しやすくします。接客の均一化は顧客の安心感を高め、店舗全体のブランド価値向上にもつながるでしょう。
また、スタッフの教育負担も減り、効率的な運営が可能になります。加えて、システム上で接客内容の記録や分析することで、改善点を把握しやすくなる点もメリットとして挙げられます。
多店舗展開や長時間営業が求められる店舗では、すべての店舗や時間帯に十分な人員を配置することが難しくなってきました。人手不足の問題もあり、限られたスタッフで効率よく接客するためにデジタル接客の導入が注目されています。
デジタル接客ツールは、自動応答や遠隔サポートなどを通じて、リアルタイムで顧客に対応できる環境を作り出します。実際に、AIチャットボットが24時間対応を担い、スタッフは一部の接客業務をオンラインでサポートする仕組みも増えてきました。
これにより、店舗ごとの人員配置を抑えつつ、顧客の待ち時間を減らし、スムーズな接客体験を実現しやすくなります。結果として、店舗全体の稼働率向上やコスト効率の改善につながるでしょう。
デジタル接客の強みは、顧客一人ひとりの行動履歴や購買データを活用できる点です。従来の対面接客では難しかった詳細な顧客理解が、デジタルツールを通じて実現しやすくなります。
例えば、過去の購入履歴やウェブ上の閲覧履歴を基におすすめ商品を提示したり、顧客の嗜好に合わせたキャンペーン情報を配信したりできます。これにより、来店客に対してより魅力的な提案ができ、購買意欲を高める効果が期待できるでしょう。
さらに、デジタル接客は顧客の反応やフィードバックをリアルタイムで収集しやすいため、サービスの柔軟な改善にも役立ちます。顧客に合わせたきめ細やかな対応は、顧客満足度の向上やリピート率の増加につながりやすいでしょう。
外国人観光客の増加に伴い、多言語対応の重要性が高まっています。日本政府観光局によると、訪日外客数は2025年6月時点で累計2,000 万人を突破しました。そのため、店舗スタッフがすべての言語をカバーするのは難しく、デジタル接客は助けとなるでしょう。
自動翻訳機能を備えたチャットボットや多言語表示対応のタブレット端末は、言語の壁を超えた接客を実現します。これにより、訪日外国人が安心して商品を選べる環境が整い、顧客体験の向上につながるでしょう。
また、多言語対応によって、インバウンド客の購買機会を逃しにくくなるだけでなく、口コミ評価の向上や再訪問の促進も期待されます。店舗のブランドイメージ向上にも寄与すると考えられます。
出典参照:訪日外客数(2025 年 6 月推計値)|日本政府観光局
デジタル接客システムは、顧客の反応や購買行動をリアルタイムでデータとして収集します。これにより、店舗側は瞬時に顧客のニーズやトレンドを把握し、柔軟な対応が可能となる点がメリットです。
例えば、特定の商品に対する関心が高まっている場合は、販売促進や陳列の強化を迅速に検討できるでしょう。さらに、顧客からの問い合わせ内容やフィードバックを分析し、サービス改善に活かすこともできます。
こうしたリアルタイムの情報活用により、店舗は顧客満足度を高めながら、競合他社との差別化を図りやすくなります。時代の変化や顧客ニーズの多様化に対応するためには、デジタル接客の導入が有効な手段といえるでしょう。
店舗DXの推進によって、従来の対面接客に加えデジタルを活用した新しい接客スタイルが広がってきました。顧客の利便性を高めるだけでなく、店舗運営側も効率的に対応できるため、多様な店舗で注目されています。
ここでは、デジタル接客の具体的な取り組み例を紹介します。実際にどのようにテクノロジーが顧客体験の質を向上させているのか、どの技術が導入できるのかと照らし合わせながら理解を深めましょう。
AIチャットを活用した接客は、顧客からの質問に24時間対応できる強みがあります。店舗スタッフのレビューや評価を連携させることで、より信頼性の高い商品提案が実現されている点も注目です。
顧客がAIチャットを通じて商品に関する疑問を投げかけると、過去のスタッフレビューや人気のフィードバックを参考にしながら、適切な商品や使い方のアドバイスを提示できます。これにより、商品の魅力や特徴がより具体的に伝わり、購買意欲の向上につながるでしょう。
また、AIチャットは顧客の嗜好や過去のやり取りを学習し、提案の精度を徐々に高めるため、パーソナライズされた接客も期待できます。人手だけでは難しい多様な質問に対応しつつ、スタッフの負担を減らせるメリットも見逃せません。
スマートフォンアプリと連動する店舗内ナビゲーションは、顧客が店内で目的の商品にスムーズにたどり着けるようサポートします。これに加え、顧客の購買履歴や位置情報を活用してリアルタイムに最適な商品をレコメンドする機能も実装されるケースが増えています。
店舗内での移動をサポートしながら、タイムリーに関連商品の情報や特典を通知するため、顧客の購買体験が豊かになるでしょう。例えば、特定の売り場に近づくと、そのエリアの商品をおすすめしたり、限定クーポンを配信したりできるため、来店時の満足度の向上につながります。
こうしたデジタル接客は、多店舗展開している企業でも一貫したサービス提供を促しやすく、人手が足りない時間帯でも高品質な顧客対応を実現しやすくなるのが魅力です。
デジタルサイネージは視覚的に強い訴求力を持ち、商品情報の案内やキャンペーンの告知に役立ちます。さらに多言語対応を組み合わせることで、外国人観光客など多様な顧客への接客にも役立つでしょう。
画面上で商品説明や使用シーンを映像で紹介することで、店頭での疑問解消につながりやすくなります。加えて、多言語表示が可能なサイネージは、スタッフが対応しきれない言語ニーズに応え、スムーズなコミュニケーションを促す役割を果たします。
多言語案内は特にインバウンド客の多い地域での店舗運営において重要で、顧客満足度の向上や購買機会の増加につながるでしょう。視覚と情報を同時に届けるツールとして、今後も活用範囲が広がると考えられます。
美容や化粧品店では、デジタルカウンセリング端末による肌診断が注目されています。これは、顧客が端末で肌の状態をチェックすると、AIが分析結果を基に最適なケア商品を提案してくれる、という仕組みです。
このような診断と提案がデジタル化されることで、顧客は専門知識がなくても自分に合った商品を選びやすくなり、スタッフの接客も補完されます。端末は顧客情報を蓄積し、継続的なフォローアップにも活用されるため、リピート促進にもつながるでしょう。
また、肌診断のデータを集めて分析することで、店舗側は商品の品揃えやプロモーション戦略の最適化にも役立てられます。個別化された接客を実現しながら、店舗運営の効率化も期待できる手法です。
デジタル接客を支援するツールは多様化しており、顧客の利便性向上だけでなく店舗運営の効率化にも役立っています。特に、顧客が店舗内でどのように動いているかを詳細に把握し、その情報を基に個々のニーズに合わせたパーソナライズされた案内を実現するツールは、店舗DXの推進において重要視されているといえるでしょう。
こうしたツールは、単に情報を提供するだけでなく、顧客の興味や行動履歴を分析し、最適なタイミングで適切な提案を行えます。そのため、機能の充実度や他のシステムとの連携のしやすさが接客の質に影響します。
Walkbaseは、顧客のスマートフォンアプリと連動し、店舗内での移動をナビゲートすると同時に、購買履歴や行動データを活用して最適な商品をレコメンドするプラットフォームです。これにより、来店客の利便性が向上し、接客の質も安定しやすくなります。
具体的には、顧客が店舗内のどのエリアにいるかをリアルタイムで把握し、その位置情報に応じた商品情報や特典をプッシュ通知で届けられます。こうした機能は顧客の興味関心に応じた提案につながり、購買意欲を高めやすいでしょう。
また、Walkbaseは複数店舗のデータを集約し、店舗ごとの特性や顧客動向の違いを分析できるため、多店舗展開する企業にとって運営効率の改善や戦略立案に役立つという特徴があります。
出典参照:Walkbase|Walkbase

店舗でデジタル接客を推進する際には、メリットだけでなく注意すべき点も存在します。ツールの選定や運用の仕方によっては、期待した効果が得られなかったり、現場の混乱を招いたりするケースも散見されます。
ここでは、デジタル接客を活用する際に陥りやすい代表的な失敗例を挙げ、その背景や防止策のヒントを考えていきましょう。これらのポイントを押さえることで、よりスムーズな店舗DXの推進につながるでしょう。
デジタル接客のツールは、操作のわかりやすさが大切です。いくら優れた機能をもっていても、顧客が操作方法を理解しにくいと、利用される機会が減ってしまいます。特に高齢者やITリテラシーに差がある顧客にとっては、画面の複雑さや入力の手間が利用の障壁になることが多いです。
そのため、直感的でシンプルなUI設計が求められます。操作のガイドやヘルプ機能を充実させることも、利用率の向上につながるでしょう。また、スタッフによる使い方の案内やフォローアップも有効な対策です。これらの工夫が不足すると、顧客満足度が低下し、デジタル接客の効果が限定的になるリスクが高まります。
デジタル接客はツールだけで完結するものではなく、店舗スタッフとの連携が不可欠です。システムが導入されても、スタッフが使いこなせなかったり、連携のルールが曖昧だったりすると、現場で混乱が生じやすくなります。
例えば、チャットボットやデジタルカウンセリング端末が出した情報をスタッフが把握していなければ、顧客との会話が一貫しません。また、ツールの通知やアラートがスタッフに適切に共有されないと、対応の遅れや二重対応の原因になります。こうした問題は、スタッフ教育の徹底や運用ルールの整備、役割分担の明確化を進めることで軽減できます。スタッフの協力を得ながらツールを活用する体制づくりが成功のカギです。
デジタル接客の魅力は、顧客データを活用して個々のニーズに応じた対応を可能にする点ですが、データの活用が不十分だと効果は限定的になります。収集した情報を分析・反映する仕組みが整っていなかったり、データの精度や更新頻度が低かったりすると、提案内容が一般的で顧客に響きにくいものになりがちです。
さらに、プライバシー保護の観点から適切なデータ管理が行われていない場合、顧客の信頼を損ないかねません。データの活用を進めるためには、信頼性の高い分析ツールの導入や運用ルールの整備、定期的な見直しが必要です。これにより、顧客一人ひとりに合わせた接客が実現しやすくなります。
デジタル接客ツールは便利ですが、システム障害が発生した場合に代替手段が用意されていないと、接客が停止し顧客対応に支障が出かねません。通信障害やソフトウェアの不具合などは避けがたい問題であり、そうした状況に備えたバックアッププランやマニュアルの整備が求められます。
障害発生時にスタッフが適切に対応できるよう、従来の対面接客の流れを維持したり、電話応対や紙媒体の案内を活用したりする準備も大切です。定期的なシステムチェックや訓練も含め、トラブル時の対応力を高めることで、顧客満足度の低下を防げるでしょう。
デジタル接客は単なる情報提供ツールとして使われがちですが、それだけでは顧客体験の向上につながりにくい面があります。接客の質を高めるには、顧客の興味や購買履歴に基づいた提案や、対話的なコミュニケーションが必要です。案内や表示のみに終始すると、顧客の関心を引けず、再来店や購買促進には結びつきにくいでしょう。
高度な機能を活かして双方向のやり取りや感情分析、顧客の反応をリアルタイムに反映した対応を目指すことが望ましいです。そうすることで、単なる案内ツールを超えた価値のある接客が実現し、店舗の競争力強化につながります。
デジタル接客の普及は多くの企業で加速しており、店舗DXを推進する上で重要な役割を果たしています。導入事例を通じて、実際にどのような効果や工夫があるのかを知ることができるでしょう。
ここでは、さまざまな業界で実践されているデジタル接客の取り組みを3つ紹介し、それぞれの特徴や活用方法に焦点を当てます。これらの事例から、自社に応用できるヒントを探ることができるでしょう。
アットホーム株式会社では、不動産業界のDX推進の一環として、入居申込手続きをオンライン化するシステムを導入しています。このシステムは、従来は店舗で行っていた申し込み作業をデジタル化し、顧客がスマホやPCからいつでも申込めるようにしています。これにより、顧客は店舗に足を運ぶ手間が省け、利便性が向上しました。
加えて、スタッフの業務負担が軽減され、効率的な運営が可能になった点が注目されています。また、申込情報はデジタルで一元管理されるため、情報の取り扱いもスムーズになり、ミスや重複を防止しやすくなりました。この取り組みは、店舗DX推進によるデジタル接客の好例として評価されています。
出典参照:京急不動産、首都圏エリアでアットホームの「スマート申込」を導入|アットホーム株式会社
株式会社メニコンでは、デジタル接客の一環としてアバター型のスタッフがコンタクトレンズのオンライン相談を担当しています。このシステムは、顧客が自宅にいながら専門的なアドバイスを受けられるサービスで、実店舗での接客に近い体験を提供します。アバターが質問に答えたり商品の特徴を説明したりすることで、初めての利用者でも安心して相談できる環境を実現しました。
また、相談内容は蓄積されるため、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされた対応につながるでしょう。このように、メニコンはデジタル接客を活用して顧客満足度の向上と店舗運営の効率化を図っている点が注目されています。
出典参照:「Miruオンライン相談サービス」導入のご案内~オリジナルアバター店員に相談してお悩み解決|株式会社メニコン
株式会社HISは、チャットコマースとリアル店舗での接客を連携させた新たなデジタル接客モデルを推進しています。チャットを通じて旅行商品の相談や予約ができる仕組みを構築し、顧客の利便性を高めました。リアル店舗ではチャット履歴を共有することで、スムーズで的確な接客が実現され、顧客のニーズに応じたサービスを提供しています。
こうした連携により、オンラインとオフラインの接客が融合し、顧客体験の質が向上しました。また、多様な顧客層に対応するため、多言語対応や24時間体制のチャットサポートも取り入れています。HISの事例は、店舗DXにおけるデジタル接客の可能性を示すものとして注目されます。
出典参照:接客DX(デジタルトランスフォーメーション)導入|株式会社HIS

店舗DXを推進する際にデジタル接客を取り入れることで、接客の質を一定に保ちながら省人化を図る効果が期待されます。ツールやシステムを活用することで、顧客への対応速度が上がり、多様なニーズに応じた柔軟な接客も可能になります。また、スタッフの業務負担を軽減し、限られた人員で多店舗や多時間帯をカバーできる点もメリットです。
ただし、導入にあたっては顧客視点を重視し、使いやすさやデータ活用を意識した運用が必要になります。今回の事例を参考にしながら、自社に合ったデジタル接客の推進方法を考えてみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
