店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
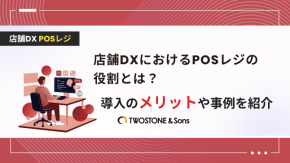
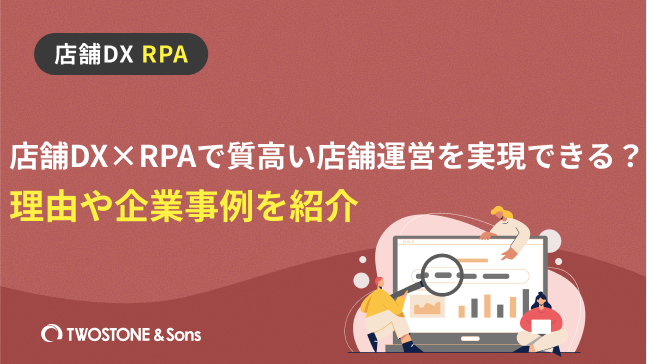
人手不足が常態化し、業務の属人化やスタッフの負荷が課題となる中、多くの店舗運営者が効率化のヒントを模索しています。厚生労働省によると、令和3年8月1日現在で小売業の労働人口は17%不足している状況です。売場づくりや接客といった本来注力すべき業務とは別に、受発注管理や帳票作成、在庫の確認といったバックオフィス作業が日常的に発生し、それらが従業員の生産性を圧迫しているという声は少なくありません。
その中でも注目されているのが、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用です。RPAは繰り返し発生する定型業務をソフトウェアロボットに代行させる仕組みで、属人的な作業を自動化する手段として広がりを見せています。
本記事では、RPAの基本的な特徴を整理しつつ、店舗業務との親和性が高い業務領域や具体的な活用例、運営面での効果について解説します。読後には、店舗DXの新たな切り口として、どのようにRPAを活かしていけばよいか、そのイメージをつかむヒントが得られるでしょう。
出典参照:労働経済動向調査(令和3年8月)の概況|厚生労働省

RPAとは、Robotic Process Automationの略称で、人間がパソコン上で行っている定型的な操作をソフトウェアロボットが代行する技術です。マウスのクリックやキーボード入力、ファイルの読み書き、Webブラウザでの検索やコピー&ペーストなど、ルール化された業務を人手に代わって処理するのが特長です。RPAはAIと異なり、自律的に判断や学習するものではありませんが、あらかじめ設定されたルールに沿って高精度な作業を反復的にできるという利点があります。
近年は中小規模の事業者でも手軽に導入できるRPAツールが増え、IT人材が不足する現場でも活用の幅が広がっています。特に業務フローが標準化されている店舗業務では、日次・週次・月次で発生するルーティン作業が多く、RPAとの相性が高いといえるでしょう。
店舗業務には、接客や販売といった現場での作業と、売上集計や在庫報告といった本部指示に基づく業務の中間に位置する「中間的業務」が数多く存在します。これらの業務は、手順自体はシンプルでも、繰り返し発生するために手間と時間がかかり、従業員の負担となりやすいのが現状です。
こうした中間業務をRPA(Robotic Process Automation)で自動化することにより、人的リソースの削減だけでなく、ヒューマンエラーの防止や業務品質の均一化も図ることができます。
受注情報の確認や、取引先ごとの発注フォーマットへの入力作業は、多くの店舗で日常的に発生する業務です。特に複数のシステムを跨いで情報を確認しなければならない場合、作業に時間がかかり、ヒューマンエラーが生じる要因ともなりかねません。RPAを活用することで、注文情報を自動的に集約し、指定されたフォーマットに従って発注書を作成・送信する一連の処理を自動化することが可能になります。
定期的に発生する同様の作業に関しては、作業手順をルール化しやすいため、RPAによる自動化との相性が良いとされています。
店舗では商品ごとの在庫状況を把握し、売れ筋や死に筋を分析する作業が欠かせません。特に月末や期末の棚卸作業は膨大な手間を要し、人為的なミスが発生しやすい業務といえるでしょう。RPAを活用すれば、在庫数の集計や各拠点のデータ収集、システムへの自動入力といった作業を効率化できます。
例えば、複数店舗から送られてくる棚卸データを指定フォーマットに自動で転記し、本部の在庫管理システムへ一括で登録する処理をRPAに任せることで、データ処理の一貫性を保ちつつ作業時間を削減できます。こうした積み重ねが、より正確な商品発注や棚割りの最適化にも寄与する結果となるでしょう。
売上報告や日報、週次・月次の各種レポート作成は、店舗における定型業務の中でも手間がかかりやすい作業です。担当者が複数のシステムから売上データを手動で抽出し、表計算ソフトで加工・集計を行うというフローは、業務量が増えるほど負荷が高まり、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
RPAを活用すれば、複数のデータベースから必要な情報を取得し、所定のフォーマットに整えて出力までを自動で行うことが可能になります。これにより、担当者は確認作業や内容分析など、付加価値の高い業務に集中できるようになり、レポートの質と業務全体の効率性を同時に向上させる流れをつくれるでしょう。
店舗に蓄積される顧客データは、販促活動やサービス改善の基盤となる重要な情報資産です。一方で、顧客情報の登録や更新、照合といった作業は入力のミスが起こりやすく、情報の正確性を損なう原因にもなり得ます。
こうした業務にRPAを活用することで、入力ミスや二重登録といった人為的なトラブルの発生を抑えつつ、一定のルールに基づいた自動処理が実現されます。例えば、会員登録フォームに入力された内容を店舗システムとCRMに同時反映させる処理や、既存データと突き合わせて重複をチェックするような作業も、RPAによって自動化することで作業負荷を軽減できます。
こうした取り組みは、顧客対応の質を保ちながら業務の効率化を促進するための手段として有効です。
店舗運営においては、POSシステム、在庫管理、勤怠管理、会計ソフトなど、複数のシステムを併用するケースが一般的です。しかし、これらのシステム間でデータが自動連携していない場合、スタッフが手作業で情報を入力・転記しなければならず、業務負担の増加やデータの不整合といった課題が発生します。
RPAを活用すれば、複数システムにまたがるデータの収集・統合・登録といった一連の作業を自動で処理できるため、業務全体のスピードと正確性が高まります。例えば、在庫数の変動をリアルタイムでPOSと在庫管理システムに同期させるような運用も実現できるでしょう。こうした取り組みは、情報の一元化を通じて部門間の連携精度を高め、DX推進の基盤づくりにもつながります。
店舗業務の多くは、短時間かつ正確な処理が求められる一方で、反復的で人手に依存する作業が数多く存在します。こうした業務構造においてRPAを活用すると、効率や精度の向上だけでなく、人的負荷の分散や人材活用の幅を広げるきっかけにもなるでしょう。
ここでは、店舗運営の現場においてRPA活用が特に推奨される理由を5つの観点から具体的に見ていきます。自社の課題を思い浮かべながら参考にしてください。
業務効率の向上は、店舗運営におけるRPA活用の主要な目的の一つです。売上入力、在庫更新、データ照合といった単純作業は日常的に発生するにもかかわらず、手作業では時間と労力がかかり、他の重要業務への影響も避けられません。
RPAを用いることで、こうした反復的な処理を短時間かつ安定的に遂行することが可能になります。例えば、発注処理をRPAが実行すれば、時間帯や曜日に関係なく処理が進み、スタッフの拘束時間を抑えられるでしょう。これにより、人的リソースの配置を柔軟に調整でき、全体的な業務運用の見直しや効率化にもつながります。
店舗現場では、シフトの都合や人手不足により業務が滞るリスクが常にあります。特に繁忙期や急な欠勤が発生した場合、限られた人員で業務を回す必要があり、従業員の負担が高まりかねません。
こうした状況において、RPAは人的リソースを補完する存在として効果を発揮します。あらかじめ設定された業務を24時間稼働で遂行するため、シフトの空白時間や営業時間外の処理にも対応できます。人間と異なり疲労や集中力の低下がないため、精度を保ったまま継続的に業務を実行し続ける点もメリットです。このような機能は、限られた人材で店舗運営を支える体制を構築する上で、後押しとなるでしょう。
RPAを活用することで、業務の標準化と品質向上が図れます。手作業に頼った業務では、担当者の経験やスキルによって処理の正確性やスピードに差が出ることは避けられません。とくに複雑な帳票の作成やシステム間のデータ照合といった作業では、見落としや誤入力が品質を下げる要因となりかねません。
RPAは設定されたルール通りに一貫した処理を行うため、人によるばらつきを排除し、均一な品質を保てるでしょう。また、ログの取得により作業のトレーサビリティも確保されるため、業務の透明性が高まり、不具合の検知や改善にも役立ちます。結果として、店舗全体の運営品質を安定させる土台が構築されていきます。
現代の店舗では、POS、在庫、EC、会計、人事など複数のシステムを併用するケースが一般的です。しかし、それぞれのシステムが独立している場合、情報の整合性を保つためにデータ転記や集計などの手作業が必要となり、非効率かつエラーの原因にもなりかねません。RPAはこうした複数システム間の情報連携を自動で行う手段として活用されます。
例えば、POSシステムの売上データを自動で会計ソフトに入力し、在庫データと突き合わせて次の発注に反映するなどの処理が実現されるでしょう。こうした仕組みにより、現場での入力作業を削減しながらも、データの整合性と更新性を保てます。業務全体のスピードと正確性を向上させる要因として重要な役割を担います。
RPAの活用によって定型業務の負担が軽減されることで、従業員はより人間的な対応が求められる業務に集中できるでしょう。店舗における顧客満足度の向上には、タイムリーな接客や丁寧な対応が欠かせませんが、裏方業務に追われる状態ではその実現が難しくなります。
業務の一部をRPAに委ねることで、従業員は顧客とのコミュニケーションや提案活動、クレーム対応など、人的対応が価値を生む領域に注力できます。こうした働き方の変化は、サービスの質だけでなく、従業員のモチベーションや職場環境の改善にもつながるでしょう。RPAは、業務の裏方を支える存在として、現場の働き方そのものを変えるきっかけにもなり得る存在です。

店舗DXを推進する上で欠かせないのが、業務効率化を支援するRPA(Robotic Process Automation)ツールの導入です。RPAは、定型的な事務作業や繰り返し業務を自動化することで、人手不足の解消やミスの削減に貢献します。
特に、レジ周りの売上データの集計、在庫管理、勤怠処理、発注業務といったルーティンワークを正確かつ迅速に処理できる点がメリットです。ここでは、実際に店舗運営で導入が進んでいる代表的なRPAツールとして「WinActor」と「BizRobo!」を紹介します。
NTTアドバンステクノロジが開発した「WinActor」は、Windows環境で動作するアプリケーション操作を自動化できる国産RPAツールです。マウス操作やキーボード入力といったユーザーの操作を「シナリオ」として記録し、繰り返し実行する仕組みで、特別なプログラミング知識がなくても扱えるのが特徴です。
店舗においては、売上報告の作成や勤怠データの取りまとめ、請求書の処理など、バックオフィスにおける多くのルーティン業務を自動化するのに適しています。特に中小規模の店舗でも導入しやすく、現場のスタッフによる内製化も可能なため、コストを抑えながら業務効率を高める手段として注目されています。日本語UIで初心者でも扱いやすく、サポート体制も充実している点も魅力です。
出典参照:WinActor|NTTアドバンステクノロジ株式会社
「BizRobo!」は、RPAテクノロジーズが提供するRPAツールで、特に大規模なチェーン店舗を展開する企業に適した機能が備わっています。ブラウザベースで動作し、クラウド環境での展開が可能なため、全国に複数拠点を持つ企業にとってはスケーラビリティの高い選択肢となるでしょう。
店舗間で共通する事務処理やレポート作成、在庫情報の取りまとめ、発注処理などを自動化することで、業務の標準化と省人化を同時に実現できます。また、ロボットの稼働状況を一元管理できる「BizRobo! Lite」など、運用負荷を抑える設計も魅力。導入後のサポートや教育体制も整っており、多店舗展開企業にとっては有用なRPAツールといえるでしょう。
出典参照:BizRobo!|オープン株式会社
RPAツールの導入は、単なる業務の自動化にとどまらず、業務プロセスの見直しや従業員の生産性向上にも直結する重要な施策です。近年では、流通業や小売業をはじめとした多くの企業が店舗DXの一環としてRPAを活用し、人的リソースの最適化を進めています。
ここでは、実際にRPAを導入し成果を上げている3社の事例を取り上げ、どのような業務にRPAを活用し、どのような効果を得ているのかを詳しく紹介します。導入を検討中の企業にとって、参考になる内容でしょう。
ホームセンター大手のカインズでは、日々発生する大量の定型業務に対してRPAを導入し、業務効率化を実現しています。具体的には、経理処理や売上データの集計、在庫確認など、これまで人手で行っていた単純作業の多くをRPAに任せることで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。
導入にあたっては、現場からの要望を細かく拾い上げ、業務にフィットする形でRPAのシナリオを構築しました。結果として、1件あたり数分かかっていた作業を数秒で処理できるようになり、作業時間を年間で数百時間削減する成果を上げています。RPA活用を現場主導で進めた点も、成功のカギとなりました。
出典参照:カスタマーサポートの変革──キャリア20年の経験をもとにもたらす新たな息吹|株式会社カインズ
SGホールディングスのIT子会社であるSGシステム株式会社では、宅配便受付などの窓口業務にRPAを導入することで、顧客対応の効率化を図っています。例えば、荷物の追跡情報を基にした返答メールの自動作成や、料金計算・伝票発行などを自動処理することで、人的ミスの減少と応対時間の短縮に成功しました。
これにより、現場スタッフはより複雑な対応や対面接客に集中でき、顧客満足度の向上にも貢献しています。また、RPAの運用管理も内製化しており、全社的なITスキルの向上にもつながりました。窓口業務という属人性が高い領域でもRPAが活用できる好例として注目されています。
出典参照:福知山市の窓口に関連する業務の一部自動化に向けAI-OCRとRPAの適用を開始 ~実証実験の結果、業務時間が約20%削減され本格導入へ~|SGシステム株式会社
イオングループでは、RPAを核としながらAIやOCRなどの先端技術と組み合わせることで、従来では自動化が困難だった業務領域にも積極的にチャレンジしています。例えば、手書きの発注書類をOCRで読み取り、AIで内容を判断し、RPAで処理するといった一連の流れを自動化しました。これにより、手間がかかる紙ベースの業務が簡素化され、データのデジタル化と業務効率化を同時に実現しました。
また、グループ全体での業務プロセスの標準化も進められており、RPA導入によって業務の品質やスピードに一貫性が生まれています。イオンでは、RPAを単なるツールではなく「業務変革のパートナー」として位置づけており、先進的な事例として注目されています。
出典参照:業務改善を通して、会社の生産性向上に貢献|イオン株式会社
RPAの導入は、店舗DXを推進する上で有効な施策ですが、運用の定着には事前準備と長期的視点が欠かせません。単に自動化ツールを設置するだけでは、想定通りの成果につながらないケースも多く見られます。
特に、現場の業務フローが属人的であったり、例外処理が多く含まれていたりする場合、RPAがうまく機能しにくくなります。導入効果を高めるためには、いくつかの注意点を押さえておきましょう。
ここでは、RPA導入時に確認すべき重要な視点を4つ紹介します。
RPAは、あらかじめ定義された手順を繰り返す仕組みであるため、対象業務のフローが曖昧なままでは思うように動作しません。特に多店舗展開する企業では、同じ業務であっても拠点ごとに作業手順が異なりやすく、こうした差異を放置したまま自動化を試みると、エラーの温床になります。
RPAを活用するには、まず対象業務の手順や条件分岐を明確にし、全店舗で統一された手順書やマニュアルを整備する必要があります。フローの見直しは、業務のムダを洗い出す機会にもなり、自動化以前に業務効率そのものを高める効果も期待できるでしょう。RPAの前提としての業務の標準化は、重要なステップです。
RPAは、ルール化された処理には高い適性を持ちますが、例外が発生した際には処理が止まったり、意図しない動作を引き起こしたりするリスクがあります。例えば、取引先の仕様変更やネットワークの遅延、入力データの形式の違いなど、日常的に発生しうるイレギュラーに備えておく必要があります。
これらの状況に対応するためには、エラー発生時のログ取得や通知、バックアップ処理のフローなどをあらかじめ設計しておきましょう。また、現場スタッフが異常を検知しやすいように可視化されたダッシュボードやアラート機能を活用すると、初動対応を迅速に行いやすくなります。自動化を安定運用するためには、例外を想定した運用設計が不可欠です。
RPAは既存の業務アプリケーションの画面操作やファイル構造に依存するため、OSや業務システム、Webサイトの仕様変更が発生すると、シナリオが正常に動作しなくなるかもしれません。例えば、表示位置の変更やボタンの名称変更といった些細な修正でも、ロボットは処理を継続できなくなることがあります。
そのため、システム側のアップデートを実施する前にRPAの影響範囲を確認し、必要な修正を計画的に行う体制を構築しておく必要があります。また、保守担当者が常に最新の業務フローやシステム仕様に精通している状態を維持することで、突発的なエラーへの対応力を高められるでしょう。RPAの持続的な運用には、システム更新と連携したメンテナンス体制の整備が必要です。
RPAは導入すればすぐに効果が出るわけではなく、業務への定着には一定の期間と運用スキルが必要です。そのため、初期段階から全社的に展開するのではなく、まずは一部業務や限定された店舗での試験導入からスタートすることが大切です。
こうした段階的な導入によって、現場の反応や運用上の課題を可視化しやすくなり、フィードバックを基にシナリオの修正や管理体制の見直しが行えます。実績が積み上がった後に、他店舗への横展開を行えば、無理なく自動化を広げることが可能になります。RPA導入には過度な期待や短期的な成果を求めるのではなく、長期的な業務改革の一環として取り組む姿勢が大切です。

店舗DXを推進する中で、RPAは業務の省力化や属人性の排除といった面で有効な選択肢となります。ただし、RPAの効果を引き出すためには、事前に業務フローを整理・標準化し、例外処理や運用体制の整備も並行して進める必要があります。また、導入は段階的に行い、現場での課題や改善点を把握しながら拡大していくと良いです。
今回紹介したツールや事例を参考に、自社の業務においてRPAが適している領域を見極め、業務全体の見直しにつなげることで、より現実的な店舗DXの実現が見えてくるでしょう。短期的な効率化だけでなく、長期的な業務変革の一環として捉える視点が必要です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
