店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
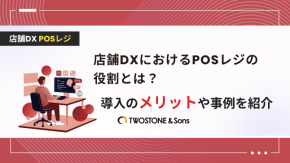
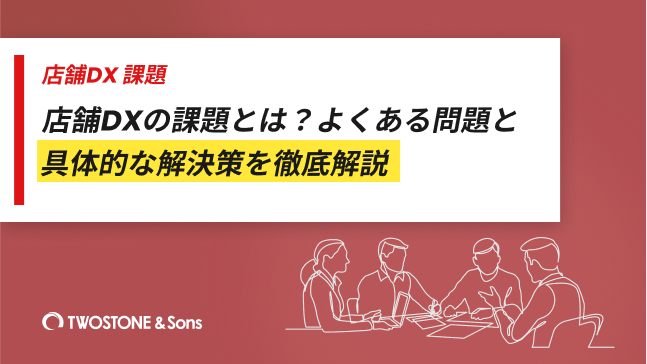
本記事では、店舗DX推進でよくある課題と効果的な解決策を詳しく解説します。初期投資コストの負担、システム選定、スタッフの抵抗感といった準備段階から運用中の問題まで、ノジマやスターバックスなどの成功事例とともに具体的な対策をご紹介します。
店舗経営において、デジタル技術を活用した業務効率化や顧客体験向上への期待が高まる一方で、多くの企業が店舗DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進過程で様々な課題に直面しています。初期投資の負担やシステム選定の困難さ、現場スタッフの抵抗感など、理想と現実のギャップに悩む経営者は少なくありません。
特に中小企業では限られた予算と人材の中で成果を出さなければならず、競合他社がデジタル化を進める中、何もしなければ競争力の低下は避けられないでしょう。
本記事では店舗DX推進時に遭遇しがちな課題を準備段階から運用段階まで体系的に整理し、それぞれの具体的な解決策を詳しく解説します。実際の企業事例も交えながら、課題を乗り越えて成功に導くためのノウハウをお伝えします。

店舗を取り巻く環境は急速に変化しており、消費者の購買行動のデジタル化や人手不足による運営コストの上昇など、従来の手法だけでは対応しきれない課題が山積みです。これらの構造的な問題に対処するため、多くの企業が店舗DXの推進に乗り出していますが、実際の取り組みでは様々な壁に直面することになります。
店舗DXで発生する課題は大きく「システム・技術領域」「予算・費用対効果領域」「組織・人材育成領域」の3つの領域に分類されます。
ここでは、それぞれの課題について詳しく見ていきましょう。
システム・技術領域の課題は、店舗DXの根幹に関わる重要な問題です。多くの企業で見られるのは、導入したいシステムと既存の業務システムとの連携がうまくいかないケースです。例えばPOSシステムと在庫管理システムの情報が連動せず、二重入力が発生してしまうといった状況が考えられます。
また技術的な知識不足により、自社の業務に適さないシステムを選んでしまい、期待した効果が得られないという問題も頻繁に発生します。セキュリティ対策についても、適切な対策を怠ると深刻な事故につながる可能性があります。
予算・費用対効果の課題は、特に中小企業の店舗DX推進において大きな障壁となることがあります。初期投資だけでなく、システムの維持費用やアップデート費用、スタッフの研修費用など、継続的に発生するコストの全体像が見えにくいという問題があります。
特に、業務効率化といった効果は定性的な部分も多く、経営陣への説明や継続的な予算確保に苦労するケースも少なくありません。
さらに予算制約により段階的な推進を検討する場合、どの領域から着手すれば最大の効果が期待できるかの判断に迷うという課題もあります。限られた予算の中で優先順位を適切に設定し、投資対効果を最大化する戦略的なアプローチが求められるでしょう。
組織・人材育成の課題は、店舗DXの成功を左右する重要な要素です。まず社内にDXを推進できる専門知識を持った人材が不足しているという根本的な問題があります。外部の専門家に依存せざるを得ない状況では、自社の業務特性に合わない提案を受け入れてしまうリスクも考えられます。
さらに経営陣と現場の間で、DXの目的や方向性に対する認識のずれが生じることもあります。経営陣は効率化やコスト削減を重視する一方、現場は顧客サービスの質を優先したいと考えるなど、優先順位の違いが組織内の足並みを乱す要因となる可能性があるでしょう。
店舗DXの推進を決定し、具体的な準備を進める段階で多くの企業が計画段階では見えなかった現実的な課題に直面します。理想的なDX像を描いていても、いざ実行に移そうとすると予算やシステム選定、既存環境との整合性など、様々な障壁が立ちはだかります。
準備段階での課題解決は、その後の推進・運用フェーズの成功を大きく左右するため、十分な時間をかけて慎重に検討することが重要です。ここでは、それぞれの課題について詳しく見ていきましょう。
店舗DXの準備段階で多くの企業が初期投資コストの想定以上の高さに直面します。
システム本体の導入費用だけでなく、ハードウェアの購入、既存システムとの連携作業、スタッフの研修費用、セキュリティ対策など、関連する費用を総合すると当初の予算を上回るケースが少なくありません。
さらに導入効果が現れるまでに時間がかかる場合、投資回収期間が延びることで資金繰りに影響を与えることも考えられるでしょう。こうした費用面の課題は、DX推進の継続性や規模に直接影響するため、慎重な検討が求められます。
市場には店舗運営を支援する多種多様なDXツールが存在し、POSシステム、CRMツール、在庫管理システム、決済システムなど、それぞれに多数の選択肢があります。機能や価格、サポート体制が異なる中から、自社の業務に最適なツールを選定することは容易ではありません。
特に技術的な知識が不足している場合、販売会社の営業担当者の説明だけでは真の適合性の判断が困難になります。
ツール選定の誤りは導入後の運用効率や費用対効果に大きく影響するため、選定プロセスでは十分な検討時間を確保し、複数の選択肢の比較が重要です。場合によっては専門家のアドバイスを求めることも必要になるでしょう。
多くの店舗ではすでに何らかの業務システムを運用しており、新たにDXツールを導入する際には既存システムとの連携が課題となります。例えば従来のPOSシステムと新しいCRMシステムの顧客データが同期されない、といった問題の発生は珍しくありません。
システム間の連携には技術的な専門知識が必要で、API連携やデータ形式の統一など、複雑な作業を伴う場合があります。また連携作業には追加費用が発生することも多く、当初の予算に含まれていないケースも見られます。
既存システムとの連携問題は、店舗運営の効率性や正確性に直接影響するため、導入前の入念な調査と計画が不可欠です。
店舗DXの推進には、現場スタッフの業務フローや作業内容を大きく変える可能性があるため、スタッフからの反発や不安の声が上がることは珍しくありません。長年慣れ親しんだ作業方法を変更することへの抵抗感や、新しいシステムを覚えることへの不安、さらには業務効率化により雇用に影響が出るのではないかという懸念もあります。
特にデジタル技術に不慣れなスタッフや年配のスタッフからは、システム操作への苦手意識や学習負担に対する不満が表れやすい傾向にあります。
現場スタッフの理解と協力なしにはDXの成功は困難であるため、実施前の段階から十分なコミュニケーションを取り、スタッフの不安や懸念に真摯に向き合うことが重要です。
店舗DXのシステム導入が完了し、実際の運用が始まると、準備段階では予想できなかった新たな課題が浮上してきます。開始時には順調に進んでいたプロジェクトでも、日常的な運用の中で様々な問題に直面し、期待した効果が得られないケースは少なくありません。
運用段階での課題は準備不足だけでなく、外部環境の変化や予想外の状況によって発生することもあります。重要なのは問題が発生した際に迅速に対応し、改善につなげる体制を整えることです。ここでは、運用中に発生しやすい具体的な課題について詳しく解説します。
店舗DXシステムを導入すると、売上データや顧客情報、在庫データなど大量の情報が蓄積されますが、これらのデータを効果的に活用できずに悩む企業は多く存在します。データは収集できているものの、分析方法が分からない、分析結果をどう業務改善に活かせば良いかが不明確という状況に陥りがちです。
データ活用の効果が見えないと、DX投資の正当性を疑問視する声が社内で高まり、継続的な取り組みに支障をきたすことも考えられます。データを価値ある情報に変換し、具体的な成果につなげる仕組みづくりが重要な課題となるでしょう。
店舗DXの推進により、顧客の個人情報や決済データ、企業の機密情報などがデジタル化され、サイバー攻撃の標的となるリスクが高まります。セキュリティ事故が発生すると、顧客からの信頼失墜、法的責任の追及、事業継続への影響など、企業経営に深刻なダメージを与える恐れがあります。また事故対応にかかる費用や時間も大きな負担となり、場合によってはDXの推進どころではなくなってしまうでしょう。
さらに従業員のセキュリティ意識が不十分な場合、人的要因によるセキュリティリスクも増大します。技術的な対策だけでなく、組織全体でのセキュリティ意識の向上と継続的な対策の見直しが必要になるでしょう。
店舗DXシステムの導入後には、継続的な保守・運用費用が発生し、これが企業の財務負担となることがあります。月額利用料やライセンス費用、システムのアップデート費用、技術サポート費用など、運用段階で必要となる費用は多岐にわたります。
特にクラウド型システムでは利用規模の拡大に伴い費用も増加する傾向があり、当初の想定を上回るコストが発生することは珍しくありません。
これらの継続費用が経営を圧迫し、DXの推進を断念せざるを得ない状況に陥ることもあるため、長期的な費用計画と予算管理が重要な課題となります。
店舗DXの推進時には売上向上や業務効率化、顧客満足度の向上などの成果を期待しますが、実際にはこれらの効果が現れるまでに想定以上の時間を要する場合があります。システムの習熟期間や業務プロセスの定着、顧客の新しいサービスへの適応など、様々な要因により成果の実現が遅れがちです。
また成果の測定方法が明確でない場合、実際には効果が出ているにも関わらず、それを適切に評価できないという問題も発生します。
成果が見えない期間が長く続くと、社内でDXに対する疑問の声が高まり、継続的な投資や取り組みに対する支持が得られなくなる可能性すらあります。

店舗DXの成功は、技術やシステムの導入だけでは実現できません。組織全体でDXを推進し、継続的に取り組む体制を構築することが不可欠です。しかし多くの企業では、人材不足や組織内の意識の違い、部門間の連携不足といった組織・体制面での課題に直面します。
特に中小企業では限られた人員の中でDXを推進しなければならず、専門知識を持った人材の確保が困難になりがちです。
ここでは、組織・体制面でぶつかりやすい課題について詳しく見ていきましょう。
店舗DXを成功に導くには、デジタル技術に関する知識と店舗運営の実務経験を併せ持つ人材が必要ですが、このような人材の確保は容易ではありません。社内でDXを主導できる人材がいない場合、外部のコンサルタントや専門会社に依存することになり、自社の業務特性が十分に反映されない施策となる可能性があります。
また既存の従業員にDXの知識やスキルを身につけてもらう場合でも、十分な専門性を習得するまでに長期間が必要になることが考えられます。特に技術の進歩が早いデジタル分野では、継続的な学習が必要となり、人材育成への投資も継続的に必要となるでしょう。
店舗DXの推進において、経営陣が描く理想像と現場スタッフの認識との間に大きなギャップが生じることは珍しくありません。経営陣は売上向上やコスト削減、競争力強化といった経営的な観点からDXの必要性を感じる一方、現場スタッフは日々の業務効率化や顧客対応の改善といった実務的な課題解決を重視する傾向があります。
このような認識の違いにより、導入するシステムや機能の優先順位について意見が分かれ、DXの方向性が定まらないこともあるでしょう。また経営陣が理想とするDXの姿が現場の実情にそぐわない場合、現場からの協力を得ることが困難になり、システムの定着や活用が進まない可能性もあります。
店舗DXの効果を最大化するには、販売、在庫管理、顧客管理、経理、マーケティングなど複数の部門が連携して取り組む必要があります。しかし部門ごとに異なる業務目標や評価指標を持つため、全社的な協力体制を構築することは、容易ではありません。
例えば販売部門は売上向上を重視する一方、在庫管理部門はコスト削減を優先するといったように、部門間で利害が対立する場合もあります。またDXによる業務プロセスの変更が一つの部門には有益でも、他の部門には負担増となるケースもあり、全体最適と部門最適のバランスを取ることが困難になります。
これまで見てきた店舗DX推進時の様々な課題は、適切な対策を講じることで軽減可能です。重要なのは、課題の性質を理解し、自社の状況に応じた実践的なアプローチの選択です。多くの企業が成功している解決策には共通のパターンがあり、これらを参考にすることで効率的な課題解決が期待できます。
ここでは、実際に多くの企業で成果を上げている具体的な解決策を詳しく解説します。自社の課題と照らし合わせながら、最適な組み合わせを見つけることが成功に繋がるでしょう。
店舗DXの推進において、初期投資リスクや失敗の影響を最小限に抑える効果的な方法は、スモールスタートで始めることです。一斉導入ではなく、まず1つの店舗や特定の業務領域に限定してシステムを試験的に導入し、効果を検証してから段階的に拡大していくアプローチが有効です。
この手法により、システムの使い勝手や業務への適合性を実際の運用環境で確認でき、問題点があれば早期に発見・修正することが可能になります。また初期投資額を抑えることで、万が一想定した効果が得られない場合でも損失を最小限に留めることができるでしょう。
店舗DXには専門的な知識や技術が必要であり、社内リソースだけでは対応困難な場合が多いため、外部の専門会社のサポートの効果的な活用が重要です。ただし、すべてを外部に依存するのではなく、自社の業務特性や課題を正確に伝え、最適なソリューションを提案してもらうのが良いでしょう。
専門会社を選定する際には、同業界での実績や導入事例の豊富さ、アフターサポートの充実度を重視し、複数の会社から提案を受けて比較検討することが大切です。また導入後の保守・運用についても、社内で対応可能な範囲と外部サポートが必要な領域を明確に分け、継続的なサポート体制を確保しておく必要があります。
店舗DXの成功において、現場スタッフの理解と協力は不可欠です。新しいシステムやツールを導入しても、それを使いこなすスタッフのスキルが不足していては期待した効果は得られません。そのため、スタッフ教育には十分な時間と予算を投資し、段階的かつ継続的な研修プログラムを実施することが重要です。
教育内容は単なる操作方法の説明に留まらず、DX推進の目的や期待される効果、業務改善にどのように寄与するかといった理解促進も含める必要があります。またスタッフのITスキルレベルには個人差があるため、それぞれのレベルに応じた個別指導やフォローアップ体制を整えることも大切です。
店舗DXの取り組みを継続的に改善し、投資対効果を最大化するには、効果を数値で測定し分析することが不可欠です。売上高、顧客数、平均客単価、作業時間、エラー率など、DXの目的に応じた適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、実施前後での変化の定期的な測定が大切です。
数値による効果測定により、DXの成果を客観的に評価でき、経営陣や現場スタッフに対して具体的な改善効果を示すことが可能になります。また期待した効果が得られていない場合には、データ分析を通じて原因を特定し、システムの設定変更や運用方法の見直しなど、具体的な改善策を検討できます。
店舗DXは一度の取り組みで完結するものではなく、技術の進歩や市場環境の変化に合わせて継続的に改善・発展させていく必要があります。そのため短期的な成果だけでなく、長期的な視点でDXに取り組む体制の構築が重要です。
継続的なDX推進には、専任の担当者や部署の設置、定期的な見直しプロセスの確立、技術動向の情報収集体制の整備などが必要となります。また予算計画においても、初期投資だけでなく継続的な改善や機能追加のための予算を確保しておくことが大切です。
さらに組織全体でDXに対する理解を深め、変化を受け入れる企業文化を醸成することも長期的な成功には欠かせません。
店舗DXの推進において、理論的な解決策を理解することも重要ですが、実際に課題を乗り越えて成果を上げた企業の事例から学ぶことで、より具体的で実践的なヒントを得ることができます。
ここで紹介する3つの企業事例は、それぞれ異なる業界・業態でありながら、共通してDX推進時の典型的な課題に直面し、それを独自の工夫と継続的な改善により克服してきました。これらの事例を通じて、課題解決のプロセスや成功要因を理解し、自社の店舗DX推進に活かせる要素を見つけることができるでしょう。
家電量販店を展開する株式会社ノジマは、店舗DXの一環として、パナソニック製の電子棚札システムを全184店舗に導入し、価格変更作業の効率化という課題を解決しました。
同社が導入した電子棚札システムは、POSシステムとの連携により、価格の一括更新が可能で、全店舗合計約140万枚の電子棚札を効率的に管理できます。1.6インチから7.4インチまで4種類のサイズバリエーションを用意し、商品に応じて最適なサイズを選択することで、視認性と機能性を両立させています。
この導入により、2019年の消費税増税時には店舗での切替作業時間をほぼゼロへ短縮しています。人手不足が深刻化する小売業界において、業務効率化と顧客サービス向上を同時に実現した好事例といえるでしょう。
出典参照:国内初 ノジマがパナソニックの「電子棚札システム」を全184店舗に導入完了|株式会社ノジマ
百貨店業界の三越伊勢丹ホールディングスは、デジタル技術を活用した新しい顧客体験の創出という課題に対し、VR(仮想現実)技術を活用したスマートフォン向けアプリ「REV WORLDS(レヴ ワールズ)」を2021年に導入しました。従来の店舗運営では、営業時間や物理的な制約により顧客との接点が限定されるという課題がありましたが、このVRプラットフォームにより24時間いつでもアクセス可能な仮想店舗空間を実現しています。
同アプリでは、新宿東口の街並みと伊勢丹新宿本店の一部をリアルに再現した仮想空間を構築し、顧客はアバターを操作して店内を歩き回り、商品の閲覧・購入が可能です。
VRでしか体験できない遊び心ある世界観を表現することで、従来の百貨店にはない魅力的なサービスを実現し、デジタルネイティブ世代を含む新たな顧客層の獲得にもつながっています。
出典参照:VRを活用したスマートフォン向けアプリ「REV WORLDS (レヴ ワールズ)」の提供を開始|三越伊勢丹ホールディングス
カフェチェーンを展開するスターバックスコーヒージャパン株式会社は、店舗の混雑時におけるレジ待機時間の長さという課題を抱えていました。そこで、「Mobile Order & Pay(モバイルオーダー&ペイ)」システムを導入し、顧客の利便性向上と店舗運営の効率化を同時に実現しました。これにより、アプリのインストールや会員登録をしなくても、店内のApp Clipコードをスマートフォンで読み取るだけで、注文から決済まで完結できるシステムを構築しています。
この取り組みにより、顧客はレジに並ぶことなく席に座りながらゆっくりとメニューをカスタマイズでき、注文完了後は指定時間に商品を受け取るだけで済むようになりました。約1,000店舗での試験導入を経て全国約1,900店舗への展開を予定しており、デジタル技術を活用した顧客体験の向上と業務効率化の両立を実現した代表的な事例といえるでしょう。
店舗DXの推進において、課題が発生してから対応するのではなく、事前に問題を予測し適切な対策を講じることで、リスクの軽減が期待できます。多くの企業がDX推進で直面する典型的な課題は、ある程度パターン化されており、先行事例を参考にした予防的なアプローチが効果的です。
事前対策は一見すると時間と手間がかかるように思えますが、後から発生する課題への対応コストや機会損失を考慮すれば、結果的に効率的で確実なDX推進につながります。ここでは、具体的な予防策について詳しく見ていきましょう。
店舗DX推進の成功は、開始前の現状把握と目標設定の精度に大きく左右されます。まず自社の現在の業務プロセス、システム環境、スタッフのスキルレベル、顧客ニーズなどを詳細に分析し、改善すべき課題を明確に特定することが不可欠です。この段階で曖昧な認識のままDXを進めると、後になって想定外の問題が発生し、軌道修正が必要になる可能性があります。
目標設定においては、「レジ待機時間を30%短縮」「在庫回転率を20%改善」など、具体的で測定可能な指標の設定が重要です。また目標達成までの期間やマイルストーンも明確にし、進捗を定期的に評価できる体制を整えておくのが良いでしょう。
店舗DXを成功に導くためには、経営トップが単に承認するだけでなく、自ら率先してDXの重要性を社内外に発信し、推進の先頭に立つことが極めて重要です。経営陣の本気度が伝わらない場合、現場スタッフのモチベーション低下や、部門間の連携不足、予算確保の困難といった課題が発生しやすくなります。
なぜDXが必要なのか、どのような成果を期待しているのか、そのために何を犠牲にしてでも取り組むのかといったメッセージを、社内会議や研修の場で繰り返し伝えることが大切です。また予算配分や人員配置においても、DXを最優先事項として位置づける姿勢を行動で示す必要があるでしょう。
店舗DXにおいて、いきなり全店舗で本格的に推進するのではなく、限定的な範囲での試験運用により、多くのリスクを事前に回避できます。
試験運用の範囲は、特定の店舗、特定の時間帯、特定の業務プロセスなど、管理可能な規模に限定することが重要です。この段階では完璧な運用を求めるのではなく、問題点の洗い出しと改善策の検討に重点を置きましょう。
また試験運用中は、効果測定のためのデータを詳細に記録し、設定した目標に対する達成度の客観的な評価も大切です。期待した効果が得られない場合は、システムの設定変更、運用方法の見直し、追加研修の実施など、具体的な改善策を検討し実行するのが良いでしょう。

店舗DXの推進は、現代の店舗経営において避けて通れない重要な課題です。本記事で解説したとおり、DX推進には様々な課題が伴いますが、それらは決して乗り越えられないものではありません。重要なのは、課題の性質を正しく理解し、適切な対策を計画的に実行することです。
店舗DXは一朝一夕で完成するものではありませんが、長期的な視点で継続的に取り組むことで、競争力強化と持続的な成長を実現できます。まずは自社の現状を見つめ直し、本記事で紹介した解決策を参考に、店舗DX推進に取り組んでみてください。適切な対策と着実な実行により、成功の可能性を高めることができるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
