店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介
店舗
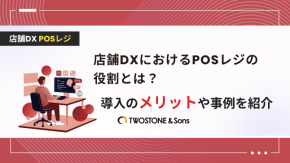
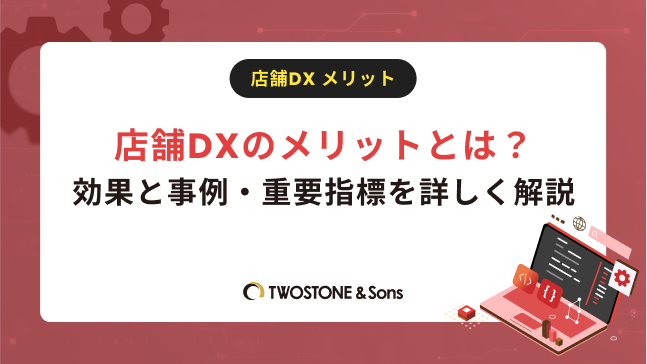
店舗DXがもたらす経営・顧客・従業員の3つの視点からのメリットを詳しく解説します。コスト削減や売上向上から顧客体験革新、働きやすさ改善まで、実際の企業事例と効果測定方法、推進時の注意点も含めて包括的にお伝えします。
2024年の小売業販売額は167兆1,530億円となり、前年比2.5%増加しました。その一方で人手不足や運営コスト増などの課題が深刻化し、従来の手法だけでは限界が見え始めています。こうした状況を受け、DXの推進を検討する企業も顧客ニーズと共に増えてきました。
店舗DXがもたらすメリットは、コスト削減や売上向上といった経営面だけでなく、顧客体験の向上、従業員の働きやすさの改善など多岐にわたります。適切に取り組めば、短期間で効果を実感でき、長期的な競争力強化にもつながります。しかし投資対効果を最大化するには、自社の課題や目標に応じた戦略的なアプローチが不可欠です。
本記事では店舗DXがもたらす具体的なメリットを経営・顧客・従業員の3つの視点から詳しく解説し、実際の企業事例や効果測定方法も含めて包括的にお伝えします。

店舗DXが経営に与える影響は多面的で、短期的なコスト削減から長期的な競争力強化まで幅広い効果をもたらします。特に経営面では、業務効率化による運営コストの削減、データ活用による売上最大化、人材不足への対応、科学的な経営判断の実現という4つの主要メリットが期待できます。
従来の店舗経営では多くの業務が人的作業に依存し、コスト構造の改善や効率化に限界がありました。しかし店舗DXの推進により、これらの構造的課題を根本から解決し、新たな価値創出の機会を生み出すことが可能になります。
ここでは経営面で得られる4つの主要なメリットを詳しく解説します。
店舗DXの直接的なメリットの一つが、業務の自動化とデジタル化によるコスト削減です。従来手作業で行っていた在庫管理、発注業務、レジ操作、顧客対応などをシステム化することで、人件費の削減と作業精度の向上が期待できます。
また予測AIを活用した需要予測により、過剰在庫や品切れによる機会損失を防ぎ、適正在庫の維持によるコスト最適化も可能です。さらにクラウド型システムの活用により、複数店舗の一元管理や遠隔監視が実現し、管理コストの削減にもつながります。
店舗DXは単なるコスト削減だけでなく、売上と収益の向上にも大きく貢献します。顧客データ分析により購買パターンや嗜好を把握し、効果的な商品配置や販促戦略を立案できるため、客単価の向上とリピート率の増加が期待できます。動的価格設定システムにより、需要と供給のバランスを考慮した最適な価格決定が可能になり、収益の向上も期待できるでしょう。
また、ECサイトとの連携によるオムニチャネル戦略では、店舗とオンラインの境界を越えた顧客体験を提供し、新たな売上機会を創出できます。
厚生労働省「一般職業紹介状況」によると、卸売業・小売業の新規求人は前年同月比7.7%減となっています。このような深刻化する人手不足に対し、店舗DXは根本的な解決策となりえるでしょう。
例えば、チャットボットによる24時間顧客対応、自動レジシステムによる会計業務の効率化、在庫管理の自動化などにより、少ない人員でも高品質なサービスを維持できます。また定型業務の自動化により、スタッフはより付加価値の高い業務に集中でき、限られた人材を有効活用できるようになるでしょう。
さらにデジタルツールの活用により新人スタッフの研修時間を短縮し、早期戦力化も可能です。働き方の改善により従業員満足度が向上し、離職率の低下と人材定着にもつながります。結果として採用コストの削減と安定した店舗運営を両立できるでしょう。
出典参照:一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について|厚生労働省
店舗DXにより蓄積される膨大なデータを活用することで、従来の経験や勘に頼った経営から、データに基づく科学的な経営判断への転換が可能になります。売上データ、顧客行動、在庫状況、スタッフの作業効率などの情報をリアルタイムで分析し、迅速で正確な意思決定を行えるようになります。またKPI(重要業績評価指標)の設定と継続的な監視により、目標達成状況を客観的な評価が可能です。
これらのデータ活用により経営の透明性と説明責任が向上し、ステークホルダーからの信頼獲得にもつながるでしょう。
店舗DXは経営効率化だけでなく、顧客体験の革新的な改善をもたらします。デジタル技術の活用により、従来では実現困難だった高度にパーソナライズされたサービスや、シームレスな購買体験を提供できるようになります。
現代の消費者はオンラインとオフラインを問わず一貫した高品質なサービスを期待しており、単なる商品販売では差別化が困難です。店舗DXによる顧客体験の向上は、価格競争から脱却し付加価値による競争優位を確立する有効な手段です。
ここでは顧客面で得られる3つの重要なメリットを詳しく見ていきましょう。
店舗DXの推進により、顧客の購買体験が向上します。例えば、モバイルオーダーやセルフレジの導入により待ち時間を短縮し、店内Wi-Fiや充電スポットの提供により快適な滞在環境を整備できます。また、商品検索システムやデジタルサイネージにより、顧客が求める情報を迅速に提供し、スムーズな買い物体験の実現が可能です。
これらの取り組みにより顧客満足度が向上し、口コミやSNSでの好意的な評価拡散も期待できます。結果として新規顧客の獲得とリピーターの増加につながり、持続的な事業成長を支える基盤となるでしょう。
店舗DXによる利便性の向上は、顧客ロイヤルティの強化に直結します。具体的には、会員アプリの導入により、ポイント管理や購買履歴確認、限定クーポンの配信などが一元化され、顧客にとっての利用価値が向上するでしょう。また、店舗とECサイトの連携により、オンラインで注文して店舗で受け取るサービスや、店舗で確認してオンラインで購入するといったオムニチャネル体験を提供できます。
これらの利便性向上により、顧客は他店舗での購買よりも自社での購買を優先するようになり、長期的な関係構築が可能になります。高いロイヤルティを持つ顧客は購買頻度と客単価が高く、安定した収益源となるでしょう。
店舗DXにより蓄積される顧客データを活用することで、個々の顧客に最適化されたパーソナライズサービスの提供が可能になります。購買履歴や行動パターンを分析し、顧客の嗜好に合わせた商品推薦や特別オファーを自動配信できます。また来店時に過去の購入商品や関心のある商品カテゴリに基づいて、最適な商品配置や店内案内も可能です。
さらに顧客の声やフィードバックをリアルタイムで収集・分析し、継続的なサービス改善に活用できます。
このような高度にパーソナライズされたサービスにより、顧客は特別感を感じ、ブランドへの愛着と信頼が深まるでしょう。
店舗DXは顧客や経営面だけでなく、従業員の働きやすさ向上にも大きな効果をもたらします。働き方改革が求められる現代において、従業員満足度の向上は人材確保と定着率改善の重要な要素となります。
特に人手不足が深刻化する小売・サービス業界では、既存従業員の満足度向上と生産性向上が事業継続の鍵を握るといっても過言ではないでしょう。店舗DXによる働きやすさの改善は、離職率の低下、採用力の強化、従業員エンゲージメントの向上といった複合的な効果をもたらし、組織全体の競争力強化につながります。
ここでは従業員の働きやすさ向上につながる3つの主要なメリットを詳しく解説します。
店舗DXの推進により、従業員の身体的・精神的負担を軽減できます。自動レジやセルフサービス端末の導入により、繁忙時のレジ業務負担が軽減され、長時間の立ち仕事や反復作業によるストレスが軽減されます。また在庫管理システムの自動化により、重い商品の運搬や手作業による棚卸し作業が効率化され、身体的負担の軽減につながるでしょう。
さらにシフト管理システムの導入により、公平で効率的なシフト作成が可能になり、スタッフの希望を反映しやすくなります。これらの改善により、ワークライフバランスの向上と従業員満足度の向上が期待できるでしょう。
店舗DXにより定型業務が自動化されることで、従業員はより高度で創造的な業務に時間を割けるようになります。また、顧客データ分析や販売戦略立案など、これまで本部や管理職Tが担っていた業務にも参画できるようになり、専門性の向上が期待できるでしょう。
新しいシステムの導入に伴う研修やトレーニングにより、継続的な学習機会も提供されます。さらにAIやデータ分析ツールを活用した業務により、論理的思考力や問題解決能力の向上も図れます。これらのスキルアップにより、従業員の市場価値が向上し、長期的なキャリア形成にもプラスの影響をもたらすでしょう。
店舗DXの推進により、職場環境の質的改善と従業員のモチベーション向上を実現できます。例えば、デジタルサイネージや音響システムの導入により、快適で働きやすい環境を整備できるでしょう。また従業員向けアプリの導入により、社内コミュニケーションの活性化や情報共有の効率化が図れ、チームワークの向上につながります。
加えて、業務効率化により残業時間が削減され、プライベートな時間を確保しやすくなることで、仕事に対する満足度が向上します。さらに成果が数値で可視化されることにより、自身の貢献度を客観的に把握でき、達成感や充実感を得やすくなるでしょう。これらの環境改善により、従業員の離職率低下と優秀な人材の確保が可能になり、組織全体の競争力向上にもつながります。

店舗DXの効果を具体的に理解するには、実際に成功を収めている企業の事例を詳しく分析することが重要です。業界ごとに異なる課題やニーズに対応した多様なDX施策が展開されており、それぞれの取り組みから学べる実践的なノウハウが豊富にあります。
成功企業の事例には、課題設定からシステムの導入プロセス、効果測定まで、自社での応用に役立つ具体的な情報が含まれています。ここでは異なる業界の代表的な企業事例を紹介し、店舗DXがもたらす多面的なメリットを見ていきましょう。
コーナン商事株式会社では、店舗とオンラインの融合を目指す「店舗デジタル化戦略」の一環として、ECサイト「コーナンeショップ」の大幅なリニューアルを実施しました。
同社が重点的に取り組んだのは、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」の導入による検索機能の強化です。ホームセンターという業態の特性上、膨大な商品数と専門的な工具名などロングテール検索への対応が課題でしたが、ZETAとの連携により継続的なチューニング体制を構築しました。
これらの改善により、コンバージョン率が0.2ポイント向上、直帰率が45%から42%に改善、セッション時間が3割アップするなど、顧客体験の向上を実現しました。
出典参照:ECサイトの顧客体験向上・店舗スタッフの業務効率を同時実現したコーナン商事の店舗DX推進のカギは「検索」にあり|コーナン商事株式会社
メガネ販売チェーン「Zoff」を運営する株式会社インターメスティックでは、店舗のDX推進の一環として、AI技術を活用した接客支援システムの開発に取り組んでいます。同社が設立したDX推進組織「ZEPS」では、AIベンチャーのACESと連携し、約1年間にわたって店舗に設置したカメラやアンケートから顧客の購買行動やスタッフの接客行動データを収集・分析しました。
同社では「AIはツール。コアではない」という考えのもと、技術そのものではなく顧客体験の向上を最優先に据えています。店舗カメラ画像から接客の様子を分析し、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)評価にも活用するなど、データ活用の範囲を拡大しているのが特徴です。
出典参照:AIの接客支援で「Zoff」売り場のメガネ選びを変える、DX組織の狙いとは|株式会社インターメスティック
スーパーマーケットの株式会社東急ストアでは、「DX推進プロジェクト」を発足し、全社的なデジタルトランスフォーメーションを推進しています。同社では業界トップを目指すのではなく、今ある仕組みやシステムをブラッシュアップし、他社のDX事例を研究して自社版にアレンジする現実的なアプローチを採用しています。
同社のDX推進は「守りのDX」と「攻めのDX」の2つの軸で構成されているのが特徴です。守りのDXでは業務効率化による生産性向上を目指し、無人決済店舗「TOUCH TO GO」の実験導入により、日商4万円規模の店舗で人的コストの課題を解決しました。攻めのDXでは競争力強化に向けた取り組みを推進し、「AI値引き」システムによりSDGsにも貢献しています。
出典参照:東急ストア「リテールDX」の取り組み|株式会社東急ストア
店舗DXの投資対効果を最大化するには、適切な効果測定と継続的な改善が不可欠です。定量的・定性的な指標を組み合わせて多角的に評価し、DXの真の価値を把握することで、さらなる投資判断や施策改善につなげることができます。重要なのは短期的な成果だけでなく、中長期的な競争力向上も含めて包括的に評価することです。
ここでは効果測定の具体的な手法と重要指標について詳しく解説します。
店舗DXの直接的な効果測定は、売上・収益面での数値変化です。主要指標として、月次・年次売上高の推移、客単価の変動、顧客数の増減、リピート率の向上などを継続的に監視するのが良いでしょう。特に重要なのは、DX施策実施前後での比較分析で、季節変動や外部要因を考慮した正確な効果測定が必要です。
また商品カテゴリ別、時間帯別、顧客セグメント別の詳細分析により、どの施策がどの領域で効果を発揮しているかを特定できます。収益性の観点では、粗利率の改善、値引きロス削減率、在庫回転率の向上などが重要な指標となります。
業務効率化の効果は、作業時間短縮、人員配置最適化、エラー削減などの指標で測定します。具体的には、レジ処理時間の短縮率、在庫管理作業の効率化、発注業務の自動化率、顧客対応時間の改善などを数値で追跡します。例えばPOSシステムの改善により1取引あたりの処理時間が何秒短縮されたかなどを正確に測定することが重要です。
人件費削減効果も重要な評価指標で、従業員の労働時間削減、残業時間減少、適正人員配置による生産性向上を定量化します。また業務品質の向上として、誤出荷率の減少、在庫差異の削減、顧客クレーム件数の減少なども測定対象となります。
顧客体験向上の評価には、定量的指標と定性的指標を組み合わせたアプローチが効果的です。定量的指標として、顧客満足度スコア(CSAT)、ネット・プロモーター・スコア(NPS)、顧客努力スコア(CES)などの標準的な指標を定期的に測定します。また店舗滞在時間、リピート来店間隔、クロスセル成功率、アプリダウンロード数やアクティブユーザー数なども重要な指標となります。
さらに顧客の声を直接収集するため、定期的なアンケート調査、フォーカスグループインタビュー、ソーシャルメディアでの言及分析なども実施すると良いでしょう。これらの定性的フィードバックから、数値では現れない顧客体験の質的変化を把握し、継続的な改善につなげることができます。
店舗DXを成功に導くためには、技術的な側面だけでなく、人的要素や運用面での注意点を十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。多くの企業がDX推進で失敗する原因は、これらの注意点を軽視したことにあります。特に従業員の理解不足、システムの性急な全面導入、セキュリティ対策の不備は、DXの効果を減少させる可能性があります。ここでは店舗DX推進時に特に注意すべき3つの重要なポイントを詳しく見ていきましょう。
店舗DXの成功において、従業員の理解と積極的な協力は不可欠な要素です。新しいシステムやツールを導入しても、実際に使用する従業員が抵抗感を持っていては、期待した効果を得ることはできません。まず経営陣は、なぜDXが必要なのか、どのようなメリットがあるのかを従業員に丁寧に説明し、変革の必要性について共通認識を形成することが重要です。「業務が楽になる」「スキルアップにつながる」「顧客満足度が向上する」など、従業員にとっての具体的なメリットを明確に示すことが効果的です。
さらに従業員からのフィードバックを積極的に収集し、システムの改善や運用方法の見直しに反映させることで、従業員の当事者意識を高めることができるでしょう。
店舗DXでは一度にすべてを変革するのではなく、段階的なアプローチでリスクを最小化しながら着実に成果を積み重ねることが重要です。まず影響範囲の小さい業務や特定の店舗でパイロット導入をし、効果検証と課題抽出を実施します。
PDCAサイクルの実践では、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の各段階で明確な目標と評価指標を設定し、定期的にレビューを行います。特にCheck段階では、事前に設定したKPIに基づいて客観的に効果測定し、目標との乖離がある場合は原因分析を実施しましょう。そしてAct段階で具体的な改善策を立案・実行し、次のサイクルにつなげることで、継続的な改善が実現できます。
店舗DXの推進に伴い、顧客の個人情報や企業の機密データがデジタル化されるため、セキュリティとプライバシー保護の強化は必須の取り組みです。特に顧客の購買履歴、決済情報、行動データなどの機微な情報を扱う場合、適切な保護措置を講じないと重大なセキュリティ事故につながる可能性があります。
具体的な対策として、データの暗号化、アクセス権限の厳格な管理、定期的なセキュリティ監査の実施、従業員へのセキュリティ教育などが挙げられます。また、顧客に対してもデータ利用目的や保護措置を明確に説明し、同意を得る仕組みを整備することで、信頼関係を維持しながらDXを推進できるでしょう。

店舗DXは経営面、顧客面、従業員面という3つの視点から多面的なメリットをもたらし、企業の持続的な成長と競争力強化を実現する重要な戦略です。本記事で解説したとおり、コスト削減や売上向上といった経営効果だけでなく、顧客体験の革新や従業員の働きやすさ向上など、組織全体に好循環を生み出します。
重要なのは、従業員の理解と協力を得ながら段階的に推進し、適切な効果測定とセキュリティ対策を実施することです。また短期的な成果に一喜一憂するのではなく、中長期的な視点で継続的な改善を重ねることが成功につながります。
本記事で紹介したメリットや事例を参考に、店舗DX推進を進めてみてください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
